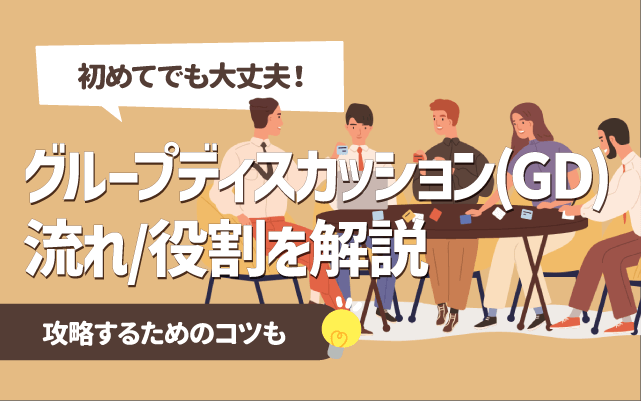- グループディスカッション(GD)の評価は、結論よりもチームの中での振る舞い方
- グループディスカッションの評価ポイント
- グループディスカッションの流れ5つ
- グループディスカッションの5つの役割
- グループディスカッションを攻略する3つのコツ
- グループディスカッションはチームとしての成果を最優先する
-
【優良版】GDを練習できるおすすめツール
-
【就活生】ミーツカンパニー
(企業の前でグループワーク) -
【就活生】適性診断AnalyzeU+
(251問で性格診断) -
【就活生/転職者】LINE適職診断
(あなたの適職を16タイプで診断)
-
【就活生】ミーツカンパニー
 GD対策を受けてみる
GD対策を受けてみる(ミーツカンパニー)
公式サイト
(https://meetscompany.jp/)
*上場企業からベンチャー企業まで様々な企業が集結!
こんにちは。「就活の教科書」編集部の宮原です。
みなさんは、「グループディスカッション(GD)ってどう立ち回るのが正解?」「グループディスカッション(GD)ではどこをみてる?」などの疑問を持っているのではないでしょうか?
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
 就活生くん
就活生くん
今度初めてグループディスカッション(GD)があるのですが、どういうふうに立ち回るのが正解かわかりません。
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
普段人前で喋るのが苦手なのですが、グループディスカッション(GD)乗り切るためのコツなどありますか?
グループディスカッション(GD)って何が正解かわからなくて、困りますよね。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
そこで、本記事では「グループディスカッション(GD)」を中心に解説していきます。
合わせて、「グループディスカッション(GD)の流れ」「グループディスカッション(GD)を攻略するためのコツ」なども解説していきます。
本記事を読めば「グループディスカッション(GD)とは何か」「グループディスカッション(GD)の評価ポイント」がわかります。
「初めてのグループディスカッション(GD)で不安」「グループディスカッション(GD)では何が求められるの?」と思っている方はぜひ最後まで記事を読んでください。
先に伝えておくと「グループディスカッションなどの選考対策をしたい!」という方は、選考対策が受けられ、優良企業のグループワークを通してGDの練習ができる「ミーツカンパニー」を使うのが一番おすすめです。
ちなみに「【就活生】ミーツカンパニー」以外なら、簡単な質問で自分のキャリアの価値観が診断できる「適性診断AnalyzeU+」、あなたの適職を16タイプで診断できる「LINE適職診断」を使って、今あなたがすべき対策を把握しましょう。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
- 【就活生】ミーツカンパニー(グループワークを通してGD練習ができる)
【公式サイト】https://www.meetscompany.jp/
- 東証プライム上場からベンチャー企業までマッチング
- 【就活生】適性診断AnalyzeU+(全251問、客観的な性格診断)
【公式サイト】https://offerbox.jp/
- 診断でSPI性格検査の練習も
- 【就活生/転職者】LINE適職診断(公式LINEで無料診断)
【公式サイト】https://reashu.com/linelp-tekishoku/
- あなたの適職を16タイプで診断
「結局どのサービスを使えば良いかわからない…」という方は、選考対策と優良企業紹介をしてくれる「【就活生】ミーツカンパニー」で対策してもらうのが一番おすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
目次
- 【ざっくり解説】グループディスカッション(GD)とは
- 【初めてでも大丈夫】グループディスカッション(GD)の5つの流れ
- グループディスカッション(GD)の5つの役割を解説
- グループディスカッションで面接官がみているポイント
- 初めてのグループディスカッション(GD)を攻略する3つのコツ
- 企業がグループディスカッションを行う理由とは?
- 【完全解説】グループディスカッションの進め方
- グループディスカッション対策【5タイプ】
- グループディスカッションの練習方法
- グループディスカッションに落ちる人の特徴
- グループディスカッション(GD)に関するよくある質問
- まとめ:流れと役割を理解して、初めてのグループディスカッション(GD)を攻略しよう
【ざっくり解説】グループディスカッション(GD)とは
 就活生くん
就活生くん
今度初めてのグループディスカッションがあるのですが、そもそもグループディスカッションでは何をするのでしょうか?
グループディスカッション(Group Discussion:GD)とは、4〜6人のグループで、「答えのないお題」に対して、制限時間内に結論を導く選考形式です。
その過程でどんな役割を担い、どれだけチームの議論に貢献できたのか、企業は就活生を評価します。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
今度初めてグループディスカッション(GD)をするのですが、評価のポイントがわからず対策できません。評価のポイントがあれば教えてほしいです。
初めてだと、グループディスカッション(GD)で何をするのかどこを見られているのかわからないですよね。まずは、グループディスカッション(GD)とは何か?について解説しますね!
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
グループディスカッション(GD)は選考序盤で実施されやすい
グループディスカッション(GD)を選考方法として採用している企業は、一度に多くの学生を選考できるというメリットがあるため選考序盤で実施されることが多いです。
また面接官と学生が対するという面接の場合、学生は「自分をよく見せたい」や「不利なことを隠したい」と思って自分を偽ったりすることがあります。それに対して、グループディスカッション(GD)では学生同士が対するので、学生1人1人についてその主体性を見極めやすいとされています。
また、基礎的なコミュニケーション力も見ることができるのでグループディスカッション(GD)は選考の序盤に使われやすいです。
入社してから企業側・学生側の双方のギャップを減らすことができ、どちらにも働きやすい結果をもたらしてくれると考えられます。
グループディスカッション(GD)は企業側にメリットが多くあるので、選考方法として採用している企業が増えています!
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
「チームの中でどのように振る舞うか」を評価している
グループディスカッション(GD)では、話し合いの結果・発表よりも「チームの中でどのように振る舞うか」を評価しています。つまり結果=評価ではありません。
グループディスカッション(GD)では、グループごとに評価されるのではなく、個々で評価されるので話し合いの過程を重要視し、採用担当は話し合いの中で学生がどのように動くかを見ています。
グループディスカッション(GD)で企業が見ている評価ポイントは4つ
グループディスカッション(GD)で企業が見ている評価ポイントは大きく4つです。
- 評価ポイント①:積極性
- 評価ポイント②:協調性
- 評価ポイント③:論理的思考力
- 評価ポイント④:発想力
評価ポイント1つ目は、「積極性」です。
積極性は多くの企業が見ているポイントで、話し合いの中で進んで発言できているかどうかを評価します。
話し合いで発言ができる積極性がある人がいると、議論に参加していると話し合いが活発化し、参加メンバーから意見を引き出せる可能性が高まります。積極性は「自分が自分が」のようなエゴとは異なります。自分の意見を長々と話すのではなく、簡潔にまとめることが重要です。
「自分はこう思う」といったような発言をおこない、同時に他人の意見も引き出すのが真の積極性です。議論は一人でおこなうものではなく、複数人の知恵をより合わせなければ意味がありません。
評価ポイント2つ目は、「協調性」です。
グループディスカッション(GD)ではチーム内で協力して議論を進める必要があり、協力できなければマイナスの印象を与えてしまいます。
議論を進めるために適切な発言、主張をしなければなりませんが、議論が停滞してしまうこともあります。このときに否定するのではなく、一度受け入れて全体の議論にどのように反映させるかを考えることが大切です。しかし、同意するだけが協調性ではないので議論に必要な意見かどうかを見極める必要もあります。
他人の意見を汲み取り全体に反映することが協調性ですので、グループ全体のバランスを取ることを意識しておきましょう。
評価ポイント3つ目は、「論理的思考力」です。評価されるには、筋道を立てて物事を考えられることが重要なポイントです。
議論を円滑に進めるためには、根拠を示しながら発言しなければなりません。突拍子もない主張はマイナスの評価になってしまいます。
根拠と結論をしっかりと紐づけして、考えをきちんと言語化できるかどうかが評価のポイントであり、イメージを言葉で具現化できるかどうかも評価の対象です。
評価ポイント4つ目は、「発想力」です。
既存の意見に縛れることなく色々な視点から意見を出したり、議論を進むような情報・知識を発言し共有できているかどうかを見ています。企業側からすると、学生が普段どんな情報を取り入れているかなどの姿勢についても垣間見ることのできます。
企画部などの発想力が重要視される職種では、グループディスカッション(GD)でこのような力を見せられるようにアピールすることも大切です。
自分が一番アピールできそうな評価ポイントを見つけて、グループディスカッション(GD)の準備をしましょう。
自分がアピールできそうな評価ポイントは自己分析をして見つけることができます。
自己分析の仕方がわからない方は以下の記事をぜひ参考にしてください。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
(ミーツカンパニー)
【初めてでも大丈夫】グループディスカッション(GD)の5つの流れ
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
グループディスカッション(GD)を初めてするですが、何もわからなくて不安です。
グループディスカッション(GD)は、どのような流れで行われるのでしょうか?
流れがわからないと不安ですよね。
なのでグループディスカッション(GD)の流れ5つについて解説しますね!
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
- 役割・時間配分を決める
- 前提を確認する
- アイディアを出し合う
- 議論をまとめる
- 発表する
①:役割・時間配分を決める
グループディスカッション(GD)の流れ1つ目は、「役割・時間配分を決める」です。
グループディスカッション(GD)には様々な議論の仕方がありますが、どんな議論だとしても個々が自分勝手に発言していては時間内にいい結論を導き出すことは難しくなります。
なので、まずは司会進行・書記・タイムキーパー、発表者等の必要な役割を決めていきましょう。初めに司会進行を決めると他の役割もスムーズに決めることができます。
ここの進め方で大切なことは、自己紹介や役割分担にあまり時間掛けすぎないことです。あくまでも本題に入るための、導入部分です。
それぞれの役職の細かい役割については、「グループディスカッション(GD)の流れ5つ」の後で解説します。
役割を決めたら、次は時間配分を決めます。
グループディスカッション(GD)には制限時間があり、企業は「時間内に結論を出すことができるか」という点も評価のポイントとなるため、良い結論を導き出すためにも時間配分は決めておく必要があります。
議論する時間を多くとりたくなってしまいますが、意見をまとめる時間もしっかりとることが重要です。
グループディスカッション(GD)の目的は、あくまでも議論をすることではなくグループで結論を導き出すということです。
そのため、良い評価を得るためにも議論をする時間だけでなく、意見をまとめる時間もしっかりと確保するように意識しましょう。
②:前提を確認する
グループディスカッション(GD)の流れ2つ目は、「前提を確認する」です。
前提を確認するということは、出された議題をチーム全体で確認して具体的にすることです。
これはグループディスカッション(GD)において最も重要な工程となります。
前提を確認せずに議論を行うと、メンバー間で議題を正しく理解できずに論点がずれてしまい、解決策の幅広くなってしまい結論を導き出すのが難しくなってしまいます。認識のずれをなくすことで時間を無駄にせずに使うことができます。
そのために議論するための前提条件をチーム全体で確認・形成していきましょう。
この段階では、5W2H(Who、When、Where、What、How、Why、How much)を意識することが重要です。
議題「ある会社でコミュニケーションが増えるような施策を考えてください」
このような抽象的なテーマの前提を確認するとしたら「ある会社ってどのくらいの規模?」「コミュニケーションが増えるとは」「どんなコミュニケーション?」「会社全体のコミュニケーション?部署ないのコミュニケーション?」「施策の種類はイベントor環境整理?」などが挙げられます。
このように細かくすり合わせをすれば、「社員が100名くらいの会社で、部署関係なく社員が喋ることができるような施策を考える」のような具体的な議題にすることができます。これである程度、議論の結論がしぼれて、話しやすくなりますよね。
③:アイディアを出し合う
グループディスカッション(GD)の流れ3つ目は、「アイディアを出し合う」です。
先ほどのテーマ例「ある会社でコミュニケーションが増えるような施策を考えてください」であれば、以下のようなアイディアを出すことができます。
- 専用の机をなくして、移動しやすく話しやすくする
- 部署関係なくチームを作り、商品開発する
- 話がしやすいように、ゲームやソファーなどをおいたコミュニケーションスペースを作る
ここで大切なのは、「チーム全員が議論に参加して、どれだけアイディアを引き出せるか」です。時間内であればアイディアは多いほうがより良い結論を導くことができると言えます。
またアイディアを出すときは、ただ発言すれば良いわけではありません。自分の意見をまとめて周りににわかりやすく主張することが大切になります。
自分の意見を述べる時には、「結論⇨理由⇨証拠・具体例⇨結論」の順番で喋るようにしましょう。
④:議論をまとめる
グループディスカッション(GD)の流れ4つ目は、「議論をまとめる」です。
議論をまとめるには、同じような意見をまとめてアイディアを整理していきます。グループディスカッション(GD)では多くのアイディアが出るため、整理しなければまとまらなくなります。
つまり、グループディスカッション(GD)において一番重要とされている”結論を出す“という工程の時間が十分に確保できず、議論自体が中途半端になってしまう可能性があるということです。
話し合いが終わったらいよいよグループ内での結論を出します。
ここで大切なのは、グループ全員が納得している結論であるかです。
グループディスカッション(GD)では合意形成が重要となるので、多数決や誰かの意見で決めたというようなことにならないよう気をつけましょう。
⑤:発表する
グループディスカッションの流れ5つ目は「発表する」です。
テーマに対する結論が出た後には、その内容を他のグループや面接官に伝えるプレゼンを行います。活発な議論をおこない、どんなに素敵な結論が出たとしても、面接官に上手く伝えることができなければ意味がありません。
発表者はどのような結論を出し、その過程にどのような議論があったのかをわかりやすく伝えることができるように準備しましょう。
発表は大体1分程度で済ませるようにしましょう。
グループディスカッション(GD)の流れが分かりましたね!
議論をする前に前提を確認することで、ある程度結論の方法を導き出すことができましたね。
そしてアイディアを出すことに時間を費やしがちですが、議論をまとめることに時間を残すことが重要だと分かりました!
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
「グループディスカッションの対策何すれば良い?」「グループディスカッションに苦手意識がある」という就活生には、「ミーツカンパニー」の利用がおすすめです。

ミーツカンパニーでは、1日に2~8社の企業と少人数で話せるイベントに参加でき、イベント後は専属のアドバイザーが内定まで就活をサポートしてくれます。
イベントでは、企業と少人数で話せるだけではなく、グループワークの時間も設けられているなど、グループディスカッションの練習も行えます。
有名企業で実際に行ったグループディスカッションを体験できるだけではなく、その後選考サポートも受けられるので、ぜひ一度イベントに参加してみてくださいね。
\ 30秒でカンタン無料エントリー /
グループディスカッション(GD)の5つの役割を解説
 就活生くん
就活生くん
グループディスカッション(GD)では結論よりもチームの中での振る舞い方が重要なんですよね。
役割別の振る舞い方を教えてほしいです!
それではチームの中での振る舞い方に大きく関係するグループディスカッション(GD)の5つの役割について、解説していきますね!
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
- 役割①:司会進行
- 役割②:書記
- 役割③:タイムキーパー
- 役割④:発表者
- 役割⑤:役職なし
役割①:司会進行
グループディスカッションの役割1つ目は、「司会進行」です。
司会進行は、話し合いを進行するリーダー的な役割となります。参加者の意見を取りまとめる、あまり発言していない人に話を振るといったことも司会の重要な役目です。
司会進行をすると面接官にリーダーシップの能力を強くアピールできるでしょう。
話し合いの進行は司会の役目ですが、他の参加者の意見を無視し、むりやり議論を進めてしまうことはマイナスの評価につながってしまうので避けるようにしましょう。
時間が足りなくなってきた場合は、焦ってしまうこともあると思いますが、そんな時こそ冷静に対処しましょう。司会進行には判断力や会話の流れを読む力も必要なため、難易度が高いポジションとも言えます。
司会進行は、周りを見ることができ、コミュニケーション能力に自信がある人が向いています。
- 初めに発言して、議論しやすい雰囲気を作る
- メンバー全員に視線を送り、全体を把握する
- 発言が少ない人に話を振る
- 論点を整理し結論につながる発言を切り出していく
役割②:書記
グループディスカッション(GD)の役割2つ目は、「書記」です。
議論の内容やメンバーが出した意見を書き、グループ全体に見えるような形で提示しておく役割です。
特に、メンバー全員が積極的に発言するような活発な議論となった場合は、それぞれが意見を記憶することは難しいため、重要な役目となるでしょう。
書記になったときは、書くことに夢中になり、メンバーへの情報共有ができていなかったり、発言しないと言うことは避けるようにしましょう。
書記は記録と発言を並行して行うため、大変な役割です。しかし、上手くこなせばチーム貢献している印象を残すことができます。
書記は、筆記速度や情報の整理に自信がある人が向いています。
- メモをとりながら、同じような意見をまとめたり、対立点を整理しておくこと
- メモを取った内容をメンバーに共有する
- 書記の役割だけに夢中にならず、意見を言う
役割③:タイムキーパー
グループディスカッション(GD)の役割3つ目は、「タイムキーパー」です。
時間内に議論を進め、発表内容をまとめるためにタイムコントロールをする役割です。議論が白熱してくるとつい時間を忘れてしまいがちですが、時間内に仕事を完了するスキルは社会人にとって重要なものです。
事前に定めた時間が守れないときは、参加者を急かすといった対応も求められます。
ただ時間を読み上げるだけでなく、ディスカッションの流れによって時間配分を変えて、臨機応変に対応できると評価が上がることもあります。また、タイムキーパーはほかの役割と兼務することもあります。
タイムキーパーは、臨機応変にチームを動かせる人が向いています。
- 議論が時間内で結論に至るように声かけをする
- 議論が盛り上がっている状況でも、予定時刻を伝える
- 議論の展開状況に合わせて、うまく時間配分を変えられているか
グループディスカッションではうまく進まないことが多いので、時間配分をするときにきっちり時間を使うのではなく1分程度余裕を持って終わるような時間配分にしましょう。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
役割④:発表者
グループディスカッション(GD)の役割4つ目は、「発表者」です。
グループディスカッション(GD)で話し合った内容を、採用担当者やほかのグループの前で発表する役割です。
まとめた内容をただ読み上げるだけでなく、自分なりの言葉で、抑揚をつけて話すスキルが求められます。またチームで出した結論をメンバー内で乖離がないように理解する必要があります。
発表者は、人前で発表することに慣れている人や緊張しない人が向いています。
- 決められた時間内に発表をし終えること
- 発表内容に対してメンバーの同意を得て、付け加えることがないか確認する
- 抑揚をつけて、分かりやすく発表する
- プレゼン能力やパフォーマンス能力が評価対象になるとは限らない
役割⑤:役職なし
グループディスカッション(GD)の役割5つ目は、「役職なし」です。
グループの人数次第では、上記の役割に当てはまらない人が出ることもあります。
もし役割がなかった場合は、以下の方法を参考にディスカッションに参加しましょう。
- 書記役を2名に増やす
- 議論の論点がずれないようにするための「監視役」を置く
- たくさんのアイディアを出す「アイディアマン」になる
グループディスカッション(GD)の目的は結論を出すことなので、時間内に効率よく議論を進めることができることが重要視されるためメンバーそれぞれが役割を持つことが推奨されます。
自分が向いている役割というものは存在しますが、場合によっては他の人としたい役割が被ってしまうことがあります。ここで、「〇〇の役割しかしたくない」など固執するのは危険です。
固執してメンバー内で役割争いなどが起これば、企業にマイナスな評価を与えることになるので自分にできそうな役割を複数用意しておくことをおオススメします。
- 自分にできそうな役割を複数用意しておく
- メンバーそれぞれが役割を持つことが推奨される
グループディスカッション(GD)の役割が分かりましたね!
自分に向いている役割を見つけて、グループディスカッションの練習をしておきましょう。
自己分析をすることで、自分の向いている役割が見つかることもあります。
自己分析の仕方を解説しているので、自己分析の仕方がわからない方は以下の記事を参考にしてみてください。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GD選考に関する記事一覧
「グループディスカッションが苦手」という就活生には、 グループディスカッション対策とコツ という記事がおすすめです。
この記事を読めば、「GDではファシリテーター(司会)をすべき?」「役割が無ければ落ちるの?」という疑問が全て解決できるので、GD選考を控えている就活生はぜひ読んでください。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
ちなみに、「就活の教科書」では有給インターンを募集しています。
以下のリンクからぜひ応募してみてください。
 「就活の教科書」編集長 岡本恵典
「就活の教科書」編集長 岡本恵典
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
(ミーツカンパニー)
グループディスカッションで面接官がみているポイント
グループディスカッション選考では、面接官が1人1人の学生の動きを用心深く見ています。
そのため、面接官がどのような部分を評価しているのかを把握しておくことが大切です。
グループディスカッションで面接官が見ているポイントは以下の5つです。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
- 面接官の評価ポイント①:積極性
- 面接官の評価ポイント②:思考力
- 面接官の評価ポイント③:リーダーシップ
- 面接官の評価ポイント④:協調性
- 面接官の評価ポイント⑤:論理性
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
面接官の評価ポイント①:積極性
グループディスカッションで面接官がみているポイント1つ目は「積極性」です。
グループディスカッションで出されるお題は正解のないテーマがほとんどです。
正しいか正しくないかよりもとにかく積極的に発言をすることが大切です。
積極的とは、自分だけの意見を押し通すだけでなく、周りのメンバーに「何か意見はないでしょうか?」「僕はこう思うのですが、どうでしょうか?」など議論を活性化させるために積極的に動いているかどうかが大切です。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
面接官の評価ポイント②:思考力
グループディスカッションで面接官がみているポイント2つ目は「思考力」です。
思考力とは、なんとなくで解決策をすぐに出すのではなく、本質的な課題を仮説ベースで見つけられる力です。
例えば、飲食店の純利益を改善したいという課題にぶつかった時に、
- 「提供する商品が美味しくないのか」
- 「提供する場所や立地が悪いのか」
- 「そもそもその商品が流行っていないのか」
- 「商品としては、売れているものの人件費が高いのか」
などの様々な課題を仮説ベースで考えて、どれが真の課題かを発見する力を指します。
思考力を上げるためには、とにかく仮説を立てて「なぜ」「なぜ」を繰り返すことが必要です。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
面接官の評価ポイント③:リーダーシップ
グループディスカッションで面接官がみているポイント3つ目は「リーダーシップ」です。
グループディスカッションはその日初めてあった学生同士で議論を行うため、どうしても協調性のないメンバーが出てきます。
例えば、消極的で意見を出さないメンバーに、「チームではこのように意見が出ているけど、何か意見はない?」とリーダーシップをとってチームを動かすことによって、面接官から高い評価を得られるようになります。
そのため、いかにリーダーシップをとって、チームをまとめていくかは非常に重要なポイントになります。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
面接官の評価ポイント④:協調性
グループディスカッションで面接官がみているポイント4つ目は「協調性」です。
協調性があると議論が活発になり、チームとしても最高の結果を出すことができます。
なので、質の高い意見や主体性を見せても、協調性がない学生は、面接官からすぐに低い評価を受けます。
そのため、周りのメンバーの進捗や意見とすり合わせながら議論を進めて行くことを重要視しましょう。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
面接官の評価ポイント⑤:論理性
グループディスカッションで面接官がみているポイント5つ目は「論理性」です。
意見を述べる上で、論理的に物事を話す力は重要です。
例えば、どれだけ素晴らしい意見でも、論理性がなくダラダラと話してしまうとチームの時間も奪われ、面接官からの評価も大きく下がります。
自分の意見は、まず端的に結論から伝え、そのあと理由と根拠を付け足して話ようにしましょう。
論理的に話すのが苦手な方は、ぜひ以下の手順に沿って話してみてください。
- 私の意見は〇〇です。
- なぜならば、〇〇だからです。
- その理由は〇つあります。
- そのため〇〇です。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
「グループディスカッションの対策何すれば良い?」「グループディスカッションに苦手意識がある」という就活生には、「ミーツカンパニー」の利用がおすすめです。

ミーツカンパニーでは、1日に2~8社の企業と少人数で話せるイベントに参加でき、イベント後は専属のアドバイザーが内定まで就活をサポートしてくれます。
イベントでは、企業と少人数で話せるだけではなく、グループワークの時間も設けられているなど、グループディスカッションの練習も行えます。
有名企業で実際に行ったグループディスカッションを体験できるだけではなく、その後選考サポートも受けられるので、ぜひ一度イベントに参加してみてくださいね。
\ 30秒でカンタン無料エントリー /
初めてのグループディスカッション(GD)を攻略する3つのコツ
 就活生くん
就活生くん
グループディスカッション(GD)の役割について理解することができました!
ですが、グループディスカッション(GD)をするにはまだ不安です。。。
初めてでもグループディスカッション(GD)を攻略する方法はありませんか?
グループディスカッション(GD)について知ることができても、初めてだと不安ですよね。
そこで初めてでもグループディスカッション(GD)を攻略する3つのコツを解説しますね!
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
- コツ①:積極的に発言する
- コツ②:他の人の意見には肯定から入る
- コツ③:何を議論しているのかをはっきりさせる
前提:チームとしての成果を最優先する
前提としてグループディスカッション(GD)の目的はチームで一つの結論を出すことです。なので、チームとしての成果を最優先しましょう。
採用担当者にアピールしたいという気持ちから自分ばかり発言してしまいがちですが、チームで良い結論を出すことが重要です。
コツ①:積極的に発言をする
初めてのグループディスカッション(GD)を攻略する1つ目のコツは、「積極的に発言する」です。
議論をするので、発言をしないと採用担当者からも評価されず記憶に残ることはありません。
またグループディスカッション(GD)では、一つのチームだけでなく複数のチームと同時に行われます。なので、採用担当者は自分のチームだけをみているわけではありません。採用担当者にアピールするためにも、積極的に発言をしてみてもらえるチャンスを増やしましょう。
しかし、発言が議題から逸れたものではいけません。多く意見することは大切ですが、同じく質も大切な評価のポイントとなります。発言するときは以下のことを意識しましょう。
- 自分の意見がまとまってから完結に喋る
- ハキハキ伝わる声で喋る
- アイディアを言うときは理由もセットで言おう
- 相手が発言中は割って喋らない
- だらだら喋らない
コツ②:他の人の意見には肯定から入る
初めてのグループディスカッション(GD)のコツ2つ目は、「他の人の意見には肯定から入る」です。
自分の意見ばかりでは、協調性がないと思われてしまいます。自分の意見と違った意見でもすぐに否定せずに最後まで聞きましょう。そして一度受け入れてから、自分の意見を言ったり他の人に意見を求めるようにしましょう。
また議論の中で熱くなってしまって相手を論破してしまったと言うことにならないようにしましょう。グループディスカッション(GD)ではチームで結論を出すと言うことが大切です。
コツ③:何を議論しているのかをはっきりさせる
初めてのグループディスカッション(GD)のコツ3つ目は、「何を議論しているかをはっきりさせる」です。
議論が盛り上がってくるとついつい意見が出てすぎてしまい、論点がずれてしまうことがあります。そこで意識してほしいのが、今自分達は何を議論しているのかです。
論点がずれていると感じたら、チーム全体に何を議論しているかを確認するのも必要です。
初めてのグループディスカッション(GD)を乗り切るには、発言するときに「完結にまとめる」「何を話しているかを確認する」を意識することが重要です!
コツ④:アイデアをグルーピングする
初めてのグループディスカッション(GD)のコツ4つ目は、「アイデアをグルーピングする」です。
議論を活性化させるためには、まずアイデアを各自で自由に出す作業が必要です。
そしてアイデアがいくつか出たあと、議論をまとめるために名アイデアをグループ分けする作業が必要です。
例えば、
| 実現難易度が低い | 実現難易度が大きい |
| 実現した時のインパクトが低い | 実現した時のインパクトが大きい |
などの4グループに分けて進めていけば、お互いの認識のズレがなくなり、議論がスムーズに進められるようになります。
[say name="「就活の教科書」編集部 宮原" img="https://reashu.com/wp-content/uploads/2022/08/dc738463f32239f7a21b88417e40c76f-e1660833919652.jpg" from="right"]アイデアが分散しすぎると議論に収集が付かなくなるのでグルーピングして上手にまとめていく必要があります。 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
コツ⑤:議論が対立した時の決め方を決める
初めてのグループディスカッション(GD)のコツ5つ目は、「議論が対立した時の決め方を決める」です。
4人以上で議論を進めると必ず意見が対立するときがあります。
議論が対立してしまうと、
対立したときにモノゴトを判断する基準や、
どのように意見を決定していくのか、つまり「決め方の決め方」を決めておく必要があります。
例えば、
 就活生くん
就活生くん
などと判断軸をチームで共有していれば、無駄な時間を使わなくて済むので、グループディスカッションを効率よく進められるようになります。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
コツ⑥:結論から伝えることを意識する
初めてのグループディスカッション(GD)のコツ6つ目は、「結論から伝えることを意識する」です。
限られた短い時間の中で複数人で議論を進めていかなければなりません。
理由から話し、結論から伝えると、最終的に何が言いたいのかを全員が待たなければならないため、とても非効率です。
まずは、結論から伝え、理由は後から添えるようにしましょう。
ほかにも結論を伝えるときコツとしては、
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
よりも
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
と伝えるだけで何と比較してAなのかが一発で理解できるので説明コストも下がり議論がスムーズに進みます。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
以下の記事では、さらにグループディスカッション(GD)のコツについて解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
[/say]
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
(ミーツカンパニー)
企業がグループディスカッションを行う理由とは?
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
グループディスカッションがどのような選考項目なのか理解できました。
そして素の部分を引き出すということも理解できたのですが、なぜ企業はそこまでして積極的にグループディスカッションを導入するのでしょうか。
企業の目的は何なのでしょうか?
社会人になると仕事を一人で行うことはほとんどありません。
チームのメンバーやクライアントと共にコミュニケーションを取りながら最善策を考えていくケースが非常に多いです。
面接での受け答えや過去にやってきた経歴だけで仕事をうまく進めることは困難なので、入社前にグループディスカッションの選考を通じて能力を判断しているのです。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
本当にその通りです。
グループディスカッション対策は社会人になって活躍するための必要な要素がたくさん入っているので、ぜひ対策することをおすすめします。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
「グループディスカッションの対策何すれば良い?」「グループディスカッションに苦手意識がある」という就活生には、「ミーツカンパニー」の利用がおすすめです。

ミーツカンパニーでは、1日に2~8社の企業と少人数で話せるイベントに参加でき、イベント後は専属のアドバイザーが内定まで就活をサポートしてくれます。
イベントでは、企業と少人数で話せるだけではなく、グループワークの時間も設けられているなど、グループディスカッションの練習も行えます。
有名企業で実際に行ったグループディスカッションを体験できるだけではなく、その後選考サポートも受けられるので、ぜひ一度イベントに参加してみてくださいね。
\ 30秒でカンタン無料エントリー /
【完全解説】グループディスカッションの進め方
 就活生くん
就活生くん
グループディスカッションを選考としてやる意味が理解できました。
しかし、実はまだグループディスカッションを受けたことがないので、どのように進んでいくのかイメージできていません。
グループディスカッションの進め方について教えていただきたいです。
グループディスカッションの進め方には必ず同じ規則に従って進みます。
グループディスカッション以下の手順で進行していきます。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
- GDの進め方①:メンバーを名チームに振り分ける
- GDの進め方②:メンバーと軽く自己紹介をする
- GDの進め方③:面接官からGDについての説明
- GDの進め方④:GDのテーマが発表される
- GDの進め方⑤:メンバーの役割を決める
- GDの進め方⑥:課題に対するゴールと定義を決める
- GDの進め方⑦:時間配分を決める
- GDの進め方⑧:アイデアをブレストする
- GDの進め方⑨:方向性を決めアイデアを1つにする
- GDの進め方⑩:チームメンバー全体の結論を出す
- GDの進め方⑪:発表に向けて準備を行う
- GDの進め方⑫:発表する
- GDの進め方⑬:面接官からフィードバックをもらう
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GDの進め方①:メンバーを名チームに振り分ける
GDの進め方1つ目は「メンバーを名チームに振り分ける」です。
選考会場に着くと、面接官からすぐにチームメンバーのいるテーブルに案内されます。
そして名札とペンが用意されているので、自分の名前を書いて着席しましょう。
チームメンバーと顔合わせした時は元気よく挨拶をしましょう。
実は最初の挨拶は非常に大事です。
周りの就活生も緊張しているので、元気よく挨拶するだけで進行する上で有利になれます。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GDの進め方②:メンバーと軽く自己紹介をする
GDの進め方2つ目は「メンバーと軽く自己紹介をする」です。
グループディスカッションのチームメンバーはだいたい4人以上からが多いです。
名札に名前を書いたらすぐに挨拶をして笑顔で名前と大学名伝えて自己紹介をしましょう。
前提としてグループディスカッションはあくまでチーム戦です。
どれだけ良いアウトプットを出してもチームの雰囲気が悪いと面接官からの評価は最悪です。
面接を含む他の選考では、内定枠を奪い合う敵かもしれませんが、グループディスカッションにおいてはみんなで乗り切るものだと理解する必要があります。
自分だけ合格しようとするとチームとしての議論も最低なものになり、結果として選考に落ちる可能性が上がってしまいます。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GDの進め方③:面接官からGDについての説明
GDの進め方3つ目は「面接官からGDについての説明」です。
グループディスカッションをする上で、ルール、時間、注意点、発表の仕方などの説明が口頭であります。
グループディスカッションの選考でどのような点を評価しているのかを少しだけ教えてくれる企業もあるので、必ずメモをとって聞くようにしましょう。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GDの進め方④:GDのテーマが発表される
GDの進め方4つ目は「GDのテーマが発表される」です。
企業によって、グループディスカッションのテーマは毎回異なります。
そのため、あらかじめ予測することはできないので当日に初めてグループディスカッションのテーマを知ることになります。
しかしグループディスカッションのテーマは大きく5種類に分けられるのであらかじめ対策することができます。
- 抽象的テーマ型グループディスカッション
- 課題解決型グループディスカッション
- 資料読取型グループディスカッション
- ディベート型グループディスカッション
- その他特殊型グループディスカッション
名それぞれの対策方法については後半で説明します。
気になる方は後半の部分も合わせて読んでください。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GDの進め方⑤:メンバーの役割を決める
GDの進め方5つ目は「メンバー役割を決める」です。
グループディスカッションが開始したらすぐに、議論を効率よく進めるために役割分担をしましょう。
大まかな役割としては、ファシリテーター(進行役)、書記(議論を文字にまとめる人)、タイムキーパー(時間管理をする人)などがあります。
チームメンバーの適性をを見たときに自分が一番力を発揮できそうな役割を選びましょう。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GDの進め方⑥:課題に対するゴールと定義を決める
GDの進め方6つ目は「課題に対するゴールと定義を決める」です。
ゴールと定義を決めると聞くと難しそうに聞こえますが、非常に簡単なので、安心してください。
具体例とともに説明していきます。
仮に「世の中にまだない新規事業を生み出してください。」というグループディスカッションのテーマがあったとします。
ここで、まずはメンバーの共通認識としてゴールを設定してください。
例えば、
・「新規事業を生み出す=大衆向けにみんなが使いそうなサービスを作るのか」
・「新規事業を生み出す=使う人は少数でも良いのでとにかく刺さるサービスを作るのか」
・「新規事業を生み出す=サービス内容よりもとにかく収益目的で作るのか」
など名チームで議論のゴールを決めなければなりません。
ゴールを決めることによって、チームの方向性が決まり、議論がスムーズに進められるようになります。
そして二つ目が定義を決めるです。
例えば、「とにかく収益目的のサービスを作る」をゴールと決めた場合に、どれだけ収益が上がれば達成なのかを定義して決めなければなりません。
1億円売り上げることが収益達成なのか、1グループディスカッショングループディスカッショングループディスカッション億円売り上げることが達成なのかで議論の進め方も変わってくるはずです。
定義をしっかりと決めることによって、お互いに認識のズレがなくなり議論を進められるようになるので必ず定義づけをしていきましょう。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GDの進め方⑦:時間配分を決める
GDの進め方7つ目は「時間配分を決める」です。
グループディスカッションには必ず時間制限があります。
そして短い時間でその日、初対面の学生同士で議論を進めて良い結論(アウトプット)を出さなければなりません。
そのため、「いつまでに何を決定するのか」を必ず決めて議論を進行しないければなりません。
時間に間に合わなくて、上手くまとまらずに発表しないといけなかった。というのは絶対に避けましょう。
ゴールを決めて何を話すべきか決まったら、
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
などと声をかけてチームに時間配分を共有するよう意識しましょう。
GDの進め方⑧:アイデアをブレストする
GDの進め方8つ目は「アイデアをブレストする」です。
議論のゴールを決めて時間も決まったらとにかくアイデアをブレストしましょう。
ここで大事なのは、とにかく相手の意見を否定せずに、一旦意見をとにかく多く出し合うことです。
相手の意見を根拠なして否定しすぎると、議論がまとまらずにチームの進行を壊してしまう恐れがあります。
グループディスカッションの一番の成功例はチームで議論を活発に起こし、たくさんのアウトプットを出すことです。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GDの進め方⑨:方向性を決めアイデアを1つにする
GDの進め方9つ目は「方向性を決めアイデアを1つにする」です。
時間制限の5分前にはチームで出した結論を1つにまとめる準備をしましょう。
どれだけ良いアイデアが出ても、最終的に発表するのは1つです。
しっかりと発表する内容を明確にしておくまとめておく必要があります。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GDの進め方⑩:チームメンバー全体の結論を出す
GDの進め方1グループディスカッションつ目は「チームメンバー全体の結論を出す」です。
質の高い議論を進めて行けば行くほど、全員が完璧に納得する結論を出すのはほぼ不可能です。
このチームは何を基準にこの結論を決定したのかという過程(プロセス)が大切です。
なぜこの結論に至ったのですか?と面接官に質問されてもしっかりと答えられるように準備しておきましょう。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GDの進め方⑪:発表に向けて準備を行う
GDの進め方11つ目は「発表に向けて準備を行う」です。
チームの代表者が一人で話すのか、それぞれのポイントをメンバーごとに分けて話すのかを決めましょう。
話す内容が決まったら、面接官に深堀りの質問が飛んできそうな部分を予測して回答を考えておきましょう。
例えば、
- 「なぜその結論になったのですか?」
- 「他に迷った選択肢は何ですか?」
- 「議論していて詰まった部分は何ですか?」
などが予測される質問です。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GDの進め方⑫:発表する
GDの進め方12つ目は「発表する」です。
発表するときはPREP法を意識して話しましょう。
PREPとは論理的に話すための手順方法です。
PREP法
- 結論(Point)
- 理由(Reason)
- 具体例(Example)
- 結論(Point)
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GDの進め方⑬:面接官からフィードバックをもらう
GDの進め方13つ目は「面接官からフィードバックをもらう」です。
チームでグループディスカッションのお題についてプレゼンした後、人事からのフィードバックがあります。
フィードバックを聞いている時の姿勢も面接官は見ているので真摯に取り組みましょう。
面接官のフィードバックに納得がいかなかったとしても、素直に受け止めることを意識してください。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
(ミーツカンパニー)
グループディスカッション対策【5タイプ】
グループディスカッションでは、頻出のテーマのタイプが5つあります。
事前にグループディスカッションのテーマの種類を把握して対策することによって、通過率はグッと上がります。
グループディスカッションのテーマのタイプは以下の5つです。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
- GD種類①:抽象的テーマ型グループディスカッション対策
- GD種類②: 課題解決型グループディスカッション対策
- GD種類③: 資料読取型グループディスカッション対策
- GD種類④: ディベート型グループディスカッション対策
- GD種類⑤: その他特殊型グループディスカッション対策
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GD種類①:抽象的テーマ型グループディスカッション対策
グループディスカッション対策1つ目のテーマは「抽象的テーマ型グループディスカッション」です。
抽象的なテーマをもとに、学生同士で意見を出し合って1つの結論を決めるタイプのグループディスカッションです。
テーマが抽象的だと、正解がないため、誰もがすぐに意見を出しやすいので、結論がまとまりきらずに、アイデアだけが出て、根拠の薄い議論になりがちのテーマです。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
このグループディスカッションでは、とにかく「定義付け」を徹底して意識しましょう。
議論をする上で、「まずはお互いに意見を出し合いましょう」という風に進めてしまいがちなのですが、このアプローチは絶対にやってはいけません。
なぜならば、抽象的なテーマだからこそ、お互いの意見が一致することはほぼ不可能だからです。
そのため、「平和というのはどのような状況をさすのか?」「逆に平和ではない状況とはどのような状態なのか?」というようにまずは、「平和」に関して定義づけを行いましょう。
そして、自分たちなりに定義づけが完了したら、次は色を決めていきましょう。
ここで大事なのは、とにかく結論を出すことです。
最終的な結論がないと、時間管理ができないチームだと思われてしまい、面接官から評価が下がってしまいます。
そしてとにかく意識することは、結論よりも過程です。
「定義づけを行い、結論に行き着く」この具体と抽象を行き来することがこのテーマの議論においては非常に大事な考え方です。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GD種類②: 課題解決型グループディスカッション対策
グループディスカッション対策2つ目のテーマは「課題解決型グループディスカッション」です。
課題が与えられ、その課題に対して解決策を考えていくタイプのグループディスカッションです。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
このグループディスカッションで大事なのは、「定義づけ」と「現状の分析」の二つを意識することです。
まず、最初に「広める」というのはどのような状態をさすのかを定義づけしましょう。
例えば・・・
- 「広める=世界中の人々の選択肢に麦茶が入るようにする」
- 「広める=日本の若い世代の5人に1人が麦茶を持ち歩いている状況を作る」
- 「広める=麦茶の文化がない国で麦茶が当たり前のように飲まれるようになる」
このように、「広めるってどこまでのことを指すの?」を定義することによって、議論が円滑に進むようになります。
そして次に、現状を分析し、なぜ「ある国では麦茶の文化がないのか」など広まっていない現状がおきている原因を追求するようにしていきましょう。
定義づけをして現状を分析し、最終的にどのような状態になっていたいのかをチームで意見を出し合います。
解決策を考える上で、実現可能性が高い低いは一旦考えずに議論を進めていきましょう。
議論を進めていく上で、「どうすれば実現できるのか?」を考えて結論を出していくことが大切です。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GD種類③: 資料読取型グループディスカッション対策
グループディスカッション対策3つ目のテーマは「資料読取型グループディスカッション」です。
このグループディスカッションのテーマの特徴は、解決策を述べる上での根拠が資料にあるということです。
アイデアや仮説ベースでの話だけではなく、資料の中の事実から何が課題かを読み取り、議論を進めなければならないため、数字を正確に読み取る能力が必要とされます。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
このタイプのグループディスカッションを進めていく上で、有効な手順は以下です。
- 前提の確認
- 現状の分析
- 原因の特定
- アイデアを考える
- アイデアを選ぶ
- 結論
このグループディスカッションのポイントは、資料から正確に情報を読み取ることです。
他のテーマのグループディスカッションでは、定義づけを自分たちで行い、自分たちなりの回答を出すことができれば、評価されます。
しかし、資料がある以上事実ベースで議論を進めていくことが必要です。
事実が記載されている資料があるため、周りを引っ張るコミュニケーション能力や、姿勢などの「人柄」ではなく、正解を導き出すための論理的な思考能力や仮説構築力のような「能力」が評価されます。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GD種類④: ディベート型グループディスカッション対策
グループディスカッション対策4つ目のテーマは「ディベート型グループディスカッション」です。
このタイプのグループディスカッションでは、賛成/反対の立場が明確に分かれて議論を進めていくことになります。
自分なりの根拠と理由をしっかりと論理的に相手に伝える必要性があります。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
このタイプのグループディスカッションで大事なのは、「議論が分かれた時の判断基準を作っておく」ことです。
判断基準を作っておくことで、明確な根拠のもと、議論を進めることができます。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GD種類⑤: その他特殊型グループディスカッション対策
グループディスカッション対策5つ目のテーマは「その他特殊型グループディスカッション」です。
実際にで出題されたテーマは以下の通りです。
【例題】
- 新宿にある全ての映画館の年間売上はいくらでしょうか?
- 携帯を持っている日本人は何人?
- あなたは今、世界で何番目に若い?
- 日本で昨年1年間に消費された割り箸の本数は?
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
「グループディスカッションの対策何すれば良い?」「グループディスカッションに苦手意識がある」という就活生には、「ミーツカンパニー」の利用がおすすめです。

ミーツカンパニーでは、1日に2~8社の企業と少人数で話せるイベントに参加でき、イベント後は専属のアドバイザーが内定まで就活をサポートしてくれます。
イベントでは、企業と少人数で話せるだけではなく、グループワークの時間も設けられているなど、グループディスカッションの練習も行えます。
有名企業で実際に行ったグループディスカッションを体験できるだけではなく、その後選考サポートも受けられるので、ぜひ一度イベントに参加してみてくださいね。
\ 30秒でカンタン無料エントリー /
グループディスカッションの練習方法
グループディスカッションはとにかく慣れることが必要です。
どれだけ頭の中で対策しても、いざ当日本番に見知らぬ学生同士で力を発揮するのは困難です。
グループディスカッションの具体的な対策と練習方法は以下の5つです。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
- GD練習方法①:模擬グループディスカッションに参加する
- GD練習方法②:就活生同士でグループディスカッションの練習する
- GD練習方法③:グループディスカッションに関する本を読む
- GD練習方法④:早期選考のグループディスカッションをたくさん受けて慣れる
- GD練習方法⑤:普段からニュースや新聞を読んで関心をもつ
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GD練習方法①:模擬グループディスカッションに参加する
グループディスカッションの練習方法1つ目は「模擬グループディスカッションに参加する」です。
就活生の選考対策として、実は、模擬グループディスカッションを無料で行なっている就活イベントを運営している会社はたくさんあります。
例えば、株式会社DYMが運営するMeets Company(ミーツカンパニー)というイベントが非常におすすめです。
模擬グループディスカッションに参加すると、必ず社会人の方からフィードバックもくれるので、ぜひ、積極的に参加して役立ててみてください。
下記の記事では、本当におすすめできるグループディスカッションイベントを厳選して紹介しています。
ぜひ、参加して他の就活生と差をつけたいという方は合わせて読んでみてください。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
⇒グループディスカッションイベントおすすめ5選 準備中
GD練習方法②:就活生同士でグループディスカッションの練習する
グループディスカッションの練習方法2つ目は「就活生同士でグループディスカッションの練習する」です。
就活友達やイベントで出会った就活生に声をかけて、4人以上のメンバーで制限時間内に議論してみましょう。
普段から仲の良い友達同士でグループディスカッションをすると、つい楽しい談笑で終わってしまうので、緊張感の持てるメンバーでやりましょう。
終了後は、お互いにフィードバックをしていきましょう。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GD練習方法③:グループディスカッションに関する本を読む
グループディスカッションの練習方法3つ目は「グループディスカッションに関する本を読む」です。
グループディスカッションで他の就活生と差をつけて面接官から評価されるためには、「ロジカルシンキング」が必要です。
「ロジカルシンキング」とは、物事を要素別にグルーピングし、一貫性のある道筋を建てていく思考法です。
社会人になると、「ロジカルシンキング」は当たり前のように求められるものなので、学生時代から関連する書籍を必ず1冊は読んでおくことをおすすめします。
ロジカルシンキングでオススメの本は以下です。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
⇒ロジカルシンキングの鍛え方 準備中
GD練習方法④:早期選考のグループディスカッションをたくさん受けて慣れる
グループディスカッションの練習方法4つ目は「早期選考のグループディスカッションをたくさん受けて慣れる」です。
ベンチャー企業や外資系企業では、サマーインターン含め早期選考を行なっている企業が多数存在します。
とにかく数をこなしてグループディスカッションの選考に慣れていきましょう
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GD練習方法⑤:普段からニュースや新聞を読んで関心をもつ
グループディスカッションの練習方法5つ目は「普段からニュースや新聞を読んで関心をもつ」です。
意見が分かれるニュースに対して、自分なりの考えや意見を普段から持つようにクセづけましょう。
普段から訓練しておくことで、自分の引き出しが増え、グループディスカッションの場でも、力を発揮することができます。
具体的な対策としては、TwitterやNewsPicks(ニューズピックス)を利用して他人の意見を取り入れながら、自分の意見を考えるクセをつけましょう。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
(ミーツカンパニー)
グループディスカッションに落ちる人の特徴
 就活生くん
就活生くん
よかったです。
合わせて、グループディスカッションに落ちる人の特徴について解説するのでぜひ当てはまっていない確認してみてください。
グループディスカッションに落ちる人の特徴は以下の3つです。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
- GDに落ちる人の特徴①:すぐに相手の意見を否定する人
- GDに落ちる人の特徴②:極端な同調をする人
- GDに落ちる人の特徴③:自分の意見を全く主張しない人
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GDに落ちる人の特徴①:すぐに相手の意見を否定する人
GDに落ちる人の特徴1つ目は「すぐに相手の意見を否定する人」です。
グループディスカッションで一番大切なのは、議論を活性化させチームで良い結論を導き出すことです。
例えば、メンバーの1人が意見を述べた時に、直感的にすぐに否定するのではなくて
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
- 「なぜそれが良いと思ったのですか?」
- 「何と比較してそれを選んだのですか?」
- 「その施策のデメリットは何ですか?」
と、相手の意見をさらに引き出すように努力しましょう。
すぐに意見を否定すると、あなたにしっかりとした根拠がない限り、面接官に悪い印象を与えてしまうので避けましょう。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GDに落ちる人の特徴②:極端な同調をする人
GDに落ちる人の特徴2つ目は「極端な同調をする人」です。
意見を否定せずに、賛成することは議論を進めていく上で決して悪いことではありません。
しかし、根拠なしに、良さそうな意見ばかりに同調していては、受け身な態度で挑んでいると面接官に思われて評価を下げてしまいます。
賛成するときは、しっかりとした根拠を述べて賛成しましょう。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
GDに落ちる人の特徴③:自分の意見を全く主張しない人
GDに落ちる人の特徴3つ目は「自分の意見を全く主張しない人」です。
グループディスカッションにおいて一番やってはいけないのが全く意見を主張しない行為です。
グループディスカッションはあくまで選考であるため、何も発言しないと面接官も評価することができないため自動的に選考に落ちてしまいます。
勇気を出してしっかりと発言するようにしましょう。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
「グループディスカッションの対策何すれば良い?」「グループディスカッションに苦手意識がある」という就活生には、「ミーツカンパニー」の利用がおすすめです。

ミーツカンパニーでは、1日に2~8社の企業と少人数で話せるイベントに参加でき、イベント後は専属のアドバイザーが内定まで就活をサポートしてくれます。
イベントでは、企業と少人数で話せるだけではなく、グループワークの時間も設けられているなど、グループディスカッションの練習も行えます。
有名企業で実際に行ったグループディスカッションを体験できるだけではなく、その後選考サポートも受けられるので、ぜひ一度イベントに参加してみてくださいね。
\ 30秒でカンタン無料エントリー /
グループディスカッション(GD)に関するよくある質問
 就活生くん
就活生くん
グループディスカッション(GD)について知ることができました。
他にもグループディスカッション(GD)について知っておくべきことがあれば、教えてください!
それでは、グループディスカッション(GD)に関するよくある質問3つを解説しますね!
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
質問①:司会進行役が一番評価されるの?
グループディスカッション(GD)に関するよくある質問1つ目は、「司会進行役が一番評価されるの?」です。
結論から言うと、良くも悪くも目立つため評価の対象となりやすいです。
先述した通り、司会進行は判断力や周りの人を見る力が必要となるので立ち回りが難しい役職となっています。
そして他の役職よりも話す機会が多いので、他の役職より目立ちリーダシップをアピールすることはできるのですが、うまく回すことができないと悪目立ちしてしまいます。
しかし、うまくグループディスカッション(GD)を回すことができれば、企業に自分をアピールすることができます。
質問②:グループディスカッション(GD)のクラッシャーとは?
グループディスカッション(GD)に関するよくある質問2つ目は、「グループディスカッション(GD)のクラッシャーとは?」です。
グループディスカッション(GD)のクラッシャーとは、自己中心的な態度で進行を妨げ、場を乱す人のことを指します。
協力して話すことが必要なグループディスカッション(GD)において、「全く発言しない」「自己主張が激しく意見を言う好きを与えない」などの行動をとる人は、クラッシャーと言っていいでしょう。
クラッシャーを制御しないとチーム全体の評価が下がってしまう可能性があります。なのでクラッシャーに飲まれないように対処することが必要です。
以下がクラッシャーの対処法です。
- 自己主張が強いクラッシャーの場合:否定せずに褒めて、違う人に意見を求める
- 相手の意見を否定する場合:なぜそう思うのかを聞く
- 全く発言しない場合:発言できるような声かけを促す
質問③:グループディスカッション(GD)の通過率はどれくらい?
グループディスカッション(GD)に関するよくある質問3つ目は、「グループディスカッション(GD)の通過率はどれくらい?」です。
グループディスカッションの通過率は、企業によってバラバラです。
ほとんどの就活生がグループディスカッション(GD)を通過できる場合や50%ほど通過する場合もあります。
どれくらい落ちるなど正しい情報がないので、通過率は気にしなくても良いと言えるでしょう。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
(ミーツカンパニー)
まとめ:流れと役割を理解して、初めてのグループディスカッション(GD)を攻略しよう
本記事はいかがでしたか?
少しでも初めてのグループディスカッション(GD)で不安を感じている方の力になれれば幸いです。
 「就活の教科書」編集部 宮原
「就活の教科書」編集部 宮原
本記事では、「グループディスカッション(GD)」を中心に解説しました。
合わせて、「グループディスカッション(GD)の流れ」「グループディスカッション(GD)を攻略するためのコツ」なども解説しました。
初めてのグループディスカッション(GD)では、自分の向いている役割を複数見つけておくことや5つ流れを意識して行うことが重要でしたね。
初めてのグループディスカッション(GD)では、不安が多いと思いますが本記事で紹介したコツを押さえて準備して挑みましょう。
以下に本記事をまとめたので、ぜひ参考にしてください。
◆【ざっくり解説】グループディスカッション(GD)とは
- グループディスカッション(GD)は選考序盤で実施されやすい
- 「チームの中でどのように振る舞うか」を評価している
- グループディスカッション(GD)で企業が見ている評価ポイントは4つ
◆【初めてでも大丈夫】グループディスカッション(GD)の5つの流れ
- ①:役割・時間配分を決める
- ②:前提を確認する
- ③:アイディアを出し合う
- ④:議論をまとめる
- ⑤:発表する
◆グループディスカッション(GD)の5つの役割を解説
- 役割①:司会進行
- 役割②:書記
- 役割③:タイムキーパー
- 役割④:発表者
- 役割⑤:役職なし
◆初めてのグループディスカッション(GD)を攻略する3つのコツ
- 前提:チームとしての成果を最優先する
- コツ①:積極的に発言をする
- コツ②:他の人の意見には肯定から入る
- コツ③:何を議論しているのかをはっきりさせる
◆グループディスカッション(GD)に関するよくある質問
- 質問①:司会進行役が一番評価されるの?
- 質問②:グループディスカッション(GD)のクラッシャーとは?
- 質問③:グループディスカッション(GD)の通過率はどれくらい?
◆まとめ:流れと役割を理解して、初めてのグループディスカッション(GD)を攻略しよう