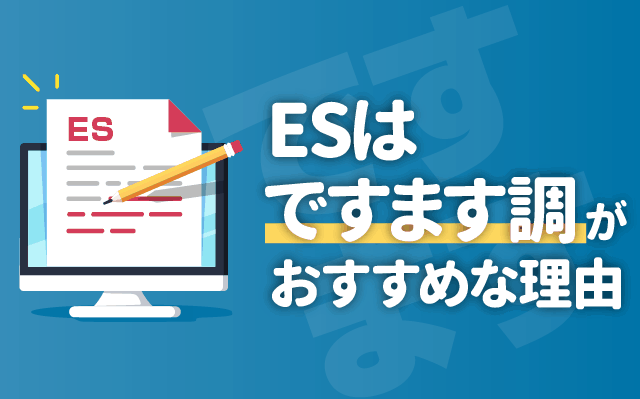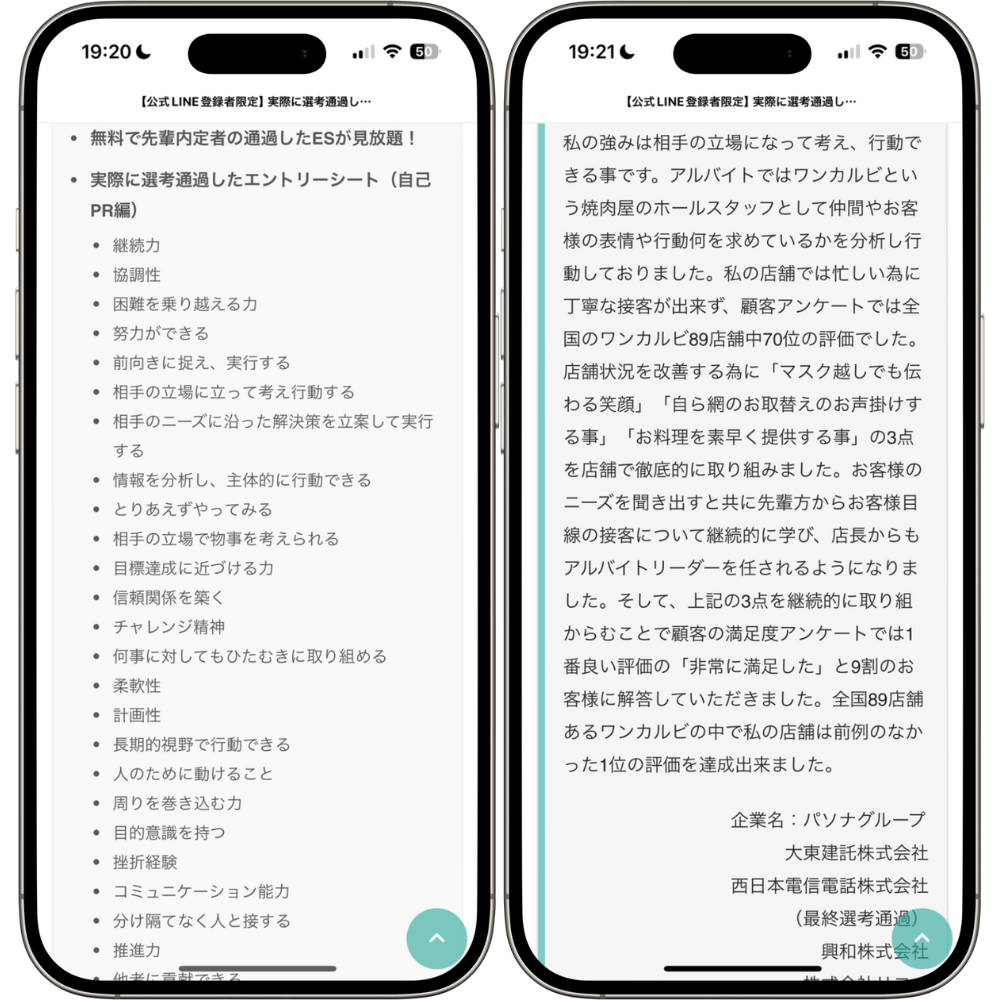- エントリーシートは「ですます調」がおすすめ
- エントリーシートで「ですます調」がおすすめな理由
- エントリーシートを「ですます調」で書いた場合のメリット・デメリット
- エントリーシートを「である調」で書いた場合のメリット・デメリット
- エントリーシートの「ですます調・である調」を使い分けるポイント
-
【就活生】選考に通過するESを作成したい人におすすめのツール(LINEで無料配布)
-
選考通過ES
(無料で100枚以上の選考通過したESが見放題) -
適性診断AnalyzeU+(251問の性格診断)
(251問の詳しい性格診断があり、こまめにログインすると特別招待がくることも) -
ES作成AIツール
(人事から高評価なESをAIが自動作成) -
ES添削AIツール
(たった数分で今あるESが選考突破レベルに仕上がる)
-
選考通過ES
-
【就活生/転職者】自分に合った優良企業に就職したい人におすすめの便利ツール(LINEで無料配布)
-
面接回答集100選
(よく出る質問と模範回答で面接対策) -
SPI頻出問題集
(SPI/Webテストの問題練習) -
適職診断
(あなたの適職を16タイプで診断) -
AI業界診断ツール
(自分に向いている業界を高性能AIが自動診断) -
隠れホワイト企業500選
(無理せず入社できる優良企業が見放題)
-
面接回答集100選
こんにちは、「就活の教科書」編集部の小渕です。
この記事では、エントリーシートの口調は、ですます調・である調のどちらが良いかについて解説していきます。
就活生のみなさんはエントリーシートをですます調・である調のどちらを使うかで迷ったことはありませんか?
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
 就活生くん
就活生くん
僕はですます調を使うことが多いです。
エントリーシートはでですます調・である調のどちらかを使ったほうがいいとか、正解はあるのでしょうか?
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
私もですます調でエントリーシートを書いていますが、友達はである調で書いていました。
エントリーシートの口調をですます調にするか、である調にするか、使い分けのポイントはあるのでしょうか。
エントリーシートの口調をですます調にするか、である調にするかは、悩みどころですよね。
ですます調か、である調かによって、エントリーシートの印象が変わりますからね。
ちなみに、「志望企業のESで落ちたくない!」という方は、難関企業内定者のESが無料で見れる「選考通過ES(公式LINEで無料配布)」などのサービスを活用しましょう。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
そこでこの記事では、エントリーシートの口調で迷ったら「ですます調」がおすすめな理由を3つご紹介します。
合わせて、エントリーシートをですます・である調で書くメリット・デメリット、使い分けポイント3つについて解説していきます。
この記事を読めば、エントリーシートの口調を、ですます調とである調のどちらにするか、状況に合わせて選べるようになりますよ。
エントリーシートの口調をですます調にするか悩んでいる方や、適切な口調でエントリーシートを仕上げて書類選考を通過したい方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
ES通過に役立つおすすめサービス(無料)
| 選考通過ES |
|---|

公式LINEで無料見放題 |
| ES作成AIツール |
|---|
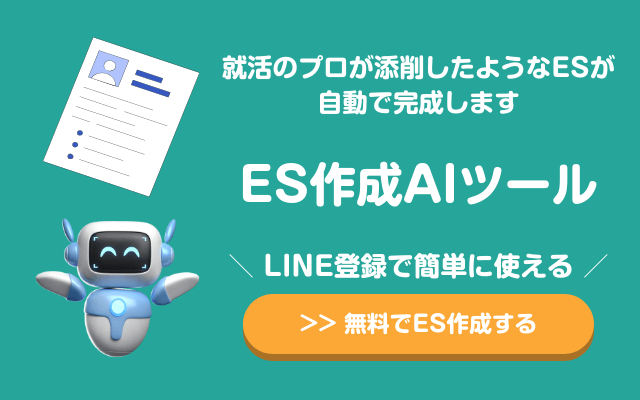
公式LINEで無料作成 |
| ES添削AIツール |
|---|
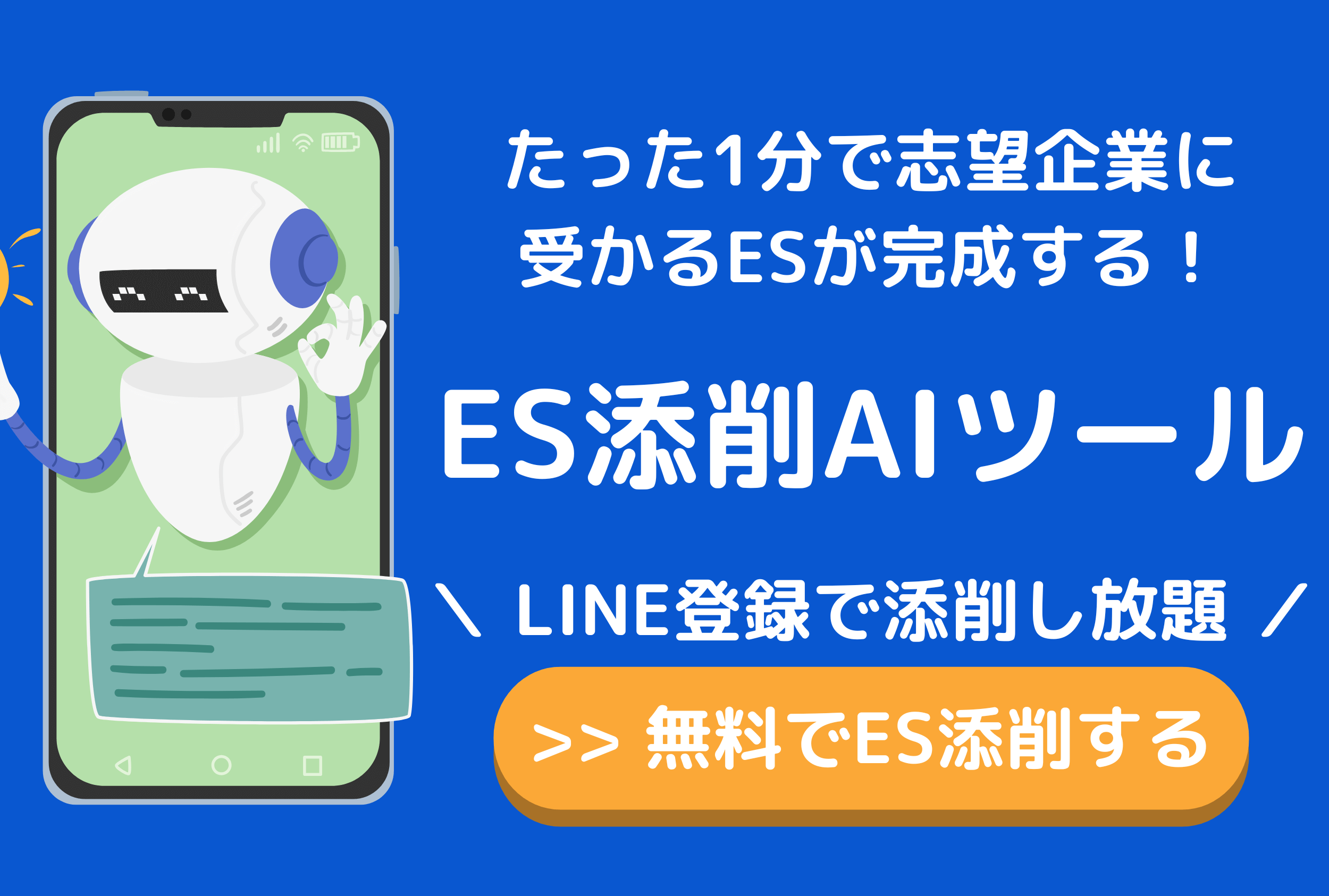
公式LINEで無料添削 |
【無料登録】就活/転職でおすすめツール
| 適性検査AnalyzeU+ |
|---|

全251問、客観的な性格診断 |
| キャリアチケット就職エージェント |
|---|
| 面接回答集100選 |
|---|

公式LINEで無料配布 |
| SPI頻出問題集 |
|---|

公式LINEで無料配布 |
「結局どのサービスを使えば良いかわからない…」という方は、「選考通過ES(公式LINEで無料見放題)」が一番おすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
目次
【ですます調/である調】エントリーシートの口調はどちらがいいの?
 就活生くん
就活生くん
エントリーシートの口調は、ですます調とである調のどちらを使うのがいいのでしょうか?
初めてエントリーシートを書くとなると、口調も気になりますよね。
そこで、「ですます調」と「である調」のどちらがいいのかについて解説していきます。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
【結論】「ですます調」「である調」のどちらでも問題ない
結論としては、「ですます調」「である調」のどちらでも問題ありません。
大切なのは、語尾の統一です。
「ですます調」と「である調」が混在しているエントリーシートは良くありません。
語尾を統一すれば、どちらの口調でも問題ないです。
個人的には「ですます調」がおすすめ
エントリーシートの口調は、個人的にはですます調をおすすめします。
しかし、エントリーシートの口調が、書類選考の結果を直接左右するわけではないので、である調でも大丈夫です。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
エントリーシートの合否を決めるのは、ですます調・である調のどちらを使っているかではなく、あくまでも書いている内容ということですね。
エントリーシートの口調はですます調・である調のどちらも、エントリーシート全体で口調を統一するようにしてください。
1枚のエントリーシート内で、ですます調・である調が混在していると、ちぐはぐした印象になりますし、読みにくくなるからです。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
 就活生くん
就活生くん
ですます調・である調が混在するエントリーシートは、マイナスの印象になってしまうということですね。
エントリーシート全体で口調を統一するように気をつけます!
「自分の強みがわからないからESが書けない…」「ESを書くのに時間がかかる…」など不安な方には、OfferBoxの無料適性検査「AnalyzeU+」の利用がおすすめです。
AnalyzeU+は、100万人のデータをもとにした正確さが推しの無料適性検査です。
メールアドレスだけで登録が完了し、正確な自己分析を受けられるので、まずは気軽に登録してみてください!
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香

- あなたの強みや個性が分かるため、短時間でESが作れる
- 診断結果をもとに、あなたの特性を活かせたガクチカも作れる
- 100万人のデータをもとにした正確さでESに活用できる
AnalyzeU+
また、ES添削については「【誰に頼むのが良い?】エントリーシート添削の無料サービスおすすめ15選 | ES添削の有料サイトも」という記事にまとめています。
この記事を読むと選考に通過するES添削をしてもらえます。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
エントリーシートの口調で迷ったら「ですます調」がおすすめな理由3つ
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
エントリーシートの口調で迷ったら「ですます調」がおすすめなのは、どうしてですか?
エントリーシートの口調で迷ったら「ですます調」がおすすめな理由は、3つあります。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
- 理由①:丁寧な印象になるから
- 理由②:敬語と併用しやすいから
- 理由③:一般的な口調で違和感がないから
それでは、エントリーシートの口調で迷ったら「ですます調」がおすすめな理由について、それぞれ詳しく解説していきます。
ですます調・である調のどちらでエントリーシートを書くか迷っている方は、読んで参考にしてみてくださいね。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
理由①:丁寧な印象になるから
エントリーシートの口調で迷ったら「ですます調」がおすすめな理由1つ目は、「丁寧な印象になるから」です。
である調に比べ、ですます調は礼儀正しく、丁寧な印象になります。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
私は一人の力ではなく、集団として最大の成果を目指すことに大きな喜びを感じます。
貴社の一員として、一人では挑戦できないようなグローバルな社会課題の解決に挑戦したいです。
私は一人の力ではなく、集団として最大の成果を目指すことに大きな喜びを感じる。
貴社の一員として、一人では挑戦できないようなグローバルな社会課題の解決に挑戦したい。
 就活生くん
就活生くん
である調も悪くないですが、エントリーシートは企業とのファーストコンタクトなので、ですます調で丁寧な印象を残すのが得策な気がしますね。
ですます調の方が、就活生らしくフレッシュで、企業への敬意も感じる文体になっていますよね。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
理由②:敬語と併用しやすいから
エントリーシートの口調で迷ったら「ですます調」がおすすめな理由2つ目は、「敬語と併用しやすいから」です。
エントリーシートは企業に提出する書類のため、敬語を使う方が違和感なく書けるという方は多いのではないでしょうか。
ですます調は敬語との相性が良く、書きやすいというメリットがあります。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
- ~という理由で、貴社を志望致しました。
- 以前貴社のインターンシップにお伺いした際、~な印象を受けました。
- お店にいらっしゃったお客様から、~という言葉をいただきました。
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
例文と同じ文章をである調で書こうとすると、何だか書きづらい感じがします。
企業の面接を受ける際には、敬語を使って、ですます調で話しますよね。
エントリーシートも、敬語とですます調を使った方が、企業に話をする感覚でスラスラ書けますよ。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
理由③:一般的な口調で違和感がないから
エントリーシートの口調で迷ったら「ですます調」がおすすめな理由3つ目は、「一般的な口調で違和感がないから」です。
私たちが普段目にする文章の多くは、ですます調で書かれていますよね。
ですます調は文章を書く上で一般的な口調なので、書き手にとっても読み手にとっても違和感がありません。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
 就活生くん
就活生くん
確かに一般的な書籍は、ですます調で書かれたものが多い気がします。
でも、新聞やネットニュース、論文は、である調で書かれたものが多いですよね。
新聞やネットニュース、論文は、個人の主観的な主張ではなく事実を述べるものなので、説得力を高めるために、である調が採用されています。
エントリーシートは、企業に自分をアピールするための個人の主観的な主張ですから、「ですます調がしっくりくる」と感じる人は多いはずです。
実際、大多数の学生は、エントリーシートをですます調で書いているんですよ。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
「ESが上手く書けない…」「ES選考で落ちてしまう…」なら、OfferBoxの無料適性診断 「AnalyzeU+」がおすすめです。
AnalyzeU+を使えば、簡単に自分の強みや個性がわかるようになるので、選考で落とされないエントリーシートを書けるようになります。
また実際に利用した就活生からは、「診断するだけでESに何を書けばいいかわからない...ということがなくなった!」などの口コミもいただいています。
ESで落ちる確率をかなり減らせるだけでなく、あなたにあった職種や役割もわかるので、まずは、無料簡単登録から自己分析をしてみてくださいね。
AnalyzeU+
エントリーシートで「ですます調」を使うメリット
 就活生くん
就活生くん
エントリーシートで「ですます調」を使うメリットについて詳しく教えてほしいです。
それでは次にエントリーシートで「ですます調」を使うメリットについて詳しく解説していきます。
エントリーシートで「ですます調」を使うメリットは以下の3つです。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
- メリット①:礼儀正しく感じる
- メリット②:文字数が稼げる
- メリット③:印象が悪くなるリスクが低い
メリット①:礼儀正しく感じる
エントリーシートで「ですます調」を使うメリット1つ目は、「礼儀正しく感じる」です。
ですますは丁寧語なので、であるよりもより丁寧に感じます。
メリット②:文字数が稼げる
エントリーシートで「ですます調」を使うメリット2つ目は、「文字数が稼げる」です。
「だ」よりも「です」の方が文字数が多いです。
また、「だと考える」よりも「だと考えます」の方が文字数が多いです。
小さな差ですが、多少ですます調の方が文字数を稼げます。
メリット③:印象が悪くなるリスクが低い
エントリーシートで「ですます調」を使うメリット3つ目は、「印象が悪くなるリスクが低い」です。
である調は読み手によってはきつい表現だと解釈する人もいます。
一方で、ですます調であれば、全員が違和感なく読むことができます。
よって、ですます調の方が印象が悪くなるリスクは低いと言えます。
ESの対策に悩んでいる人にオススメの記事一覧
「エントリーシートで落とされる…」という人は、まず、 自己分析をやり直してみましょう。
また、自己分析後の流れは以下記事で説明しています。
スムーズにES作成ができ就活が上手くいくので、合わせて読んでみてください。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
①自己分析をする
⇒自己分析ツール/アプリおすすめ41選
②企業研究をして企業の強みや求める人物像を知る
⇒企業分析の簡単なやり方7選
③ESに書く内容を決めて書く
⇒ESの書き方
⇒ES作成ツールおすすめ10選
⇒ES頻出質問100選
④添削してもらう
⇒ES添削の無料サービスおすすめ19選
「自分の強みがわからないからESが書けない…」「ESを書くのに時間がかかる…」など不安な方には、OfferBoxの無料適性検査「AnalyzeU+」の利用がおすすめです。
AnalyzeU+は、100万人のデータをもとにした正確さが推しの無料適性検査です。
メールアドレスだけで登録が完了し、正確な自己分析を受けられるので、まずは気軽に登録してみてください!
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香

- あなたの強みや個性が分かるため、短時間でESが作れる
- 診断結果をもとに、あなたの特性を活かせたガクチカも作れる
- 100万人のデータをもとにした正確さでESに活用できる
AnalyzeU+
また、ES添削については「【誰に頼むのが良い?】エントリーシート添削の無料サービスおすすめ15選 | ES添削の有料サイトも」という記事にまとめています。
この記事を読むと選考に通過するES添削をしてもらえます。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
エントリーシートで「ですます調」を使うデメリット
 就活生くん
就活生くん
次はエントリーシートで「ですます調」を使うデメリットについて詳しく教えてほしいです。
それでは次にエントリーシートで「ですます調」を使うデメリットについて詳しく解説していきます。
エントリーシートで「ですます調」を使うデメリットは以下の3つです。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
- デメリット①:リズムが単調になりやすい
- デメリット②:文章が長くなる
- デメリット③:アピール力が強くない
デメリット①:リズムが単調になりやすい
エントリーシートで「ですます調」を使うデメリット1つ目は、「リズムが単調になりやすい」です。
語尾が全て「です」であるとリズムが単調になります。
「です」と「ます」を交互に組み合わせるなどの工夫をしてリズムに変化を加えると良いでしょう。
デメリット②:文章が長くなる
エントリーシートで「ですます調」を使うデメリット2つ目は、「文章が長くなる」です。
文字数を稼ぎたい人にはメリットですが、書きたいことがたくさんある人にはデメリットになります。
デメリット③:アピール力が強くない
エントリーシートで「ですます調」を使うデメリット3つ目は、「アピール力が強くない」です。
語尾が「です」「ます」と単調になるため、アピール力は弱くなってしまいます。
しかし、他の就活生もですます調を使っている人が多いため、大きなマイナスにはなりません。
「ESが上手く書けない…」「ES選考で落ちてしまう…」なら、OfferBoxの無料適性診断 「AnalyzeU+」がおすすめです。
AnalyzeU+を使えば、簡単に自分の強みや個性がわかるようになるので、選考で落とされないエントリーシートを書けるようになります。
また実際に利用した就活生からは、「診断するだけでESに何を書けばいいかわからない...ということがなくなった!」などの口コミもいただいています。
ESで落ちる確率をかなり減らせるだけでなく、あなたにあった職種や役割もわかるので、まずは、無料簡単登録から自己分析をしてみてくださいね。
AnalyzeU+
エントリーシートで「である調」を使うメリット
 就活生くん
就活生くん
エントリーシートで「である調」を使うメリットについて詳しく教えてほしいです。
それでは次にエントリーシートで「である調」を使うメリットについて詳しく解説していきます。
エントリーシートで「である調」を使うメリットは以下の3つです。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
- メリット①:自信のある印象になる
- メリット②:文字数を節約できる
メリット①:自信のある印象になる
エントリーシートで「である調」を使うメリット1つ目は、「自信のある印象になる」です。
「ですます」よりも「である」の方が強い表現であり、自信がありそうな印象がありますよね。
就活生の多くがですます調を使うため、良くも悪くもである調のエントリーシートは目立ちます。
メリット②:文字数を節約できる
エントリーシートで「である調」を使うメリット2つ目は、「文字数を節約できる」です。
「ですます」よりも「である」の方が文字数が少なくて済みます。
そのため、書きたい内容がたくさんある場合には、である調を使った方が良いかもしれません。
「自分の強みがわからないからESが書けない…」「ESを書くのに時間がかかる…」など不安な方には、OfferBoxの無料適性検査「AnalyzeU+」の利用がおすすめです。
AnalyzeU+は、100万人のデータをもとにした正確さが推しの無料適性検査です。
メールアドレスだけで登録が完了し、正確な自己分析を受けられるので、まずは気軽に登録してみてください!
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香

- あなたの強みや個性が分かるため、短時間でESが作れる
- 診断結果をもとに、あなたの特性を活かせたガクチカも作れる
- 100万人のデータをもとにした正確さでESに活用できる
AnalyzeU+
また、ES添削については「【誰に頼むのが良い?】エントリーシート添削の無料サービスおすすめ15選 | ES添削の有料サイトも」という記事にまとめています。
この記事を読むと選考に通過するES添削をしてもらえます。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
エントリーシートで「である調」を使うデメリット
 就活生くん
就活生くん
次はエントリーシートで「である調」を使うデメリットについて詳しく教えてほしいです。
それでは次にエントリーシートで「である調」を使うデメリットについて詳しく解説していきます。
エントリーシートで「である調」を使うデメリットは以下の2つです。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
- デメリット①:上から目線に感じる
- デメリット②:文字数が少なくなる
デメリット①:上から目線に感じる
エントリーシートで「である調」を使うデメリット1つ目は、「上から目線に感じる」です。
である調はどうしても威圧感を与えてしまいます。
そのため、読み手によっては多少の違和感をおぼえてしまいます。
デメリット②:文字数が少なくなる
エントリーシートで「である調」を使うデメリット2つ目は、「文字数が少なくなる」です。
ですます調よりもである調は文字数が少なくなってしまいます。
よって、文字数を稼ぎたいという人にはデメリットになってしまいます。
「ESが上手く書けない…」「ES選考で落ちてしまう…」なら、OfferBoxの無料適性診断 「AnalyzeU+」がおすすめです。
AnalyzeU+を使えば、簡単に自分の強みや個性がわかるようになるので、選考で落とされないエントリーシートを書けるようになります。
また実際に利用した就活生からは、「診断するだけでESに何を書けばいいかわからない...ということがなくなった!」などの口コミもいただいています。
ESで落ちる確率をかなり減らせるだけでなく、あなたにあった職種や役割もわかるので、まずは、無料簡単登録から自己分析をしてみてくださいね。
AnalyzeU+
エントリーシートのですます・である調の使い分けポイント3つ
 就活生くん
就活生くん
エントリーシートで、ですます調・である調のメリットを上手く活かすには、どのような使い分けをすれば良いでしょうか。
エントリーシートのですます調・である調の使い分けのポイントは、3つあります。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
- ポイント①:文字数制限で使い分ける
- ポイント②:業界や業種で使い分ける
- ポイント③:企業に与えたい印象で使い分ける
それでは、エントリーシートのですます調・である調の使い分けのポイントについて、それぞれ詳しく解説していきます。
ですます調・である調の使い分け方がよくわからない方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
ポイント①:文字数制限で使い分ける
エントリーシートのですます・である調の使い分けのポイント1つ目は、「文字数制限で使い分ける」です。
エントリーシートの文章は、ですます調で書くと長くなり、である調で書くと短くなります。
この特徴を活かして、以下のように、エントリーシートの文字数制限によって使い分けるのがひとつの方法です。
- 制限されている文字数が少ない場合(目安:200文字未満)…である調
- 制限されている文字数が普通~多い場合(目安:200文字以上~)…ですます調
文字数制限が200文字未満など、かなり少ない文字数でまとめなければならない場合は、である調で文字数を節約すると良いです。
文字数制限が200文字以上の場合や、特に指定がない場合は、基本的にですます調でエントリーシートを書くことをおすすめします。
文字数を極力抑えて簡潔にまとめたいときは、である調が便利です。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
文字数制限が少ない場合のESを書きたい方は、以下の記事で、文章を短くまとめるコツを紹介しています。
合わせて読んでみてくださいね。
ポイント②:業界や業種で使い分ける
エントリーシートのですます・である調の使い分けのポイント2つ目は、「業界や業種で使い分ける」です。
エントリーシートを提出する業界や業種によっては、ですます調ではなく、である調が一般的に使われている場合があります。
- マスコミ
- コンサルティング
- 商社
上記のような業界では、である調でエントリーシートを書いても違和感がなく、むしろ説得力と自信のある口調が歓迎される可能性があります。
エントリーシートの提出先に合わせて、ですます調・である調を使い分けましょう。
エントリーシートで、ですます調・である調のどちらが一般的に使われているかは、ESの無料閲覧サービスで内定者のESをチェックするとわかりますよ。
ESの無料閲覧サービスについては、以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ読んでみてくださいね。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
ポイント③:企業に与えたい印象で使い分ける
エントリーシートのですます・である調の使い分けのポイント3つ目は、「企業に与えたい印象で使い分ける」です。
エントリーシートで企業にどんな印象を与えたいのかを考え、戦略的にですます調・である調を使い分ける方法があります。
例えば、対人スキルや人柄を強みとしてアピールする場合は、ですます調の丁寧な口調の方がふさわしいですよね。
一方で、推進力や人をまとめる力を強みとしてアピールする場合は、である調の自信に満ちた感じの方が、説得力が増します。
そのため、エントリーシートで企業にアピールしたい強みによって、ですます調・である調を使い分ければ、企業に与える印象をより強いものにできますよ。
ですます調・である調の使い分け次第で、企業が受ける印象は、多少変わります。
でも、エントリーシートで一番大切なのは口調よりも中身だということは、忘れないでくださいね。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
ESには「ですます調」以外にも、書き方で注意する点はたくさんあります。
ESでの空欄・空白や改行、訂正方法ついても知りたい人は、ESの通過率を上げる方法が分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
「自分の強みがわからないからESが書けない…」「ESを書くのに時間がかかる…」など不安な方には、OfferBoxの無料適性検査「AnalyzeU+」の利用がおすすめです。
AnalyzeU+は、100万人のデータをもとにした正確さが推しの無料適性検査です。
メールアドレスだけで登録が完了し、正確な自己分析を受けられるので、まずは気軽に登録してみてください!
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香

- あなたの強みや個性が分かるため、短時間でESが作れる
- 診断結果をもとに、あなたの特性を活かせたガクチカも作れる
- 100万人のデータをもとにした正確さでESに活用できる
AnalyzeU+
また、ES添削については「【誰に頼むのが良い?】エントリーシート添削の無料サービスおすすめ15選 | ES添削の有料サイトも」という記事にまとめています。
この記事を読むと選考に通過するES添削をしてもらえます。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
まとめ:ですます・である調を効果的に使い分け、選考を通過できるエントリーシートを書こう
エントリーシートの口調は、ですます調・である調のどちらを使っても間違いではありません。
もし迷うようなら、ですます調を使いましょう。
志望先やエントリーシートの文字数制限によって、使い分けするのもありです。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕
◆エントリーシート口調はですます・である調どちらで書いてもOK
◆1枚のエントリーシートの中で口調を統一する
◆エントリーシートの口調で迷ったら「ですます調」がおすすめな理由3つ
- 理由①:丁寧な印象になるから
- 理由②:敬語と併用しやすいから
- 理由③:一般的な口調で違和感がないから
◆エントリーシートをですます・である調で書いたときの印象
- ですます調:礼儀正しく丁寧な印象
- である調:自信に満ちた印象
◆ですます調のメリット
- メリット①:礼儀正しく感じる
- メリット②:文字数が稼げる
- メリット③:印象が悪くなるリスクが低い
◆ですます調のデメリット
- デメリット①:リズムが単調になりやすい
- デメリット②:文章が長くなる
- デメリット③:アピール力が強くない
◆である調のメリット
- メリット①:自信のある印象になる
- メリット②:文字数を節約できる
- メリット③:アピール力が強い
◆である調のデメリット
- デメリット①:上から目線に感じる
- デメリット②:親しみやすさに欠ける
- デメリット③:企業への敬意を表現しづらい
◆エントリーシートのですます・である調の使い分けポイント3つ
- ポイント①:文字数制限で使い分ける
- ポイント②:業界や業種で使い分ける
- ポイント③:企業に与えたい印象で使い分ける
◆志望先やエントリーシートの文字数制限によって、ですます調・である調を使い分けよう
「就活の教科書」では、エントリーシートの書き方のコツについても詳しく解説しています。
他の記事もぜひ読んでみてくださいね。
 「就活の教科書」編集部 小渕
「就活の教科書」編集部 小渕