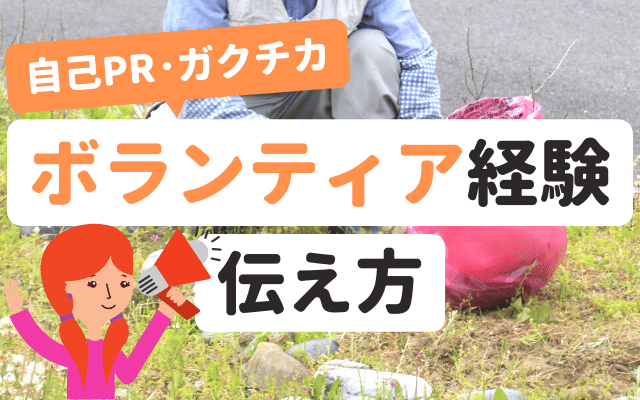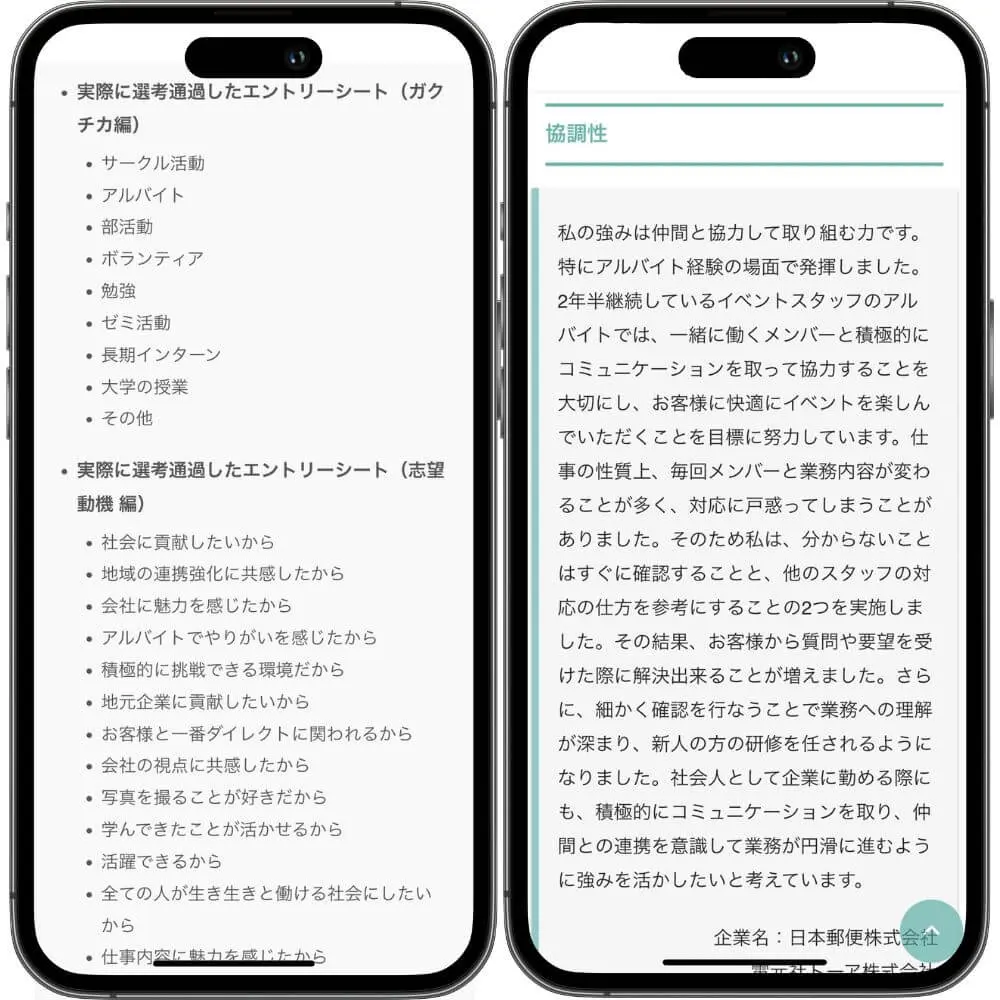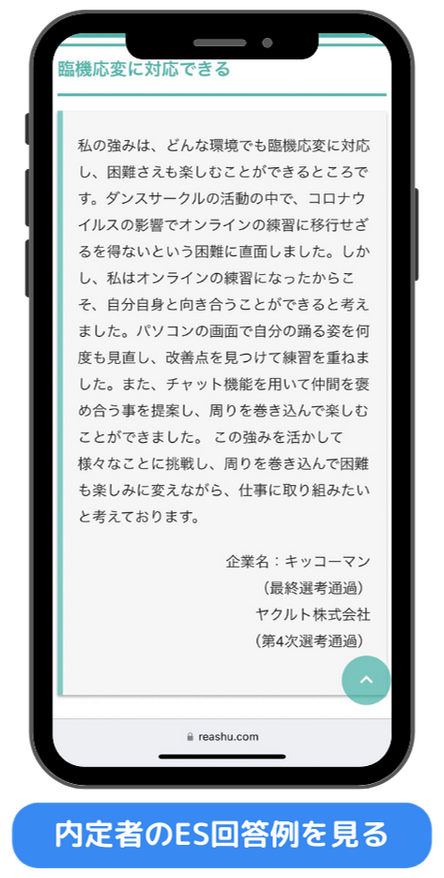- 「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝えた時に、面接官にネガティブに捉えられる点5つ
- 「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝える例文21選(地域活性化、学習支援、献血など)
- 「自己PR/ガクチカでボランティア」を魅力的に伝えるには、ボランティア前後のプロセスを伝えることが大切
- 「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝えるときは、目標を含めるように注意する
-
【就活生】選考通過するESを作成したい人がまず入れるべきツール(LINEで無料配布)
-
選考通過ES
(無料で100枚以上の選考通過したESが見放題) -
適性診断AnalyzeU+
(251問の詳しい性格診断。スカウト機能付き) -
ES作成AIツール
(人事から高評価なESをAIが自動作成) -
ES添削AIツール
(たった数分で今あるESが選考突破レベルに仕上がる)
-
選考通過ES
-
【就活生/転職者】自分に合った優良企業に就職したい人におすすめの便利ツール(LINEで無料配布)
-
面接回答集100選
(よく出る質問と模範回答で面接対策) -
SPI頻出問題集
(SPI/Webテストの問題練習) -
適職診断
(あなたの適職を16タイプで診断) -
AI業界診断ツール
(自分に向いている業界を高性能AIが自動診断) -
隠れホワイト企業500選(公式LINEで無料配布)
(無理せず入社できる優良企業が見放題)
-
面接回答集100選
この記事では、「ガクチカ/自己PRボランティア」を伝えることに悩んでいる人に、上手く伝えるコツや、やってはいけないことを解説します。
合わせて、「ガクチカでボランティア」を伝える例文や就活生が「ガクチカでボランティア」を伝えた時に、面接官の感じることも紹介しています。
ちなみに、「志望企業のESで落ちたくない!」という方は、難関企業内定者のESが無料で見れる「選考通過ES(公式LINEで無料配布)」などのサービスを活用しましょう。
- ガクチカでボランティアについて伝えたいけど伝え方がわからない・・・
- そもそもガクチカでボランティア経験について使ってもいいの?
- ガクチカでボランティアのついて伝えるときのコツを知りたい
この記事を読めば、上記のような「ガクチカでボランティア」を伝えることについての悩みを解決でき、安心して選考に臨めるようになります。
ぜひ最後まで読んでくださいね。
ES通過に役立つおすすめサービス(無料)
| 選考通過ES |
|---|

公式LINEで無料見放題 |
| ES作成AIツール |
|---|
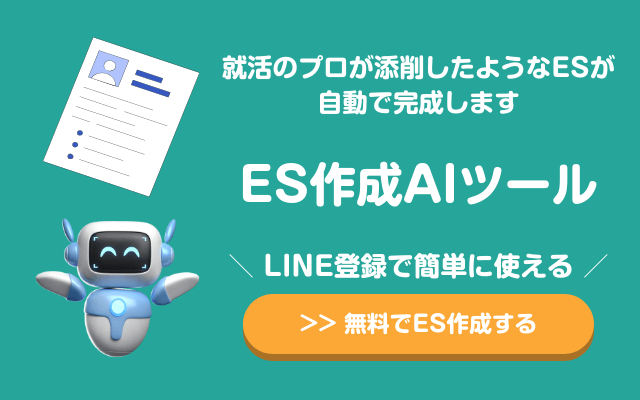
公式LINEで無料作成 |
| ES添削AIツール |
|---|
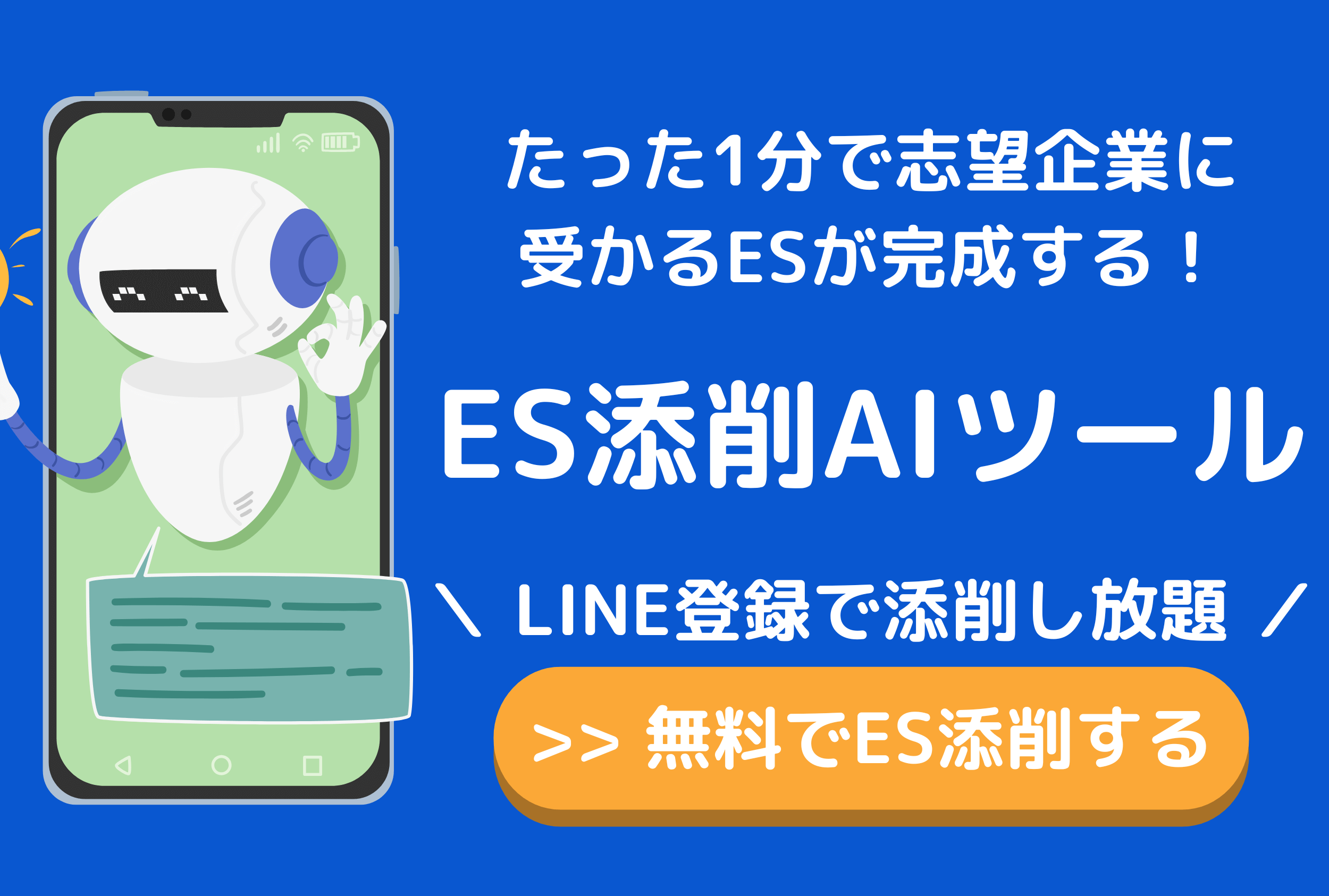
公式LINEで無料添削 |
【無料登録】就活/転職でおすすめツール
| 適性検査AnalyzeU+ |
|---|

全251問、客観的な性格診断 |
| キャリアチケット就職エージェント |
|---|
| 面接回答集100選 |
|---|

公式LINEで無料配布 |
| SPI頻出問題集 |
|---|

公式LINEで無料配布 |
「結局どのサービスを使えば良いかわからない…」という方は、「選考通過ES(公式LINEで無料見放題)」が一番おすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
目次
- 【例文21選】「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝える例文
- 例文①:地域活性化ボランティアサークル
- 例文②:地域復興のボランティア
- 例文③:地域清掃ボランティア
- 例文④:地域のマラソン大会の運営ボランティア
- 例文⑤:大学の地域連携プロジェクト
- 例文⑥:小学生向けの科学教室の開催
- 例文⑦:学生生活サポートボランティア
- 例文⑧:子ども向け学習支援ボランティア
- 例文⑨:児童養護施設でのボランティア活動
- 例文⑩:野外活動ボランティア
- 例文⑪:途上国での環境教育
- 例文⑫:献血推進ボランティア
- 例文⑬:生協学生委員会
- 例文⑭:高齢者施設でのボランティア
- 例文⑮:災害支援ボランティア
- 例文⑯:国際交流ボランティア
- 例文⑰:環境保護活動
- 例文⑱:医療支援のボランティア
- 例文⑲:障がい者施設での支援活動
- 例文⑳:図書館での本の整理やイベント運営ボランティア
- 例文㉑:外国人観光客への案内
- 「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝えた時に、面接官にネガティブに捉えられる点5つ
- 「自己PR/ガクチカでボランティア」を魅力的に伝えるコツ3つ
- ボランティア経験をガクチカを簡単に作成するステップ
- 「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝える時にやってはいけないこと3つ
- ガクチカでボランティア以外のエピソード一覧
- 就活のエントリーシート/面接で、どうして「ガクチカ」を聞かれるの?
- 「自己PR/ガクチカにおけるボランティア」に関するよくある質問
- まとめ:「自己PR/ガクチカでボランティア」を使うときは背景や目的、学んだことを具体的に書くようにしよう
【例文21選】「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝える例文
それでは「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝える例文を紹介していきます。
例文①:地域活性化ボランティアサークル
私は地域活性化を目的とした学生団体の代表として、ボランティア活動に取り組み、リーダーシップと意思決定力を身につけました。大学が住宅地の一画にありながら地域との関わりがない現状に課題を感じ、学生と地域住民が交流できるイベントの企画・運営を行いました。活動の中で、メンバーの意見の相違や、当事者意識の欠如といった困難にも直面しました。しかし、「弱さを見せて仲間を頼る」という自分なりのリーダーシップを実践することで、周囲の人を巻き込みながら前向きに課題解決を図りました。その結果、地域と学生がつながる機会を創出し、団体としても個人としても成長することができました。この経験を通じて培ったリーダーシップと迅速な意思決定力を、御社でのチームマネジメントや営業の場で活かし、組織やお客様に貢献していきたいと考えています。(355文字)
この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。
また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
 就活生くん
就活生くん
どのような想いでボランティアサークルの活動をしていたのかがイメージすることが出来ました。
これはどんなことを意識して伝えているんですか?
「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝える時は、
①学んだことや身に着けたスキルや能力
②ボランティア活動を行うまでの経緯や理由、目標
③活動を通して、具体的に感じたこと、結果、今後の課題
④企業でどのように貢献するか
これらの順で話を構成すると、就活生が伝えるべき点を網羅することが出来ます。
くれぐれもボランティア活動自体の話がメインにならないように注意する必要があります。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
 就活生くん
就活生くん
なるほど!
ボランティアをしていることが他の就活生との差別化になり武器と考えていたのですが、それは大きな間違いなのですね。
「ガクチカでボランティア」を伝える時は、意外と注意することがたくさんありますね。
例文②:地域復興のボランティア
私が学生時代に最も打ち込んだことはプロジェクトに参加した経験です。私は1年生の時に、地域映画を制作する地域復興プロジェクトに参加しました。このボランティアに参加した理由は8ミリフィルムを使って一本の映画を作るというものです。映画を作るということに興味があったからです。最も印象に残っていることは8ミリフィルムを提供してくれてた方へインタビューをしたことです。質問は事前に映像を視聴しある程度考えていましたが、予定通りに進むことはありませんでした。この経験を通じて、臨機応変に対応することの難しさを学び、私はインタビューが苦手だということに気が付きました。東京カメラ機材レンタル株式会社 4することとインタビューの違いが分かり、これから達成するべき課題を見つけることができました。(339文字)
この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。
また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
活動を行う中で最も印象に残っていることには人柄があらわれます。
ボランティアについて伝える時は、印象に残っていることについて話すことも効果的です。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文③:地域清掃ボランティア
私は大学2年から、地元の海岸清掃活動に参加していますが、活動初期の参加者がわずか5名と少ない状態でした。私は、特に若年層の参加が乏しいことに課題を感じ、「次回の清掃活動で大学生の参加者を20名以上にする」という目標を設定しました。そして目標達成のために、SNSや大学内の掲示板を活用した広報活動や、環境問題に関する講義を開催し、啓発活動に力を入れました。その結果、次回の清掃活動では大学生の参加者が25名に増加し、全体の参加者数も30名を超えました。この経験から、相手に合わせた方法で情報発信をすることの重要性を学びました。入社後も、相手のニーズを的確に捉え、効果的なアプローチを行うことで、プロジェクトの成功に貢献したいと考えています。(319文字)
取組前の人数と取り組み後の人数が具体的に記されていてわかりやすいですね。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文④:地域のマラソン大会の運営ボランティア
私は大学時代に地域のマラソン大会の運営ボランティアに参加し、給水所の責任者を務めました。当初、スタッフ間の連携が不十分だったことが原因で、選手への給水が遅れるなどの問題が発生しました。そこで、スタッフ全員で事前に役割分担を明確にし、シミュレーションを行うことで、スムーズな運営を目指しました。その結果、給水の待ち時間を平均30秒から10秒に短縮し、選手からも好評を得ることができました。この経験から、チーム内でのコミュニケーションと協力の重要性を学びました。入社後も、チームワークを大切にし、円滑な業務遂行に努めたいと考えています。(266文字)
改善できた事柄を数値を用いて表現していて、イメージしやすいです。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文⑤:大学の地域連携プロジェクト
私は大学の地域連携プロジェクトで、地元の祭りの企画運営を担当しました。当初、若者の参加者の減少が課題となっていました。そこで、若者向けのフォトスポットなどのコンテンツを追加し、SNSでの広報を強化しました。その結果、来場者数が前年より20%増加し、地域の活性化に貢献できました。この経験から、企画力と実行力の重要性を学びました。入社後も、顧客のニーズを捉えた提案を行い、成果に繋げていきたいと考えています。(203文字)
当初の課題が文章の初めで明記されていて、わかりやすいですね。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文⑥:小学生向けの科学教室の開催
大学の理工系サークルで、小学生向けの科学教室を開催しました。当初、専門用語が多く、子どもたちに内容が伝わりにくい状況でした。そこで、実験を交えた体験型の授業に変更し、理解を促進しました。その結果、参加者の満足度がアンケートで90%以上となり、リピーターも増加しました。この経験から、相手の立場に立った伝え方の重要性を学びました。入社後も、顧客やチームメンバーに対して分かりやすい説明を心がけ、信頼関係を築いていきたいと考えています。(216文字)
アンケートなどの客観的な評価があると成果が分かりやすくなります。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文⑦:学生生活サポートボランティア
大学時代には、学生生活をサポートする学部所属学生団体の活性化に副代表として尽力した。昨年コロナ禍で団体の活動が無くなり、学生の士気が下がった中、学生間のコミュニティを創りたいと思い、3点の施策に取り組んだ。1点目は、企画の運営である。学生のための企画を運営・学生・学校の角度から考え、17本の企画を行った。2点目は、組織改革だ。懸念していた組織間でのコミュニケーション不足を解消するために、企画運営を3学年で交えて行う仕組み創りを行った。3点目は、SNSでの広報活動である。団体内の活動内容の明確化、新規学生獲得のための宣伝を目的として行った結果、半年間でフォロワーが200人から700人に伸びた。任期一年間で結果として、学生数は70人から170人に、積極的活動参加人数は10人から100人に増えた。この活動を通して、多角的な視点から物事について考え、周囲を巻き込みながら行動する能力が身についた。(399文字)
この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。
また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
はじめに施策の数を提示しています。
そのため、話の流れが分かりやすい文章ですね。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文⑧:子ども向け学習支援ボランティア
私は地元の子どもたちを対象にした学習支援ボランティアに参加していました。主に宿題のサポートや苦手科目の指導を行い、子どもたちの成長を見守りました。ある日、算数が苦手な子が「分かる喜び」を感じてくれた瞬間を目の当たりにし、教育が人の未来を切り拓く力を持つと実感しました。この活動を通じて、人の可能性を信じ、サポートすることの大切さを学びました。ボランティアでの学びを仕事にも活かし、チームやクライアントの成長を支える存在になりたいです。(217文字)
活動を通して何を感じたのかが分かりやすい文章になっています。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文⑨:児童養護施設でのボランティア活動
大学の児童養護施設でのボランティア活動に参加しました。当初、子どもたちとの信頼関係を築くのに時間がかかり、活動が思うように進みませんでした。そこで、定期的に訪問し、一人ひとりと丁寧に接することを心がけました。その結果、子どもたちが心を開いてくれるようになり、活動の効果が高まりました。この経験から、信頼関係を築くには時間と忍耐が必要であることを学びました。入社後も、顧客との信頼関係を大切にし、長期的な関係構築に努めたいと考えています。(218文字)
どんなことを意識して取り組んだのかが明確になっていますね。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文⑩:野外活動ボランティア
私は野外活動に取り組んできました。大学生のうちに5回ほど参加をしていました。一班に大学生2人で、10人ほどの小学生と一緒に野外活動を行いました。活動内容としては、山登りや沢登り、カレー作りなどを行いました。私の役割は子供たちの指導者として、活動を援助することでした。しかし、活動を進めていく上でチームワークが必要となる場面で子供たちの喧嘩が起こりました。この問題に対して、子供は自分の意見を受け入れてもらえないため、他の子に反発をするのではないかと考えました。そこで、大学生が子供の一人一人の意見を尊重できるように心がけてきました。結果として、子供たちは大学生の私達に影響されて、仲間の意見を尊重するように心がけてくれるようになりました。人と関わる上で、相手の意見を理解することが最も大切だと気付きました。非日常的な生活を送る事で大切なことを再確認し、貴重な体験が出来ました。(388文字)
この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。
また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
ボランティアに参加していたときにどんな役職だったのかが明らかになっており、採用担当者が状況をイメージしやすい文章になっています。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文⑪:途上国での環境教育
「自発的に行動を取ってボランティア団体を設立し、途上国で環境教育を行った経験」です。2年次、友人と海外旅行について話していました。○○が大好きな彼は現地の美しい海がゴミの山で台無しになっていることを教えてくれました。外国が好きで環境を専攻としている私は現地に興味がわき、彼と現地を訪ねました。実際にゴミの山を見たときはショックを受け、何か手助けがしたいと思いました。しかし、現地ではゴミの焼却は違法であり、捨てる場所に大差がないことも知りました。ただ、未来を担う子どもたちには今のシステムを変えてほしいと思い、環境教育を行うことを決めました。友人と共に団体を設立し、7人の仲間を集めました。そして、2回目の渡航では、4つの学校で150人の子どもに授業をしました。3回目の渡航では子どもたちが私たちのことを覚えていてくれ、諦めずに行動を続けたことへの意義を感じることができました。(389文字)
この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。
また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
具体的な数値がいくつも挙げられており、イメージしやすい文章になっていますね。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文⑫:献血推進ボランティア
ボランティアに参加した経験です。私は大学1年生から3年生の間、献血を推進する学生ボランティア団体に所属していました。このボランティアに参加した理由は、献血の必要性をより多くの人に伝え、輸血を必要としている人を間接的に救う活動に魅力を感じたからです。活動当初、足を止めてくれる方が少ないという問題がありました。原因は訴え方が弱いことだと考えました。そこで、献血連盟のメンバーに相談しました。一人一人の目を見てしっかり呼びかける、団体の透明性を出すために団体名も言う、献血の必要性や手軽さを伝える、といった改善をしました。その結果、直近のキャンペーンのとき初めて「学生さんが呼びかけを頑張っているから献血したい」と私に直接声をかけて下さった方がいました。若年層の献血者数アップという目標達成のために、協調性を活かして主体的に取り組むことができたのは私の強みだと考えます。(383文字)
この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。
また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
ボランティアに参加した理由が初めに明記されており、人柄が伝わりやすい文章になっています。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文⑬:生協学生委員会
私は大学の生協学生委員会に3年間所属し、その中で開催されたイベントのクイズ大会では、企画チームの一員として活動しました。私は、円滑な企画運営の実現のためにチームリーダーを支えるということに注力しました。具体的には、資料作成や備品の準備、参加者対応など、周囲が気づきにくい雑務を積極的に引き受けることで、リーダーが本来の企画立案に集中できるように努めました。このような裏方の役割を通じて、私は相手の立場や考えを汲み取りながら、自分にできることを考えて行動する力を身に付けました。また、チーム全体の動きを見て先回りして動く意識も身に着けることができました。この経験から得た「人を支える力」や「周りに気を配る力」は、どのような組織においても信頼される基盤になると感じており、今後も活かしていきたいと考えています。(353文字)
この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。
また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
活動の中でどのようなことに注力していたのかを始めに伝えることで、文章の流れがスムーズになっています。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文⑭:高齢者施設でのボランティア
私は大学時代、高齢者施設でのボランティア活動に取り組みました。週末に施設を訪問し、入居者の方々とお話ししたり、ゲームを一緒に楽しむなどの活動を通じて交流を深めました。ある日、普段あまり笑顔を見せない方が、自分の昔話を熱心に語ってくださる場面がありました。その時に私は、大切なのは「話すこと」ではなく「聞くこと」なのだと気づきました。相手の目線に立ち、興味を持って話を聞く姿勢が、信頼を築く鍵になると実感できたのです。この経験を通じて、相手の立場に立つ共感力の大切さを学びました。職場でも同じように、相手のニーズを理解しながら信頼関係を築いていきたいと考えています。(282文字)
学んだことをどのように社会で活かすのかがわかりやすく書かれていますね。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文⑮:災害支援ボランティア
大学の夏休みに、災害被災地での支援活動に参加しました。瓦礫の撤去や避難所での物資配布を行う中で、迅速な行動とチームワークの重要性を痛感しました。特に、物資が不足している状況で、リーダーとして周囲の意見を取り入れながら配布計画を立てたことが印象に残っています。そのように行動できた結果、限られた物資を効率的に配布でき、多くの方から感謝の言葉をいただきました。この活動を通じて、状況に応じた柔軟な判断と行動力の大切さを学びました。この経験を活かし、社会人としても困難な課題に積極的に取り組みたいと思います。(251文字)
周囲の人からの評価を含めて書くと説得力が強くなりますね。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文⑯:国際交流ボランティア
大学の国際交流ボランティアで、留学生との交流イベントの運営を担当しました。当初、文化や言語の違いからコミュニケーションがうまく取れず、参加者の満足度が低いという課題がありました。そこで、「イベント参加者の満足度を80%以上にする」という目標を設定しました。具体的には、事前に参加者の興味や文化背景をリサーチし、共通の趣味を活かしたアクティビティを企画しました。結果として、イベント後のアンケートで満足度が85%を超え、参加者同士の交流も深まりました。この経験から、多様な価値観を尊重し、共通点を見出すことで円滑なコミュニケーションが図れることを学びました。入社後も、異なるバックグラウンドを持つ人々との相互理解を深める橋渡し役として貢献したいと考えています。(329文字)
目標と結果で数値が用いられていて、採用担当者がイメージしやすいガクチカになっています。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文⑰:環境保護活動
大学の環境サークルで、地域の森林保全活動に参加しました。当初、参加者が少なく、活動の継続が困難な状況でした。そこで、「月間参加者数を20人に増やす」という目標を掲げ、SNSでの広報や地域イベントでのPR活動を行いました。その結果、3か月後には平均参加者数が22人に増加し、活動範囲も拡大しました。この経験から、持続可能な活動のためには、広報戦略とコミュニティの巻き込みが重要であることを学びました。入社後も、この学びを活かしてプロジェクトの継続性を意識して、貢献していきたいと考えています。(245文字)
入社後にどのようにこれまでの経験を活かすかが、明確になっています。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文⑱:医療支援のボランティア
大学の医療系ボランティア団体で、病院での患者支援活動に参加しました。ある高齢患者と話をしていたところ、言葉の壁から医療スタッフとのコミュニケーションに困難を感じているという問題点に気が付きました。私はその患者と日常会話を重ね、信頼関係を築くことで、医療スタッフとの橋渡し役を担いました。結果として、患者の治療への理解と協力が深まり、治療の進行がスムーズになりました。この経験から、共感力と信頼関係の構築の重要性を学びました。入社後も、顧客やチームメンバーとの信頼関係を築き、円滑な業務遂行に努めたいと考えています。(257文字)
どのような過程で課題に気が付いたのかが書かれており、具体性のある文章になっています。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文⑲:障がい者施設での支援活動
大学のボランティアサークルで、障がい者施設での支援活動に参加しました。当初、コミュニケーションが難しい利用者との関わり方に悩みました。そこで、絵カードやジェスチャーを活用したコミュニケーション方法を取り入れました。その結果、利用者との意思疎通がスムーズになり、活動の満足度が向上しました。この経験から、相手に合わせた工夫と柔軟な対応の重要性を学びました。入社後も、顧客のニーズに応じた柔軟な対応を心がけ、満足度の向上に努めたいと考えています。(221文字)
解決策が具体的に提示されているため、独自性のあるガクチカになっています。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文⑳:図書館での本の整理やイベント運営ボランティア
私は大学時代に、地域の図書館でボランティアとして本の整理やイベントの運営を担当しました。当初、蔵書の分類が不十分で利用者からの問い合わせが多発していました。そこで、分類システムの見直しを提案し、週に10時間を割いて再分類作業を行いました。結果として、利用者からの問い合わせが月平均で30%減少しました。この経験から、情報を整理し、利用者の利便性を高める重要性を学びました。入社後も、情報の整理と共有を通じて業務効率の向上に貢献したいと考えています。(224文字)
数値がいくつも提示されており、説得力の高い文章になっています。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文㉑:外国人観光客への案内
大学の観光ボランティアで、外国人観光客への案内を行いました。当初、言語の壁や文化の違いから、コミュニケーションに苦労しました。そこで、毎日30分の英語学習を継続し、観光案内に必要なフレーズや表現を習得しました。また、ジェスチャーや視覚資料を活用し、言語の壁を越えたコミュニケーションを心がけました。その結果、観光客からの感謝の言葉を多くいただき、満足度向上に繋がりました。この経験から、異文化理解と柔軟な対応の重要性を学びました。入社後も、多様なバックグラウンドを持つ人々との円滑なコミュニケーションを図りたいと考えています。(263文字)
経験から学んだことの活かしが分かりやすく書かれています。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
「自分の強みがわからないからESが書けない…」「ESを書くのに時間がかかる…」など不安な方には、OfferBoxの無料適性検査「AnalyzeU+」の利用がおすすめです。
AnalyzeU+は、100万人のデータをもとにした正確さが推しの無料適性検査です。
メールアドレスだけで登録が完了し、正確な自己分析を受けられるので、まずは気軽に登録してみてください!
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香

- あなたの強みや個性が分かるため、短時間でESが作れる
- 診断結果をもとに、あなたの特性を活かせたガクチカも作れる
- 100万人のデータをもとにした正確さでESに活用できる
AnalyzeU+
また、ES添削については「【誰に頼むのが良い?】エントリーシート添削の無料サービスおすすめ15選 | ES添削の有料サイトも」という記事にまとめています。
この記事を読むと選考に通過するES添削をしてもらえます。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝えた時に、面接官にネガティブに捉えられる点5つ
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
ボランティアは自主性や問題意識が高い人が多いと感じています。
それなのにどうしてボランティアを頑張ってきたのに、面接官にとってネガティブな印象を与えてしまうのですか?
それは、「ボランティア」に対する認識や特性、伝え方に問題があることが多いです。
そこでまず、「ガクチカでボランティア」を伝えた時に、面接官にネガティブに捉えられる点について確認していきましょう。
そして、しっかり正しい考え方を理解した上で、アピールできるよう努力していきましょう。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
ここでは、就活での「ボランティア」に対して正しい認識を持っておくために、「ガクチカでボランティア」を伝えた時に、面接官にネガティブに捉えられる点を確認します。
「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝えた時に、面接官にネガティブに捉えられる点は5つあります。
- ネガティブな点①:お金に対する価値観がずれていることがある
- ネガティブな点②:ストレス耐性が弱いことがある
- ネガティブな点③:目標・目的を持っておらず、ボランティアをしている人が多い
- ネガティブな点④:責任感があまりない可能性がある
- ネガティブな点⑤:仕事とボランティアを同様に考える人がいる
それでは1つずつ確認し、「ボランティア」に対して、正しい認識を持っておきましょう。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
ちなみに、ガクチカを作りたいなら、就活の教科書オリジナルの「無料AIガクチカ作成ツール」が便利です。
就活の教科書の公式LINEに登録するだけで、人事から評価されるガクチカが10秒で作成できるので、ぜひ無料登録して使ってみてください!
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
ネガティブな点①:お金に対する価値観がずれていることがある
「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝えた時に、面接官にネガティブに捉えられる点1つ目は、お金に対する価値観がずれていることがあるということです。
ボランティアはお金に関係なく働いている人が多いため、「無償=正義」と考えている人がいると捉えられているからです。
そもそもビジネスにおいて「お金」のことを正しく考えることが出来なければ成立しません。
ボランティアでお金について考えること無く活動をしてきた人にとって、お金を1つの基準として物事を考えるビジネスの話をすると、話がかみ合わないことがあるようです。
そのため、「ガクチカでボランティア」を伝える際に、お金に対する価値観がずれていることがあると捉えられてしまう可能性があります。
アルバイトとは違って、お金が発生しなくても活動するのはボランティアの良さでもあります。
しかし、どんな形であれビジネスをしている企業に入りたいのですから、お金に対しては正しい価値観を持っている必要があります。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
ネガティブな点②:ストレス耐性が弱いことがある
「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝えた時に、面接官にネガティブに捉えられる点2つ目は、ストレス耐性が弱いことがあるということです。
ボランティアに参加している人は、基本的に良い人が多いので、団体内や活動においてトラブルなどが起こりにくい傾向にあります。
そのため、社会に出てトラブルが発生した際に、トラブルに対するストレス耐性が弱いと捉えられることがあります。
団体員に恵まれ、良い人間関係の下で活動してきた人にとって、社会にいきなり出て理不尽な上司や環境に耐えられないということはよくあるパターンだそうです。
これらにより、「ガクチカでボランティア」を伝えた時に、ストレス耐性が弱いと捉えられることがあります。
ボランティアをする人の良さが、逆に、今後の理不尽な社会にやっていけるかの懸念要素になってしまうのですね。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
ネガティブな点③:目的意識がないまま活動していたと思われやすい
「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝えた時に、面接官にネガティブに捉えられる点3つ目は、目標・目的を持っておらず、ボランティアをしている人が多いということです。
大学生では、就活で話すネタになるからという理由でボランティアをする人が多いからです。
例えば、地域を活性化するという目的を持って活動しているボランティア団体で、個人として何も目的や目標を持たず、何となく活動をしている人がいます。
この場合は、団体に貢献することも難しいですし、結局は企業や面接官にストーリー性を持って語れなくなってしまいます。
「ガクチカでボランティア」を伝える時は、本当にボランティアをやりたくてやったのかと疑われるのは、目標・目的を持っておらず、ボランティアをしている人が多いと捉えられているからです。
いくら良い活動を行っている団体でも、個人としての目的や目標を持っていない人は、就活生として「ボランティア」を武器にすることは難しいでしょう。
きちんとストーリー性を持って「ガクチカでボランティア」を伝えることを意識しましょう。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
ネガティブな点④:責任感があまりないと思われる可能性がある
「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝えた時に、面接官にネガティブに捉えられる点4つ目は、責任感があまりない可能性があるということです。
ボランティアでは、企業のようにお金をもらって責任を持って仕事をするのではなく、自主的に参加し自分の生活に支障が出ない程度に活動をすることが多いからです。
例えば、営業の仕事では商談数や契約件数などの明確な目標を持ち、結果に対して責任を持って働き、それに見合った報酬をもらいます。
しかし、学生団体のボランティアでは明確なゴールやそれに対する報酬がないため、自分が満足するかどうかの基準で活動を行ってしまうことがあります。
そのため、「ガクチカでボランティア」を伝えた場合に、責任感があまりない可能性があると感じられてしまうことがあります。
ボランティアはお金との関係性が薄いため、人間の潜在意識的に責任感が薄いと感じられてしまう可能性があるんですね。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
ネガティブな点⑤:仕事とボランティアを同様に考える人がいる
「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝えた時に、面接官にネガティブに捉えられる点5つ目は、仕事とボランティアを同様に考える人がいるということです。
なぜならボランティアは「やりがいのあるもの」という観点では、仕事と同様だからです。
例えば、アルバイトとして塾講師をしている人と、ボランティアとして小学生に勉強を教えている人ではあまり違いはないように思われます。
しかし実際には、「お金の報酬」「求められる結果」「仕事に対するコミットメント」など様々な違いがあるのです。
このため、就活生が「ガクチカでボランティア」を伝える時に、仕事とボランティアを同様に考えている人という印象を与えてしまうと、「お金の価値観」「仕事に対する責任感」などにズレがあると注意されてしまいます。
就活生は「ガクチカでボランティア」を伝える前に、仕事とボランティアの違いを明確に持っておかなくてはなりません。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
 就活生くん
就活生くん
ボランティアは良いことだからアピールしようと思っていたけれど、たくさんのネガティブなイメージがあるんですね。
なんだか、「ガクチカでボランティア」を伝えることが不安になってきたなあ・・・
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
もっと他のことでアピールした方が良いのかなあ・・・
やっぱり「ガクチカでボランティア」を伝えることはやめたほうが良いですか?
いいえ!そんなことはありません。
しっかりと「ガクチカでボランティア」を伝える時の注意点と上手く答えるコツさえ抑えると、とてもアピールになりますよ。
今からは実際に例文を使って、「ガクチカでボランティア」をどのように伝えれば良いかを解説していきます。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
結論:自己PR/ガクチカでボランティア経験を伝えるのはあり
結論から申し上げると、自己PR/ガクチカでボランティア経験を伝えるのはありです。
なぜなら、ボランティア活動を行う際には協調性や継続力、主体性などが活かされていることが多いからです。
そのため、企業研究を行い企業が求める人財像を理解したうえで、最も効果的な力や学びをアピールするようにしましょう。
以下の記事では、企業研究の目的や方法について解説しています。
企業研究の際に役立つシートも配布しているので、参考にしてみてください。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
「ESが上手く書けない…」「ES選考で落ちてしまう…」なら、OfferBoxの無料適性診断 「AnalyzeU+」がおすすめです。
AnalyzeU+を使えば、簡単に自分の強みや個性がわかるようになるので、選考で落とされないエントリーシートを書けるようになります。
また実際に利用した就活生からは、「診断するだけでESに何を書けばいいかわからない...ということがなくなった!」などの口コミもいただいています。
ESで落ちる確率をかなり減らせるだけでなく、あなたにあった職種や役割もわかるので、まずは、無料簡単登録から自己分析をしてみてくださいね。
AnalyzeU+
「自己PR/ガクチカでボランティア」を魅力的に伝えるコツ3つ
それでは次に、「ガクチカでボランティア」を上手く面接官にアピールするために、「ガクチカでボランティア」を上手く答えるためのコツについて見ていきたいと思います。
- コツ①:ボランティア前後のプロセスまで伝える
- コツ②:活動自体ではなく、何を学ぶことが出来たのかを伝える
- コツ③:ボランティア経験を通して、人間性・個人の価値観を伝える
それでは1つずつ見ていき、「ガクチカでボランティア」をアピールするための武器にしましょう!
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
コツ①:ボランティア前後のプロセスまで伝える
「自己PR/ガクチカでボランティア」を上手く伝えるコツ1つ目は、ボランティア前後のプロセスまで伝えるということです。
就活生が伝えるべき点は、ボランティア活動の内容ではなく、「なぜそのボランティア活動を始めようと思ったのか」「そのボランティアを通してどのように変化したのか」だからです。
例えば「ガクチカでボランティア」をボランティア前後のプロセスまでこのように伝えます。
語学力を上げ、グローバルな課題を解決できるような人材になると目標を持ち、フィリピンの孤児に勉強を教える学生団体に所属していました。
その活動を通して、グローバルなコミュニケーション能力の大切さと世界の貧富の格差という社会問題に気が付くことができたので、英語を勉強しTOEICで850点をとり、他の貧富の格差がある国に足を運び、解決するための政策についてブラッシュアップを行いました。
このようにボランティア前後のプロセスまで伝え、ボランティアを始める背景や学びを伝えることができるとより自分の頑張りをアピールすることができます。
ボランティア活動を通して発見した課題に対して、どのように取り組んだのかまで伝えることが出来るとさらに良いですね!
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
コツ②:活動自体ではなく、何を学ぶことが出来たのかを伝える
「自己PR/ガクチカでボランティア」を上手く伝えるコツ2つ目は、活動自体ではなく、何を学ぶことが出来たのかを伝えるということです。
就活生がどれだけ素晴らしいボランティア活動をしていたとしても、ボランティアを通して何も学んでいない人は採用したくありません。
同じボランティアを活動している人が2人いて、活動内容の事ばかりを話す就活生と、活動経験から学んだことや自分がどのような役割を果たし貢献することができたかを中心に話す人のどちらを採用したいと思いますか?
間違いなく後者です。
「ガクチカでボランティア」を伝える時は、どのようなボランティア活動をしているかではなく、自分がどの役割を担い貢献することができ、学べたのかを伝えるべきなのです。
「ガクチカでボランティア」を伝える場合は、企業が面接で何を知りたがっているのかを踏まえた上で話を進めていく必要があるのですね。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
コツ③:ボランティア経験を通して、人間性・個人の価値観を伝える
「自己PR/ガクチカでボランティア」を上手く伝えるコツ3つ目は、ボランティア経験を通して、人間性・個人の価値観を伝えるということです。
あくまで「ガクチカでボランティア」を伝える上では、ボランティア経験は自己PRの材料です。
例えば、このような形で自己PRの材料として伝えます。
私は近年の自然破壊に問題意識を持っているため、積極的に川や山で自然観察や清掃を行う自然保護団体で活動を行っています。
だから「ガクチカでボランティア」を伝える時は、ボランティア経験を通して、人間性・個人の価値観を伝えることが大切なのです。
「ガクチカでボランティア」は、何をしたかよりもどのような想いで活動に参加したかを伝え、自身の人間性や価値観を知ってもらうことを意識するとより好印象を与えることが出来ます!
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
 就活生くん
就活生くん
「ガクチカでボランティア」を伝える時のコツを抑えることができました。
これで就活のガクチカを伝える時は、安心して伝えることが出来そうです。
安心するのはまだ早いですよ。
「ガクチカでボランティア」を伝える時にやってはいけないことがいくつかあります。
多くのボランティア経験者が就活でミスをしてしまう点なので、必ず確認して万全の状態で就活に臨んでください。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
ガクチカのテーマに悩んでいる人におすすめの記事一覧
「ガクチカが無くて書けない」「ガクチカの書き方が分からない」という人には、 記事「ガクチカの書き方」 がオススメです。
ガクチカができたら、添削を受けることで選考通過率がアップします。
以下にガクチカの書き方について例文を交えて解説している記事やおすすめガクチカ添削サービス解説記事をまとめました。
ESや面接で通用するガクチカ を書くのに役立つので、合わせて読んでみてください。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
「自分の強みがわからないからESが書けない…」「ESを書くのに時間がかかる…」など不安な方には、OfferBoxの無料適性検査「AnalyzeU+」の利用がおすすめです。
AnalyzeU+は、100万人のデータをもとにした正確さが推しの無料適性検査です。
メールアドレスだけで登録が完了し、正確な自己分析を受けられるので、まずは気軽に登録してみてください!
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香

- あなたの強みや個性が分かるため、短時間でESが作れる
- 診断結果をもとに、あなたの特性を活かせたガクチカも作れる
- 100万人のデータをもとにした正確さでESに活用できる
AnalyzeU+
また、ES添削については「【誰に頼むのが良い?】エントリーシート添削の無料サービスおすすめ15選 | ES添削の有料サイトも」という記事にまとめています。
この記事を読むと選考に通過するES添削をしてもらえます。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
ボランティア経験をガクチカを簡単に作成するステップ
自己PRやガクチカで面接官に評価してもらうには、正しい作り方をしないといけません。
しかし、自己PRやガクチカを間違った作り方で作成し、結果落とされる就活生は非常に多いです。
そこで、ここでは自己PRやガクチカを誰でも簡単に作れる方法を紹介します。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
- おすすめサービス:【就活生】適性診断AnalyzeU+(251問で性格診断、人気No.1)
- おすすめサービス:【就活生】Lognavi適性診断(性格テスト90問、SPI練習問題)
- おすすめサービス:【就活生】キャリアチケットスカウト診断(5問であなたのキャリア診断)
- おすすめサービス:【就活生】内定者ES(難関企業内定者のES見放題)
- おすすめサービス:【就活生】unistyle(選考通過ESが71,733枚見放題)
ステップ:アピールできるあなたの強みを探す
自己PRやガクチカを誰でも簡単に作るステップは「アピールできるあなたの強みを探す」です。
ESや面接の自己PR、ガクチカで使える強みを探すには性格診断が必須と言えます。
性格診断をすることで、客観的な視点であなたの強みや弱みがわかるので、就活や転職活動で活かしやすくなりますよ。
あなただけの強みを知りたい方は、性格診断を活用することが一番おすすめです。
数ある性格診断のうち特におすすめなのが、「適性診断AnalyzeU+」です。
適性診断AnalyzeU+は、15分程度で終わる質問と100万人のデータからあなたの強みを診断してくれます。
また、自己PRやガクチカを作成し、プロフィールに登録しておけば、大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらえます。
「自己分析はどこでやれば…」という人は、就活生の2人に1人が利用している適性診断AnalyzeU+を受けてみると良いですよ!
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香

- 251問の質問と100万人のデータから診断してくれるのでかなり正確な結果がわかる
- 診断結果からあなたにおすすめの職種もわかる
- 診断により自己PRが書きやすくなり、ESや面接で人事に評価されるアピールができる
(適性診断AnalyzeU+)
ステップ:内定者の回答とテンプレートをまねて作成する
自己PRやガクチカを誰でも簡単に作るステップは「内定者の回答とテンプレートをまねて作成する」です。
内定者の回答は企業側に評価された回答なので、回答の構成をまねることが選考突破への近道になります。
内定者の回答を見る時には、どのようなテーマで、どのような構成になっているのかを確認することがおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
- 難関企業内定者の自己PRやガクチカ、志望動機などの文章が見れる
- 評価されるESの書き方がわかるので、選考突破率UP
- 自分のESを考える時間がない方はESをそのままパクってもOK
内定者ES
「ESが上手く書けない…」「ES選考で落ちてしまう…」なら、OfferBoxの無料適性診断 「AnalyzeU+」がおすすめです。
AnalyzeU+を使えば、簡単に自分の強みや個性がわかるようになるので、選考で落とされないエントリーシートを書けるようになります。
また実際に利用した就活生からは、「診断するだけでESに何を書けばいいかわからない...ということがなくなった!」などの口コミもいただいています。
ESで落ちる確率をかなり減らせるだけでなく、あなたにあった職種や役割もわかるので、まずは、無料簡単登録から自己分析をしてみてくださいね。
AnalyzeU+
「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝える時にやってはいけないこと3つ
それでは最後に、「ガクチカでボランティア」を伝えて就活に失敗することを避けるために、「ガクチカでボランティア」を伝える時にやってはいけないことを確認していきます。
「ガクチカでボランティア」を伝える時にやってはいけないことは3つあります。
- NG①:ボランティアで学んだものが企業の求めているものとマッチしていない
- NG②:ボランティアの素晴らしさを力説する
- NG③:ボランティアに行った理由や行った時の目標を伝えない
それでは1つずつ確認し、万全な状態で就活に臨みましょう!
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
NG①:ボランティアで学んだものが企業の求めているものとマッチしていない
「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝える時にやってはいけないこと1つ目は、ボランティアで学んだものが企業の求めているものとマッチしていないということです。
就活生がボランティアを通して何かを学んだとしても、それが企業が求めているものとマッチしていないと、どのように企業で貢献してくれるのかがイメージできないからです。
例えば、事務系の仕事を志望する就活生が、「ガクチカでボランティア」を伝える時に行動力を身に着けたとアピールしたとしても、あまり仕事内容と求められているものとマッチしていません。
それなら、もっと他の仕事に適した就活生を採用しようと判断してしまうかもしれません。
よって「ガクチカでボランティア」を伝える時に、ボランティアで学んだものが企業の求めているものとマッチしていない状態で伝えることは避けましょう。
企業は慈善活動をしているのではありません。
今までボランティアで頑張ってきたとしても、それが企業に求められているものではなかったら、就活生は魅力的には感じられないのです。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
NG②:ボランティアの素晴らしさを力説する
「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝える時にやってはいけないこと2つ目は、ボランティアの素晴らしさを力説するということです。
企業にとって、就活生がどのようなボランティア活動をしてきたのかについてはあまり興味がないからです。
「ガクチカでボランティア」を伝える就活生で、ボランティア活動自体や慈善活動ということ自体を評価してもらおうとする人がいますが、就活生が伝えるべき点はそこではないのです。
だから「ガクチカでボランティア」を伝える時に、ボランティアの素晴らしさを力説することは避けましょう。
「就活生がボランティア活動を行っていたこと」自体は、就活の際にプラスの評価を得ることはないという前提を持っておく必要があります。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
NG③:ボランティアに行った理由や行った時の目標を伝えない
「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝える時にやってはいけないこと3つ目は、ボランティアに行った理由や行った時の目標を伝えないということです。
理由や目標を伝えなければ、ただ事実を述べているだけなので、就活生が伝えるべき点と的が外れているからです。
たくさん海外ボランティア活動に行っていたとしても、その行動に至った理由や目標がなければ、結局は何を伝えたいのかが定まらず、面接官の印象に残らなかったというのはよくある話です。
ボランティア活動は明確な理由や目的があるからこそ、自分にとって有意義なものになりますよね。
その一番大切な部分をしっかりと伝えるようにしてください。
それでは最後に、そもそもなぜ就活のエントリーシートや面接で「ガクチカ」を聞かれるのかの理由をおさらいしておきましょう。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
「自分の強みがわからないからESが書けない…」「ESを書くのに時間がかかる…」など不安な方には、OfferBoxの無料適性検査「AnalyzeU+」の利用がおすすめです。
AnalyzeU+は、100万人のデータをもとにした正確さが推しの無料適性検査です。
メールアドレスだけで登録が完了し、正確な自己分析を受けられるので、まずは気軽に登録してみてください!
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香

- あなたの強みや個性が分かるため、短時間でESが作れる
- 診断結果をもとに、あなたの特性を活かせたガクチカも作れる
- 100万人のデータをもとにした正確さでESに活用できる
AnalyzeU+
また、ES添削については「【誰に頼むのが良い?】エントリーシート添削の無料サービスおすすめ15選 | ES添削の有料サイトも」という記事にまとめています。
この記事を読むと選考に通過するES添削をしてもらえます。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
ガクチカでボランティア以外のエピソード一覧
 就活生くん
就活生くん
僕は大学時代に勉強や留学にも力を入れました。
ボランティア以外の経験でガクチカを書くならどうしたらいいですか?
ガクチカで使いやすいエピソードの一覧を紹介します。
あなたの経験と当てはまっている場合は、ぜひその記事も参考にしてみてくださいね。
「ESが上手く書けない…」「ES選考で落ちてしまう…」なら、OfferBoxの無料適性診断 「AnalyzeU+」がおすすめです。
AnalyzeU+を使えば、簡単に自分の強みや個性がわかるようになるので、選考で落とされないエントリーシートを書けるようになります。
また実際に利用した就活生からは、「診断するだけでESに何を書けばいいかわからない...ということがなくなった!」などの口コミもいただいています。
ESで落ちる確率をかなり減らせるだけでなく、あなたにあった職種や役割もわかるので、まずは、無料簡単登録から自己分析をしてみてくださいね。
AnalyzeU+
就活のエントリーシート/面接で、どうして「ガクチカ」を聞かれるの?
ガクチカとは「学生時代に力を入れたことについて教えてください」という質問に対する答えのことです。
学生時代に力を入れたエピソードには、あなたの性格や物事の考え方が強く影響しています。
そのため、学生時代に力を入れたエピソードから、「就活生がどんなことを考えて、どのような過程で物事に取り組んだか」を企業は知ろうとしています。
また、「ガクチカから学んだこと」で会社でどのように活躍し、この会社では、どのように学び、成長するかまで確認しているようです。
「そもそも、ガクチカがない」、「とにかく、ガクチカを伝えるのが苦手」という就活生は、「ガクチカの作り方」が網羅的に書かれている記事があるので、参照してみてくださいね!
「自分の強みがわからないからESが書けない…」「ESを書くのに時間がかかる…」など不安な方には、OfferBoxの無料適性検査「AnalyzeU+」の利用がおすすめです。
AnalyzeU+は、100万人のデータをもとにした正確さが推しの無料適性検査です。
メールアドレスだけで登録が完了し、正確な自己分析を受けられるので、まずは気軽に登録してみてください!
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香

- あなたの強みや個性が分かるため、短時間でESが作れる
- 診断結果をもとに、あなたの特性を活かせたガクチカも作れる
- 100万人のデータをもとにした正確さでESに活用できる
AnalyzeU+
また、ES添削については「【誰に頼むのが良い?】エントリーシート添削の無料サービスおすすめ15選 | ES添削の有料サイトも」という記事にまとめています。
この記事を読むと選考に通過するES添削をしてもらえます。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
「自己PR/ガクチカにおけるボランティア」に関するよくある質問
最後に、「自己PR/ガクチカにおけるボランティア」に関するよくある質問を紹介します。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
質問①:履歴書のボランティアの欄に献血を書くのはアリ?
「自己PR/ガクチカにおけるボランティア」に関するよくある質問は、「履歴書ののボランティアの欄に献血を書くのはアリ?」です。
結論から申し上げると、ボランティアの欄に献血を書くのはアリです。
ただし、献血は一人で行うため、「人と協力するのが苦手」や「集団行動を好まない」いった印象を与える可能性があります。
そのため、献血をボランティア欄に書くときはESや面接などで協調性やコミュニケーション能力などをアピールするようにしましょう。
「ESが上手く書けない…」「ES選考で落ちてしまう…」なら、OfferBoxの無料適性診断 「AnalyzeU+」がおすすめです。
AnalyzeU+を使えば、簡単に自分の強みや個性がわかるようになるので、選考で落とされないエントリーシートを書けるようになります。
また実際に利用した就活生からは、「診断するだけでESに何を書けばいいかわからない...ということがなくなった!」などの口コミもいただいています。
ESで落ちる確率をかなり減らせるだけでなく、あなたにあった職種や役割もわかるので、まずは、無料簡単登録から自己分析をしてみてくださいね。
AnalyzeU+
まとめ:「自己PR/ガクチカでボランティア」を使うときは背景や目的、学んだことを具体的に書くようにしよう
【内定者が教える】就活の「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝える時のコツ | 例文,やってはいけないこともの記事はいかがでしたか。
この記事では、「自己PR/ガクチカでボランティア」を伝えることに悩んでいる人に、上手く伝えるコツや、やってはいけないことを解説しました。
合わせて、「ガクチカでボランティア」を伝える例文や就活生が「ガクチカでボランティア」を伝えた時に、面接官の感じることも紹介しています。
この記事が、ボランティア経験について伝える役に立つことができていれば幸いです。