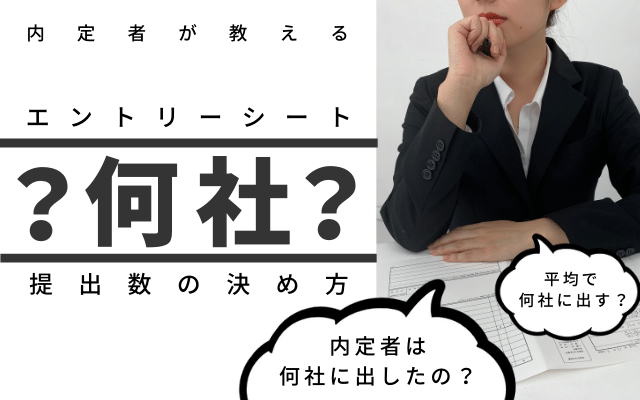- 就活でのエントリー数は何社?
- エントリーシートの平均提出数は何社?
- エントリー数が少ない時/多い時のメリット・デメリット
- エントリーシートの提出にかける時間を抑える方法
-
【優良版】就活を有利に簡単に終わらせるおすすめツール
-
【就活生】適性診断AnalyzeU+
(251問で性格診断) -
【就活生】Lognavi適性診断
(性格テスト90問、SPI練習問題) -
【就活生】SPI頻出問題集(LINEで無料配布)
(SPI/Webテストの問題練習)
-
【就活生】適性診断AnalyzeU+
 客観的な性格診断を受ける
客観的な性格診断を受ける(適性診断AnalyzeU+)
公式サイト
(https://offerbox.jp/)
*プロフィール登録で優良企業のスカウトGET!
こんにちは!「就活の教科書」編集部です。
就活をしているとたくさんの企業に興味を持ち、いったい何社にエントリーシートを提出すればよいか悩んだことはありませんか?
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
あります!
業界や企業を調べていると、いろんな企業にエントリーしたくなります。
何社にエントリーシートを提出すればよいかわからないのでみんなの提出数を知りたいです。
 就活生くん
就活生くん
エントリーシートって1枚書くのにすごく時間がかかるじゃないですか。
何十社も書かなくていい方法ってないんですか?
エントリーシートの提出数が少なすぎるとそれで足りるのか不安になり、逆に多すぎると時間の無駄になる。
難しいところです。
エントリーシートを何社に提出すべきか目安が欲しいですよね。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
そこでこの記事では「就活でのエントリー数は何社なのか?」について解説していきます。
合わせて、理系・文系の学生は何社にエントリーすべきなのか・エントリーシート(ES)の平均提出数・エントリー数が少ない時、多い時のメリット・デメリットなどについても解説していきます。
他にも、内定者が実際に何社にエントリーシートを出したかアンケートを取ってきたので参考にしてください。
この記事を読めば「何社にエントリーすればいいの…」「エントリーシートは何社に提出すればいいの…」といった悩みを解決できます。
就活で、何社にエントリーすればいいのかわからない就活生は、ぜひ最後まで読んでください。
先に結論をお伝えすると、「就活始めたけど何をすれば良いのかわからない…」なら、「適性診断AnalyzeU+」で、自分の強みと適性職種を診断するのがおすすめです。
ちなみに「適性診断AnalyzeU+」以外にも、性格テスト90問で長所や適職を診断できる「Lognavi適性診断」、Webテストで頻出の問題がわかる「SPI頻出問題集」もおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
- 【就活生】適性診断AnalyzeU+(全251問、客観的な性格診断)
【公式サイト】https://offerbox.jp/
- 診断結果より優良企業からスカウト
- 【就活生】Lognavi適性診断(性格テスト90問で長所や適職を診断)
【公式サイト】https://lognavi.com/
- SPI問題も無料、180,000人が利用中
- 【就活生/転職者】SPI頻出問題集(公式LINEで無料配布)
【公式サイト】https://reashu.com/linelp-spi/
- Webテストで頻出の問題がわかる
「結局どのサービスを使えば良いかわからない…」という就活生は、「適性診断AnalyzeU+」であなたの強みを正確に診断するのがおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
目次
【パターン別】就活のエントリー数は何社?
 就活生くん
就活生くん
僕は就活生ですが、実際にどれくらいの企業にエントリーをすれば良いのかがわかりません。
就活生のエントリー数は何社なのでしょうか?
そこでここでは、以下のパターン別に就活でのエントリー数を紹介していきます。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
- 結論:おすすめのエントリー数
- エントリー数の平均
- 文系のエントリー数
- 理系のエントリー数
- エントリーシート提出数
- 就活の教科書内定者のエントリーシート提出数
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
結論:おすすめのエントリー数は20社~30社程度
結論から言うと、就活でのおすすめのエントリー数は、20社~30社程度です。
なぜなら、多すぎてもエントリーするのに時間がかかったり、スケジュール管理が大変になるからです。
逆に少なすぎても、全部落ちてしまった時に、最初からエントリーしないといけません。
そのため「エントリーは何社すればいいの?」と悩んでいる就活生は、20社~30社程度の企業にエントリーをしましょう。
就活では、エントリーしすぎて1社1社のエントリーが疎かになるよりも、ある程度エントリーをして、1社1社丁寧に向き合うことが需要になります。
ただ、エントリーシート20~30社出すのがめんどくさいと思っている就活生もいますよね。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
「隠れ優良企業で自分らしく働ける企業に就職したい!」という方は「OfferBox」を使うのが一番おすすめです。
OfferBoxでは、251問の質問に回答することであなたの性格を徹底的に診断でき、プロフィール次第で大手や優良企業からスカウトがもらえる就活生に人気のアプリです。
すでに多くの就活生が利用しており、運がよければ優良企業の選考も一部スキップできるので、就活を有利に進められますよ。
ちなみに「OfferBox」以外にも「Lognavi」「キャリアチケットスカウト」の同時並行もおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
(OfferBox)
エントリー数の平均は24.4社
就活生の2022卒のエントリー数は、4月時点の平均で24.4社となっています。
2019卒~2022卒の平均エントリー数は、以下のようになります。
- 2019卒:27.9社
- 2020卒:25.6社
- 2021卒:24.6社
- 2022卒:24.4社
参考:株式会社ディスコ
このように、エントリー数は毎年24社~28社くらいが平均となっています。
エントリー数は何社にすべきなのかわからない就活生は、とりあえず20社~30社の企業にエントリーしてみてくださいね。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
文系のエントリー数は28社
2020卒の4月時点での文系学生のエントリー数は約28社となっています。
文系のエントリー数が多くなるのは、就活にたくさんの時間をかけることができるからです。
文系就活生の平均エントリー数が20らしいんだけど多すぎん?って思いました。そんなに行きたい会社見つかるかなふつう。笑
— やす|大学生 (@yasu20cck) February 14, 2021
このように、20社の企業にエントリーしようと思うと、しんどいと感じる就活生も多いです。
そのため、文系の就活生は、エントリー数の目安を28社として、早くからエントリーしたい企業を決めておくと良いでしょう。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
理系のエントリー数15.8社
2022卒の4月時点での理系学生のエントリー数は男子で約15.8社、女子で約23.3社となっています。
理系のエントリー数が文系よりも少なくなる理由は、理系は文系よりも忙しく、推薦応募もあるからです。
就活生の平均エントリー数調べたら20社とか出てたまげたんだけど、理系に絞ると10社行かないくらいっぽい?
本当にそのくらいならちょっと安心— ふう (@fuu_tech) November 8, 2020
調べてみても、理系は10社程度の就活性が多いです。
また、理系女子は、文系就職をする場合が多いため、男子よりもエントリー数が多くなっています。
理系の学生で、何社にエントリーすべきかで悩んでいる就活生は、15社~23社を目安にしておきましょう。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
エントリーシートの提出数12.1社
2022卒のエントリーシート提出数は、4月時点で12.1社となっています。
実際にエントリーをしてもエントリーシートを提出する数は少なくなります。
エントリーはしたけどその後の選考を辞退したり、エントリー先がエントリーシートを提出しなくていい企業だったりするからです。
エントリーシートを書くのは大変なので、スケジュール管理がより大切になってきます。
「何社にエントリーシートを提出したら良いのだろう?」と悩んでいる方は、12社程度を目安にしてみてください。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
就活の教科書内定者のエントリーシート提出数
「就活の教科書」でライターをしている内定者たちに、何社にエントリーシートを提出したのか訊いてみます。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
 「就活の教科書」編集部 橋口
「就活の教科書」編集部 橋口
 「就活の教科書」編集部 マサ
「就活の教科書」編集部 マサ
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
 「就活の教科書」編集部 アオイ
「就活の教科書」編集部 アオイ
 「就活の教科書」編集部 かめさん
「就活の教科書」編集部 かめさん
 「就活の教科書」編集部 中島
「就活の教科書」編集部 中島
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
みんな協力ありがとうございました。
本当に、人それぞれですよね。
「就活のやり方がわからない…」「就活はどこから始めれば…?」という就活生には、「適性診断AnalyzeU+」がおすすめです。
就活初期の段階で自分の強みや弱みなどの性格を把握していれば、業界・企業選びや、ES、面接で困ることはなくなるからです。
適性診断AnalyzeU+は、100万人のデータをもとに10分~15分で終わる質問からあなたの強みや弱み、適性職種を詳しく検査してくれます。
診断結果をあなたの自己PRに使用でき、プロフィールに入力することで、大手や優良企業から特別スカウトも来ます。
「自分の強みを教えて欲しい!」「ESや面接で困ることなくスムーズに就活を進めたい!」という方は、「適性診断AnalyzeU+」を利用してみてください。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
- 251問の質問と100万人のデータから強み診断してくれるのでかなり正確な結果がわかる
- 診断結果からあなたにおすすめの職種もわかる
- 診断により自己PRが書きやすくなり、ESや面接で人事に評価されるアピールができる
(適性診断AnalyzeU+)
エントリー数が少ない時のメリット・デメリット
 就活生くん
就活生くん
何社にエントリーすべきなのかはわかりました。
エントリーする企業が少ない場合は、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
何社にエントリーするかを考えるのはとても重要です。
確かにエントリー数が少ない時は、どのようなメリット・デメリットがあるかわからないですよね。
そこでここでは、エントリー数が少ない時のメリット・デメリットについて解説していきますね。
- メリット①:企業研究に時間をかけられる
- メリット②:目標を絞ることができる
- デメリット①:落ちた時に替えの企業がない
- デメリット②:視野が狭くなる
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
それでは、エントリー数が少ない時のメリット・デメリットについて、それぞれ解説していきますね。
メリット①:企業研究に時間をかけられる
エントリー数が少ない時のメリット1つ目は「企業研究に時間をかけられる」ことです。
エントリー数が少ない場合は、1つ1つの企業に時間をかけられます。
企業研究に時間をかけることで、志望動機で差別化ができたり、面接でアピールできます。
そのため、エントリー数が少ないメリットとして、企業研究を入念に行える点が挙げられます。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
企業研究は就活をする上でかなり大事です。
正しい企業研究の仕方を知らない就活生は、以下の企業研究の記事を必ず読んでください。
メリット②:目標を絞ることができる
エントリー数が少ない時のメリット2つ目は「目標を絞ることができる」ことです。
エントリー数が少ないので、1つ1つの企業に真剣になり、目標を絞れるようになります。
ずっと前から入社したい企業がある場合は、短期間で就活を終わらせることができます。
エントリー数が少ない就活生は、目標を絞って就活をすることが重要です。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
エントリーする時は、なぜエントリーするのかを考えましょう。
デメリット①:落ちた時に替えの企業がない
エントリー数が少ない時のデメリット1つ目は「落ちた時に替えの企業がない」ことです。
就活でエントリーした企業に全て落ちることは稀ではありません。
就職できると思った企業の書類選考が通らなかったり、最終面接で落とされることもよくあります。
そのため、エントリー数が少ないと、落ちた時に替えの企業がなくなることにもつながります。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
エントリーした企業に落ち続けるとメンタル的にもやられてしまいます。
だからこそ「エントリー数は何社なのか?」で悩んでいる就活生は、20社~30社の企業にエントリーすることが重要です。
デメリット②:視野が狭くなる
エントリー数が少ない時のデメリット2つ目は「視野が狭くなる」ことです。
エントリー数が少ないと、志望する業界や業種を絞ることになります。
志望業界や業種を絞ってしまうと、後々、行きたい企業を見逃してしまったりする場合もあります。
このような状態にならないためにも、できるだけ多くの企業にエントリーすることが大切です。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
何社にエントリーしたらいいのかわからない方は、早い段階から行きたい企業を見つけておきましょう。
「就活を始めてみたもののまだわからないことが多い…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」であなたの性格を診断するのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、10分~15分で終わる質問と100万人のデータからあなたの強みと弱み、おすすめ職種を診断してくれます。
また、診断後にあなたの強みや弱み、専攻などをOfferBoxのプロフィールに入力することで、大手や隠れ優良企業からの特別スカウトをもらえます!
「就活で何をすれば良いかわからない…」という人は、単なる自己分析だけではなく、「自分に合う」企業からの特別スカウト機能もある適性診断AnalyzeU+で診断してみると良いですよ!
(適性診断AnalyzeU+)
エントリー数が多い時のメリット・デメリット
 就活生くん
就活生くん
エントリー数が少ない時のメリット・デメリットについては理解できました。
では逆に、エントリー数が多い時のメリット・デメリットを教えて欲しいです。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
わかりました。
そこでここでは、エントリー数が多い時のメリット・デメリットについて解説していきますね。
- メリット①:落ちても替えの企業がある
- メリット②:視野が広がる
- デメリット①:1つの企業にかける時間が少なくなる
- デメリット②:スケジュール管理が厳しくなる
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
それでは、エントリー数が多い時のメリット・デメリットについて、それぞれ解説していきますね。
メリット①:落ちても替えの企業がある
エントリー数が多い時のメリット1つ目は「落ちても替えの企業がある」ことです。
エントリー数が多い場合は、落ちても何社も残っているので、替えの企業が増えます。
残りの企業が増えると、メンタルも安定しやすくなるので、最低でも20社にエントリーすることをおすすめします。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
また、エントリー数を増やすことで自分の経験にもつながります。
メリット②:視野が広がる
エントリー数が多い時のメリット2つ目は「視野が広がる」ことです。
エントリー巣を増やすと視野が広がり、より自分に合った企業と出会える可能性があります。
エントリー数を増やすことで、知名度は低いが、業界トップのホワイト企業を知るきっかけとなります。
そのため、何社にエントリーしたら良いかわからない方は、ぜひエントリー数を増やしてみてください。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
エントリー数を増やすと、隠れ優良企業に出会えるかもしれません。
デメリット①:1つの企業にかける時間が少なくなる
エントリー数が多い時のデメリット1つ目は「1つの企業にかける時間が少なくなる」ことです。
エントリー数を増やしてしまうと、多くの企業を調べないといけないので、1つの企業研究にかける時間が少なくなります。
企業研究を疎かにしてしまうと、志望動機も疎かになり、どれだけエントリーしても落ちることにつながります。
企業研究を丁寧にしつつ、多くの企業にエントリーすることが重要となります。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
自分に合ったエントリー数を見つけることが大切ですね。
デメリット②:スケジュール管理が厳しくなる
エントリー数が多い時のデメリット2つ目は「スケジュール管理が厳しくなる」ことです。
エントリー数が増えると、企業によってエントリーシートの提出期限が異なるので、スケジュール管理が難しくなります。
また、企業と企業の面接日程が重なってしまったりすることもあります。
自分がエントリーした企業のスケジュールを確認し、無理をしないようにしましょう。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
行きたい企業の締切日に遅れないように、しっかりとスケジュールを把握しておいてください。
就活のやり方に関する記事一覧
「最近就活を始めたけど、何から手を付ければいいか分からない」という就活生には、 就職活動の流れ という記事がおすすめです。
以下の記事を読むだけで、就活の流れを完全に理解できるので、就活生なら必ず読んでほしいです。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
ちなみに、「就活の教科書」では有給インターンを募集しています。
以下のリンクからぜひ応募してみてください。
 「就活の教科書」編集長 岡本恵典
「就活の教科書」編集長 岡本恵典
「就活のやり方がわからない…」「就活はどこから始めれば…?」という就活生には、「適性診断AnalyzeU+」がおすすめです。
就活初期の段階で自分の強みや弱みなどの性格を把握していれば、業界・企業選びや、ES、面接で困ることはなくなるからです。
適性診断AnalyzeU+は、100万人のデータをもとに10分~15分で終わる質問からあなたの強みや弱み、適性職種を詳しく検査してくれます。
診断結果をあなたの自己PRに使用でき、プロフィールに入力することで、大手や優良企業から特別スカウトも来ます。
「自分の強みを教えて欲しい!」「ESや面接で困ることなくスムーズに就活を進めたい!」という方は、「適性診断AnalyzeU+」を利用してみてください。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
- 251問の質問と100万人のデータから強み診断してくれるのでかなり正確な結果がわかる
- 診断結果からあなたにおすすめの職種もわかる
- 診断により自己PRが書きやすくなり、ESや面接で人事に評価されるアピールができる
(適性診断AnalyzeU+)
エントリーシートの提出数の決め方
エントリーシートの提出数は人それぞれだということがわかりましたよね。
では、どのようにエントリーシートの提出数を決めればよいのでしょうか?
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
エントリーシートの提出数というのは、言い換えると、「入社したいと思う」かつ「エントリーシートが必要な」企業の数になります。
就活生はそれぞれ自分なりの”就活の軸”を持っています。
就活の軸に沿って入社したい企業を探すので、エントリーシートを提出する企業が人それぞれ違うのは当然のことなのです。
企業が自分の就活の軸に沿っているかは、業界・企業研究をしっかりしていれば、自分がエントリーシートを提出すべき企業が見つかります。
就活では、エントリーしすぎて1社1社のエントリーが疎かになるよりも、ある程度エントリーをして、1社1社丁寧に向き合うことが需要になります。
ただ、エントリーシート20~30社出すのがめんどくさいと思っている就活生もいますよね。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
エントリーシートの提出数は、多ければ多いほど良いというわけではありません。
エントリーシートを書くのに時間をかけすぎてグループディスカッションや面接の対策ができなくなってしまうからです。
僕の経験から言うと、「とりあえず」でエントリーシートを提出しても時間の無駄になるだけでした。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
数々のESをどのくらいの時期から準備したら良いのか分からない人は、業界ごとのES提出時期が分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
「数が多ければいい」という訳ではないのは、本選考もインターンシップも同じです。
この記事では本選考のエントリー数について解説していますが、インターンシップのエントリー数が気になる就活生もいると思います。
そこで、インターンシップの平均エントリー数を解説している記事を紹介するので、ぜひ読んでみてください。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
「就活を始めてみたもののまだわからないことが多い…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」であなたの性格を診断するのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、10分~15分で終わる質問と100万人のデータからあなたの強みと弱み、おすすめ職種を診断してくれます。
また、診断後にあなたの強みや弱み、専攻などをOfferBoxのプロフィールに入力することで、大手や隠れ優良企業からの特別スカウトをもらえます!
「就活で何をすれば良いかわからない…」という人は、単なる自己分析だけではなく、「自分に合う」企業からの特別スカウト機能もある適性診断AnalyzeU+で診断してみると良いですよ!
(適性診断AnalyzeU+)
エントリーシートの提出にかける時間を抑える方法
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
エントリーシートをあまり書きたくないという方のために、エントリーシートの提出にかける時間を抑える方法を紹介します。
エントリーシートの提出にかける時間を抑える方法は3つあります。
- 自己分析と企業研究で絞る
- OpenESでもよい企業を受ける
- エントリーシートを出さなくてよい企業を受ける
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
それでは、1つずつ見ていきましょう。
かける時間を抑える方法①:自己分析と企業研究でエントリー数を絞る
エントリーシートの提出にかける時間を抑える方法の1つ目は、自己分析と企業研究でエントリー数を絞る方法です。
なぜなら、自己分析をすることで就活の軸がより具体的になり、企業研究によってそれに合った企業が見つかるからです。
エントリーシートを提出したい企業が多すぎると感じるときは、どの企業にも当てはまるような広すぎる就活の軸を設定していることが多いです。
例えば、「若いうちから裁量権が与えられる企業」や「人を笑顔にできる仕事」などはおおよその企業に当てはまります。
提出しようか迷っているエントリーシートがある場合は、自己分析と企業研究をやり直してみてください。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
かける時間を抑える方法②:OpenESを利用する
エントリーシートの提出にかける時間を抑える方法の2つ目は、OpenESを利用する方法です。
OpenESとは、リクナビが提供する複数の企業にエントリーシートを提出できるサービスです。
OpenESでエントリーできる企業は5000社以上あり、中にはOpenESしか受け付けていない企業もあるほどです。
エントリーシートをデータで管理できるので、印刷するだけですぐに提出できます。
そして、一度書くだけで多くの企業に使い回せるので、大幅に時間を短縮できます。
僕もOpenESを使っていましたが、好きな時に修正することもできるので、とても使いやすかったです。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
OpenESについてや書き方を詳しく知りたい就活生は、こちらの記事を参考にしてください。
かける時間を抑える方法③:エントリーシートを出さなくてよい企業を受ける
エントリーシートの提出にかける時間を抑える方法の3つ目は、エントリーシートを出さなくてよい企業を受ける方法です。
特にベンチャー企業に多いのですが、エントリーシートを出さなくてよい企業があります。
エントリーシートを書く手間は省けますが、大手企業などの選択肢を最初から削ってしまうことになります。
志望している企業にエントリーシートが必要なら、大人しくエントリーシートを書いて提出しましょう。
のちに後悔したくないですよね。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
かける時間を抑える方法④:就活エージェントを利用する
エントリーシートの提出にかける時間を抑える方法の4つ目は、就活エージェントを利用する方法です。
就活エージェントは、アドバイザーが内定までお手伝いしてくれる無料の就活サービスです。
就活エージェントを利用すると、エントリーシートの添削や就活生に合った企業を紹介してもらえます。
自分に合わない企業にエントリーシートを出さなくて済むため、提出数を抑えることができますよ。
有名な就活エージェントには、レバレジーズ株式会社が運営する「キャリアチケット」などがあります。
就活エージェントを利用するなら、こちらの記事に内定者が選んだおすすめの就活エージェントがまとめてあります。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
「就活のやり方がわからない…」「就活はどこから始めれば…?」という就活生には、「適性診断AnalyzeU+」がおすすめです。
就活初期の段階で自分の強みや弱みなどの性格を把握していれば、業界・企業選びや、ES、面接で困ることはなくなるからです。
適性診断AnalyzeU+は、100万人のデータをもとに10分~15分で終わる質問からあなたの強みや弱み、適性職種を詳しく検査してくれます。
診断結果をあなたの自己PRに使用でき、プロフィールに入力することで、大手や優良企業から特別スカウトも来ます。
「自分の強みを教えて欲しい!」「ESや面接で困ることなくスムーズに就活を進めたい!」という方は、「適性診断AnalyzeU+」を利用してみてください。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
- 251問の質問と100万人のデータから強み診断してくれるのでかなり正確な結果がわかる
- 診断結果からあなたにおすすめの職種もわかる
- 診断により自己PRが書きやすくなり、ESや面接で人事に評価されるアピールができる
(適性診断AnalyzeU+)
エントリーシートに関するよくある質問
質問:就活で10社しか受けないのは少ない?
結論、就活で10社しか受けないのが少ないかどうかは選考状況によります。
まず、エントリーを10社しかしないのは少ない、と言えます。
エントリー数の平均は20~30社立つのが一般的なので、エントリー10社は少ないですね。
続いて、エントリーシート(ES)を10社しか提出しないのはやや少ない、と言えます。
ES提出の平均は12.1社なので、やや少ないでしょう。
また、あなたがどれくらいES通過できるかによっても変わります。
ESの出来栄えに自信があり、通過率が高いなら10社でも大丈夫ですが、自信がなければ15社以上は出した方が良いでしょう。
「就活で10社しか受けないのは少ない?」以外のよくある質問は、以下の記事で紹介していますので、読んでみてくださいね。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
「就活を始めてみたもののまだわからないことが多い…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」であなたの性格を診断するのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、10分~15分で終わる質問と100万人のデータからあなたの強みと弱み、おすすめ職種を診断してくれます。
また、診断後にあなたの強みや弱み、専攻などをOfferBoxのプロフィールに入力することで、大手や隠れ優良企業からの特別スカウトをもらえます!
「就活で何をすれば良いかわからない…」という人は、単なる自己分析だけではなく、「自分に合う」企業からの特別スカウト機能もある適性診断AnalyzeU+で診断してみると良いですよ!
(適性診断AnalyzeU+)
そもそも「エントリーシート(ES)」とは
エントリーシートとは選考に使うための応募書類です。
企業はエントリーシートを見て、その就活生に面接をする価値があるか決めます。
面接もエントリーシートに書かれていることを深く質問していきます。
就活生にとってエントリーシートは、その後の面接の流れを決めるとても重要な書類なのです。
そのため、1枚ずつ丁寧に書かなければエントリーシートを出す意味がありません。
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
そうだったんですね。
1枚ずつに時間がかかるのなら、あまりたくさんエントリーシートは出せないですね。
そうです。
質を落としてまで量を重視する必要はありません。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部
エントリーシートは、文章以前に提出方法やマナーを間違えると通過率が下がります。
ES提出方法やマナーからおさらいしたい人は、メールでESを送る方法やESの印刷方法が分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
「就活のやり方がわからない…」「就活はどこから始めれば…?」という就活生には、「適性診断AnalyzeU+」がおすすめです。
就活初期の段階で自分の強みや弱みなどの性格を把握していれば、業界・企業選びや、ES、面接で困ることはなくなるからです。
適性診断AnalyzeU+は、100万人のデータをもとに10分~15分で終わる質問からあなたの強みや弱み、適性職種を詳しく検査してくれます。
診断結果をあなたの自己PRに使用でき、プロフィールに入力することで、大手や優良企業から特別スカウトも来ます。
「自分の強みを教えて欲しい!」「ESや面接で困ることなくスムーズに就活を進めたい!」という方は、「適性診断AnalyzeU+」を利用してみてください。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
- 251問の質問と100万人のデータから強み診断してくれるのでかなり正確な結果がわかる
- 診断結果からあなたにおすすめの職種もわかる
- 診断により自己PRが書きやすくなり、ESや面接で人事に評価されるアピールができる
(適性診断AnalyzeU+)
まとめ:入社する覚悟がある企業にだけエントリーシートを提出しよう!
今回の「【内定者が教える】エントリーシートは何社出すべきか?適切な提出数と数の抑え方を紹介」はいかがだったでしょうか?
この記事では、エントリーシートの平均提出数と提出数の決め方、提出数の抑え方についてまとめました。
今回の記事をまとめると以下の通りです。
就活生のエントリーシートの平均提出数 ⇒ 14.1社
内定者が実際に出したエントリーシートの数
提出数の抑え方
- OpenESを利用する
- エントリーシートを出さなくてよい企業を受ける
- 就活エージェント「キャリアチケット」を利用する
本当に入社したいと思ったら、時間が許す限り1枚ずつ時間をかけて書きましょう。
「就活の教科書」では、就活に関する有益な記事をたくさん掲載しています。
エントリーシートの対策は「【就活でよく聞かれた】エントリーシート(ES)の質問項目100選」で詳しく解説しているので合わせて読んでみてくださいね。
 「就活の教科書」編集部
「就活の教科書」編集部