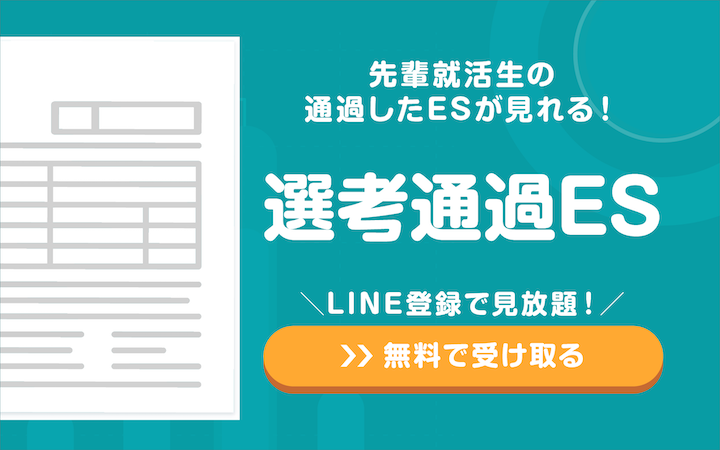- インフラ業界とは生活に密着したサービス・仕組みを提供する業界
- インフラ業界の志望動機の例文3選
- インフラ業界の志望動機を魅力的にするには実現したいことを伝える
- インフラ業界の志望動機を伝えるときは企業毎の強みを理解しないといけない
- インフラ業界の志望動機を伝える上で参考になること
-
【優良版】内定者のESが見れるおすすめツール
-
【就活生】選考通過ES(無料公式LINE)
(選考通過ES見放題,ガクチカや志望動機の書き方が分かる) -
【就活生】unistyle(ユニスタイル)
(選考通過ESが71,733枚見放題) -
【25卒優先】キャリアチケット
(プロのES添削/企業紹介から内定までサポート)
-
【就活生】選考通過ES(無料公式LINE)
みなさん、こんにちは。「就活の教科書」編集部の坂本です。
この記事ではインフラ業界の志望動機について解説していきます。
みなさんはインフラ業界の志望動機を考える時に悩んだことはありませんか?
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
私の就活の第一志望は、インフラ業界です。
ですが、インフラ業界を志望している人が多いので、どうやったら他の就活生に負けない志望動機ができるのか悩んでいます
 就活生くん
就活生くん
正直、就活を始めたばかりで、インフラとは何か分からないです。
ただ、インフラ業界は人気だと聞くので漠然と行けたらいいなと思っています。
そのため、インフラ業界の仕事を知って、インターンに参加するためにインフラ業界の志望動機の例文を参考にしたいです。
インフラ業界は、就活生から人気の業界でレベルの高い志望動機が求められますよ。
しかし、インフラ業界は、普段の生活では直接関わることが少ないので、イメージしにくいかもしれません。
ちなみに、「志望企業のESで落ちたくない!」という方は、難関企業内定者のESが無料で見れる「選考通過ES(公式LINEで無料配布)」などのサービスを活用しましょう。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
そこでこの記事ではインフラ業界の志望動機を魅力的に伝える例文を解説します。
合わせて、インフラ業界の志望動機を魅力的に伝えるコツやインフラ業界の志望動機を魅力的に伝えるための注意点も解説しています。
この記事を読めば、「もっとインフラ業界の志望動機を工夫すればよかった・・・」なんて後悔を避けられます。
魅力的な志望動機を伝えて、無事にインフラ業界の内定をもらいたい就活生は、ぜひ最後まで読んでくださいね。
「エントリーシートを上手く書けない…落ちるかも…」という方は、「選考通過ES(公式LINEで無料見放題)」を使って、難関企業内定者のESを見るのが一番おすすめです。
ちなみに「選考通過ES(公式LINEで無料見放題)」以外にも、選考通過ESが71,733枚見放題の「unistyle」、プロからのES添削/面接対策を頼める「キャリアチケット」もおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
- 【就活生】選考通過ES(公式LINEで無料見放題)
【公式サイト】https://reashu.com/linelp-es/
- 難関企業内定者のESが見放題
- 【就活生】unistyle(選考通過したESが71,733枚見放題)
【公式サイト】https://unistyleinc.com/
- 人気企業のES締め切り日が見れる
- 【25卒優先】キャリアチケット(ES添削から内定獲得までサポート)
【公式サイト】https://careerticket.jp/
- あなたに寄り添ったES添削で内定獲得
「結局どのサービスを使えば良いかわからない…」という方は、「選考通過ES(公式LINEで無料見放題)」「unistyle(ユニスタイル)」を同時に使うのが一番おすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
目次
インフラ業界とは生活に密着したサービス・仕組みを提供する業界
 就活生くん
就活生くん
就活を始めてインフラ業界に憧れを持っていますが、正直インフラとは何か理解できてないんですよね。
確かにインフラ業界と言っても、通信、ガス、鉄道など様々な業界があるので分かりづらいですよね。
そもそもインフラとは何かわからない人も多くいるんじゃないでしょうか。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
インフラ業界とはインフラストラクチャーの略称で、社会の基盤となる私たちの生活に密着したサービス・仕組みを提供することが主たる事業の業界のことです。
具体的には鉄道、航空、ガス、電力会社などがインフラ業界に当たります。
インフラ業界は常に需要のある業界なので、企業の業績も他の業界に比べ安定しているので、就活生に人気の業界になります。
そのため、インフラ業界の志望動機は他の就活生に負けない高いレベルが求められます。
人々の生活を支えることにやりがいを持つ人や、安定した業界に進みたい人にはインフラ業界は向いていますね。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
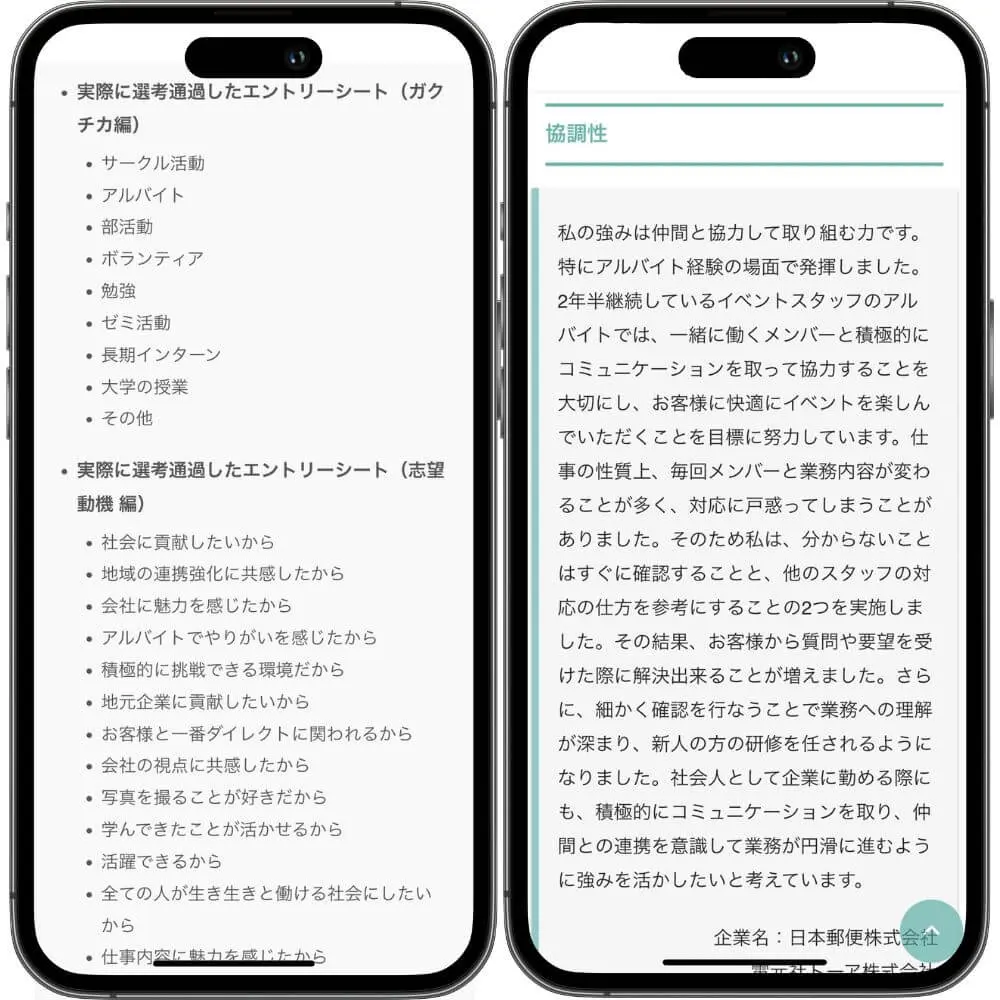
- 難関企業内定者の自己PRやガクチカ、志望動機などの文章が見れる
- 評価されるESの書き方がわかるので、選考突破率UP
- 自分のESを考える時間がない方はESをそのままパクってもOK
選考通過ES
また、ES添削については「【誰に頼むのが良い?】エントリーシート添削の無料サービスおすすめ15選 | ES添削の有料サイトも」という記事にまとめています。
この記事を読むと選考に通過するES添削をしてもらえます。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
インフラ業界の志望動機の例文3選
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
私は人々の生活を支えるインフラ業界が第一志望なので、誰にも負けない志望動機を作りたいです。
では、インフラ業界の志望動機の例文を紹介するのでぜひ参考にしてください。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
- 例文①:通信インフラ編
- 例文②:ガスインフラ編
- 例文③:鉄道インフラ編
それでは、インフラ業界の志望動機の例文を1つずつ見ていきましょう。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
例文①:通信インフラ編
インフラ業界の志望動機の例文1つ目は通信インフラ編です。
「どこにいても、まるで隣にいるような、人と人が繋がることができる世界」を当たり前にしたいです。
短期留学を通じ、人との繋がりが幸福度に繋がっていると確信しました。
この世界を実現し、孤独死や地方格差の問題を解決し、日本人の幸福度も上げていきたいです。
貴社にはICTの技術力、圧倒的顧客数によるデータ、挑戦を共に成し遂げていく人やパートナー企業、今後の5Gへの1兆円の投資により実現できると考えています。
アルバイト先の予備校では、日本1合格率の高い校舎を作るという目標を達成するために、周りと協力し困難を乗り越えてきました。
この経験を活かし、多くの人や企業を巻き込みながら貴社で上記の夢を叶えたいです。
この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。
また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文①では通信インフラの志望動機が書かれています。
自分が成し遂げたい夢と志望企業でなければいけない理由が書かれており、魅力的な志望動機です。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
例文②:ガスインフラ編
インフラ業界の志望動機の例文2つ目はガスインフラ編です。
私が貴社を志望する理由は、中国地方と都市の格差を減らしていきたいからです。
私は大学での研究を通して、中国地方と年の格差により都市部への人口流出、少子高齢化の問題を学びました。
そこから中国地方を盛り上げていきたいと感じるようになりました。
なので、電力を多くの人に届けることで様々な人の活動を支え、中国地方を盛り上げられると考え、電力業界を志望しています。
その中でも貴社を志望する理由は経営理念や地域密着で事業を行っていたからです。
ただ、電力を売るだけでなく、地域振興にも力を入れている貴社に魅力を感じました。
私の強みは行動力であり、貴社に入社した暁には、営業職としてお客様一人一人のお話を聞きいき信頼を獲得していきたいと考えています。
この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。
また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文②ではガスインフラの志望動機が書かれています。
自分の具体的な経験から志望動機が生まれていることは、非常に好印象です。
また、自分の強みを最後に伝えることも高評価に繋がる志望動機です。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
例文③:鉄道インフラ編
インフラ業界の志望動機の例文3つ目は鉄道インフラ編です。
私は地元と日本の発展に貢献したいと思い貴社を志望しました。
自分の地元だった田舎の街が新幹線の開通に向けて変わっていく姿をみて、「地元の活性化のために新幹線を支える仕事がしたい」と考えるようになりました。
貴社は職種に関係なく責任のある業務を担当でき、職種次第では特定の仕事に従事し専門性を磨ける点に魅力を感じました。
将来は、留学の経験を活かして、外国人観光客の誘致に関する業務に挑戦したいです。
この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。
また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
例文③では鉄道インフラの志望動機が書かれています。
実際の経験から志望動機が生まれているのは非常に説得力があります。
また、将来的にやりたいことを自分の強みとセットで書いているのも高評価対象になる志望動機です。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
鉄道インフラを受けたい人は、鉄道インフラに特化した志望動機の記事があるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
「ESが上手く書けない…」「ES選考で落ちてしまう…」なら、就活の教科書公式LINEから無料で受け取れる「選考通過ES」がおすすめです。
選考通過ESは、大手企業内定者のESが見放題なので自己PR・ガクチカ・志望動機などでの悩みがなくなります。
また実際に利用した就活生からは、「ESを何社か書いていて、なかなか上手く書けていなかったので、これを知ってうまく書けるようになりました。」などの口コミもいただいています。
人事に評価されるESの書き方もわかり、ESで落ちる確率をかなり減らせるので、ぜひ公式LINEから使ってみてくださいね。
選考通過ES
インフラ業界の志望動機を魅力的に伝えるコツ3つ
 就活生くん
就活生くん
やはりインフラ業界と言えども、通信業界やガス業界では志望動機は全然違うんですね。
魅力的なインフラ業界の志望動機を書くコツみたいなものはありますか。
インフラ業界の志望動機を魅力的に書くコツは3つあるので紹介しますね。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
- コツ①:絶対に志望企業でないといけない理由があるか
- コツ②:実現したいことがあるか
- コツ③:自分の長所が活かせるか
それでは、インフラ業界の志望動機を魅力的に伝えるコツを見ていきましょう。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
コツ①:絶対に志望企業でないといけない理由があるか
インフラ業界の志望動機を魅力的に伝えるコツ1つ目は、「絶対に志望企業でないといけない理由があるか」です。
もし仮に、他社でも通用するような志望動機であれば、面接官は採用しても辞退されそうと考え、内定を付与しないからです。
例えば、災害時に安心・安全の電波を届けたいので通信インフラ企業の御社で働きたいなどです。
「〇〇だから、〇〇じゃないといけないんです」と伝えられるようにしましょう。
もし、他社との違いが見出せない場合は、志望企業の文化や雰囲気を踏まえて志望動機で話すようにしましょう。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
コツ②:実現したいことがあるか
インフラ業界の志望動機を魅力的に伝えるコツ2つ目は、「実現したいことがあるか」です。
志望動機に実現したいことがある就活生だと、夢の実現のために企業を引っ張ってくれそうと面接官は感じ採用します。
例えば、ガスインフラ企業でガスをただ売るのではなく、地域振興に力を入れ、地域格差を無くしていきたいなどです。
志望企業で実現したいことが達成できるかは事前に確認しましょう。
夢がある人とない人では、単純に仕事への熱量が違うのは誰でもイメージ出来ますよね。
夢がない人はOB訪問などを行い、先輩が志していることを聞いて志望動機の参考にしましょう。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
コツ③:自分の長所が活かせるか
インフラ業界の志望動機を魅力的に伝えるコツ3つ目は「自分の長所が活かせるか」です。
志望動機に自分の長所の活かし方があると、面接官に説得力を与えられるからです。
例えば、東進の林修先生は教えるのが好きではなくても、得意であったために教育業界に進んだそうです。
自分の強みが活かせることは成果を出しやすいことに繋がります。
やりたいことがあるのは大事ですが、やりたくても自分が向いていない可能性もあります。
志望動機に自分の強みが活かせるかは本当に必要な視点になるので意識しましょう。
求められるスキルが分からない人は、OBOG訪問を行い成功している人の共通点を聞きましょう。
共通点が自分の強みと同じ場合は、志望動機に自分の強みの活かし方を伝えましょう。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
志望動機の作成に役立つ記事一覧
「志望動機が思いつかない」「内定者の志望動機の例文を見たい!」という就活生には 志望動機の書き方 という記事がおすすめです。
この記事を読めば、志望動機の書き方のコツや例文について分かり、ESの選考で落ちにくくなるので、ぜひ参考にしてください。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
ちなみに、「就活の教科書」では有給インターンを募集しています。
以下のリンクからぜひ応募してみてください。
 「就活の教科書」編集長 岡本恵典
「就活の教科書」編集長 岡本恵典
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
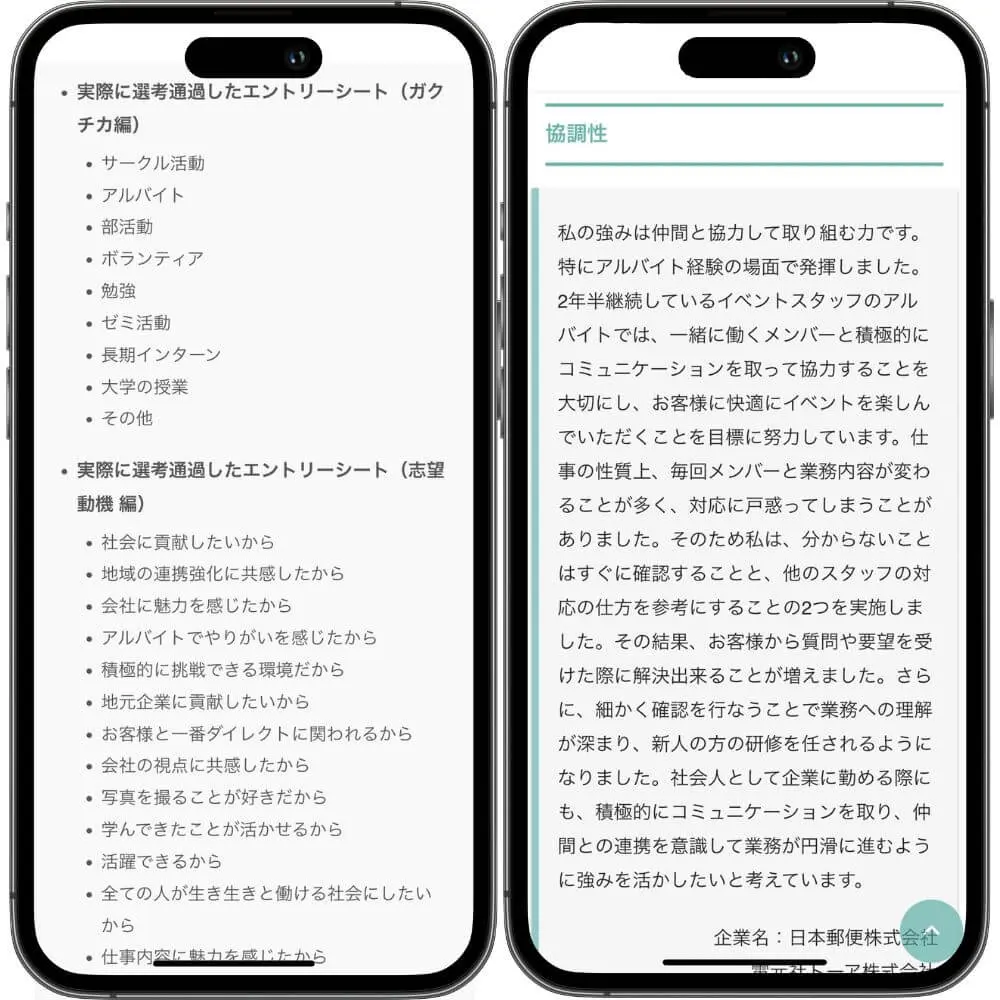
- 難関企業内定者の自己PRやガクチカ、志望動機などの文章が見れる
- 評価されるESの書き方がわかるので、選考突破率UP
- 自分のESを考える時間がない方はESをそのままパクってもOK
選考通過ES
また、ES添削については「【誰に頼むのが良い?】エントリーシート添削の無料サービスおすすめ15選 | ES添削の有料サイトも」という記事にまとめています。
この記事を読むと選考に通過するES添削をしてもらえます。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
インフラ業界の志望動機を伝えるときの注意点3つ
 就活生くん
就活生くん
インフラ業界の志望動機を魅力的に伝えるには、実現したいことがあるかどうかが大切なんですね。
では、逆にインフラ業界の志望動機を伝えるときの注意点はありますか。
インフラ業界の志望動機を伝えるときの注意点は3つあるので紹介しますね。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
- 注意点①:志望動機が明確でない
- 注意点②:企業毎の強みを理解していない
- 注意点③:業務内容が理解できていない
それでは、インフラ業界の志望動機を伝えるときの注意点を見ていきましょう。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
注意点①:志望動機が明確でない
インフラ業界の志望動機を伝えるときの注意点1つ目は、「志望動機が明確ではない」です。
なぜこの業界で、なぜこの企業で、なぜこの業種なのかを流れで伝えないと、志望動機が曖昧で落とされるからです。
例えば、災害時でも安心を届ける通信業界で、その中でも5Gの技術力が高い貴社で、より良い通信サービスを直接届けたいので営業職志望です、などです。
志望動機が明確に話せると企業への本気度も伝わり、内定までの道のりはグッと近づきます。
私も初めは友人に志望動機を聞いてもらうなどして、何度も作り直して話す練習をしていました。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
注意点②:企業毎の強みを理解していない
インフラ業界の志望動機を伝えるときの注意点2つ目は、「企業毎の強みを理解していない」です。
企業毎の強みを理解していないと、他社と自社の強みを比較して話された時に黙り込んでしまうからです。
 就活生くん
就活生くん
A社には〇〇という強みがある、その強みが私の夢の実現のためには必要不可欠です。
確かに自社には〇〇という強みはありますが、B社にも同じ強みがあるのに、どうしてB社ではダメなんですか?
 人事さん
人事さん
 就活生くん
就活生くん
…
企業毎の強みを理解し、志望動機で他社との比較までしっかり話せるようにしましょう。
ただ、インフラ業界は強みが似ている場合もあるので、その場合は「OB訪問を通して御社の社員と一緒に働きたいと感じました」などと言うのも効果的です。
実際に私も他社との違いを聞かれた時に、OB訪問での社員の雰囲気などを伝えて、高評価を変えていましたよ。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
注意点③:業務内容が理解できていない
インフラ業界の志望動機を伝えるときの注意点3つ目は、「業務内容が理解できていない」です。
業務内容が理解できていないと、面接官は入社後のイメージを想像しづらく不採用と判断するからです。
入社後は弊社のような鉄道インフラ企業でどんな仕事をしていきたいですか。
 人事さん
人事さん
 就活生くん
就活生くん
入社後は、地域発展に貢献していきたいです。
仕事のイメージを聞かれたときに抽象的な答えを返すと、面接官は仕事のイメージをつけられないので気を付けましょう。
法人企業に対して営業を行い、将来的には地域発展に貢献していきたいなどと答えましょう。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
「ESが上手く書けない…」「ES選考で落ちてしまう…」なら、就活の教科書公式LINEから無料で受け取れる「選考通過ES」がおすすめです。
選考通過ESは、大手企業内定者のESが見放題なので自己PR・ガクチカ・志望動機などでの悩みがなくなります。
また実際に利用した就活生からは、「ESを何社か書いていて、なかなか上手く書けていなかったので、これを知ってうまく書けるようになりました。」などの口コミもいただいています。
人事に評価されるESの書き方もわかり、ESで落ちる確率をかなり減らせるので、ぜひ公式LINEから使ってみてくださいね。
選考通過ES
インフラ業界の志望動機を書く上で参考になること
 就活生くん
就活生くん
インフラ業界の志望動機を書く上では、企業毎の強みなどを比較して話せないといけないんですね。
ただ、OB訪問できない企業などはどうやって企業の強みなど知ればいいのでしょうか。
確かに、企業次第ではOB訪問できない企業はありますね。
では、インフラ業界の志望動機を書く上で参考になることを紹介します。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
インフラ業界の志望動機を書く上で参考になるのはOPENWORKです。
OPENWORKは、300万人のユーザーを抱え、約740万件の様々な企業の社員の口コミが見れるサイトです。
具体的には企業毎の強みや、組織文化、入社理由などがあり、志望動機を作る上でも非常に参考になります。
私も就活生時代はOPENWORKをかなり使っていました。
実際に働いている人がどう感じているのかも見れるので、企業を選ぶ上でも非常にオススメです。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
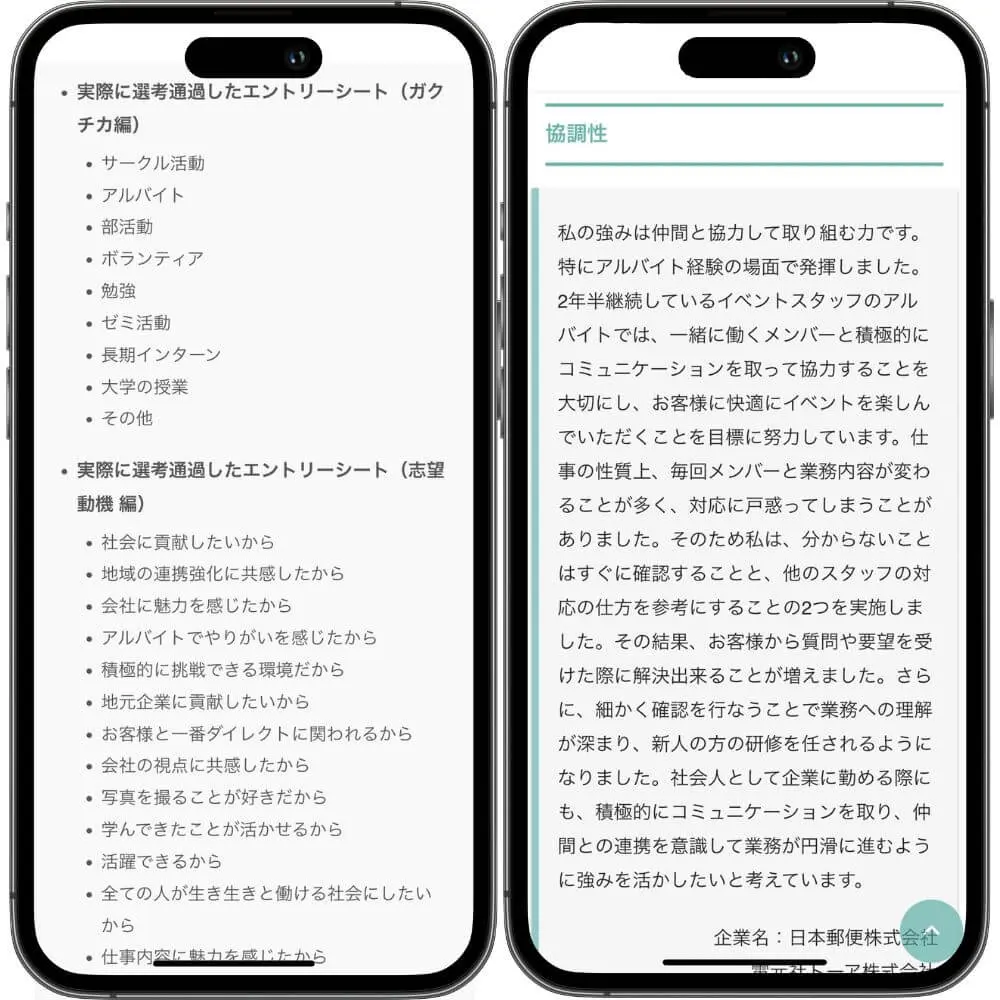
- 難関企業内定者の自己PRやガクチカ、志望動機などの文章が見れる
- 評価されるESの書き方がわかるので、選考突破率UP
- 自分のESを考える時間がない方はESをそのままパクってもOK
選考通過ES
また、ES添削については「【誰に頼むのが良い?】エントリーシート添削の無料サービスおすすめ15選 | ES添削の有料サイトも」という記事にまとめています。
この記事を読むと選考に通過するES添削をしてもらえます。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
まとめ:インフラ業界の志望動機を魅力的に伝えて内定を勝ち取ろう
「【例文あり】インフラ業界「志望動機」の上手な伝え方 | 注意点,向いている人も」の記事はいかがでしたか。
この記事では「インフラ業界の志望動機の例文」を解説しました。
合わせて、インフラ業界の志望動機を魅力的に伝えるコツやインフラ業界の志望動機を伝えるときの注意点も解説しました。
最後に、この記事のまとめをおさらいしましょう。
◆インフラ業界とは
◆インフラ業界の志望動機の例文3選
- 例文①:通信インフラ編
- 例文②:ガスインフラ編
- 例文③:鉄道インフラ編
◆インフラ業界の志望動機を魅力的に伝えるコツ3つ
- コツ①:絶対に志望企業でないといけない理由があるか
- コツ②:実現したいことがあるか
- コツ③:自分の長所が活かせるか
◆インフラ業界の志望動機を伝えるときの注意点3つ
- 注意点①:志望動機が明確でない
- 注意点②:企業毎の強みを理解していない
- 注意点③:業務内容が理解できていない
◆インフラ業界の志望動機を書く上で参考になること
◆まとめ:インフラ業界の志望動機を魅力的に伝えて内定を勝ち取ろう
インフラ業界の志望動機を伝えるときは、志望企業での実現したいことを伝えることが大切でしたね。
また、インフラ業界の志望動機を伝えるときは他社毎の強みを把握し、比較して話せるようになることが大切でしたね。
この記事が良いなと思った人は、ぜひ友人や後輩にもシェアしてあげてくださいね!
「就活の教科書」には、就活に役立つ記事が他にもたくさんありますよ。
他の記事も読んでみてくださいね。
 「就活の教科書」編集部 坂本
「就活の教科書」編集部 坂本