- 安定志向とは?
- 安定志向の特徴や業界一覧、メリット
- 実は、安定志向(大手志向)にはデメリットもある
- 個人のスキルアップのために、上昇志向(ベンチャー志向)を持つことも大切
-
【優良版】自己分析を短時間で終わらせられるおすすめツール
-
【1番おすすめ】適性診断AnalyzeU+
(251問の詳しい性格診断) -
【SPIテスト付き】Lognavi適性診断
(性格テスト90問、SPI練習もできる) -
【就活の軸を知れる】キャリアチケットスカウト価値観診断
(たった5つの質問で就活の軸を診断) -
【自分の適職が分かる】LINE適職診断
(あなたの適職を16タイプで診断)
\ 大手/優良企業からスカウトが届く! /
 客観的な性格診断を受ける
客観的な性格診断を受ける
(適性診断AnalyzeU+)
公式サイト
(https://offerbox.jp/)
*プロフィール登録で優良企業のスカウトGET! -
【1番おすすめ】適性診断AnalyzeU+
こんにちは。「就活の教科書」編集部の中澤です。
この記事では「安定志向」ついて解説します。
就活生みなさんは、「安定志向ってどうなんだろう」と思ったことはありませんか。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
 就活生くん
就活生くん
自己分析をしていて、自分は安定志向だと感じる行動がこれまで多いと感じました。
安定志向の人ってどんな特徴があるのか知りたいです。
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
最近友達と話していて、最近は、ベンチャー企業に就職するなど、上昇志向を持った就活生も多いと聞きました。
安定志向と上昇志向のどちらがいいのか分からなくなってきました。
確かに、最近は安定志向だけでなく、個人のスキルを高めていこうとする上昇思考(ベンチャー思考)をもった就活生も多くなっています。
ちなみに、「自分に合った業界が知りたい」「自分の強みがわからない…」という方は、100万人のデータからあなたの強みや性格を分析する「適性診断AnalyzeU+」などで自己分析を終わらせましょう。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
そこでこの記事では「安定志向」と「上昇志向」のそれぞれの特徴を紹介します。
合わせてこれからの時代で必要な上昇志向の考え方や取るべき行動も説明しますね。
この記事を読めば、安定志向と上昇思考のそれぞれの特徴が分かり、就活の選択の役に立ちますよ。
安定志向と上昇志向のどちらが良いか迷っているしゅうぜひ最後まで読んでくださいね。
「自己分析を簡単にやってみたい」という就活生は、「適性診断AnalyzeU+」で性格診断をし、「就活の軸」「強み」などを知るのがおすすめです。
ちなみに「【就活生】適性診断AnalyzeU+」以外にも、性格テスト90問で長所や適職を診断できる「Lognavi適性診断」、たった5つの質問で就活の軸を知れる「キャリアチケットスカウト価値観診断」、あなたの適職を16タイプで診断できる「LINE適職診断」もおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
- 【就活生】適性診断AnalyzeU+(全251問、客観的な性格診断)
【公式サイト】https://offerbox.jp/
- 診断でSPI性格検査の練習も
- 【就活生】Lognavi適性診断(性格テスト90問で長所や適職を診断)
【公式サイト】https://lognavi.com/
- SPI問題も無料、180,000人が利用中
- 【就活生】キャリアチケットスカウト価値観診断(たった5問で価値観診断)
【公式サイト】https://careerticketscout.jp/
- 優良企業からの特別案内も届く
- 【就活生/転職者】LINE適職診断(公式LINEで無料診断)
【公式サイト】https://reashu.com/linelp-tekishoku/
- あなたの適職を16タイプで診断
「結局どのサービスを使えば良いかわからない…」という就活生は、「適性診断AnalyzeU+」であなたの強みを正確に診断するのがおすすめですよ。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
目次
「安定志向」と「上昇志向」どちらが良い?
 就活生くん
就活生くん
安定志向ってそもそもどういう意味だろう・・・
一般的に、安定志向って何が安定しているんですか?
確かに、何の安定を意味しているのかは大切ですよね。
安定志向とは、「雇用や福利厚生が安定している大手の企業や組織に就職したい」という考え方です。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
 就活生くん
就活生くん
なるほど、安定志向の就活生は、将来の生活の安定を重視して就活をしているんですね。
自己分析の参考にしたいのですが、安定志向の就活生の特徴ってありますか?
安定志向の就活生にどんな特徴があるかは気になりますよね。
自分が安定志向かどうかで適正のある業界や企業も変わでしょう。
次は、安定志向に就活生の特徴を紹介します。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
安定志向の特徴
安定志向の特徴を紹介していきますね。
【安定志向の特徴】
- 特徴①:周りの変化が早いと感じる
- 特徴②:環境が変わるのを恐る
- 特徴③:真面目と言われる
- 特徴④:自信がなく挑戦をしない
変化への対応が遅かったり、自分が変化するのを好まないのが安定志向の特徴ですね。
理由としては、安定志向の人は、親や先生から言われたとおりに行動してきたため、自分から行動するのが苦手な人が多いというのがありますね。
安定志向の人は、現状維持をする傾向が強いので、変化を求めないのでしょう。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
安定志向のメリット
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
私は自分が安定志向だと思うのですが、安定志向の性格のメリットがわかりません。
安定志向であるメリットって何ですか?
安定志向のメリットはいくつかありますよ。
例えば、将来を見据えた生活を送るので精神的に安定していたり、変化による過度なストレスを感じない生活を送れます。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
 就活生くん
就活生くん
なるほど、安定志向の精神的に病んだりしにくくなるんですね。
僕は安定志向かどうかわかっていません。
安定志向かどうか知る方法はありますか?
安定志向かどうかを知るには、適性診断ツールを利用するのがおすすめです。
質問に答えるだけであなたの性格や強み、適した職業も教えてくれるため、簡単に安定志向か分かりますよ!
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
数ある自己分析ツールの中でも就活の教科書イチオシは「適性診断AnalyzeU+」です!
全251問の正確な診断ができ、手っ取り早くあなたの強みまで教えてくれます。
診断結果に基づいて
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
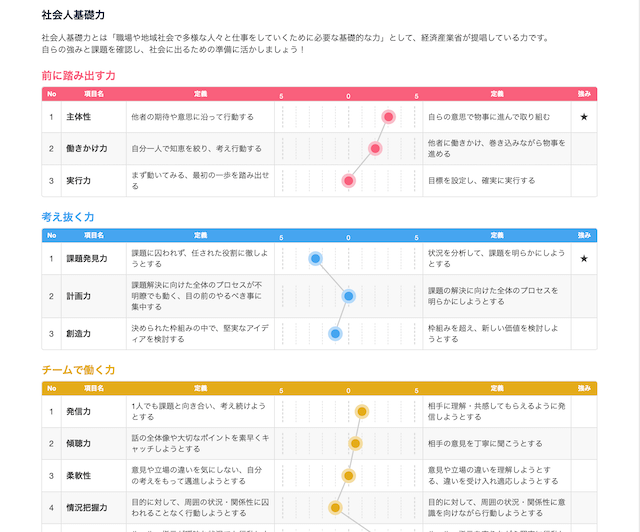
「適性診断AnalyzeU+」では、251問の質問に答えるとあなたの性格や強みが分かります。
あなたに適した組織内での役割や職種も分かるため、簡単かつ詳しく自己分析ができます。
「適性診断AnalyzeU+」は無料で使えるので、ぜひ活用してみてください!
安定志向にはデメリットもあるため、上昇志向も大切!
安定志向には、実はデメリットもあります。
今では、大手企業に入ったからと言って一生安泰という世の中ではありません。
あまりに安定志向に頼り過ぎて、自分にスキルや能力が身に付かない状況に陥るのは避けるべきです。
これからの時代では、個人のスキルや能力を高めることで、安定を得ようとする上昇志向を持つことも必要なのです。
安定志向はもちろん大切ですが、上昇志向の考え方も持っておく必要がある事を頭に入れておく必要があるのです。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
「正直めんどくさい自己分析を早く楽に終わらせたい!」「簡単に自己分析をしたい!」という就活生には「適性診断AnalyzeU+」がおすすめです。
適性診断AnalyzeU+は、100万人のデータをもとに251問の質問からあなたの性格を詳しく検査してくれます。
診断結果をあなたの自己PRに使用でき、プロフィールに入力することで、大手~ベンチャーの優良企業からスカウトも来ます。
「自分に最適な自己分析ツールが知りたい!」と不安な就活生は、「適性診断AnalyzeU+」を利用してみてください。
また、その他のおすすめ自己分析ツールは、「【内定者が選んだ】自己分析ツールおすすめ25選 | アプリ,簡単な適性診断サイト(全て無料)」という記事で紹介しています。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
- 251問の質問と100万人のデータから診断してくれるのでかなり正確な結果がわかる
- 診断結果からあなたにおすすめの職種もわかる
- 診断により自己PRが書きやすくなり、ESや面接で人事に評価されるアピールができる
(適性診断AnalyzeU+)
【安心!】安定志向の就活生が進べき業界一覧
安定志向の就活生が進む業界一覧について紹介していきますね。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
【定志向の就活生が進む業界一覧】
- 業界①:公務員
- 業界②:大手メーカー
- 業界③:インフラ
- 業界④:総合商社
- 業界⑤:大手金融機関
安定志向の就活生が志望する業界は歴史の長い企業が多いです。
なぜなら、歴史が長いと安定して経営できており、雇用が安定していると安定志向の就活生に判断されるからです。
例えば、旧財閥系の三菱、三井、住友系の企業は歴史が長く安定していますよね。
長い歴史のある業界には優秀な人材が集まりやすいので、チェックしておきましょう。
安定志向の就活生が行くべき業界は他にもあります。
安定志向の企業の中でも、本当に自分に合った企業を探すために業界研究のやり方を工夫する必要があります。
以下の記事で、業界研究や企業研究のやり方が詳しく解説されているので、ぜひ参考に自分に合った企業を探してみて下さい。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
「自己分析を簡単にやりたい」「自己分析どこから始めるべき?」という方には、「適性診断AnalyzeU+」を受けるのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、15分程度で終わる質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。
大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK!
スカウトを貰えば、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができます。
「自己分析はどこでやれば…」という人は、適性診断AnalyzeU+を受けてみると良いですよ!
(適性診断AnalyzeU+)
その他の自己分析ツールを利用してみたいという就活生には「自己分析ツールおすすめ25選」という記事がおすすめです。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
大手に行きたい安定志向の就活生がやるべきこと
大手に行きたい安定志向の就活生がやるべきことについて紹介していきますね。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
- やるべきこと①:倍率が高い企業は可能な限りの準備をする
- やるべきこと②:インターンやOB訪問をしっかりする
- やるべきこと③:企業の求める人物像に合わせて自己PRする
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
やるべきこと①:倍率が高い企業は可能な限りの準備をする
大手に行きたい安定志向の就活生がやるべきこと1つ目は、倍率が高い企業は可能な限りの準備をすることです。
大手企業は競争率がとても高く、対策をとらないと内定をもらうのは不可能だからです。
大手の食品メーカーでは、倍率が1000倍以上のところもあるので、自分の志望している業界の大手の倍率は調べてくださいね。
大手の企業はES(エントリーシート)、面接、グループワークワークなどできる限りの準備をしておかなければいけません。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
やるべきこと②:インターンやOB訪問をしっかりする
大手に行きたい安定志向の就活生がやるべきこと2つ目は「インターンやOB訪問をしっかりする」です。
理由は、インターンやOB訪問をして、密度の高い就活をすることで、周りの就活生と差をつけられるからです。
インターンやOB訪問をすれば、企業がどんな人物像を求めているのか分かるようになり、選考対策がしやすくなります。
安定志向で、大手に受かりたい人はインターンやOB訪問を徹底的にしておきましょう。
OB訪問はアポを取ったり、質問内容を考えたりなどやることが多いです。
以下の記事で、OB訪問の準備の仕方や質問の仕方など、OB訪問のやり方が紹介されいているので、ぜひ参考にしてみて下さい。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
やるべきこと③:企業の求める人物像に合わせて自己PRする
大手に行きたい安定志向の就活生がやるべきこと3つ目は「企業の求める人物像に合わせて自己PRする」です。
企業の求める人物像に合わせて自己PRすることで、入社後の活躍をイメージしてもらいやすくなり、合格率が上がります。
例えば、会社の求めている人材の特徴と自分の強みが一致していた場合、採用してもらえる確率は上がるでしょう。
企業が求めている人物像を把握した上で、自分の強みをアピールしましょう。
企業の求める人物像に合わせて、自分の強みをアピールするには、まずは自己分析が欠かせません。
以下の記事で、自己分析の様々なやり方が紹介されているので、ぜひ参考にしてみて下さい。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
自己分析に役立つ記事一覧
自己分析を時間をかけずに終わらせるには、 「①自己分析ツールを使う」 「②効率的な自己分析のやり方を知る」 という2つのやり方があります。
「自己分析をやらなければならないと分かっているけどめんどくさい」 という就活生はこれらの方法を使って自己分析をすることで、簡単に強みや向いている仕事が分かるようになるので、ぜひ参考にしてください。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
ちなみに、「就活の教科書」では有給インターンを募集しています。
以下のリンクからぜひ応募してみてください。
 「就活の教科書」編集長 岡本恵典
「就活の教科書」編集長 岡本恵典
「正直めんどくさい自己分析を早く楽に終わらせたい!」「簡単に自己分析をしたい!」という就活生には「適性診断AnalyzeU+」がおすすめです。
適性診断AnalyzeU+は、100万人のデータをもとに251問の質問からあなたの性格を詳しく検査してくれます。
診断結果をあなたの自己PRに使用でき、プロフィールに入力することで、大手~ベンチャーの優良企業からスカウトも来ます。
「自分に最適な自己分析ツールが知りたい!」と不安な就活生は、「適性診断AnalyzeU+」を利用してみてください。
また、その他のおすすめ自己分析ツールは、「【内定者が選んだ】自己分析ツールおすすめ25選 | アプリ,簡単な適性診断サイト(全て無料)」という記事で紹介しています。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
- 251問の質問と100万人のデータから診断してくれるのでかなり正確な結果がわかる
- 診断結果からあなたにおすすめの職種もわかる
- 診断により自己PRが書きやすくなり、ESや面接で人事に評価されるアピールができる
(適性診断AnalyzeU+)
上昇志向の特徴とは?
 就活生ちゃん
就活生ちゃん
最近、大手企業でも一生安泰ではないという事をよく聞きます。
大手に入社したからといって安定した生活が送れるわけではないのでしょうか。
確かに、大手に入社すれば、一生安泰という時代ではないですね。
技術革新やグローバル化によって、これまで安定した経営をしていた企業でも倒産してしまうリスクはありますよ。
そんな状況も踏まえて、最近は安定志向に変わって、上昇志向を持った就活生が多くなっています。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
現在は変化が激しい時代なので、組織に所属して安定を求めるよりも、個人のスキルを高めて安定を目指す上昇志向を持った就活生も増えてきています。
このように、個人のスキルを高めておくことで、企業の経営が悪化しても、別の仕事を獲得できます。
例えば、エンジニアとしての能力を磨いておけば、現在働いている会社がなくなっても、他の会社でスキルを活かせますよね。
個人としてのスキルを身につけるためにも、安定志向だけでなく、上昇志向の考え方も取り入れてみる事をオススメします。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
最近は「安定志向」よりも「上昇志向」の人が増えている
 就活生くん
就活生くん
私の周りの友達には起業したり、外資系に就活したりしている友達も何人かいます。
就活生は全員安定志向ではないのでしょうか。
はい、全員が安定志向ではありませんよ。
就活生の中には安定志向とは別に「上昇志向」の人もいますね。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
 就活生くん
就活生くん
なるほど、全員が安定志向ではないんですね。
上昇志向の人ってどんな人なんですか。
上昇志向の人について簡単に説明しますね。
これからの時代は個人の力で稼ぐ力を身につけた方が結果として安定に繋がると考える就活生もいます。
一般的には、個人の力を磨こうとベンチャー企業に入社する人を「上昇志向」のある人と捉えます。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
上昇志向であるメリット
次は、上昇志向のメリットについて説明しますね。
上昇志向のメリットは4つあります。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
【上昇志向のメリット】
- メリット①:成長しやすい
- メリット②:他人から評価されやすい
- メリット③:活躍の幅が広がりやすい
- メリット④:昇進しやすい
1つ目のメリットの成長しやすいというのが、他の他人からの評価、自身の活躍の幅・昇進に繋がります。
他人から認められるような成長をすれば、任せられる仕事の種類や大きさに繋がり、さらに成功すると他人から認められるという循環になるからです。
常に成長できる環境にいたいと思う人にとっては、上昇志向の人が多い職場を選ぶと良いでしょう。
ベンチャー企業には、上昇志向を持った企業が多い傾向があります。
以下の記事でベンチャー就職について解説しているので、ぜひ参考にベンチャー企業も検討してみて下さい。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
「自己分析を簡単にやりたい」「自己分析どこから始めるべき?」という方には、「適性診断AnalyzeU+」を受けるのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、15分程度で終わる質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。
大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK!
スカウトを貰えば、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができます。
「自己分析はどこでやれば…」という人は、適性診断AnalyzeU+を受けてみると良いですよ!
(適性診断AnalyzeU+)
その他の自己分析ツールを利用してみたいという就活生には「自己分析ツールおすすめ25選」という記事がおすすめです。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
上昇思考を持った就活生が取るべき行動
上昇志向を持った就活生が取るべき行動について紹介していきますね。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
- 行動①:早めから対策する
- 行動②:長期インターンをする
- 行動③:就活エージェントを利用する
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
行動①:早めから対策する
上昇志向を持った就活生が取るべき行動の1つ目は、早めから対策することです。
ベンチャー企業など、上昇志向の強い企業の募集は一般的な企業の募集より早い傾向があるからです。
一般的な企業の説明会やエントリーが始まるのは、3年生の3月からですが、良い人材を確保するために早期に選考が行われる場合もあります。
特に、ベンチャー企業に応募しようと思っている就活生は、周りの就活生よりも早く2年の春休みから就活を始めるようにしてくださいね。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
行動②:長期インターンをする
上昇志向を持った就活生が取るべき行動の2つ目は、長期インターンをすることです。
長期インターンに参加すれば、早めに社会人経験を積むことが出来るので、就活で有利になります。
特に、上昇志向を持った就活生は、早いうちから長期インターンをしている場合が多いです。
長期インターンに参加し、スキルや経験を磨いておくことをオススメします。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
行動③:就活エージェントを利用する
上昇志向を持った就活生が取るべき行動の3つ目は、就活エージェントを利用することです。
なぜなら、一般の就活サイトでは募集がされていない上昇志向の企業の求人を就活エージェントが紹介してくれる可能性があるからです。
ベンチャー企業からの応募が多く載っているサイトとしては、自分に合った企業を見つけやすいキャリアチケットを利用するのがおすすめですよ。
就活エージェントを利用すれば、自分に合った企業が見つかるでしょう。
キャリアチケットは本当に便利です。
以下にキャリアチケットについての記事を載せておくので、ぜひ参考にしてみて下さい。
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤
⇒キャリアチケット概要: あなたには就活エージェント「キャリアチケット」がおすすめ!
⇒キャリアチケット評判:【キャリアチケットの評判は?】就活生の体験談,口コミまとめ | 実際に利用した20卒にもインタビュー
「正直めんどくさい自己分析を早く楽に終わらせたい!」「簡単に自己分析をしたい!」という就活生には「適性診断AnalyzeU+」がおすすめです。
適性診断AnalyzeU+は、100万人のデータをもとに251問の質問からあなたの性格を詳しく検査してくれます。
診断結果をあなたの自己PRに使用でき、プロフィールに入力することで、大手~ベンチャーの優良企業からスカウトも来ます。
「自分に最適な自己分析ツールが知りたい!」と不安な就活生は、「適性診断AnalyzeU+」を利用してみてください。
また、その他のおすすめ自己分析ツールは、「【内定者が選んだ】自己分析ツールおすすめ25選 | アプリ,簡単な適性診断サイト(全て無料)」という記事で紹介しています。
 就活アドバイザー 京香
就活アドバイザー 京香
- 251問の質問と100万人のデータから診断してくれるのでかなり正確な結果がわかる
- 診断結果からあなたにおすすめの職種もわかる
- 診断により自己PRが書きやすくなり、ESや面接で人事に評価されるアピールができる
(適性診断AnalyzeU+)
まとめ:安定志向だけでなく、上昇志向の考え方も持って自分の進路を選択しよう
この【どっちが良い?】「安定志向」と「上昇志向」それぞれのメリットとは? | 取るべき行動も!記事のはいかがでしたか。
この記事では「安定志向」と「上昇志向」のそれぞれの特徴を紹介しました。
合わせてこれからの時代で必要な上昇志向の考え方や取るべき行動も説明しました。
最後に、この記事のまとめをおさらいしましょう。
◆大手に行きたい安定志向の就活生がやるべきこと
- やるべきこと①:倍率が高い企業は可能な限りの準備をする
- やるべきこと②:インターンやOB訪問をしっかりする
- やるべきこと③:企業の求める人物像に合わせて自己PRする
◆上昇思考を持った就活生が取るべき行動
- 行動①:早めから対策する
- 行動②:長期インターンをする
- 行動③:就活エージェントを利用する
安定志向で就活を進める就活生は、安定した経営をしている大手の企業や公務員という選択をするのが多いです。
大手の企業の将来もわからないと不安な人は、安定志向にこだわらずに、ベンチャー企業で個人のスキルを磨くというのも視野にいれて就活を進めてみてくださいね。
「就活の教科書」では、他にも様々な就活情報をわかりやすく解説しています。
ぜひ他の記事も読んでみて下さいね。
みなさんの就活が成功することを心から祈っております!
 「就活の教科書」編集部 中澤
「就活の教科書」編集部 中澤


