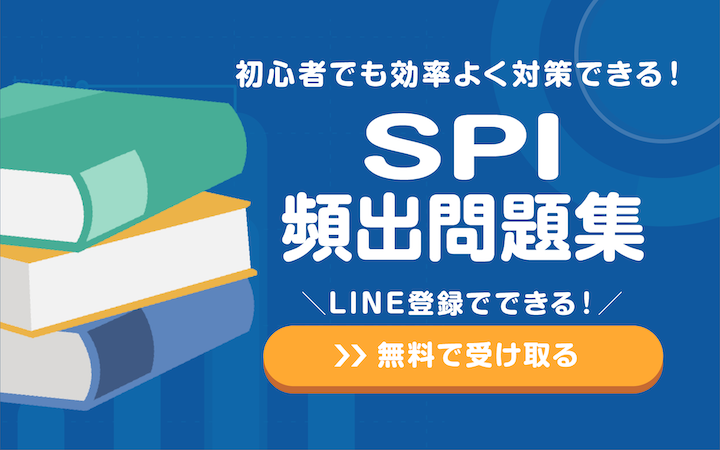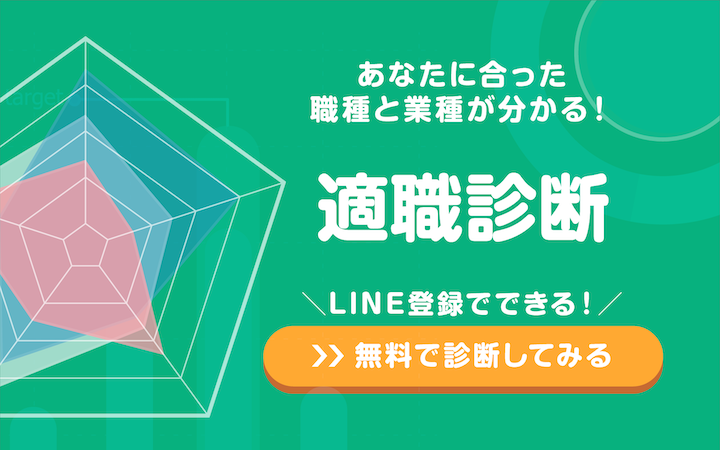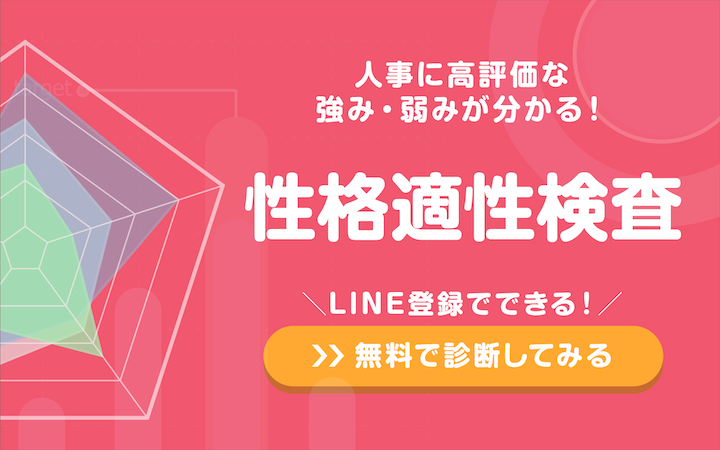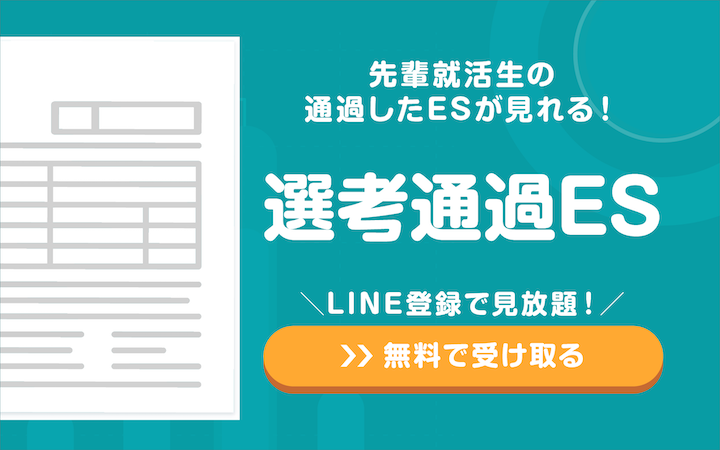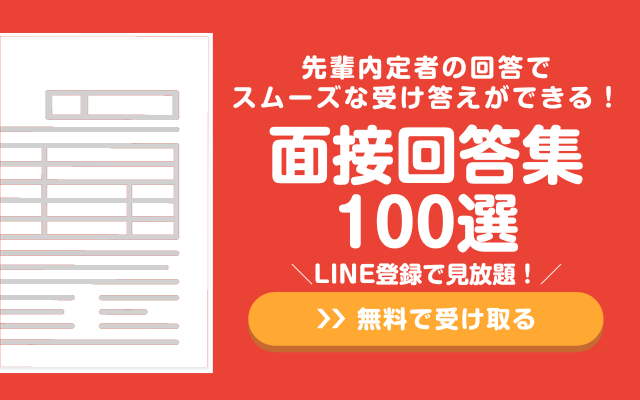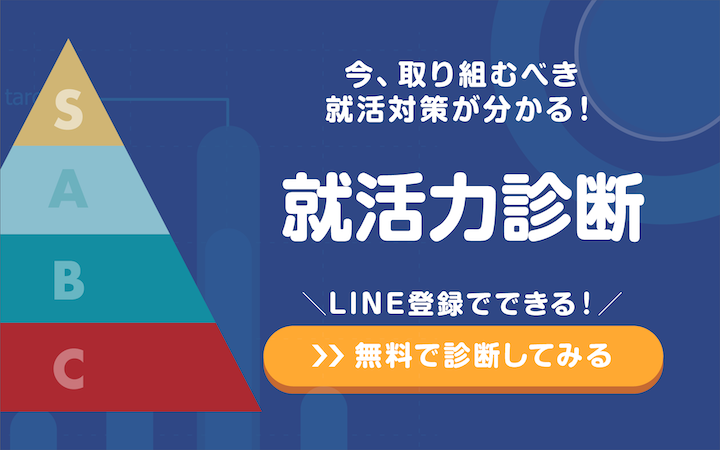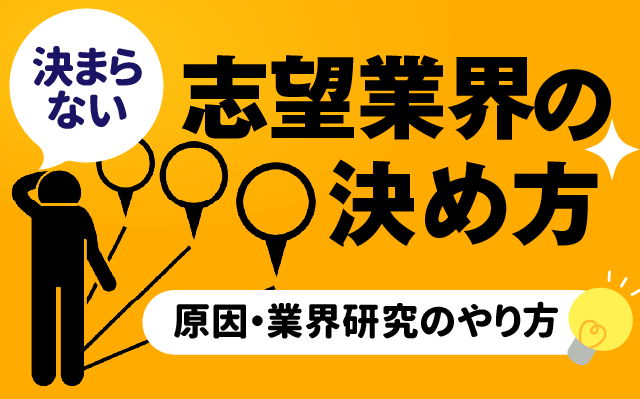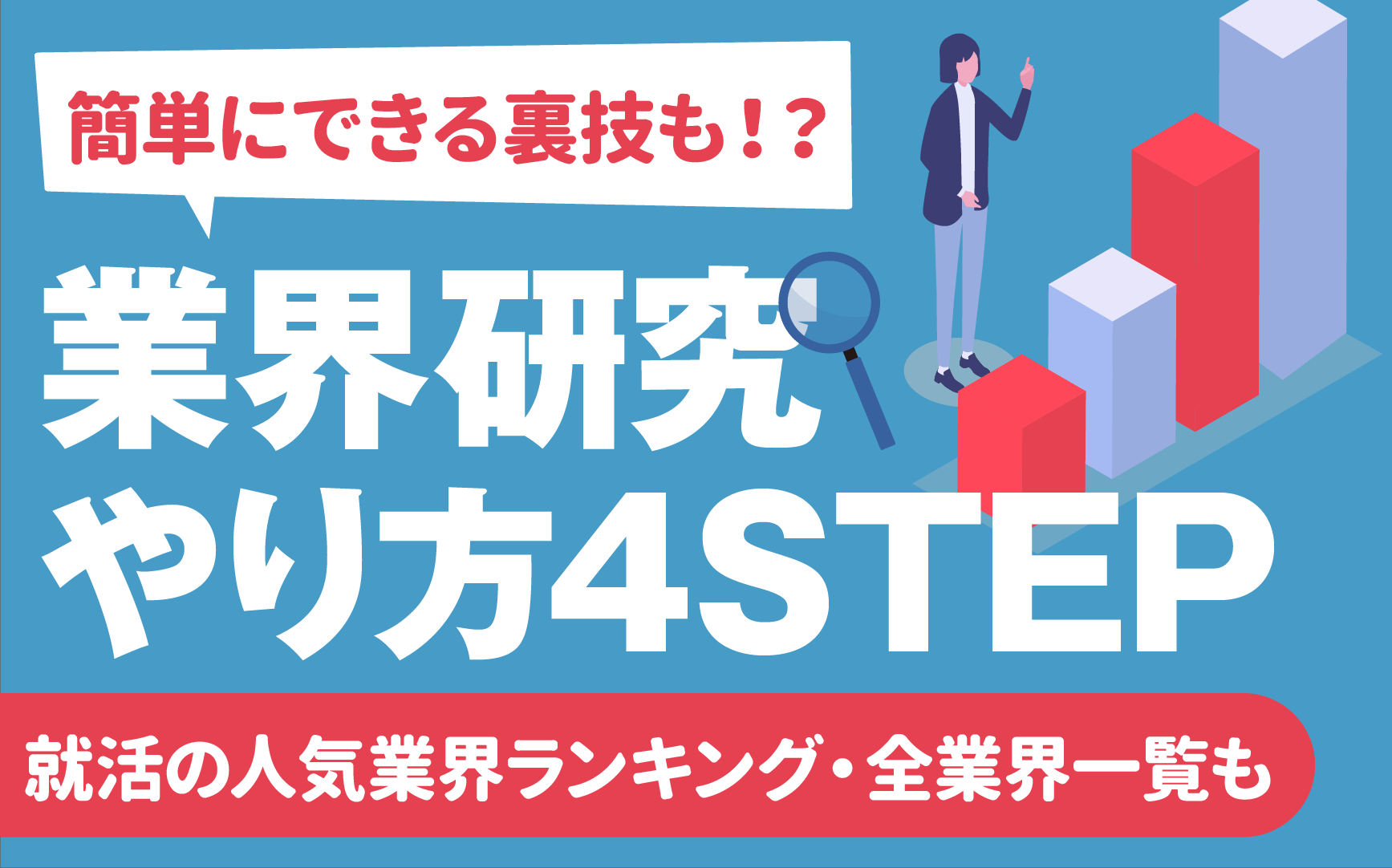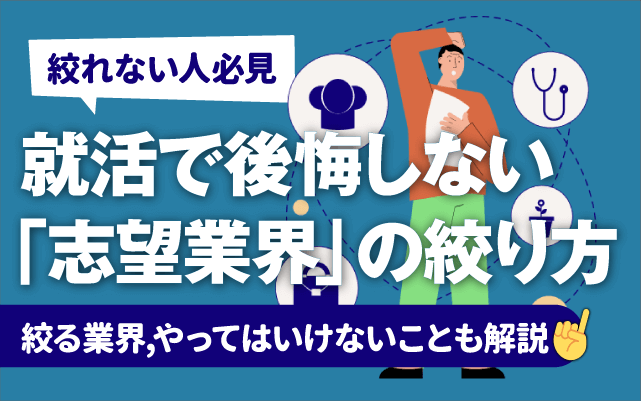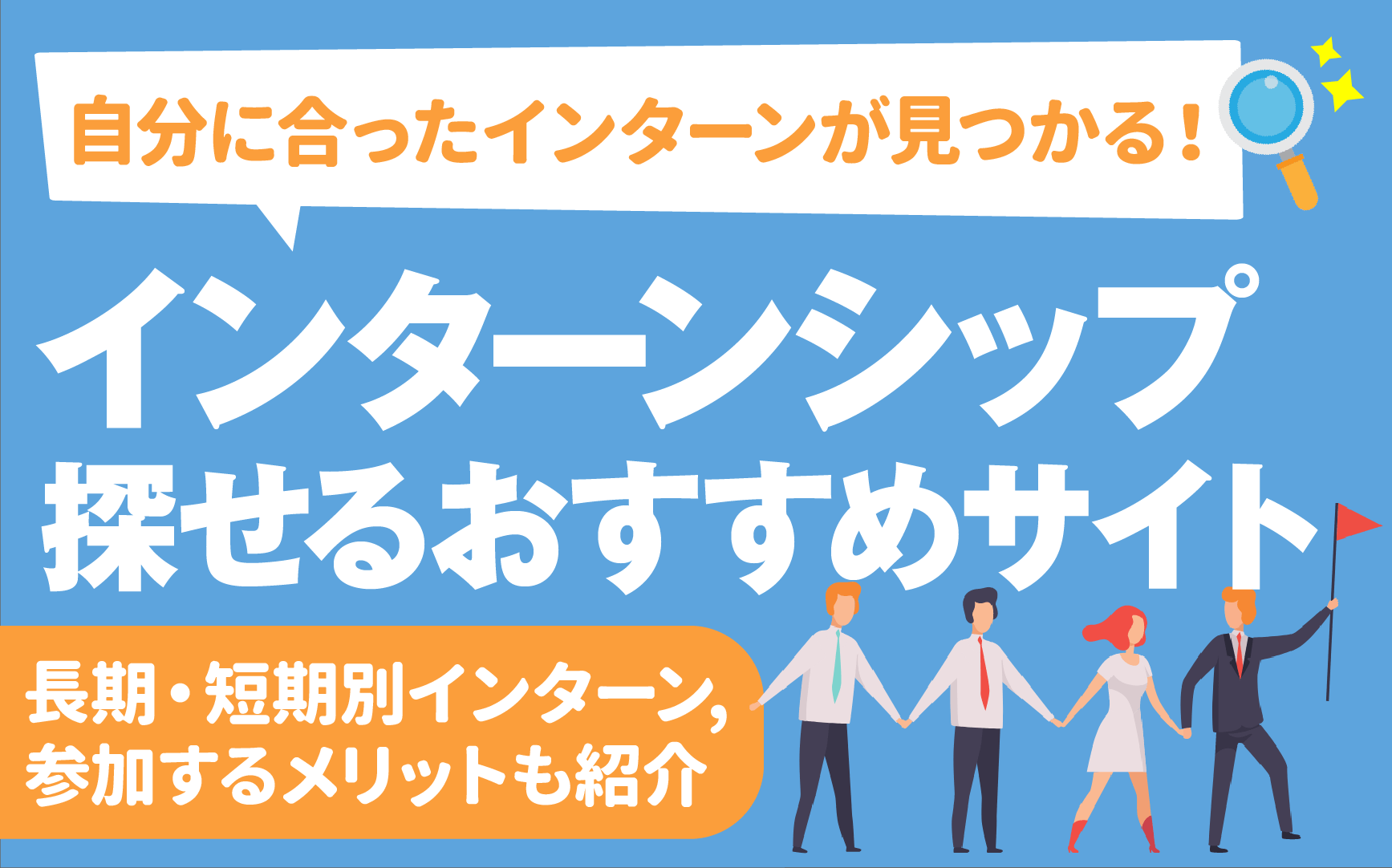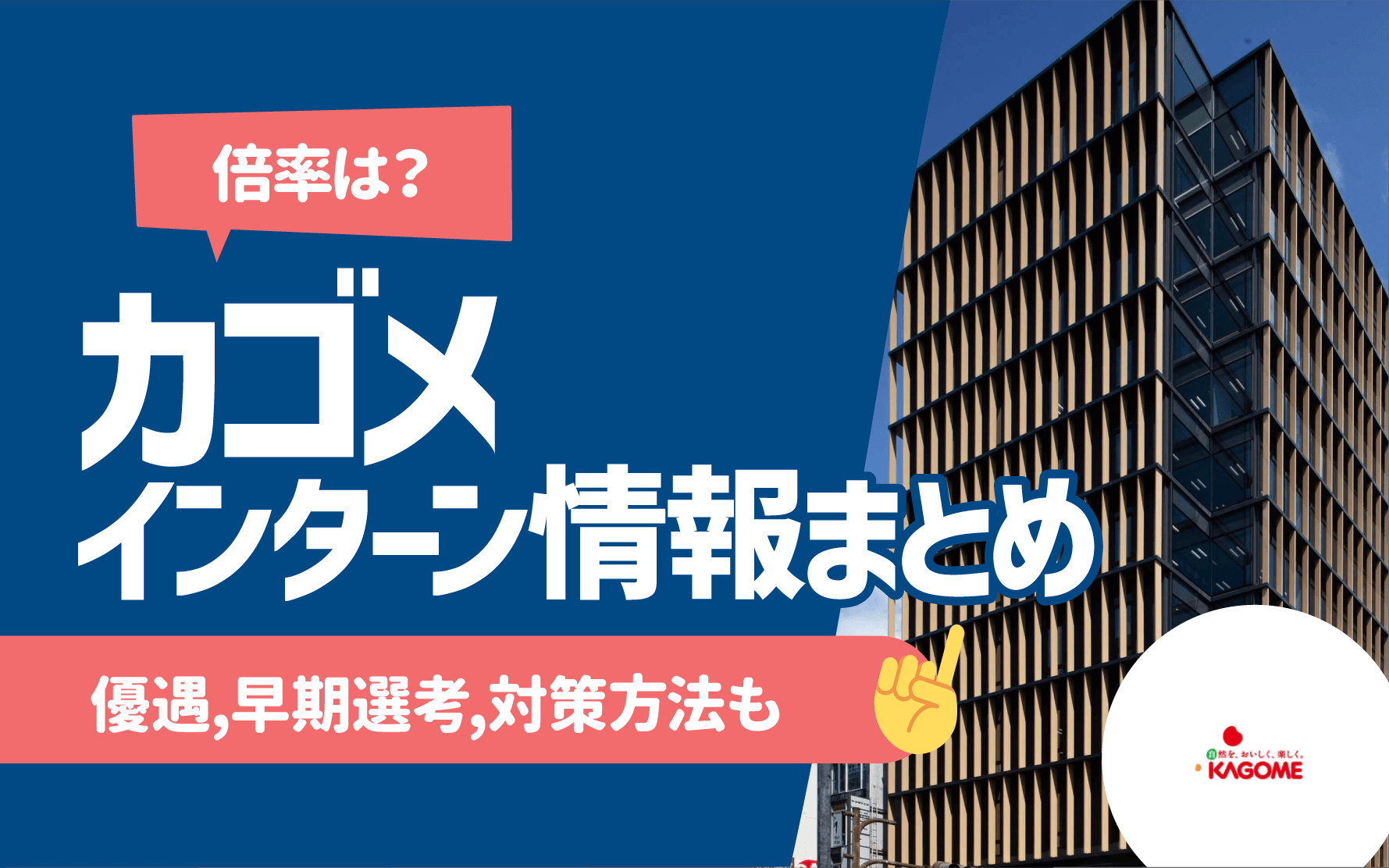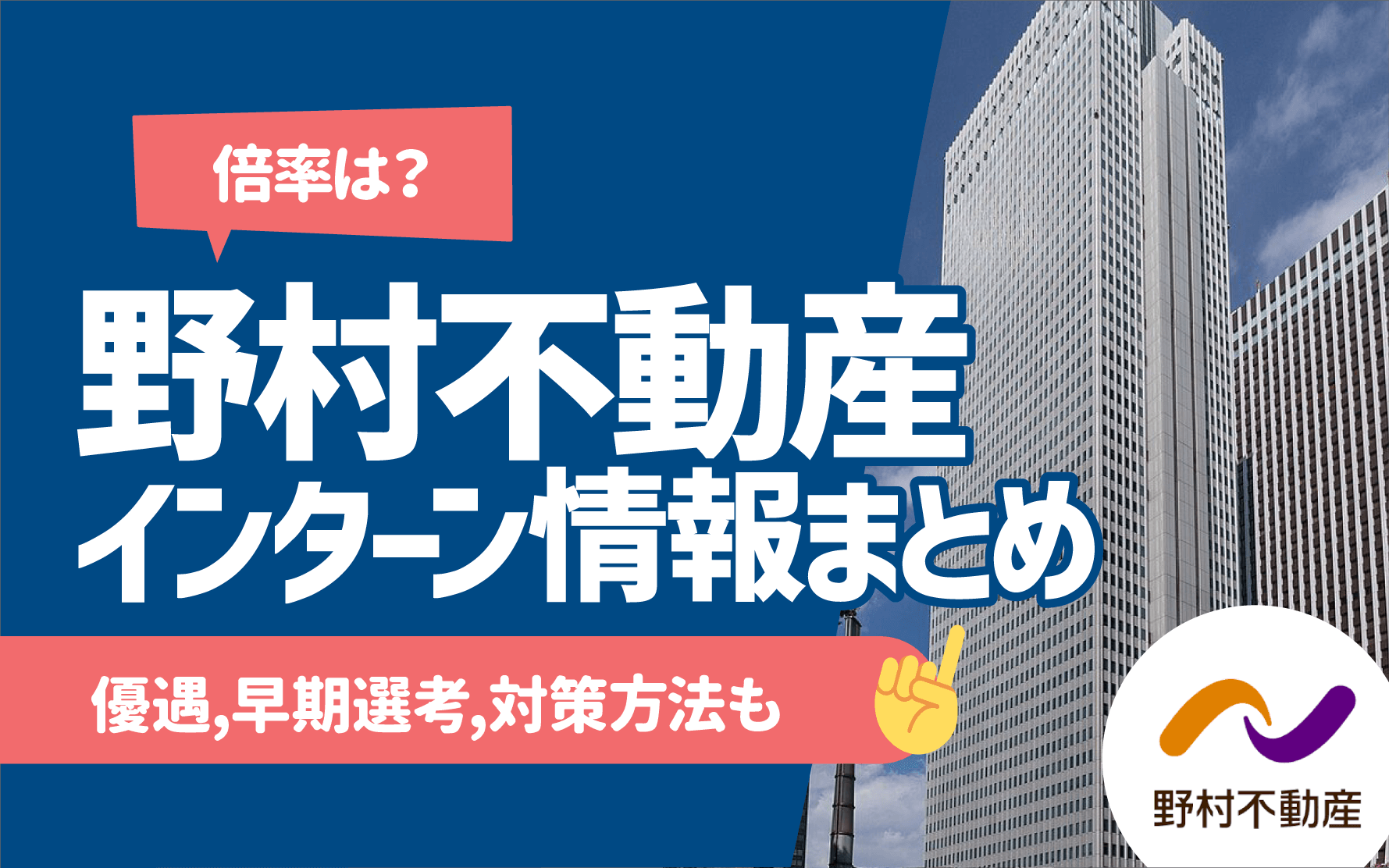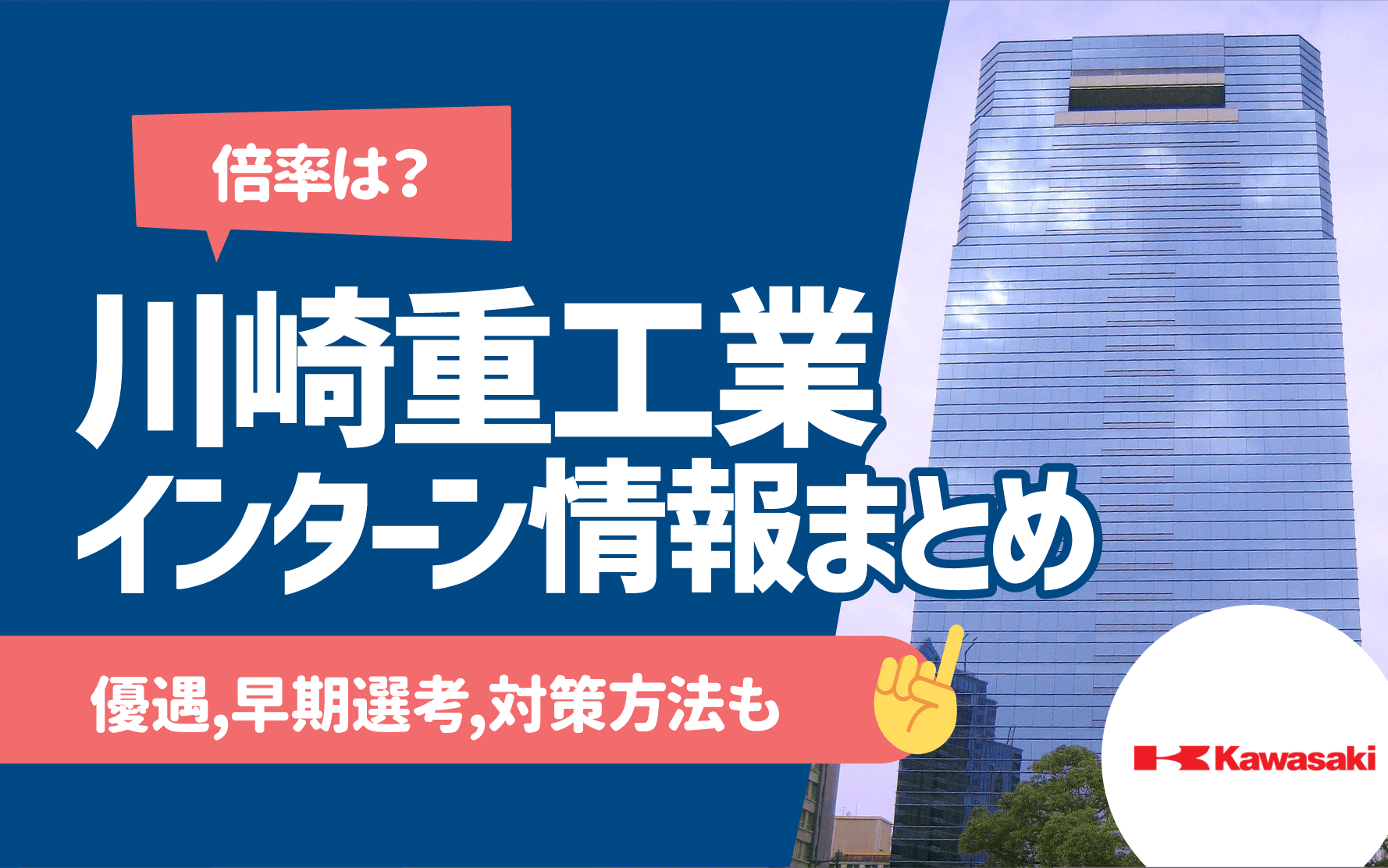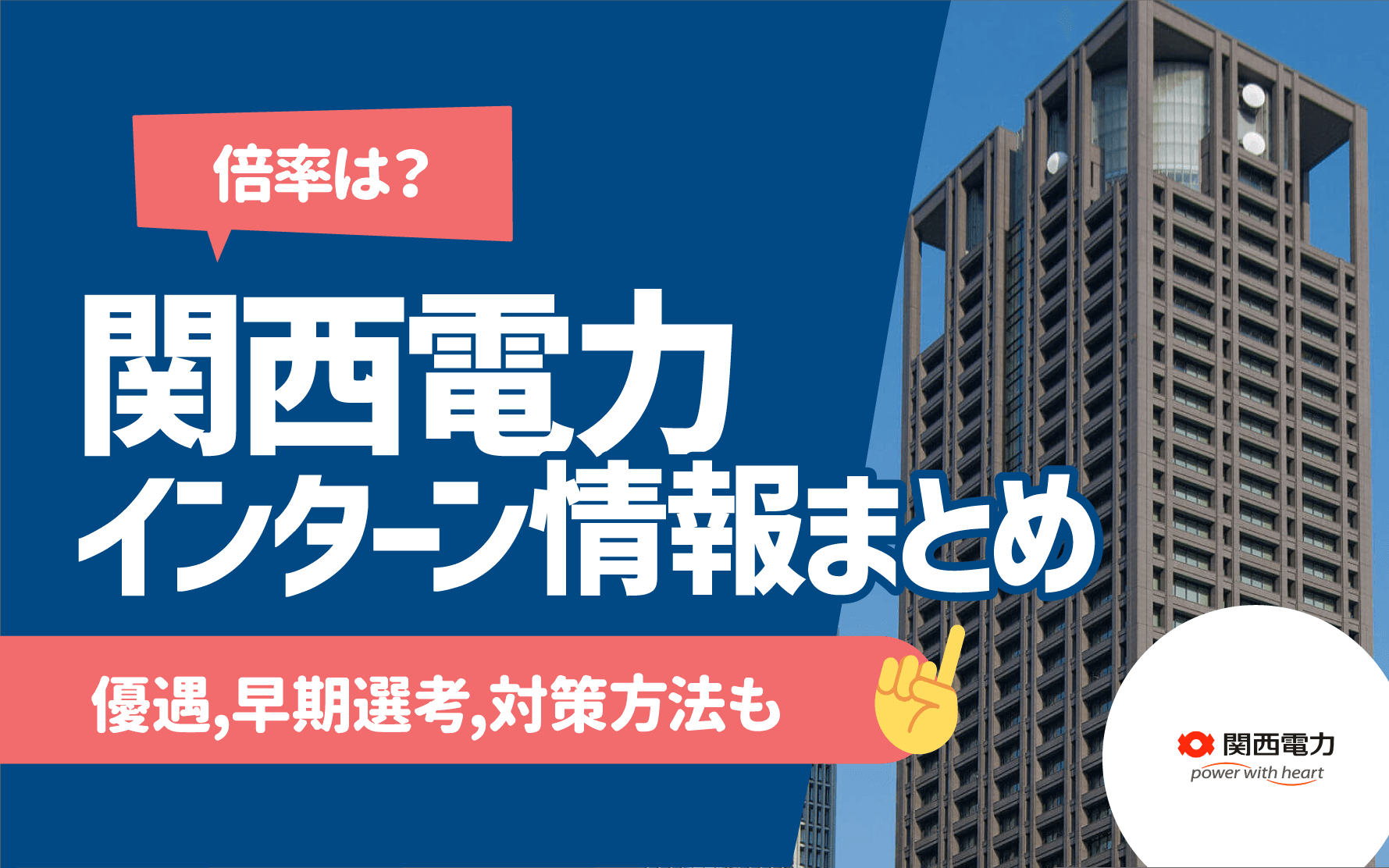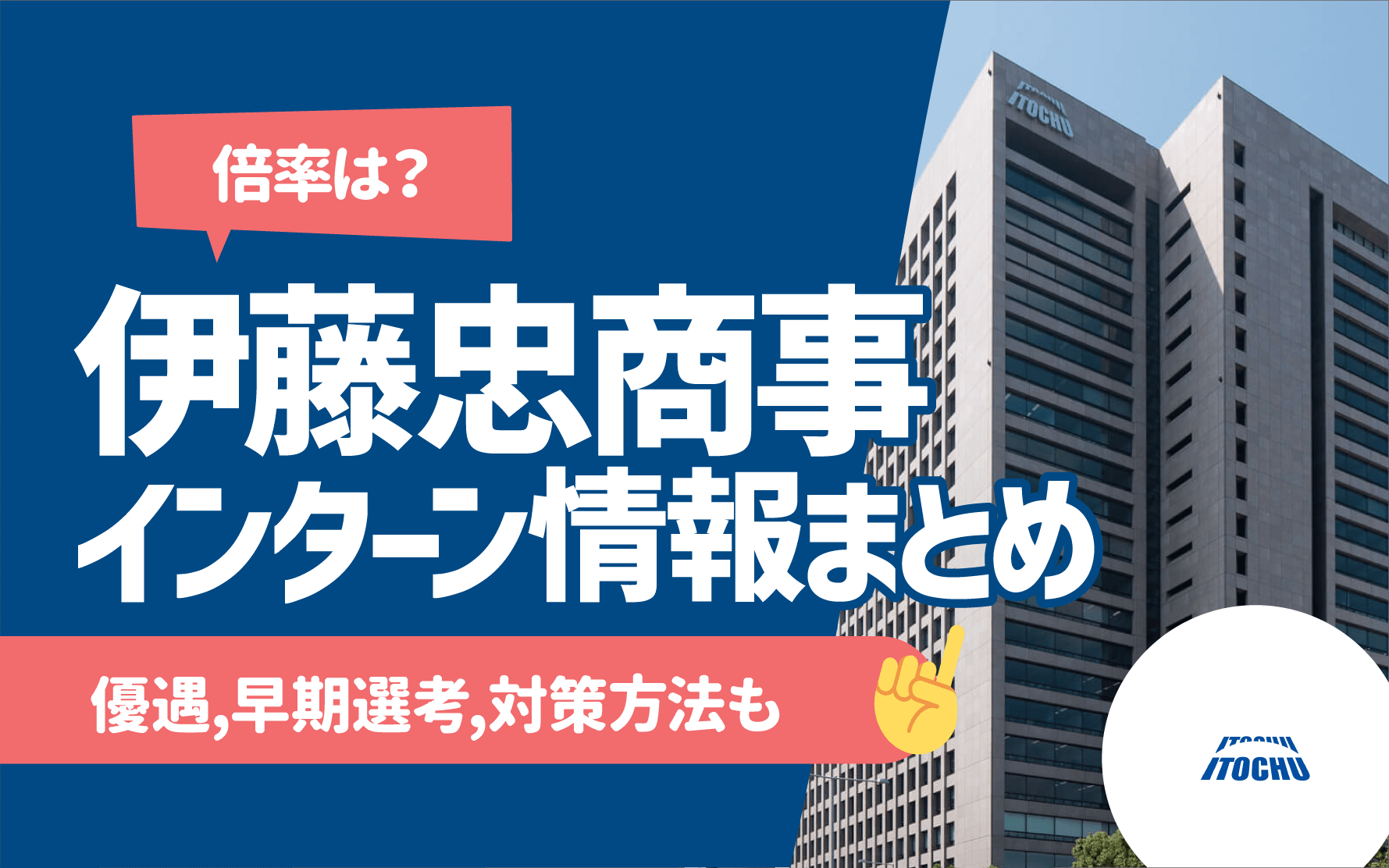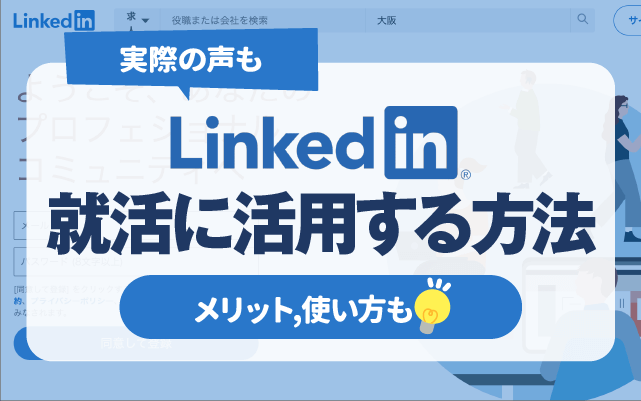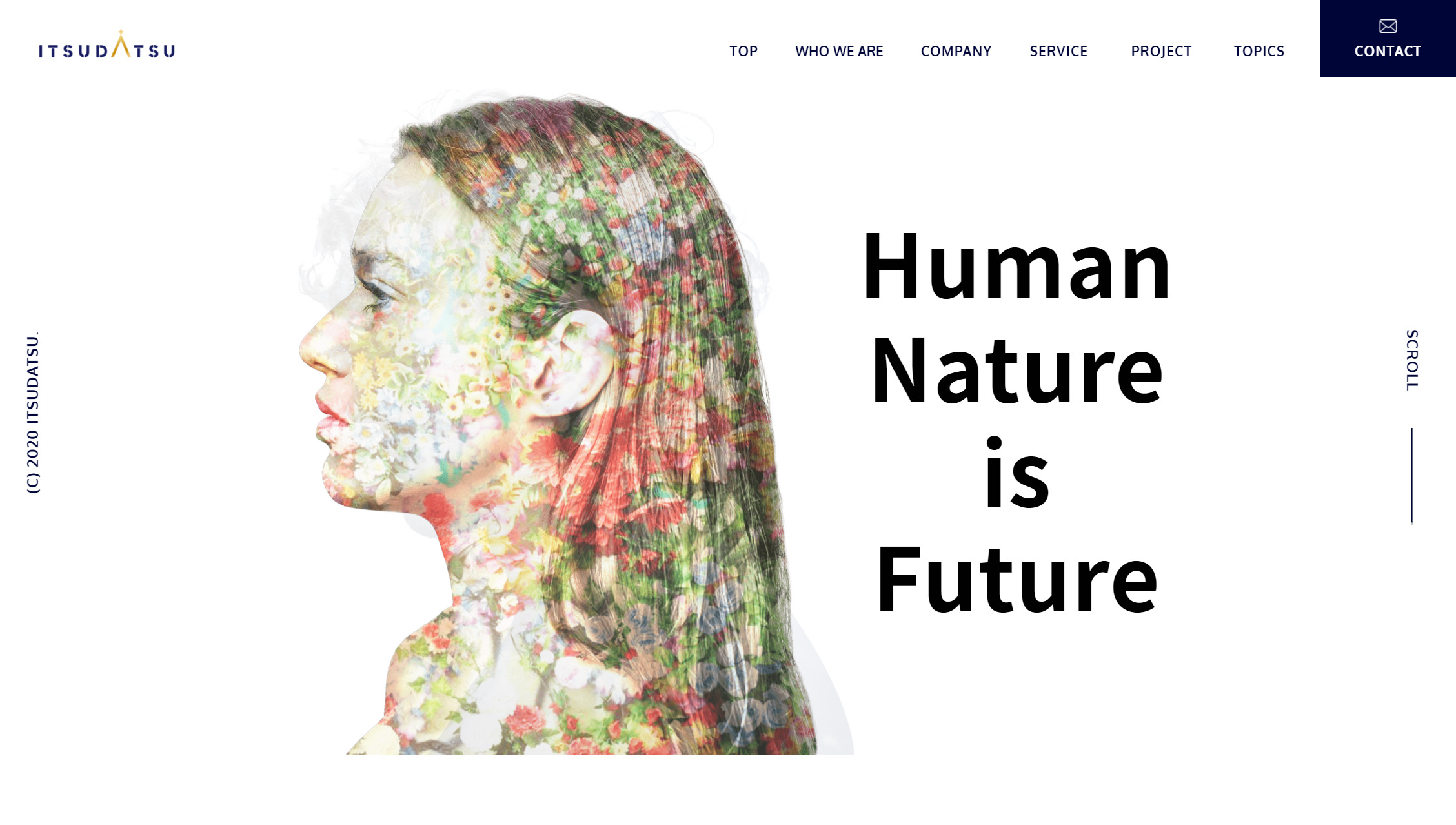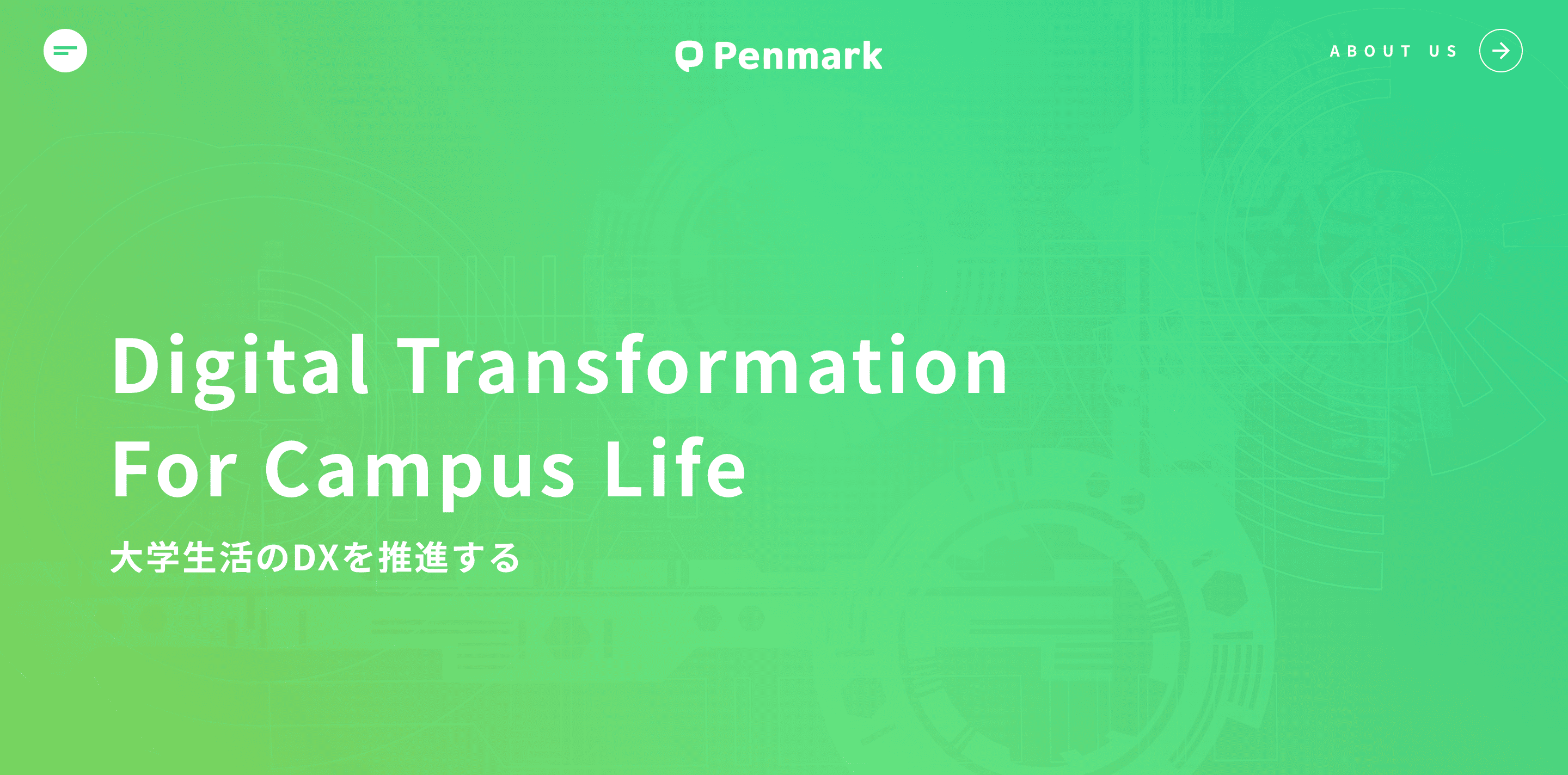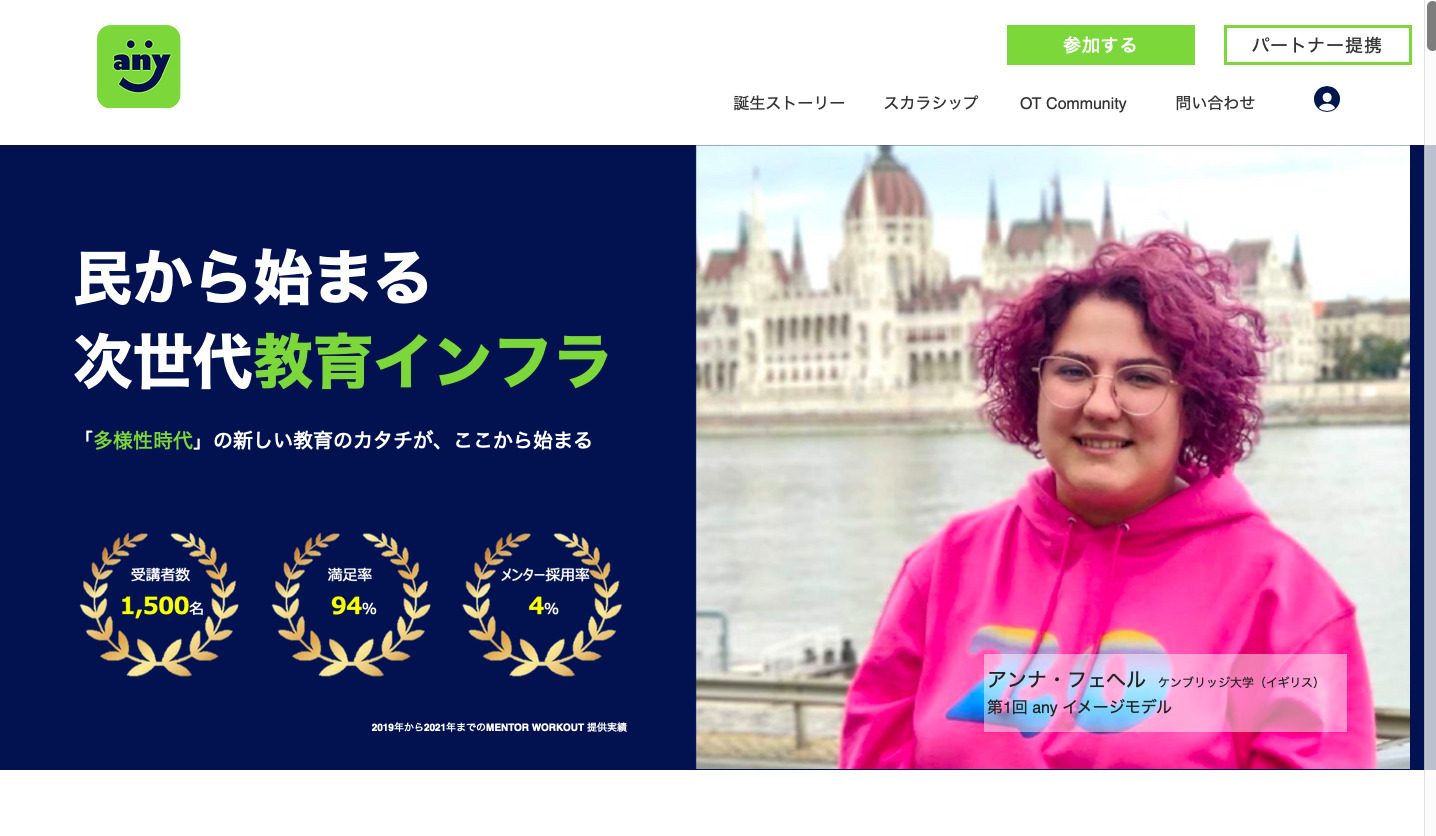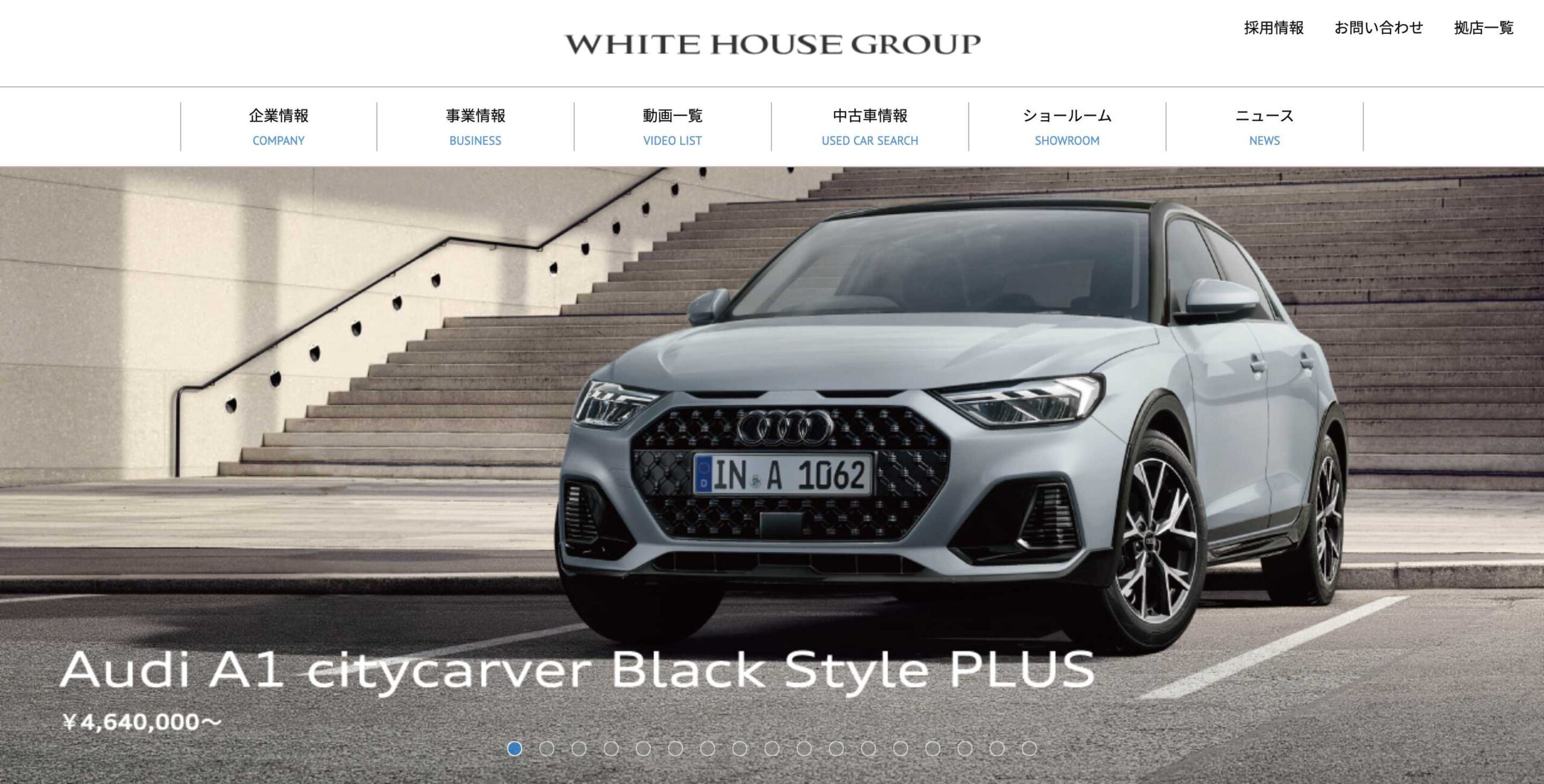就活の教科書は
累計5,000万PVの就活メディア
「就活迷子」を減らすために
就活コラムを2,000記事以上用意しました


Ranking
- おすすめ記事TOP5 -
Steps
- 就活の全体像7ステップ -

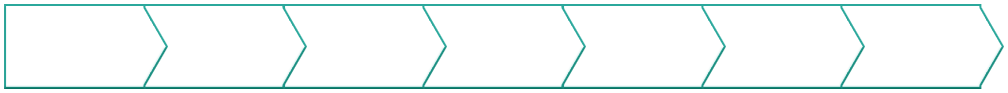
Step1
就活の始め方
Step2
自己分析
Step3
企業/業界研究
Step4
企業/業界
ランキング
Step5
ES対策
Step6
Webテスト対策
Step7
面接対策
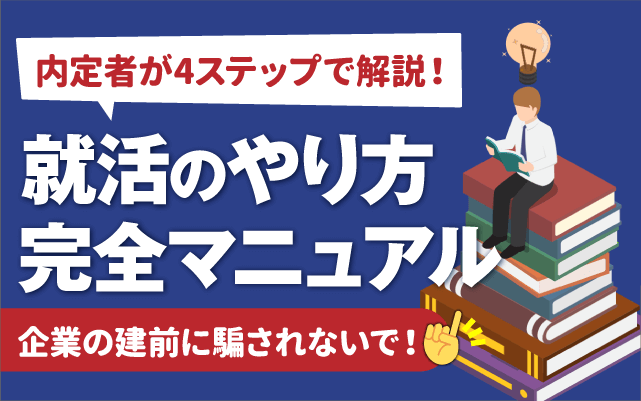
【就活やり方マニュアル】内定者が4ステップで完全解説 | 企業の建前に騙されないで!
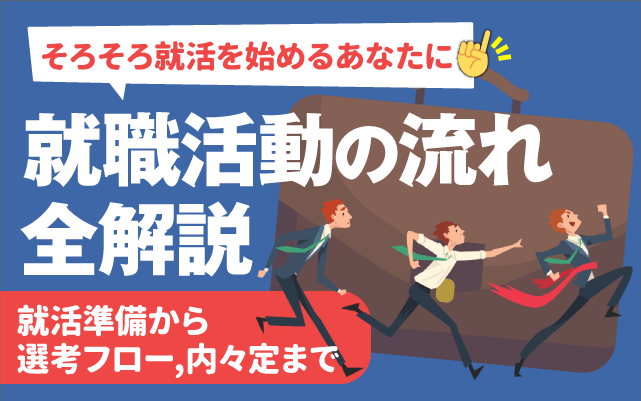
【完全解説】大学生の就職活動の流れ | 就活準備から本選考,内定まで(新卒)
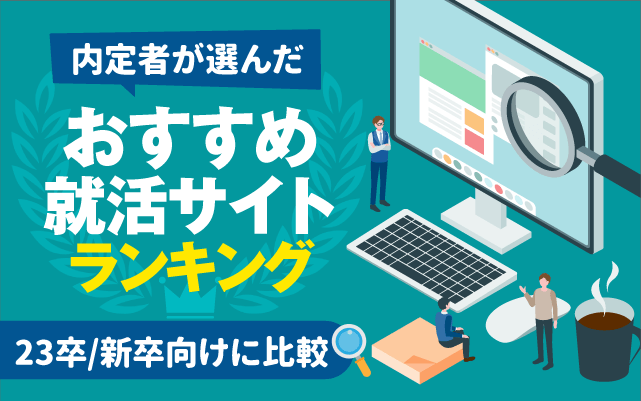
【2023年最新版】就活サイトおすすめランキング40選 | 24卒/25卒/新卒向けに比較
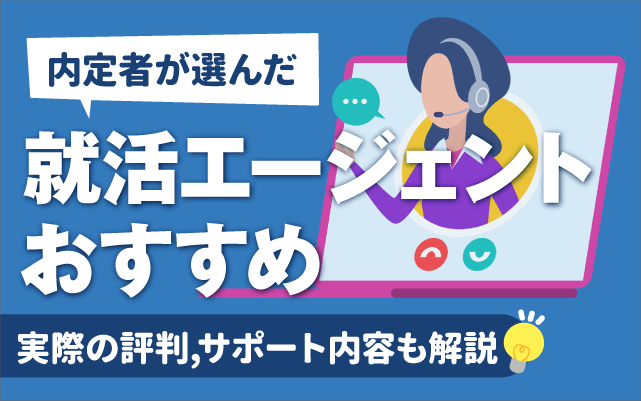
【内定者が選んだ】就活エージェントおすすめ15選 | 実際の評判,サポート内容も
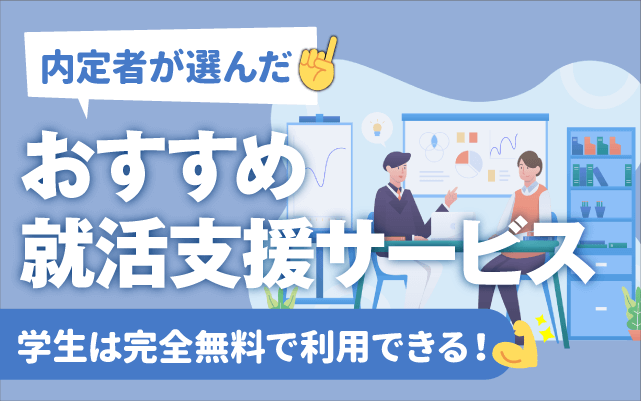
【内定者が選んだ】就活支援サービスおすすめ15選 | 学生は完全無料
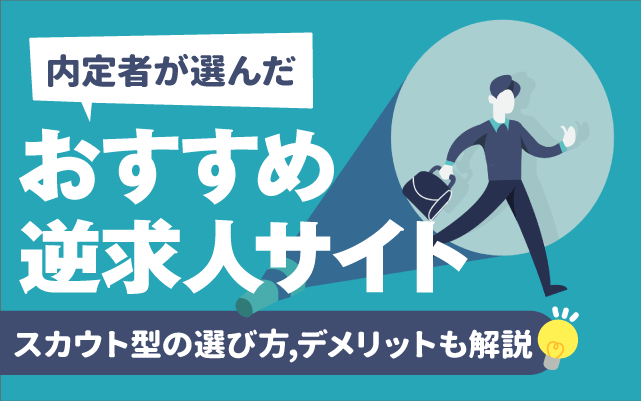
【内定者が選んだ】新卒逆求人サイトおすすめ16選! スカウト型の選び方,デメリット,既卒向けサイトも
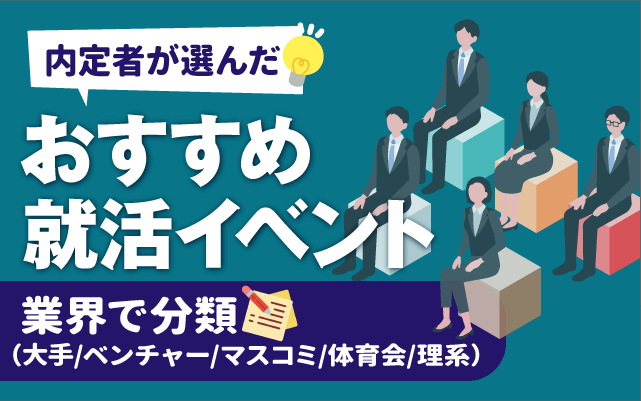
【内定者が選んだ】就活イベントおすすめ35選! 業界で分類(大手/ベンチャー/マスコミ/体育会/理系など)
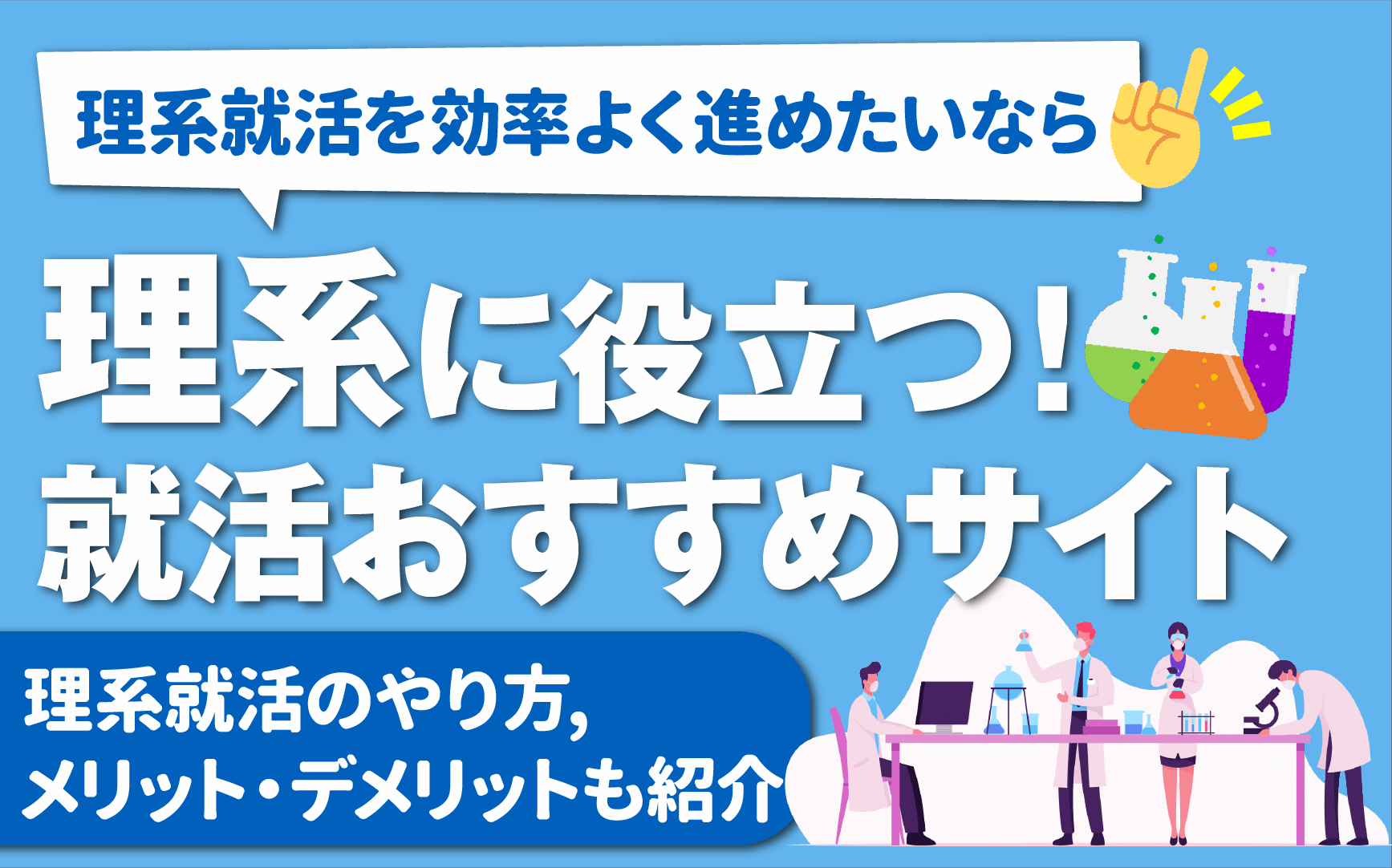
【内定者が選んだ】理系に役立つ就活サイトおすすめ13選 | 理系就活の上手なやり方も
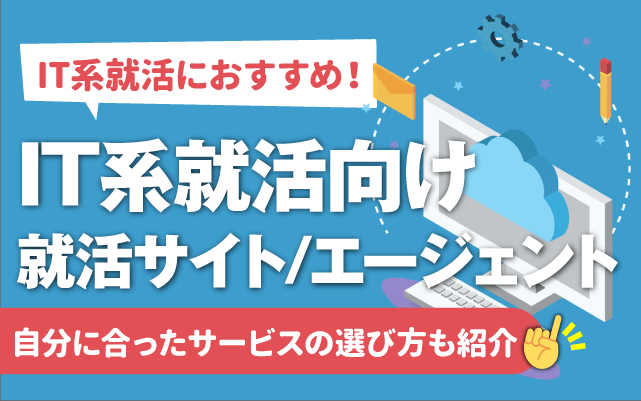
【最新版】ITエンジニア志望者向け就活サイト/エージェントおすすめ15選 | 選び方,注意点も
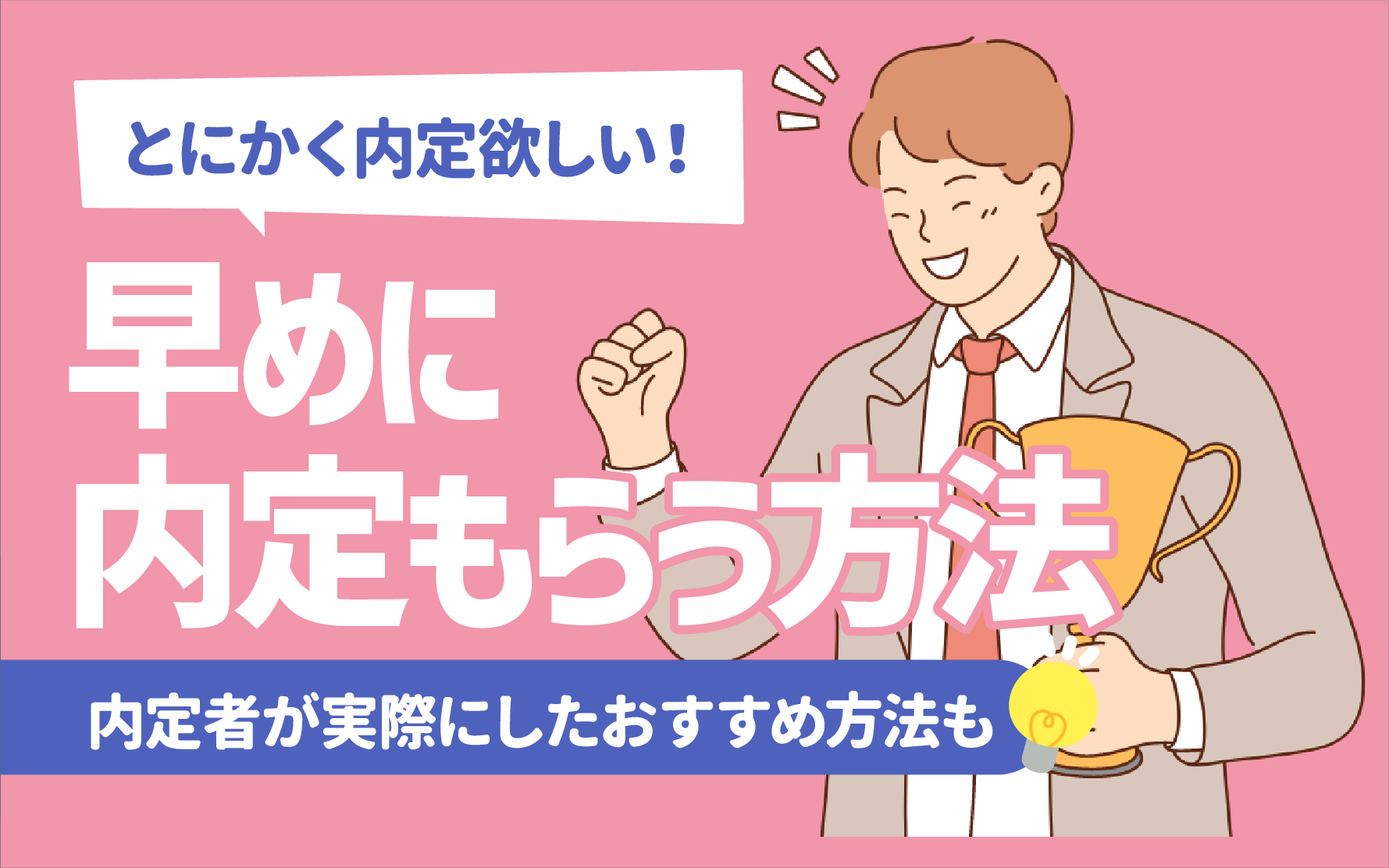
【とにかく内定欲しい!】早めに内定もらう方法おすすめ3選 | 内定者が実際にしたこと
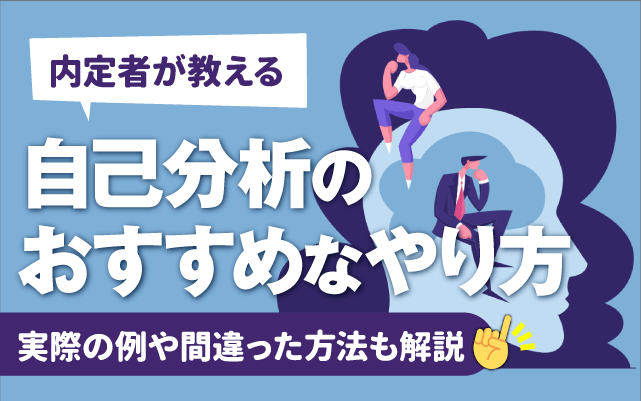
【内定者が教える】自己分析のおすすめなやり方 | 実際の例やポイントも
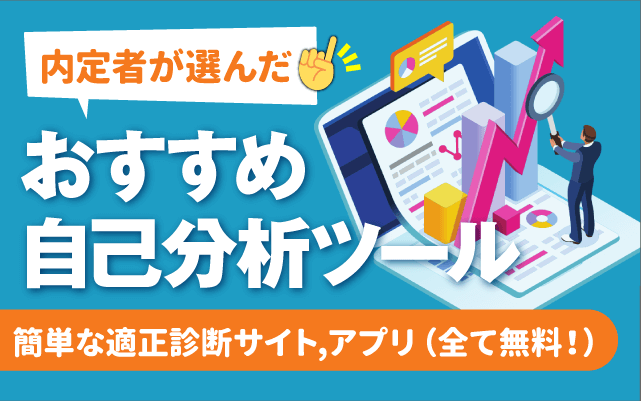
【内定者が選んだ】自己分析ツールおすすめ22選 | 簡単な適性診断サイト,アプリ (全て無料)
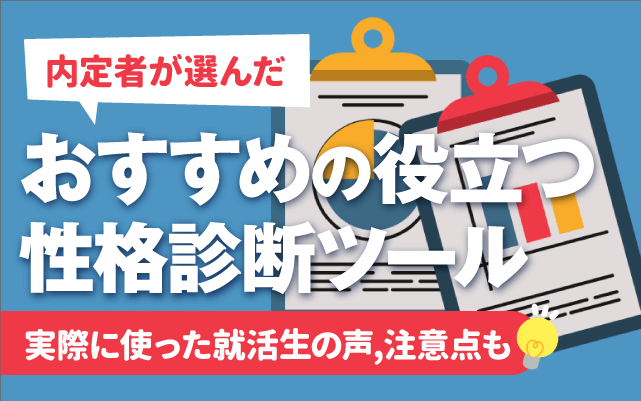
【就活で使える】無料性格診断テストおすすめ19選 | 適性検査対策,心理テストも
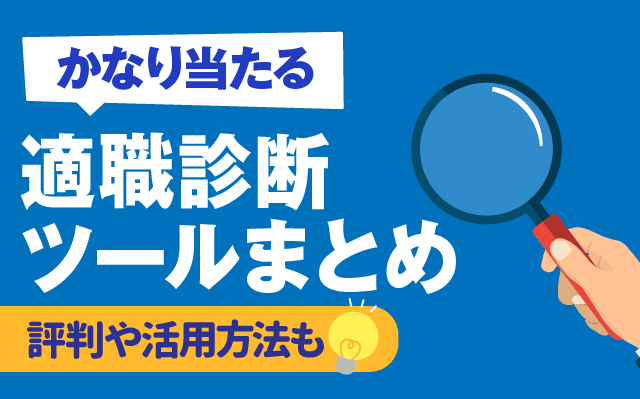
【正確で当たる!】無料で登録なしの適職/職業診断おすすめ12選 | 新卒・転職者の評判,比較一覧も
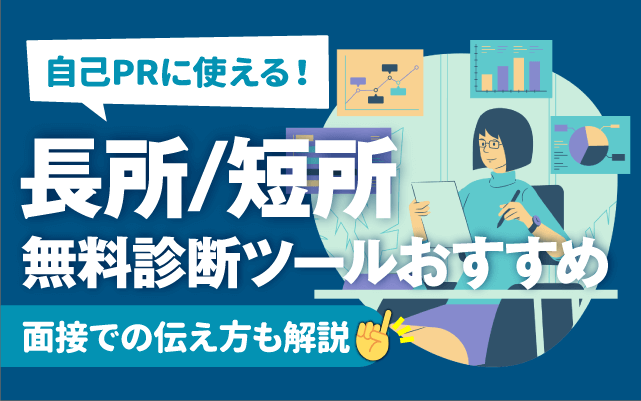
【無料/登録なし】長所と短所診断ツールおすすめ22選 | 面接,自己PRでの伝え方も

【60選】自己PR「強み」の単語/キーワード一覧表 | 言い換え表現や例文も
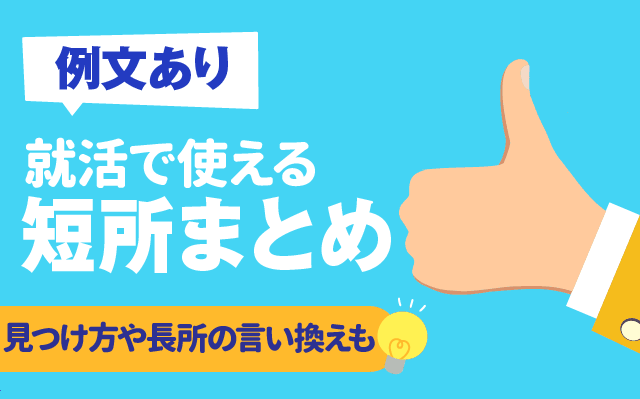
【短所一覧表】「自分の弱み」70選 | 例文,言い換え,NG例も
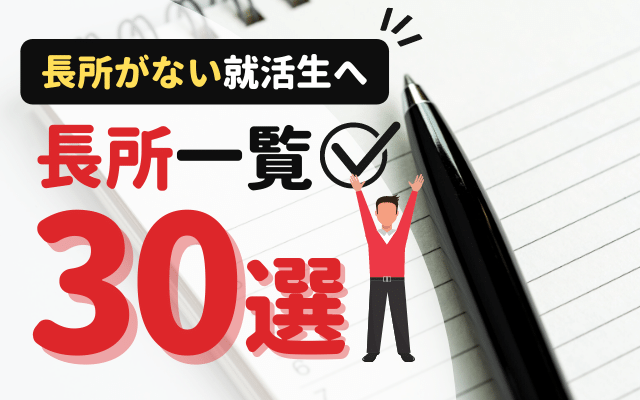
【長所一覧表】「自分の長所」おすすめ36選 | 就活,面接での性格の答え方も

【決め方】就活/企業選びの軸ランキング一覧 | 例文,面接官が質問する意図も
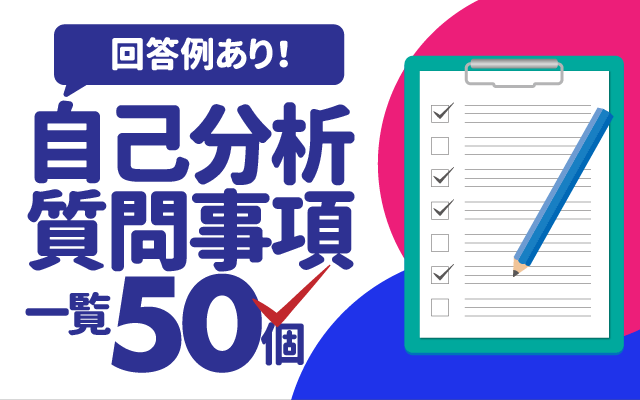
【回答例あり】自己分析の重要な質問項目一覧50個
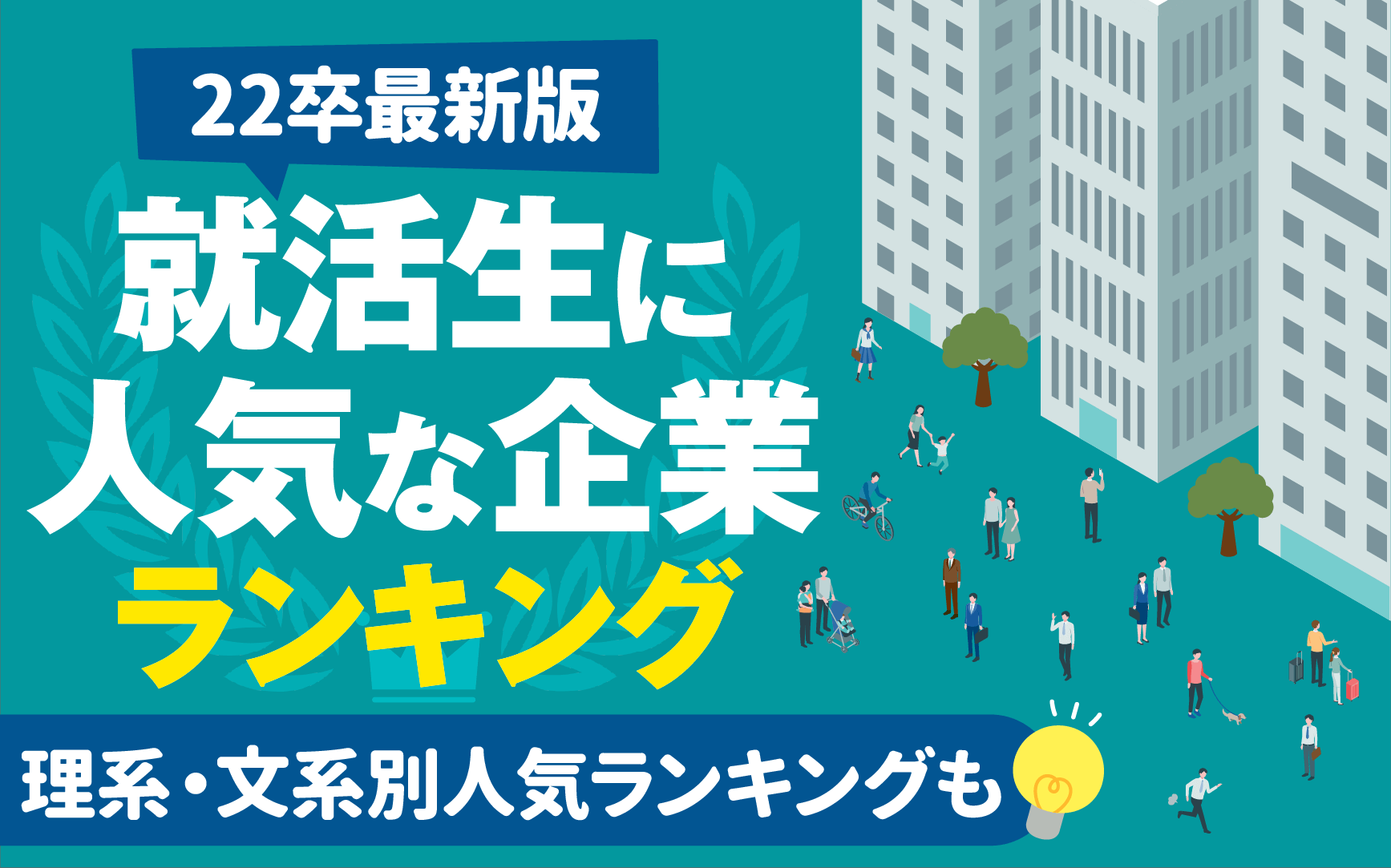
【最新版】 就活生に人気企業ランキングTOP200
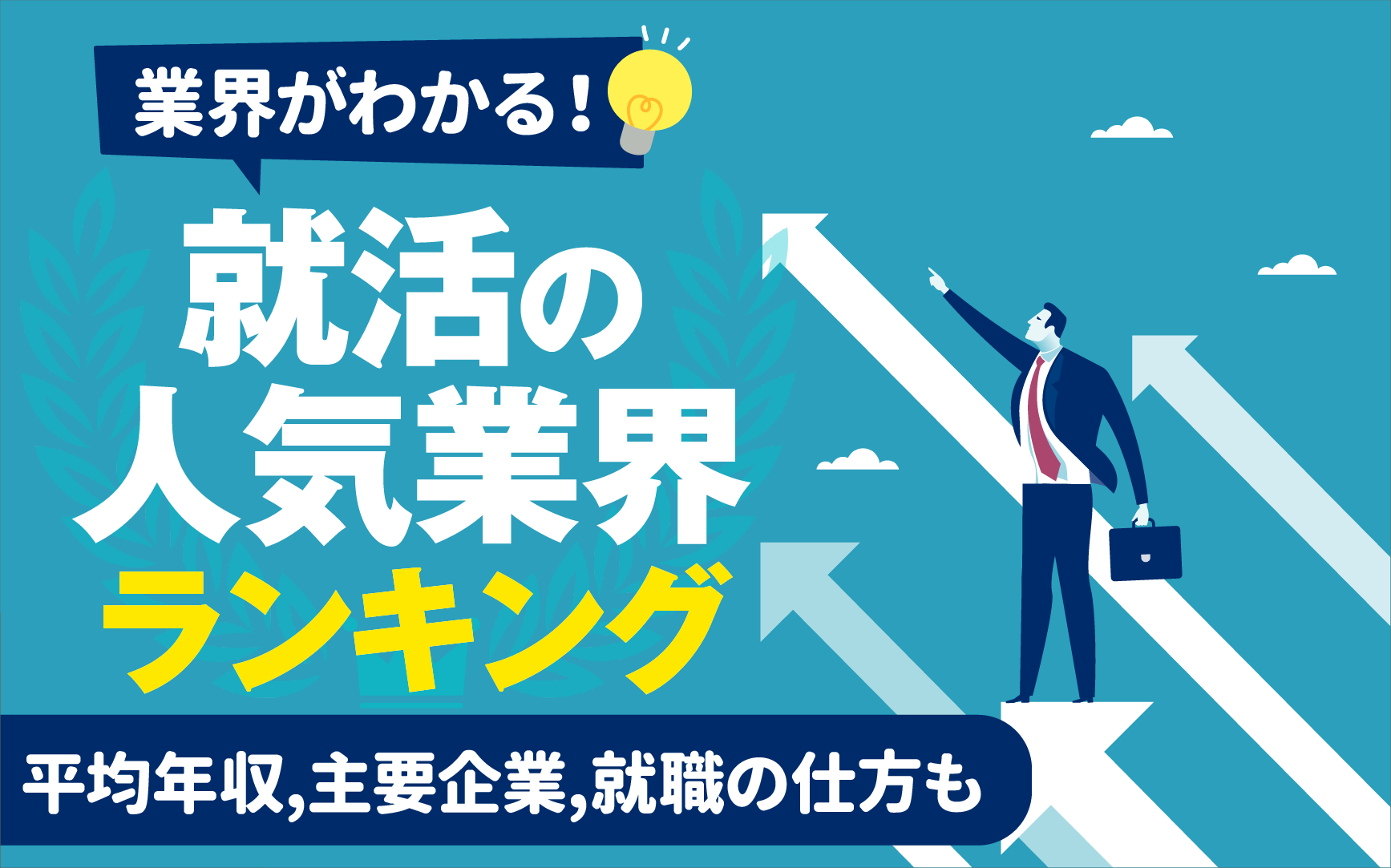
【業界が分かる】就活の人気/志望業界ランキング | 平均年収,就職の仕方も
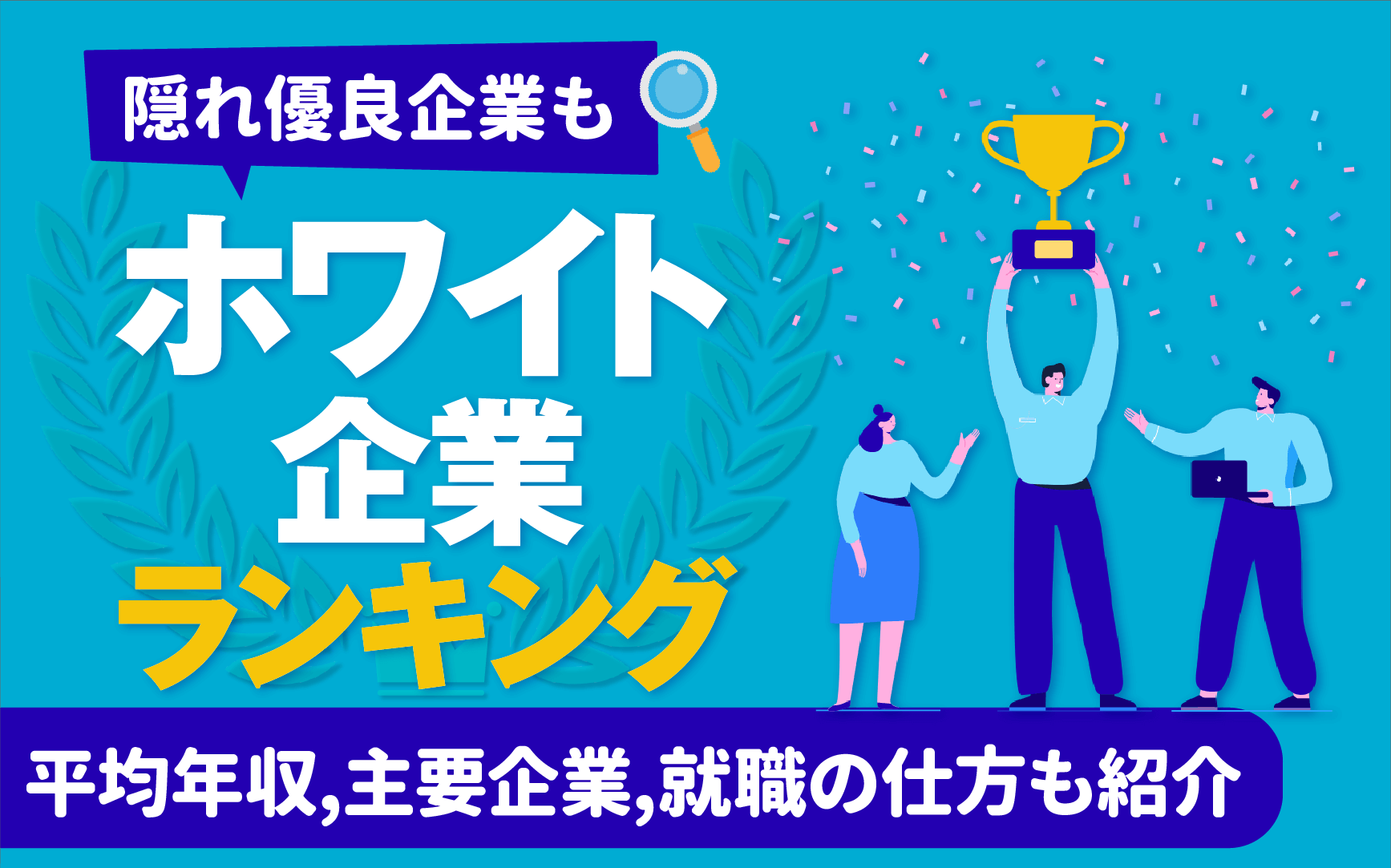
【隠れ優良企業も】ホワイト企業おすすめランキング一覧100社 | 一流ホワイト企業も

【文系/理系】ホワイト業界おすすめランキング一覧15選 | 優良企業の探し方も
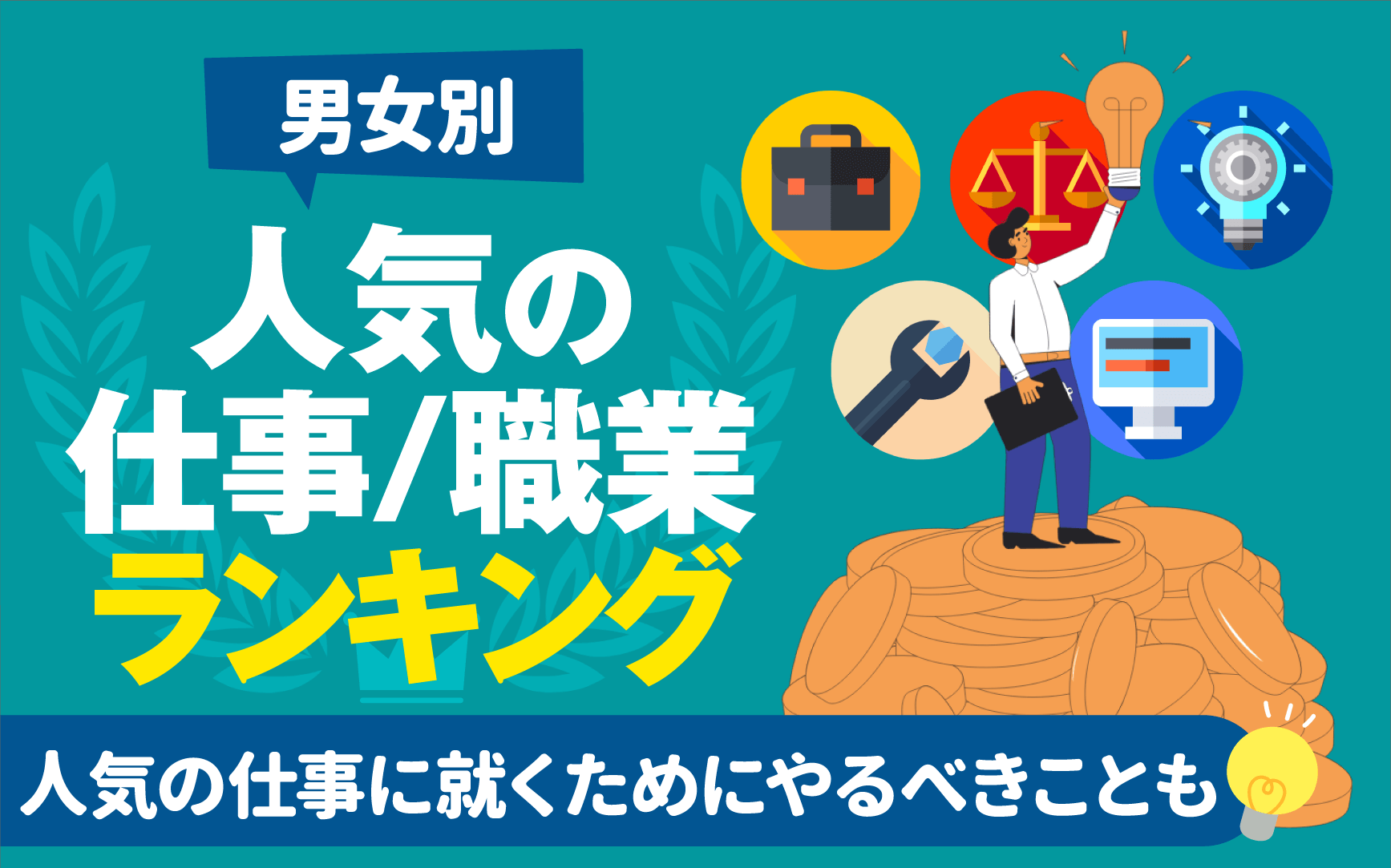
【男女別】人気の仕事/職業おすすめランキング一覧

【確実に内定ほしい】内定もらいやすい企業/業界ランキング,特徴と選び方も

【理系/文系別】就職偏差値・就活偏差値ランキング最新版 | 企業の入社難易度まとめました

【おすすめ】優良中小企業ランキング一覧 | 探し方,見つけ方,危ない会社の特徴も
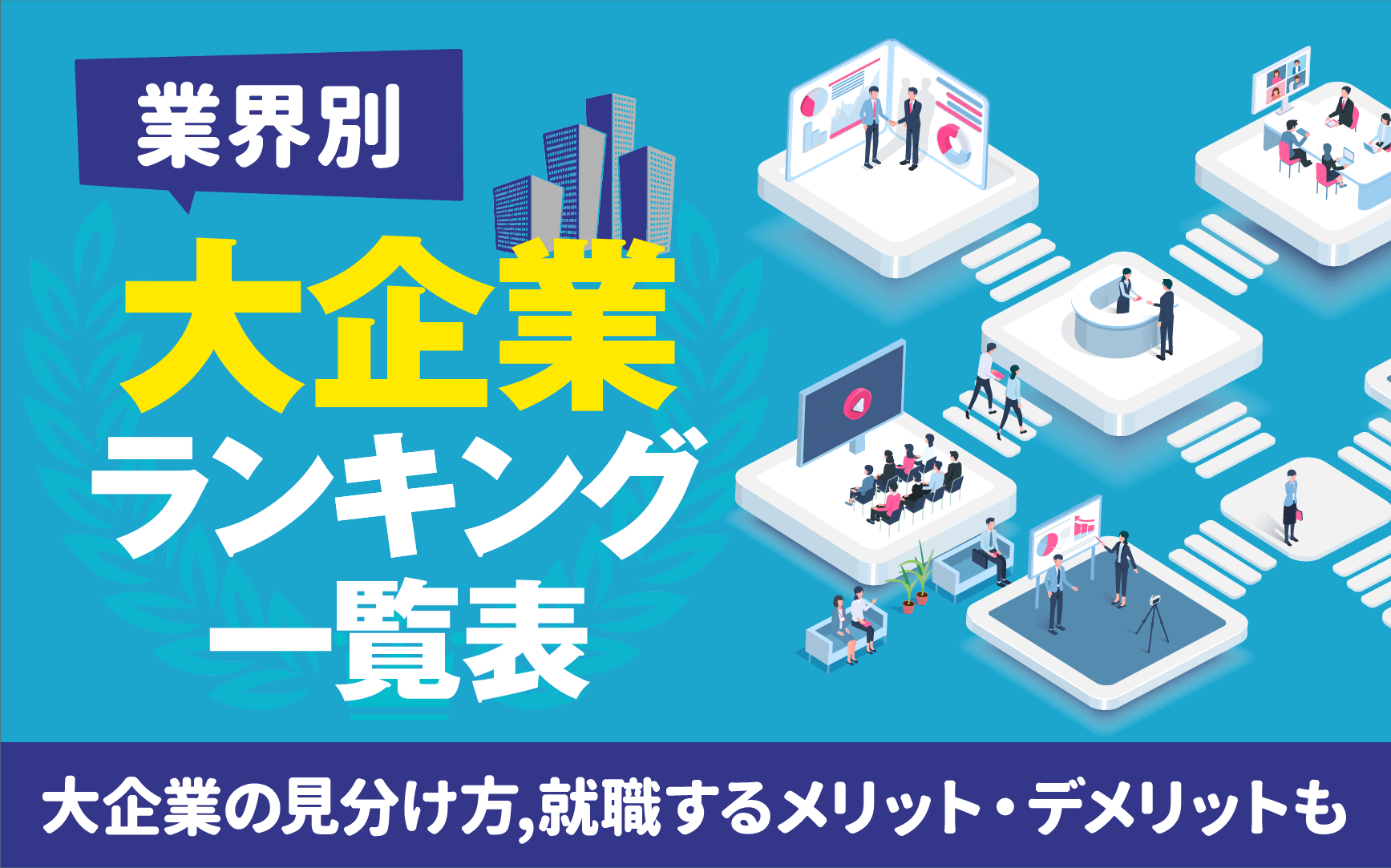
【業界別】大手企業ランキング一覧表 | 大企業の見分け方,平均年収,デメリット,入るためにやるべきことも
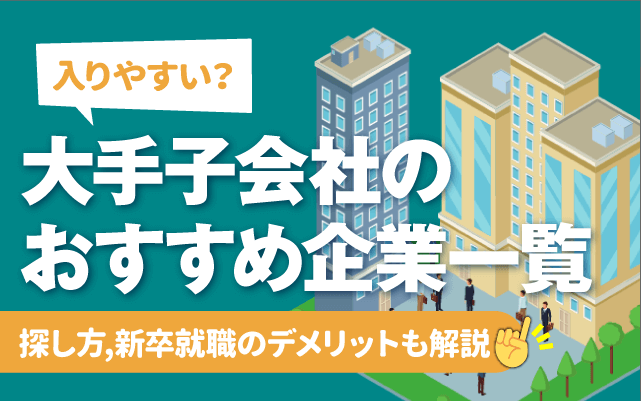
【入りやすい?】大手子会社のおすすめ企業一覧 | 探し方,新卒就職のデメリットも
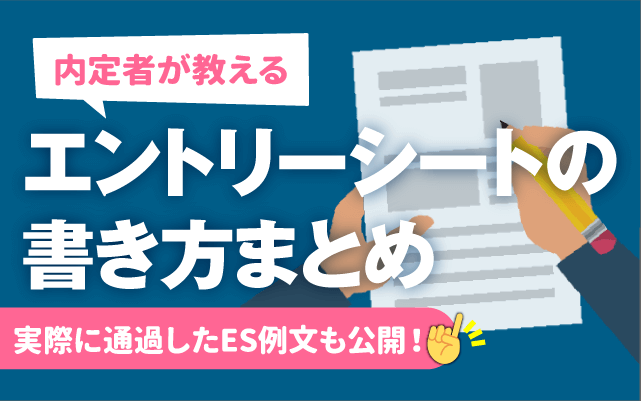
【内定者が教える】エントリーシートの書き方 | 実際に通過したES例文も公開!
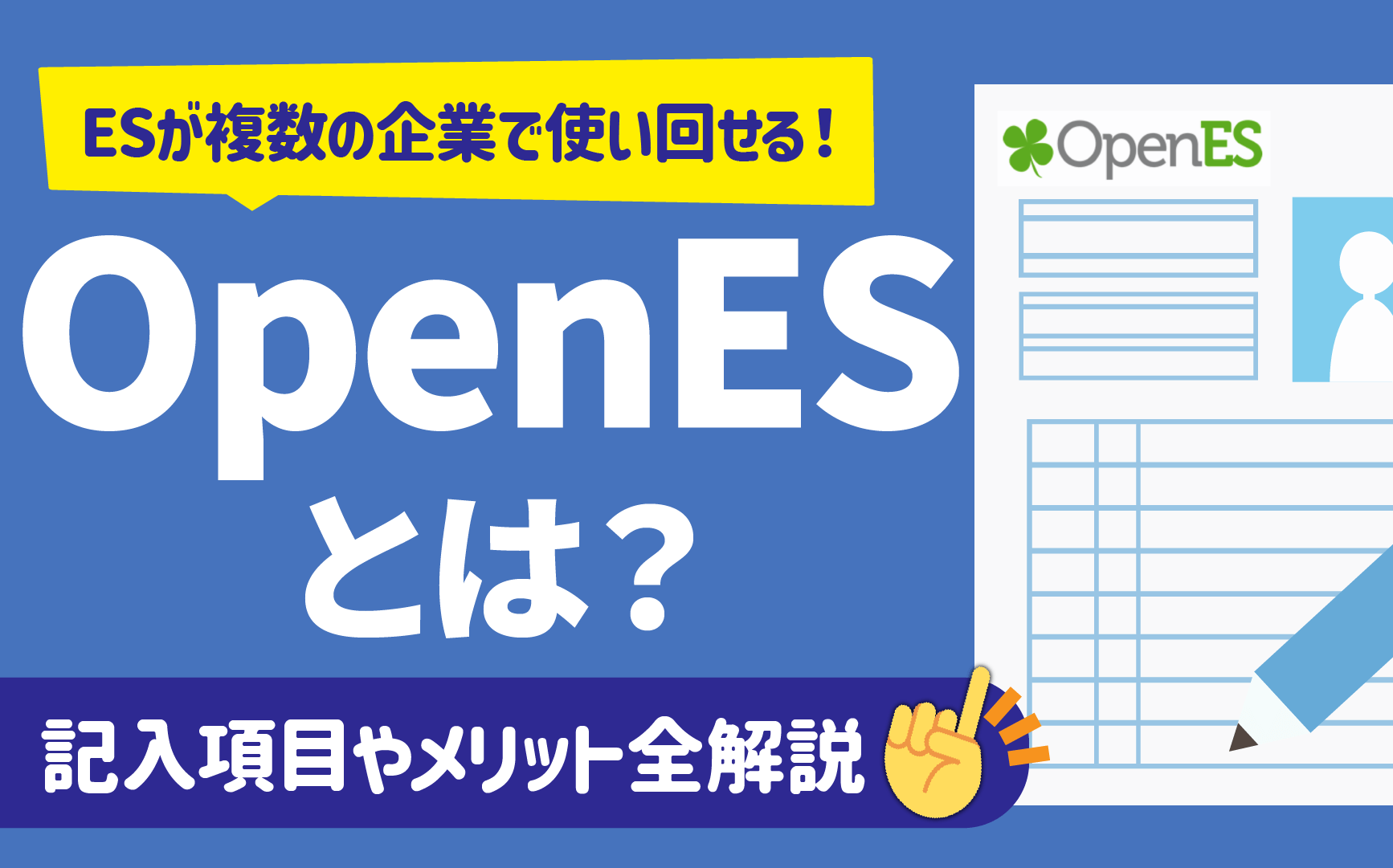
【OpenES(オープンES)とは?】記入項目,メリット,重要ポイントを解説 | エントリーシート/履歴書との違いも
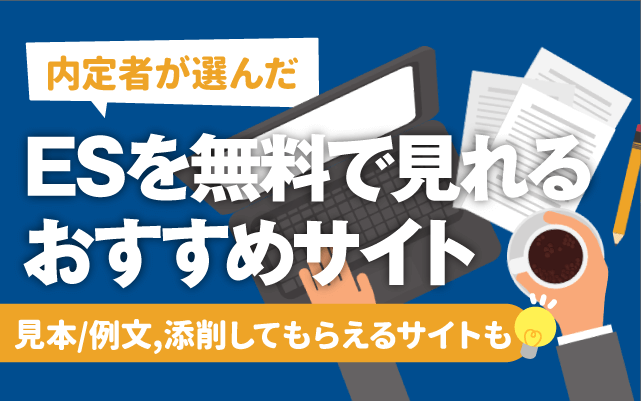
【内定者選んだ】ESを無料で見れるサイトおすすめ12選 | 見本,参考の仕方も
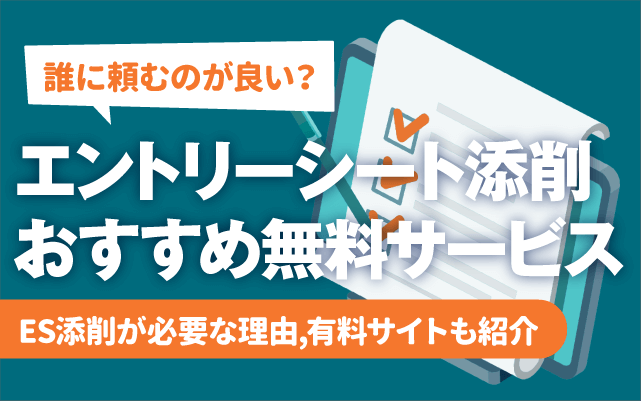
【誰に頼む?】エントリーシート添削の無料サービスおすすめ15選 | ES添削の有料サイトも
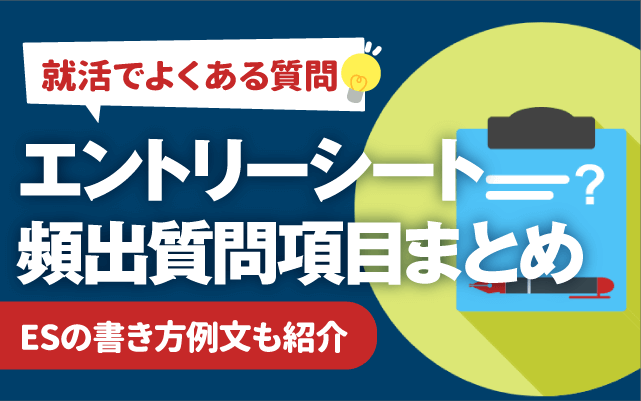
【よくある質問項目】エントリーシート(ES)で聞かれる頻出質問100選 | 書き方の例文も

【新卒向け】エントリーシート「自己PR」の構成と書き方 | 例文,注意点も
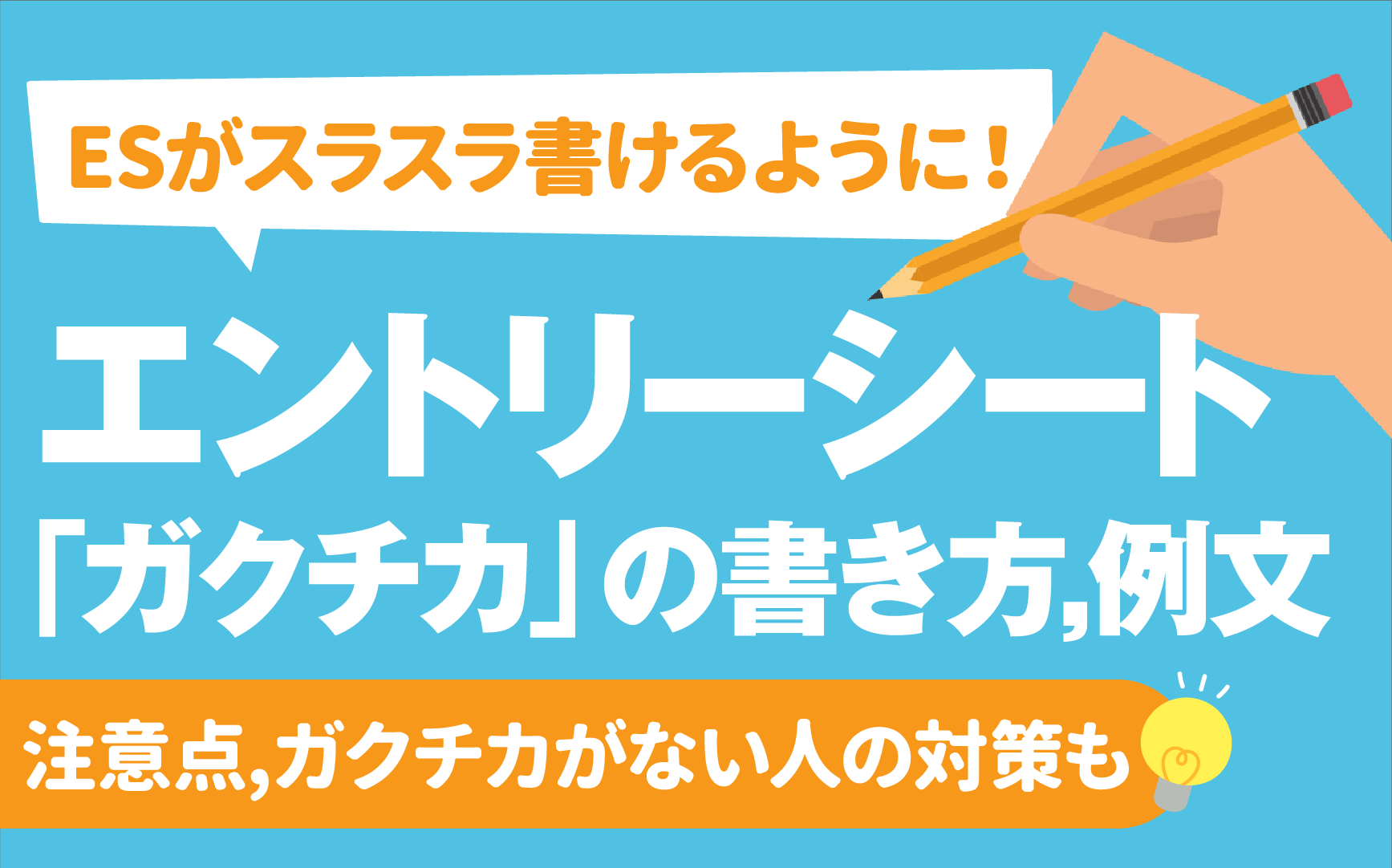
【内定者が教える】エントリーシート「ガクチカ」の書き方,例文(学生時代に力を入れたこと)
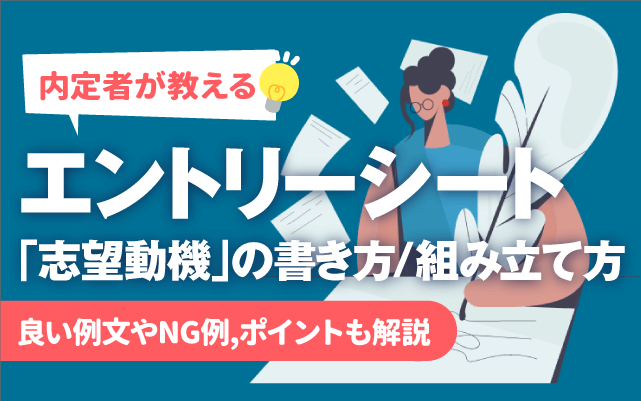
【内定者が教える】エントリーシート「志望動機」の書き方/組み立て方 | 良い例文やNG例も
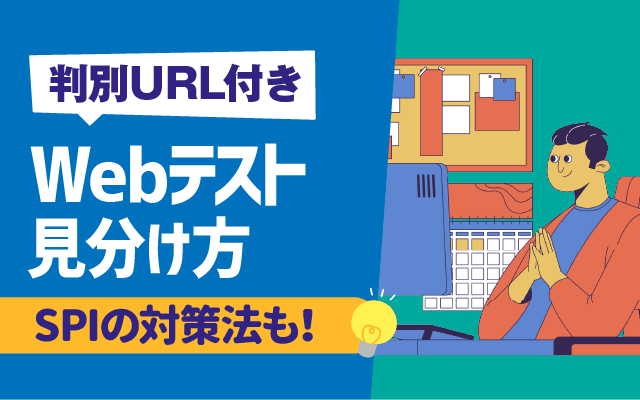
【判別URLも】Webテスト22種類の見分け方 | オンライン監視型,SPI,玉手箱などの対策方法も
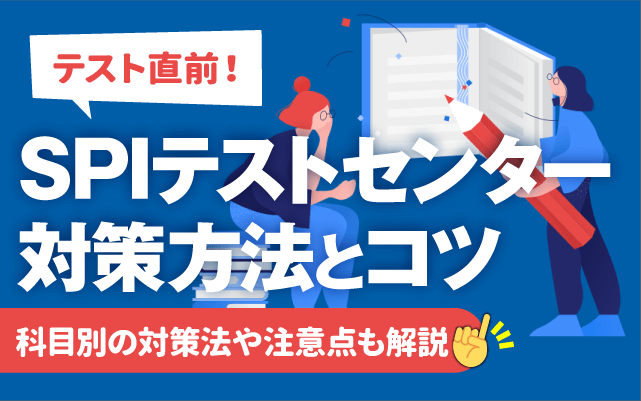
【完全版】SPIテストセンターの対策方法とコツ | 科目別のポイント,注意点も
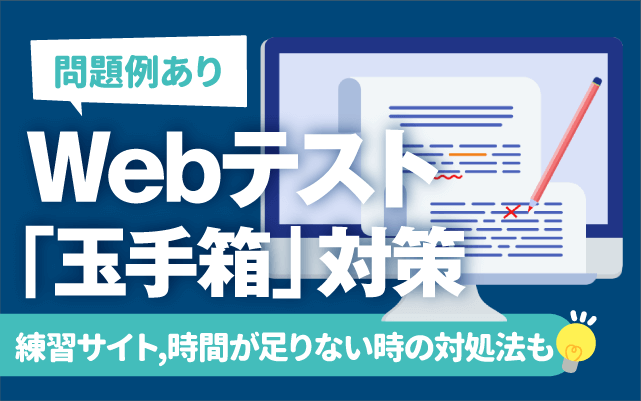
【例題あり】「玉手箱」の問題と対策 | 解答,練習サイト,出題企業も
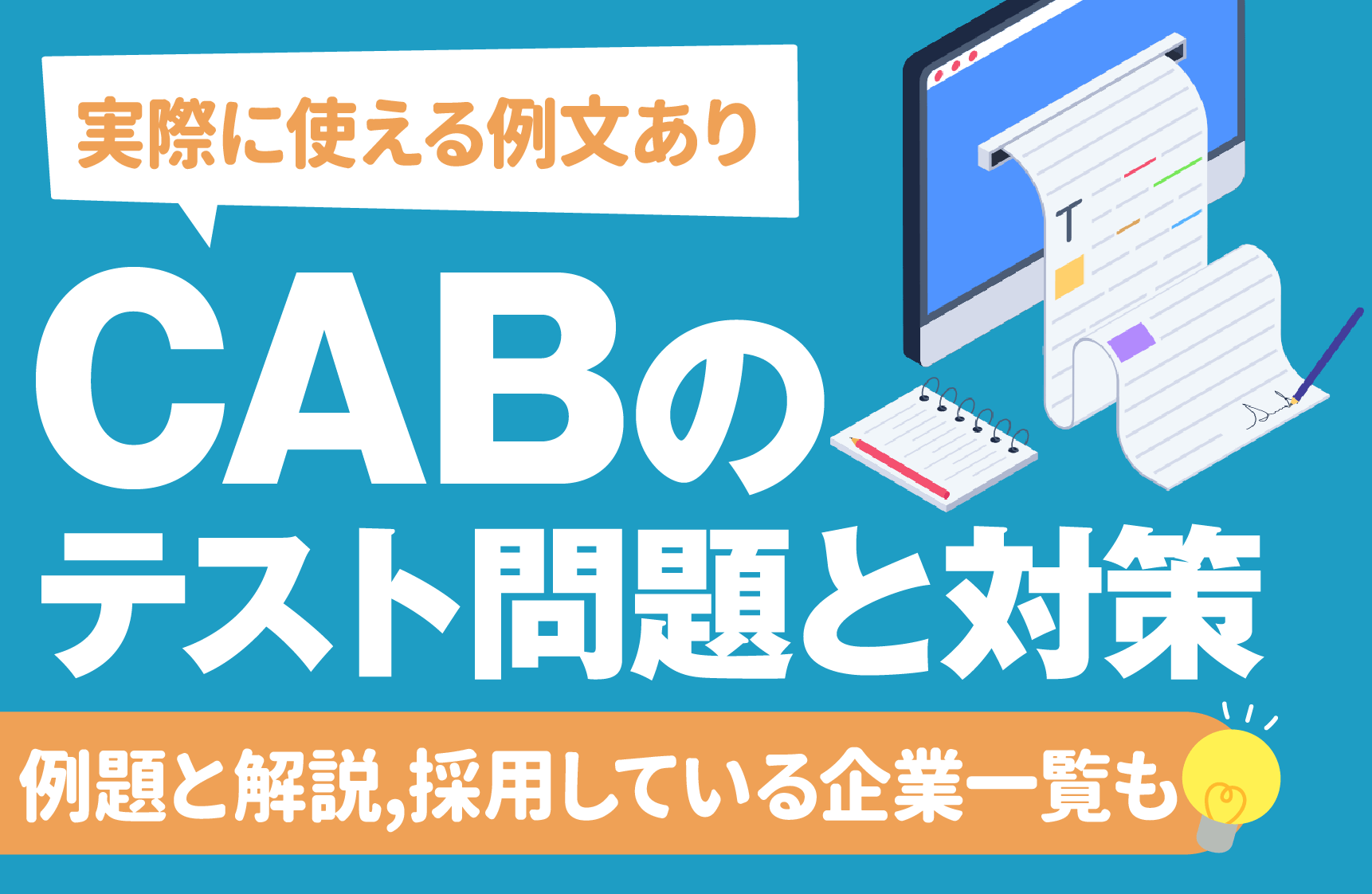
【例題あり】CAB/Web-CAB適性検査の問題と対策 | 出題企業,解答集の有無も
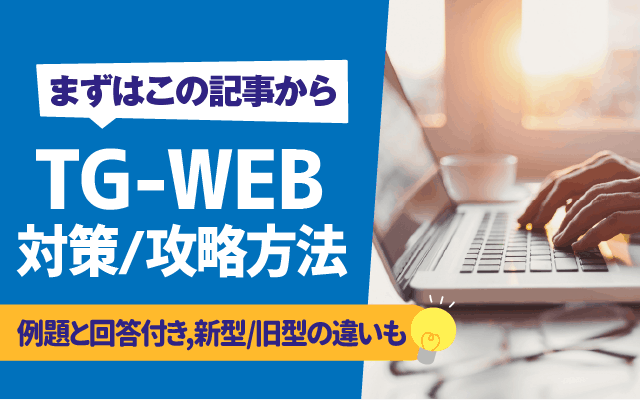
【例題あり】TG-WEBの問題と対策 | 合格ライン,問題集,監視型eyeの見分け方も
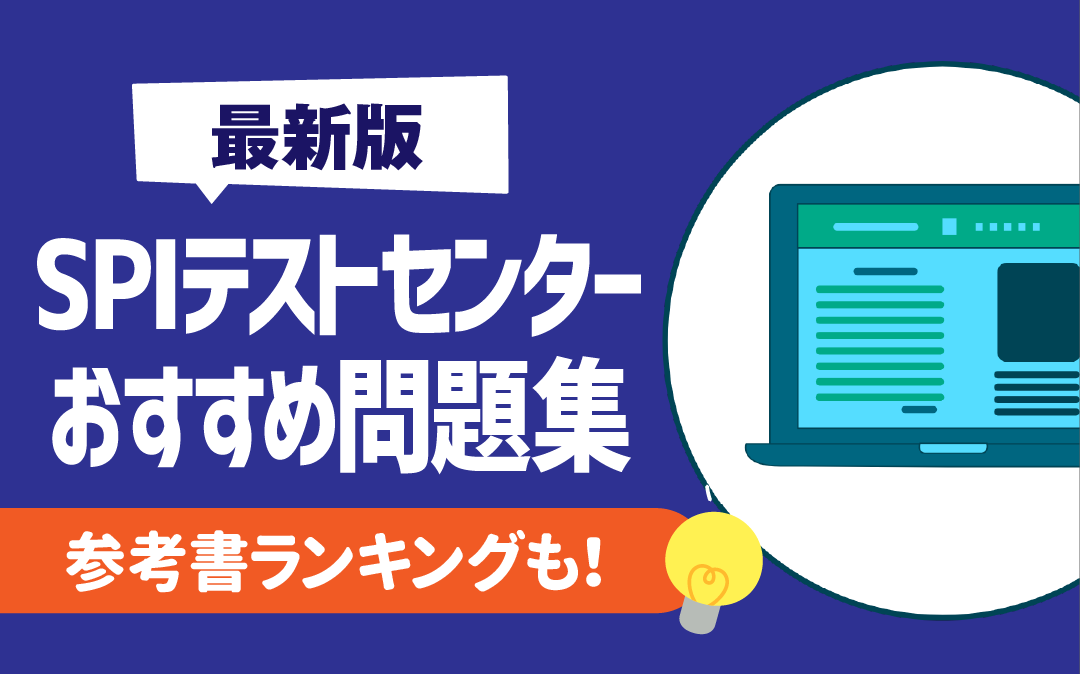
【最新版】SPIのおすすめ対策本/問題集10選 | 参考書,青本は難しい?

【無料サイト7選】SPIテストセンター練習問題のダウンロード方法 | Web問題集も
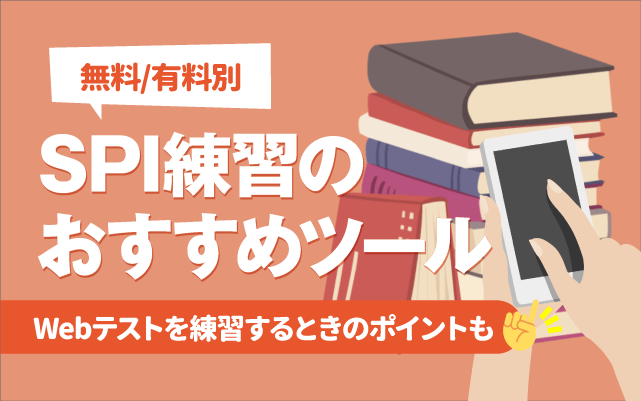
【最新版】SPI対策アプリおすすめランキング一覧 | 無料版/有料版,デメリットも
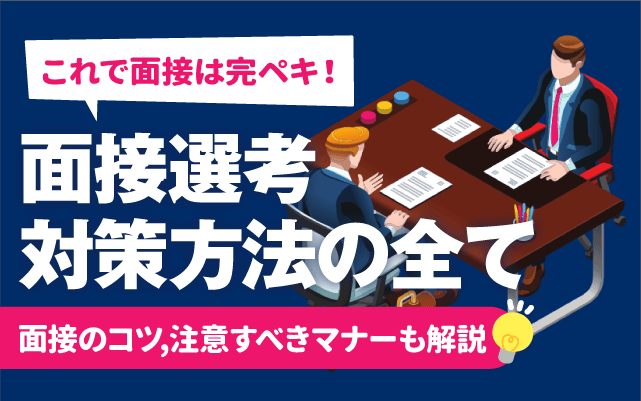
【新卒就活生へ】これで完璧!面接選考の対策方法の全て
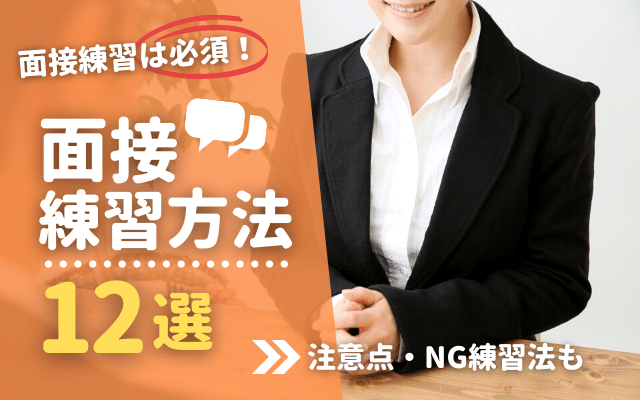
【どこでする?】面接練習のやり方12選 | 間違った練習方法,面接練習できる企業の紹介も(新卒向け)
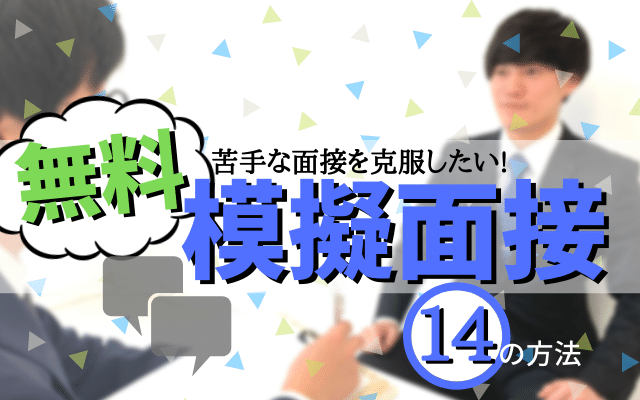
【内定者が教える】模擬面接を無料でしてもらう方法14選 | 就活支援,エージェントなど
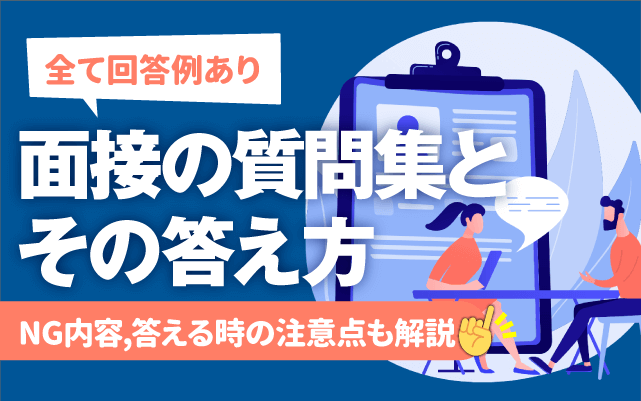
【回答例あり】面接の質問集100選と答え方 | NG内容,注意点も
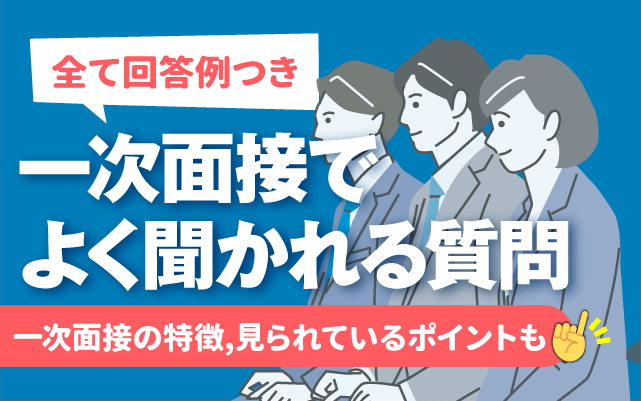
【一次面接対策】よく聞かれる質問35選と答え方 | NG回答例も
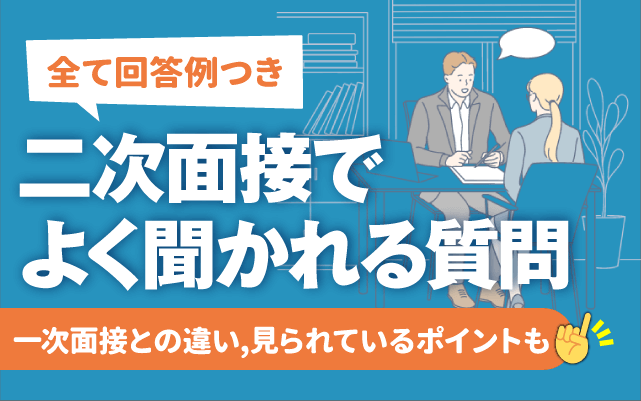
【二次面接対策】よく聞かれる質問16選と答え方 | 一次面接との違いは?
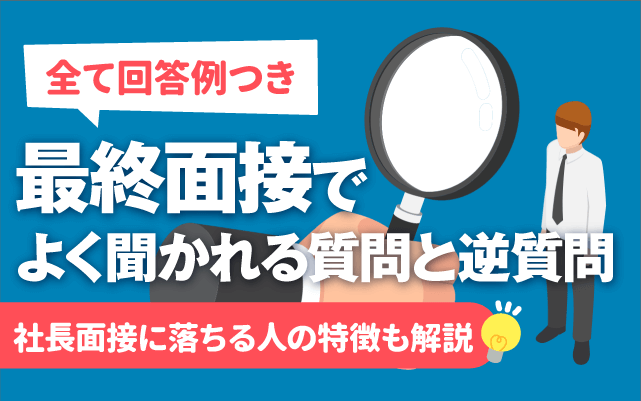
【最終面接対策】よく聞かれる質問と逆質問 | 答え方やNG例も
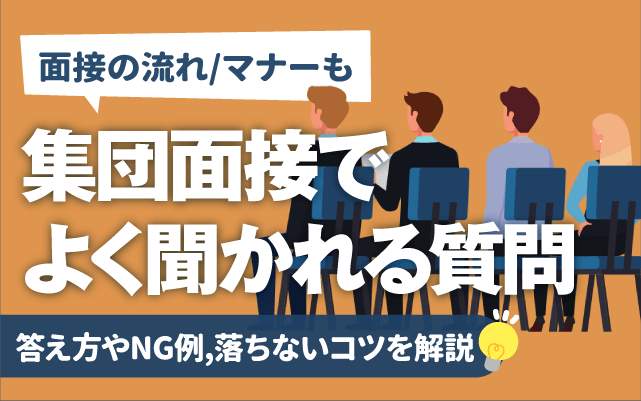
【集団面接対策】よく聞かれる質問23選と流れ/マナー | 答え方やNG例も
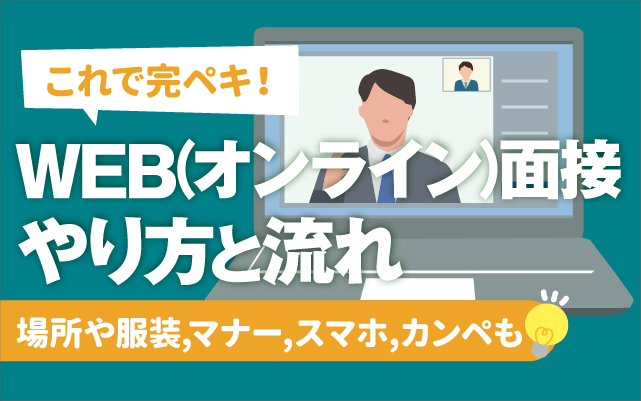
【何聞かれる?】WEB面接(オンライン面接)のマナーとやり方 | 場所や服装,マナー,スマホ,カンペも
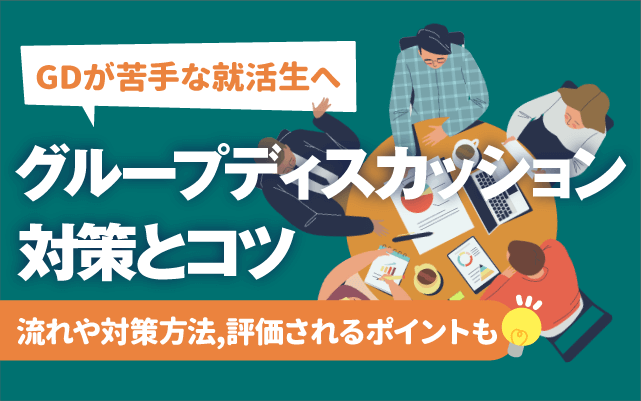
【GDが苦手な就活生へ】グループディスカッション対策とコツ
New
- 新着記事 -
Interview