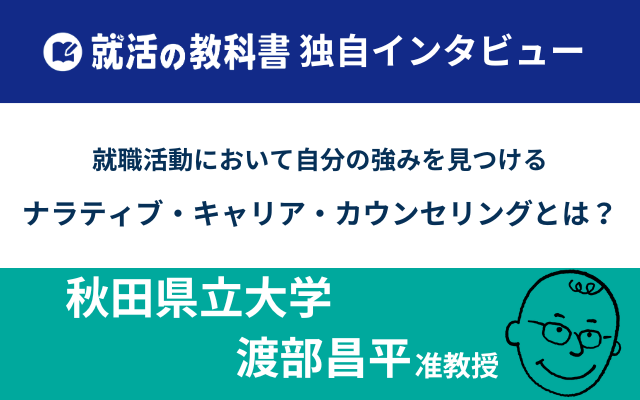「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの小林です。
本日は、秋田県立大学総合科学教育研究センターの渡部昌平准教授にお話を伺いました!
この記事を読めば、「ナラティブ(社会構成主義)」や「ナラティブ・キャリア・カウンセリング」について知ることができます。
「自分の強みが見つからない…」や「会社・仕事をどう考えたらいいんだろう?」などの悩みがある人は必見です!
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
渡部先生、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授

渡部 昌平(わたなべ・しょうへい)
秋田県立大学 総合科学教育研究センター 准教授
明星大学大学院人文学研究科心理学専修課程修了後、当時の労働省入省。
2011年4月より秋田県立大学総合科学教育研究センターで准教授を務める。
1級キャリアコンサルティング技能士をはじめ、産業カウンセラー、ガイダンスカウンセラー、上級教育カウンセラーなどの資格を持つ。
目次
秋田県立大学 渡部昌平教授にインタビュー①:「ナラティブ」とは?
人は「客観的事実」によってではなく、「自分自身や周囲が意味づけた世界」に生きている
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
さっそくですが、渡部先生の専門分野である「ナラティブ」とは何か教えてください!
ナラティブ(社会構成主義)とは、人は「客観的事実」によってではなく、「自分自身や周囲が意味づけた世界」に生きているという考え方です。
私たちは、過去の経験に意味を与え、それを物語として再構成しながら、思考や行動を決めていきます。
業界や分野によって異なる使われ方をする単語ですが、
本人の価値観(仕事観・人生観)
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
事実そのものよりも、“自分にとっての意味”が重要なんですね!
経験の「意味づけ」は人によって変わる
同じような経験をしても、それをどう受け止めるか(=意味づけ)は人それぞれです。
しかもその意味づけは、時間の経過や新たな経験によって変わっていきます。
例えば、子どもの頃に数学が得意だと思っていた人も、大学で挫折すると「数学は得意じゃない」「好きじゃなくなった」と感じるようになるかもしれません。
反対に「得意じゃなくなったけど、数学は好き」と捉える人もいます。
また、「自分はダメな人間だ」と思っている人も、実際には「集中力がある」「深い人間関係を築ける」など、ポジティブな側面を持っています。
しかしそうした“別のストーリー”が語られず、埋もれてしまっていることが多いのです。
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
自分の受け取り方によって、自分の良い側面に気づけなくなってしまうのですね…
本人の中に眠る「語られていない自己」を掘り起こす:ナラティブ・キャリア・カウンセリング
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
埋もれてしまっている“別のストーリー”に気づく方法はありますか?
意図的に掘り起こして「あって欲しい未来」を構築しようとするのがナラティブ・キャリア・カウンセリングです
ナラティブ・キャリア・カウンセリングは、本人の中に眠る「語られていない自己」や「ポジティブな物語」を掘り起こし、「こうありたい未来」の姿を描いていく支援方法です。
人は誰でも「好きだったこと」「感動したこと」「頑張った経験」を持っています。
それらを思い出し、「自分はどう生きたいのか」「何を大切にしたいか」を見つめ直すことで、前向きなキャリアの選択が可能になります。
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
ナラティブ・キャリア・カウンセリングは自分のキャリアに活かすことができるのですね!
仕事観が明確になっていない人にナラティブ・キャリア・カウンセリングが有効
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
ナラティブ・キャリア・カウンセリングはどのような人を対象に行っているのでしょうか?
対象としているのは、「自分の強みが分からない」「どこに就職すればいいか迷っている」といった、仕事観や人生観が明確になっておらず、自信を持てずに悩む人などです。
そのため、一般的な中高年向けの再就職支援とは異なり、カウンセラーの側から積極的に質問を投げかけるスタイルが多くなっています。
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
キャリア・カウンセリングというと社会人向けのイメージがありましたが、ナラティブ・キャリア・カウンセリングは特に大学生などの若者に向いているんですね!
秋田県立大学 渡部昌平教授にインタビュー②:「ナラティブ・キャリア・カウンセリング」で自分の価値を見つける
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
ナラティブ・キャリア・カウンセリングは具体的にどのように行うのか教えてください!
「できなかったこと」より「やったこと」「できたこと」に注目する
自信をなくしている学生に対して、「自信がないんだね」とその悩みに寄り添いすぎると、気持ちがますます落ち込んでしまい、相談も長引きがちです。
そこで、「勉強もサークルも頑張らなかった」と言う学生にも、「それでも何かやったことはない?」と問いかけます。
たとえば面白かった講義、印象的だった旅行、好きな趣味やゲーム、YouTubeなど、どんな些細なことでも構いません。
そこから、「友達を大切にしている」「スポーツが好き」「情報収集が得意」といった“キーワード”が見えてきたら、それに関連する他の活動も深掘りします。
こうしてポジティブな面に光を当てていくことで、学生自身も「できたこと」や「大切にしていること」に気づきやすくなり、会話も前向きになります。
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
些細なことから深掘りしていくと、どんどん自分のポジティブな面が見えてくるのですね!
未来の理想像を問う
次に、過去ではなく「これからどうなりたいか」という未来に目を向ける方法です。
自分に自信がない学生は、「明るい未来なんて想像できない」と感じがちですが、そんなときは「もしこれからうまくいったとしたら、どんな未来が理想?」と問いかけて、将来の理想像を引き出します。
理想の「仕事」が思い浮かばなくても、「どんな性格になりたいか」「どんな人間関係を築きたいか」など、将来の“ありたい姿”をイメージしてもらいます。
そのうえで、「そうなるためにこれから何をしていくか」を一緒に考えるのがポイントです。
未来に希望を描けるようになると、自然と気持ちが前向きになり、行動にも意欲が出てきます。
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
将来やりたい「仕事」を考えるとなかなか難しいですが、「なりたい姿」ならイメージしやすいですね!
過去の経験の“見方”を変える=リフレーミング
「理想の未来」が描けても、「自分には何もない」と思い込んでいる学生は少なくありません。
そんなときは、過去の経験の“見方”を変える=リフレーミングの技術を使います。
たとえば、マンガ・ゲーム・YouTubeなどに熱中していた時間も、「集中力がある」「楽しむ力がある」と捉えることができます。
また「生育環境が悪かった」「勉強ができなかった」と語る学生にも、「その中で腐らずに頑張ってきた自分」がいたことに気づいてもらうようにします。
このように、会話の中から「そんな環境や能力でもどうにか適応してきた自分」を見つけてあげるリフレーミングの技術も活用可能なのです。
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
過去の経験を悲観的に捉えるのではなく、その中でも努力してきた自分がいることに気づいてあげるんですね!
「継続していること」から自分の資源を見つける
「長所は何?」「自己PRして」と聞かれても、答えられない若者は多くいます。
でも、「友達より少しでも得意なら長所にしていい」と伝えたり、「まだ長所とは思えないかもしれないけど、継続して頑張っていることはある?」と尋ねることで、話が引き出せることがあります。
たとえば、「毎日10分英語を勉強している」「1日3キロ走っている」「剣道を9年続けた」「バイトを3年間続けている」といった具体例が挙がります。
そうした話が出たら、「なぜ続けているの?」「どうして続けられたの?」と掘り下げることで、本人の価値観や内面の強みに気づいてもらうことができます。
多くの場合、本人はそれを「当たり前」と思っているため、カウンセラーが価値として言語化し、本人に気づかせることが大切です。
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
自分が「当たり前」と思っていることに自分の強みがあるのですね!
「失敗からの学び」を資源にする
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
失敗から得た経験からその人の価値観が形成されているのですね!
秋田県立大学 渡部昌平教授にインタビュー③:「ナラティブ・キャリア・カウンセリング」で勇気づける
不安を受け入れ、前に進むための理解を育てる
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
自分の中の強みに気づいけたら、どのように行動していけばいいでしょうか?
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
行動することで自信を育てていくんですね!
ロールモデルを持つことで前向きな行動を促す
「尊敬する人」を持つことで、前向きに行動する力が高まります。
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
ロールモデルを持つことで、具体的な人物像がイメージしやすいですね!
支えとなる存在を意識的に持つ
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
自分を支えてくれる存在を“意図的に”作るという考え方があるのですね!
「ナラティブ・キャリア・カウンセリング」のポイント
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
ナラティブ・キャリア・カウンセリングは友人や家族など身近な人と実践することはできますか?
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
同じ目線に立つことが重要なのですね!
秋田県立大学 渡部昌平教授にインタビュー④:仕事を選ぶ上で大切なこと
会社の知名度や労働条件だけで考えない
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
就職活動において、仕事を選ぶ上で重要なことはありますか?
「会社の知名度や労働条件だけで考えない」。
必ず自分の価値観や強みを意識した選択肢を考えることが重要ではないかと思います。
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
会社を探すときに、どうしても労働条件ばかり見てしまうので気をつけたいです…
「その仕事・人生にドキドキワクワクできるか」を考える
就職後3年以内に離職する人が大卒でも3割以上います。
「
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
3年以内の離職率が思っていたより高くて驚きました…!
労働条件が良くても、自分の価値観に合わない会社では続かないですよね。
入社後のギャップをなくすために:「実際に働いている人の生情報」を知る
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
働いた後のギャップ(リアリティショック)をなくすために、
リアリティショックを受けないためには、しっかりとした業界・
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
事前に、実際の様子を知っておく、体験するということが大事なんですね!
秋田県立大学 渡部昌平教授から就活生へのメッセージ
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
ナラティブや就活において大切なことを教えていただきありがとうございます。
最後に、就活生へのメッセージをお願いします!
満足度100点満点の仕事じゃなくていい
すべてに満足できる仕事でなくても構いません。
いくつかの仕事を調べた中で一番満足度の高い仕事を(たとえ満足度40点でも)見つけてみましょう。
そのうえで、どんな知識や経験が必要かを調べ、今できることから取り組んでいくことが大切です。
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
とにかく動き出す、待っているだけでは納得のいく仕事は見つからない
満足度の高い仕事を見つけたければ“動く”ことが重要です。
もし、もっと満足度の高い仕事を見つけたいのであれば、自分で探す、人に聞く、いろいろ試してみることが必要です。
待っているだけでは、納得のいく仕事は見つかりません。
インターンシップやワンデー、ジョブシャドウイング、企業・工場見学(あるいは直営店)に行ってみる。
働いている人のインタビュー記事を読んだり、親や周囲の働いている人に話を聞いたりするのも効果的です。
ネット上の職業興味検査や適性検査を受けてみるのもよいですが、受けっぱなしにせず、「あなたに向いている」と出た業界や企業をしっかり調べてみてください。
1人で家の中で悩み続けても、たいてい答えは出ません。
まずは本やネットで調べ、人に聞き、実際に現場を見に行くなど、とにかく動き出すことが解決への第一歩です。
知っている人・詳しい人に相談するのも有効な方法です。
 秋田県立大学 渡部昌平准教授
秋田県立大学 渡部昌平准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
素敵なお話をたくさんありがとうございました!
私自身も自分のキャリアのために少しずつでも行動していこうと思います。
本日は本当にありがとうございました!