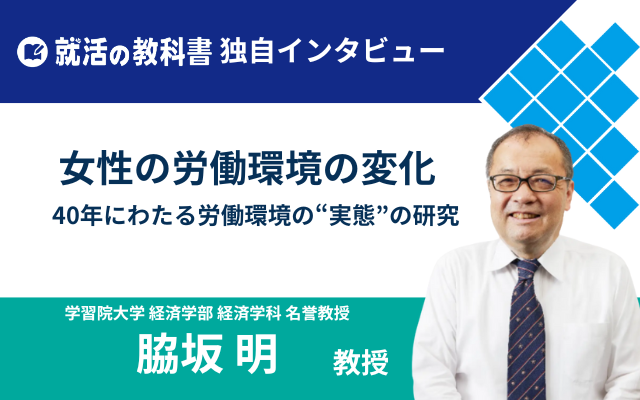「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの小林です。
本日は、学習院大学 脇坂明教授にお話を伺いました!
この記事を読めば、「女性の労働環境の変化」や「ワーク・ライフ・バランスの重要性」について知ることができます。
「女性の労働環境ってどのように変化してきたんだろう?」や「企業側の需要ってどのように変化してきたんだろう?」などの悩みがある人は必見です!
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
脇坂教授、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
目次
脇坂明教授にインタビュー①:女性の労働需要の変化
バブル景気の真っ只中で、深刻な人手不足に陥っていた
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
40年以上、女性労働の研究をされているとのことですが、その変化をどう見てこられましたか?
私が大学院生だった頃からずっとひとつのテーマで研究を続けてきまして、もう40年以上になります。
私が研究を始めたのは、ちょうど雇用機会均等法ができる前でその間に法律もいろいろと整備されてきましたが、それ以上に現場の“実態”が大きく変わったのです。
私は経済学や経営学の中でも、実際の現場に近い部分をずっと見てきたので、そういった変化を肌で感じてきました。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
どういった変化があったのでしょうか?
経済学的に言えば、労働の「需要」と「供給」の関係の変化ですね。
労働環境だけを見れば、企業=需要側の変化が大きいと思われがちですが、私は「供給側」、つまり働く女性たち自身の変化も非常に重要だと感じています。
家族の形や価値観の変化も含めて、女性たちの働き方が変わることで、逆に企業の側にも影響を与えていった。そういう相互作用がこの40年の間にあったと思います。
とくに大きな転換点だったのは1986年、雇用機会均等法が施行された時期です。
あの頃はちょうどバブル景気の真っ只中で、企業が深刻な人手不足に陥っていました。それまで企業は、正直言って女性労働をあまり重要視していませんでした。でも、もう人が足りない。そうなると、無視していた女性にも目を向ける必要があった。
その状況というのは実は現在とも似ているんです。少子化で生産年齢人口が減って、外国人労働者まで視野に入れる必要がでてきた。「平等だから」ではなく「人がいないから」必要になっているのです。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
人手不足を機に女性の労働需要が高まる
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
雇用機会均等法は、企業の女性採用にどんな影響を与えたのでしょうか?
よく「法律ができたから女性を採るようになった」と言われるんですが、私の見方は少し違います。
当時の企業は本音では「男性を採りたい」と思っていました。でもバブル期に入って大卒の男性が取れなくなってしまった。
そこで、初めて四年制大学を出た女性に目が向いたんです。
もともとは「男性は大卒、女性は短大卒で補助的な役割」というのが企業の前提でした。でもその枠組みが崩れたのです。
積極的な経営者は「これからは女性が戦力になる」と考えるようになりました。
結果として、均等法の年に多くの企業が初めて四大卒の女性を対象に本格的な採用を始めました。表向きは法律の効果に見えますが、実際は“人手不足”が一番大きな要因だったと私は思っています。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
法律によって、女性の労働需要が高まったのではなくバブル景気の“人手不足”によるものなのですね。
女性の労働内容の変化:現場労働から第三次産業へ
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
女性の労働需要が上がったことで、労働内容の方も変化したのでしょうか?
私が研究を始めた当時は、まだまだ工場などの現場労働に多くの女性がいました。
特に電機産業や繊維工場などが典型的でした。でも、それらはどんどん海外に移転していって、生産ライン自体が日本からなくなってしまった。
そうなると、企業が女性に求める仕事も変わっていきます。大きく言えば、第三次産業にシフトしていったわけです。
私は早い段階から、ホワイトカラーの女性に注目して研究してきました。当時はまだ、女性労働といえば工場などの現場ばかりに目が向けられていた時代ですけど、これからはホワイトカラーが増えると思ったんですね。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
ホワイトカラーとは、今だと事務職や営業職、専門職など、主にオフィスで働く人のことですね!
また、事務職だけで女性を雇っていても、いずれ企業が使わなくなるんじゃないかという危機感がありました。
なので私は、よりキャリアにつながるような職種、いわゆる総合職的な仕事に就く女性たちに注目して、研究を続けてきました。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
脇坂明教授にインタビュー②:女性の労働需要が高まったことによる社会の変化
企業のニーズにより女性の進学率が高まった
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
女性の労働需要が上がったことで、社会にどのような影響がありましたか?
大きく挙げられるのが、女性の進学率が上がったことです。
これは、企業の採用基準が変わったことが大きいと思っています。
昔は、短大に行くだけでも家庭には負担がありましたし、女性が大学に進学する割合は10%にも満たなかった時代が続いていました。
しかし、企業が「あるレベルの仕事には四大卒以上じゃないと採用しない」という姿勢に変わっていきました。
そうなると、当然女性の四大進学率も急上昇します。社会学的には「みんなが行くから進学する」と言われますが、私はむしろ企業のニーズが進学率を押し上げたと考えています。
このように、教育と企業の人事の関係は5年・10年の周期で大きく動いてきたと感じています。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
企業の採用方針やニーズにはものすごい影響力がありますね。
学歴の違いによる就職状況:男女関係なく能力で判断する企業も増えてきている
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
学歴の違いによる就職状況については、どのように見ていますか?
高卒での就職は、今は男女問わず厳しい状況です。。
ただ、日本とドイツは例外的に製造業が比較的強く残っているので、現場の熟練工などでの需要はまだあります。
それでも全体的には「何でも大卒」となってきていて、企業も仕事の内容に応じて「どのレベルの大卒を採るか」を考えるようになりました。
その中で性別が大きく影響する職種もあれば、男女関係なく能力で判断する企業も増えてきている。
つまり、企業ごとに事情はさまざまだというのが今の状況だと思います。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
大卒のニーズは上がっているものの、採用基準は企業によっても様々なんですね!
脇坂明教授にインタビュー③:ワーク・ライフ・バランスについて
ワーク・ライフ・バランスが生まれたきっかけ
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
脇坂教授は「ワーク・ライフ・バランス」の普及に取り組まれていたそうですね!
日本の労働環境での考え方として「ワーク・ライフ・バランス」が生まれたのはいつなんでしょうか?
きっかけは、大企業の有志グループから「ワーク・ライフ・バランスの指標を作ってほしい」と相談を受けたことです。
ちょうどその少し前にイギリスに1年間滞在していて、現地でこの概念が盛んに研究されていたこともあり、日本にも紹介し始めていた時期でした。
もともと女性労働の研究をしていて、特に出産・育児がキャリア継続の大きな壁になることを感じていました。
だからこそ、育児休業や時短勤務など個別の制度だけでなく、「ワーク・ライフ・バランス」という広い枠組みで考える必要があると思っていました。
民間企業と一緒に指標を開発して公表したことで、自治体や他の企業にも波及し、啓発や実践が広がっていきました。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
女性が出産後も働き続けられる環境をどう作るか
日本でワークライフバランスが注目されるようになった一番の原動力は「女性が出産後も働き続けられる環境をどう作るか」という課題でした。
そのためには、制度だけでなく企業文化や男性側の意識も変える必要がある。
つまり、女性の活躍推進から始まって、結果的に「働き方改革」や「家族のあり方」にまで広がっていったんです。
イギリスとは背景が違っていて、日本では女性労働の現実からこの考え方が広がっていったと私は見ています。
実際、私自身その初期の中心的な研究者の一人だったと思っています。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
日本で「ワーク・ライフ・バランス」が普及するきっかけは女性の労働環境がきっかけなのですね!
制度だけではなく、個人の役割も非常に重要
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
ワーク・ライフ・バランスの制度や意識は、どう広がっていったのでしょうか?
2007年に「ワーク・ライフ・バランス憲章」が策定されたことは大きな節目でした。
そこには、「企業・社会・個人はそれぞれ何をすべきか」が書かれていて、非常に良くできた内容だと思っています。
ただ、個人の役割については少し弱い面もありました。ワークライフバランスは制度だけではなく、個人がどのように自分のキャリアや働き方を考えるかも非常に重要です。特に出産や育児などを機にキャリアを断念するのではなく、「こうすれば続けられる」と声を上げていくことが大事なんですね。
育児休業や時短勤務が制度として整っていても、使いづらい職場では意味がありません。
かつては、結婚や出産を選ばずに働き続けた先輩女性たちが多かったですが、これからは家庭と仕事を両立しながら働ける道を個人が模索し、周囲に働きかけることが必要です。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
個人の役割も重要なのですね!
企業にとってのメリット:生産性や競争力の向上に繋がる
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「ワーク・ライフ・バランス」は企業にとってもメリットがあるのでしょうか?
私は以前から「ワーク・ライフ・バランスを推進している企業ほど、生産性や競争力が高いのではないか」という仮説で研究をしてきました。
そして多くの経済学者たちとともに、男女平等がある程度進んだうえでワーク・ライフ・バランスを整えると、生産性はむしろ上がるということが実証的に示されてきました。
短期的にはコストに見えるかもしれませんが、5年、10年という単位で見れば、人材の定着や仕事のやり方の工夫につながり、企業にとっても投資になる。
実際に、優れた企業はその視点でワーク・ライフ・バランスに取り組んでいるんです。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
一口に「ワーク・ライフ・バランス」といっても取り組み方には企業ごとに差があるんでしょうか?
その通りです。企業によって本当に温度差がある。
だからこそ、「良い企業」だけを見せるのも違うし、「悪い企業」ばかり取り上げるのも研究とは言えません。実態をきちんと見て、どうすれば多くの企業が変わっていけるかを考えることが、今後ますます大切になっていきます。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「ワーク・ライフ・バランス」は企業として取り組むことにも大きな違いがあるのですね。
脇坂明教授にインタビュー④:「キャリアデザイン」という視点
学際的な視点で「キャリアデザイン」を研究する
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
最近ではキャリアに関して様々な考え方があると思うんですが、そこはどのように見ていますか?
キャリアコンサルタントという資格もできて、厚労省も後押しする中で「キャリアブーム」になりました。
ただ、正直言うとそのブームには危うさもあるんです。というのも、学問的な裏付けがないまま、いろんなことを語ってしまっている人も多い。
だからこそ、ブームに乗るのではなく、しっかりと学際的な視点で「キャリアデザイン」を研究していくことが大事だと思っています。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
今までのキャリア教育の中に、少しでも“デザイン”の視点があればいい
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「キャリアデザイン」という視点は、キャリア研究において影響がありますか?
やっぱりキャリアデザインの考え方が背景にあると、研究に深みが出ると思います。
ただ、「キャリアデザインそのもの」を研究する必要はないんです。
たとえば、これまで通り「労働」や「教育」など、いろんな視点からキャリアを研究して、その中に少しでも“デザイン”の視点があればいい。
キャリアが実際にどう築かれているのかをまず見たうえで、「どうあるべきか」を考える。
そこにキャリアデザインという概念が生きてきます。
この分野はまだ20年ちょっとの若い学問ですが、今後、ワークライフバランスやキャリア教育など、社会にインパクトを与えるような研究がもっと出てくるといいと思っています。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
キャリアを作る一番の基礎:できるだけ多くの世界を見て、学び続ける力をつける
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
キャリアについての情報が溢れている中で、学生はどのようにキャリアに向き合ったらいいと思いますか?
キャリアとは一人ひとり違うものなので、「こうすればいい」と一括りには言えないんです。
だから、誰にでも当てはまるような抽象的なアドバイスって、学生には響かないと思うんです。
もちろん、社会に出て10年くらい経ってからなら、そうした抽象的な言葉が心に残ることもある。
でも、学生にはまだ実感がないからピンとこない。リアリティのある言葉じゃないと、伝わらないんです。
キャリアコンサルタントの資格を持っていても、それだけで良いアドバイスができるわけじゃなくて、その人自身がどんな経験を積んできたかによって、伝えられることが変わる。
自分のキャリアについて助言してくれる人が、自分の立場に立ってリアリティを持って話してくれるかどうかが重要だと思います。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
ただ、キャリア支援を受けるだけじゃなく、自分でもしっかり考えていかないといけないのですね!
キャリアを作るために、重要なことはありますか?
まず大事なのは、自分の知らない世界をきちんと知ろうとすることです。
経験していないことは、本や論文から学ぶしかない。だからこそ、読書や勉強を通じて、自分の視野を広げていくことがすごく大事なんです。
それと、知らないのに知ったかぶりをしないこと。
社会や業界はどんどん変わっていくから、謙虚に学び続ける姿勢が必要です。実際、自分の知らないことを話す人って、すぐにわかるんですよ。信頼される人っていうのは、ちゃんと勉強して、自分の言葉で話せる人です。
だから学生のうちに、できるだけ多くの世界を見て、学び続ける力をつける。
それが、これからのキャリアをつくる一番の基礎になると思います。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
きちんと“知ろうとする”ことを続けて、自分の経験や力をつけていくんですね!
脇坂明教授から学生へのメッセージ:「ステレオタイプにとらわれず、本当の意味での業界研究をしてほしい」
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
現代までの労働環境への変化やキャリアについて教えていただき、ありがとうございました!
最後に学生へのメッセージをお願いします!
今の社会は大きく変わりつつあります。実はここ40年ずっと変わり続けてきたんですが、2025年の今、特に変化が加速しています。だからこそ大事なのは、「これまでこうだったから、きっとこうだろう」と思い込まないことです。
ステレオタイプにとらわれず、本当の意味での業界研究をして欲しい。そのためには、できるだけ現場の声を聞いてみること。大学の先輩など、その業界で働いている人に直接話を聞くのがいちばんです。
少し勇気がいるかもしれないけど、それが何よりもリアルで役に立ちます。
そうした丁寧な就職活動の経験は、単に「就職先を決める」ためだけではなく、その後30年、40年にわたる人生の土台になると思います。
自分の興味ある仕事や業界があったら、まずはしっかり調べてみてください。実は、その「調べ方」こそがすごく大切なんです。本来、キャリアセンターやキャリアコンサルタントが教えるべき部分なんですが、正直まだ十分にはできていないのが現状です。
だからこそ、自分から動いて、自分の目で確かめてみてください。その経験が、きっと将来の自分を助けてくれるはずです。
 学習院大学 脇坂明教授
学習院大学 脇坂明教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
脇坂教授、本日は素敵なお話をありがとうございました!