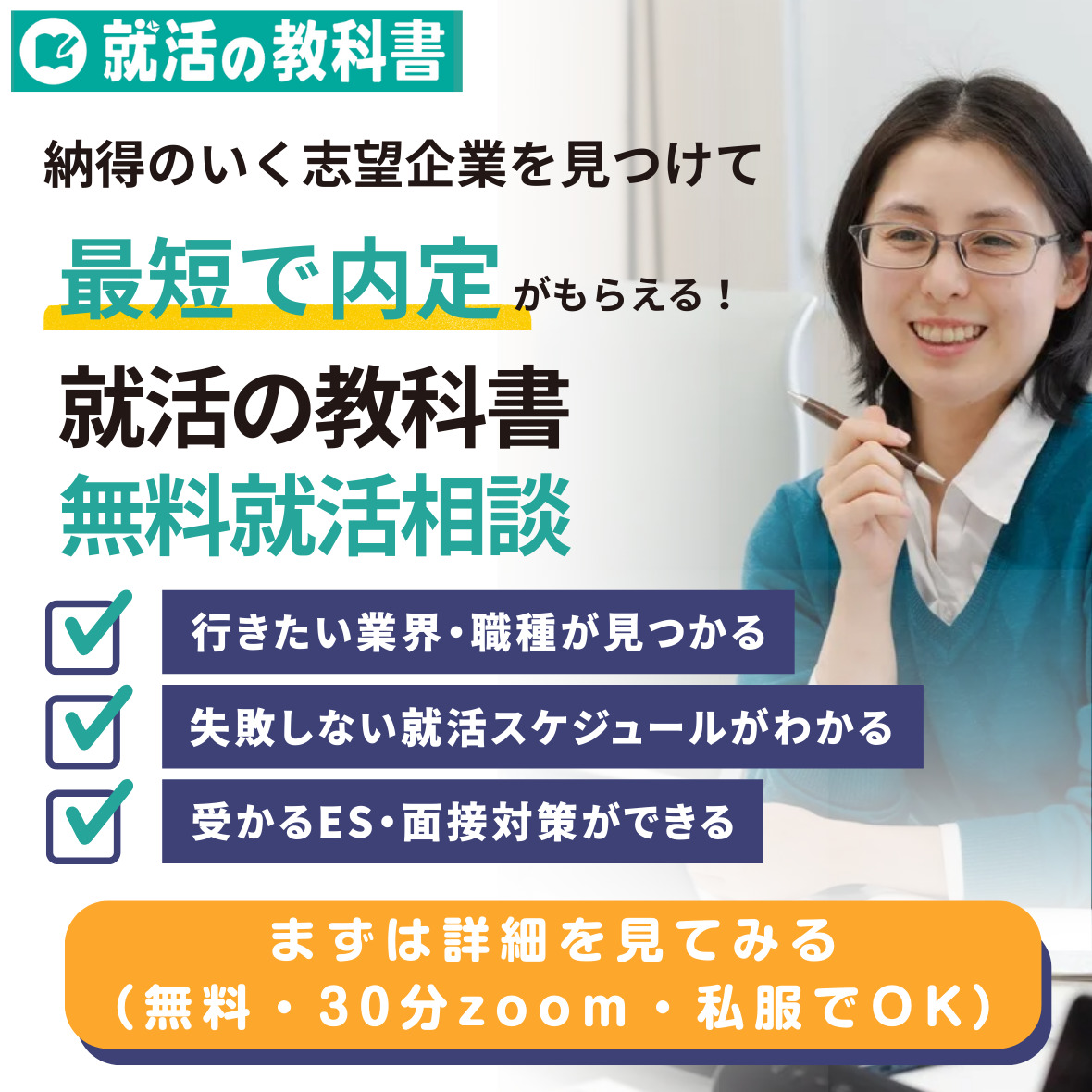「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの小林です。
本日は、びわこ成蹊スポーツ大学の清水克彦教授にお話を伺いました!
この記事を読めば、「キャリアの考え方」や「就活で身につけるべき6つの力」について知ることができます。
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
清水先生、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
清水克彦(しみず・かつひこ)
びわこ成蹊スポーツ大学 教授・キャリアセンター長
1962年愛媛県生まれ。早稲田大学大学院公共経営研究科修了、京都大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。文化放送報道キャスター、チーフプロデューサー、大妻女子大学非常勤講師を経て、2024年より現職。
現在、TBSラジオ朝ワイド番組のコメンテーターや短大講師も務める。著書は53冊。趣味は海外旅行と高校野球。
目次
びわこ成蹊スポーツ大学 清水克彦 教授にインタビュー①:キャリア教育・研究テーマ
キャリア教育の目的:若い人たちがちゃんと“自立できるようになること”
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
清水先生が行われているキャリア教育・研究について教えてください!
私はキャリアデザインを担当しているんですけど、大学の授業はどうしても“就職活動のため”っていうイメージが強いんです。
でも本来の目的は、若い人たちがちゃんと“自立できるようになること”なんです。
人口減少や外国人労働者への依存、生成AIによる仕事の変化……そういう荒波の中でも生き抜ける力をつけることが大事だと思っています。
だから研究テーマとしては“どう学生に自立心を根付かせ、社会に出ても世の中で渡り歩いていける力を身につけてもらうか”なんです。
それとは別に、私は元々政治記者をやっていたので、日本の政治や国際関係──アメリカやロシア、ウクライナ問題なども研究テーマにしています。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
“就職活動のため”ではなく、“自立して生きていけるようにする”ためなんですね!
キャリア教育に携わろうと思ったきっかけはありますか?
2016年に18歳選挙権が導入されてから、高校生や大学生と話す機会が増えました。
ただ、多くの学生は世の中に目を向けていない。
権利を得ても投票に行かないし、社会の流れを知らないと時代に合わせて自立していくのは難しいと思ったんです。
だから東京を離れて、「若い人たちに“今の世の中の動き”や“身につけるべき力”を伝える場を持ちたい」と思いました。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
実際に政治現場を見られてきたからこそ、社会問題に着目されたのですね!
自立するために必要な「6つの力」
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
“キャリア”において重要なことは何でしょうか?
やっぱり一番大事なのは“自立する力”です。
そのために必要なのが“6つの力”だと思っています。学歴や資格よりも大切なんです。
1つ目は 世渡り力。人との関係をうまく築けなければ、どんな有名大学を出ても通用しません。
2つ目は 基礎学力。読み書きや計算ができないと社会では戦えない。
3つ目は ブランド力。自分だけの強みを持つこと。
4つ目は 自衛力。時間や健康を守り、自分の時間を確保する力です。
5つ目は 学習力。学歴よりも“学び続ける姿勢”が重要になります。
6つ目は 設計力。人生を自分でプロデュースする力ですね。
この6つのうち、1つでも2つでも身につけてくれればいい。
学生の何人かが前向きに生きる力を得てくれたら、それだけで意味があると思っています。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
どれも社会で生きていくのに必要な力ですね!
理想のキャリア教育の授業は“何も教えない授業”
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
授業の中で大切にされている視点はありますか?
私自身、高校生の頃は新聞も読まなかったし、ニュース番組もほとんど見ていませんでした。
放送局に入ったのも“なんとなく目立っていていいな”という理由でしたから、18歳や19歳の学生なんてだいたいそんなものなんです。
でも、社会に少しでも目を向けている学生とそうでない学生の差は大きい。
だからキャリアデザインの授業では“教える”というより、学生自身に気づいてもらうことを大事にしています。
政治学のように文献や理論を学ぶのではなく、キャリア教育はまだ新しい分野です。
私は“気づきを与える授業”、いわば“びわこ版スタンフォードの白熱教室”を目指していて、理想は“何も教えない授業”なんです。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
ただ教えられるだけではわからない、自分で“気づく”ことで大きく成長できそうですね!
基礎力をつけ、応用で実践的なキャリア教育
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
キャリア授業はどのように展開されていますか?
1、2年生のうちは“基礎力をつける時期”だと考えています。
授業は大きく3つに分けていて、まずは記者時代の経験を活かして時事問題を15〜20分解説します。
次に、読み書きや計算など基礎学力を鍛えるため、毎回SPI形式の問題を3問解かせています。
そして残りの時間は“お金のこと”や“SWOT分析”などテーマを決めてディスカッションをします。
2年生になると少し応用編になり、実際に企業の採用担当者を招くなど社会を直に感じてもらう授業をします。
3年生は就職活動がどんどん早まっているので、まさに“就職最前線”という形でキャリア教育をしています。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
企業や事業の内部環境における「強み(Strength)」と「弱み(Weakness)」、および外部環境における「機会(Opportunity)」と「脅威(Threat)」の4つの要素を洗い出し、分析するフレームワーク。
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
基礎力から応用力まで網羅したキャリアのための授業を展開されているのですね!
企業の方を招いた際には、どのような話をされているのでしょうか?
授業では、頻繁にゲストをお招きし話してもらうようにしています。
例えば自動車メーカーの方なら“業界全体が今どう動いているか”、銀行や証券会社の方なら“今の金融市場の流れ”を、学生にも分かるように話していただいています。
うちはスポーツ大学なので、学生はスポーツ分野には強いんですが、逆にそれ以外の世界はあまり知らないんです。
だから、スポーツ選手や関連企業を目指すのももちろん良いけれど、“スポーツを活かしてこんな道もあるよ”というアナザービューを、学生のうちから知ってもらいたいと思っています。
入学したときは、サッカー部なら“Jリーガーになれる”、野球部なら“ドラフトにかかるかも”と本気で思っている学生が多いんです。でも世の中そんなに甘くなくて、途中で現実を知る学生も残念ながらいます。
一方で、“バスケットで培った力を別の分野で活かせないか”と考え始める学生もいる。
そういう子たちに“こんな登山ルートもあるよ”と新しい道を示してあげるのが、キャリアセンター長としての私の役割だと思っています。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「今まで目指していたものに届かなくても、新しい道で活かせる」という視点はとても大切ですね!
びわこ成蹊スポーツ大学 清水克彦 教授にインタビュー②:キャリアにおいて重要なこと
自分の強みや興味を見つけることがスタートライン
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
いざ、自分のキャリアのために行動しよう!と思っても「何をしたらいいかわからない…」となかなか行動できない人が多いと思うんですが、まず何から始めたらいいんでしょうか?
まずは自分の“好きなこと”や“得意なこと”、将来的に“やってみたいな”と思うことを頭の中に描くことが大事です。
はっきり決まっていなくても構いません。
これまでの18年、22年を振り返って、自分の強みや興味を見つけることがスタートラインになります。
その積み重ねが、やがて“世渡り力”や“学習力”、“設計力”につながっていくんです。
特に1年生や2年生のうちに、自分の好きなこと・得意なことを早めに見つけてほしいと思っています。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
いきなり「やりたい仕事」を考えるのではなく、まず自分の強みや興味から見つけていけばいいんですね!
自分の“好きなこと・得意なこと”の延長線にある企業を探す
繰り返しになりますが、自分の“好きなこと・得意なこと”の延長線にある企業が一番長く続けられると思います。
どうしても大企業に目が行きがちですが、同じようなことをしている中小企業や制作会社などにも目を向けてほしいです。
今、新卒の3割が3年以内に辞めると言われていますが、必ずしも悪いことではないと思っています。
たとえばいきなりテレビ局に入るのは難しいけれど、まず制作会社で経験と人脈を積み、その後キャリア採用で局に入るルートもある。
同じように、金融でもいきなりメガバンクを狙わず、まずは関連企業で経験を積んでからステップアップする道もあるんです。
今はキャリア採用の時代です。
だから3年、5年働いた後にキャリアチェンジやステップアップをしても遅くない。
むしろ30代でしっかりポジションを築けばいいんだ、という考えを学生には伝えています。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
どうしても「大企業に入らなきゃ!」と思って焦ってしまいますが、新卒で入るという道以外もたくさんあるのですね!
日本の企業の平均寿命は約30年、自分自身の力が重要
日本の企業の平均寿命は大体30年くらいなんです。
もちろん創業100年、200年という会社もありますが、多くはどこかで潰れたり吸収されたりします。
だから私たちも70歳まで働かなきゃいけないし、世の中も激動している。
会社がどうなるか分からない以上、“いつでもステップアップできる、キャリアチェンジできる”力を身につけておくことが大事なんです。
授業では、そんな話を学生と雑談を交えながら伝えています。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
人生100年時代、転職が当たり前の時代で、「一つの会社でずっと生きていく」のではなく、「どこでも生きていける」力が必要なのですね!
びわこ成蹊スポーツ大学 清水克彦 教授にインタビュー③:社会変化とキャリア
日本の深刻な少子化問題:外国人労働者・AIとの共存は避けられない
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
清水先生は社会問題にも着手されているということですが、日本で今一番深刻なことは何でしょうか?
私が一番深刻だと思っているのは少子化です。
物価高などいろいろ課題はありますが、少子化は今の学生たちの将来にも大きく影響します。
日本は毎年80万人、つまり“佐賀県1つ分”の人口が減っていて、50年後には今の1億2千万人から8千万人まで減ると言われています。
そうなれば労働力不足で定年は75歳に延び、年金も減るでしょう。
外国人労働者も今の250万人から1,000万人規模に増えて、同僚が外国人やロボット、なんて時代になるかもしれません。
だからこそ学生には、基礎力を持ち、自分の頭で考え、自分の言葉で表現できる力を身につけてもらわなければならないと思っています。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
人口減少問題は、労働問題に直結していますね…
だからこそ、時代が変化する中で対応していける力が求められるのですね!
企業の選考スピードが加速、エントリーシートの複雑化
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
就職状況などはどのように変化していますか?
インターンシップや採用活動は、年々スピードが増しています。
3年生の秋頃には、もう東京のテレビ局が採用を始めているかもしれないくらいなんです。だから早い準備をしないと間に合いません。
しかも学生に求められる内容は膨大です。自己PR、学生時代に力を入れたこと、学力……とにかくたくさん文章を書かされる。
しかも業界ごとに聞かれる内容がまったく違います。
銀行とテレビ局では全然違うし、テレビ局や芸能プロダクションだと“自分を一言で表すキャッチコピーを考えて絵を描け”なんて出題もあるんです。
そんなものは大学の授業では教えられません。
ゼロから考えていたら時間が足りないので、どう準備し、どうリカバリーするか──そこを研究して、学生に伝えているんです。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
就職活動がどんどん早くなっているのはとても感じます…
最近は学生の成績を重視する企業が増えています。
面接では皆「私は真面目です」「優秀です」とアピールしますが、実際にGPAや履修状況を見れば一目瞭然。
昔のように一発勝負ではなく、普段の学び方がしっかり問われる時代になりました。
だから学生には「学業を疎かにしないように」とよく伝えています。
さらに、昔は「アルバイトで学んだことは?」といった質問が多かったのに、今は「あなたにとって働くとは何ですか?」「人生とは何ですか?」といった哲学的な質問まで飛んできます。
そうした問いにどう答えるか、自分なりに解釈してアドバイスするのも私の役割だと思っています。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
ただ自分の長所や経験を答えるだけじゃなくて、哲学的な質問も増えて複雑化していて書くのに苦戦してしまいます…
就活や業務においてAIを使うのは必須の時代へ
自己PRをゼロから書くのは大変なので、私は生成AIをうまく使えばいいと思っています。
例えば400字のPRなら、自分の強みの材料をAIに入力して、まずはざっくりと文章を作らせる。
もちろん、そのまま提出したら全然ダメですが、AIは起承転結や結論のまとめ方も上手なので、たたき台としては非常に優秀なんです。
そうやってAIを活用すれば、採用スピードが早まっても十分に適応できると思います。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「生成AI使っていいのかな?」と躊躇ってしまうことがあるんですが、上手く利用したらいいのですね!
エントリーシートに生成AIを使うと早くできると話しましたが、これは就活だけじゃないんです。
効率よく物事を進めるには、AIを味方につけるのはもうマストです。
企画書や出張報告書も、AIを使えば圧倒的に早く書ける。そうすれば無駄な残業もしなくて済みます。
だから学生のうちから、“文章やグラフをAIで作れるくらいのスキル”は身につけておいてほしい。
就活という山を通して、生成AIで文章を作ることに慣れてもらう──それが今の私の狙いです。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
技術がどんどん進化している中で「便利なものは使っていこう!」という姿勢は大切ですね。
多文化共生社会:多様な価値観と協働する力が不可欠
これからは少子化で労働人口が減り、外国人と一緒に働くのが当たり前の時代になります。
国や地域によって文化や価値観は違います。「残業はしない」「家族優先」といった考え方の人たちと協力しなければならない。
多様な価値観と協働する力が欠かせません。
そのうえで私は、必死に英語や中国語を勉強する必要はあまりないと思っています。
今やAI翻訳の精度は高く、端末さえあれば十分にコミュニケーションが取れる。
だから無理に語学に時間を割くより、自分の“好きなこと・得意なこと”を磨いた方が将来の武器になる。
大事なのは、「これから到来する多文化共生社会にどう自分をフィットさせるか」。
その力を学生には身につけてほしいと考えています。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
“多様な価値観と協働すること”を理解して、どう自分が対応していくのか考えていかなければいけませんね!
びわこ成蹊スポーツ大学 清水克彦教授から就活生へのメッセージ:「“夢”と“志”の二つを持ってほしい」
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
貴重なお話をありがとうございます。
最後に、就活生へのメッセージをお願いします!
学生には“夢”と“志”の二つを持ってほしいと思っています。
夢は自分だけのもの。
『お金持ちになりたい』『素敵な人と結婚したい』『ベストセラーを出したい』──なんでもいいんです。
一方で志は、自分だけでなく“社会全体にどう貢献できるか”。
たとえば私は、『東京と地方の学生の情報格差を埋めたい』『地方の学生に世の中の動きを伝え、基礎力や世渡り力を身につけてもらいたい』それが私の志です。
夢と志、その両方を心に持っていれば、きっと良い大人になれる。
学生には、これから70歳まで働く長い人生を歩む中で、その二つを指針にしてほしいと思っています。
 清水克彦 教授
清水克彦 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
素敵なメッセージをありがとうございます!
清水先生、本日は本当にありがとうございました!
『知って得する、すごい法則77』(中公新書ラクレ)
https://www.chuko.co.jp/laclef/2025/02/150835.html