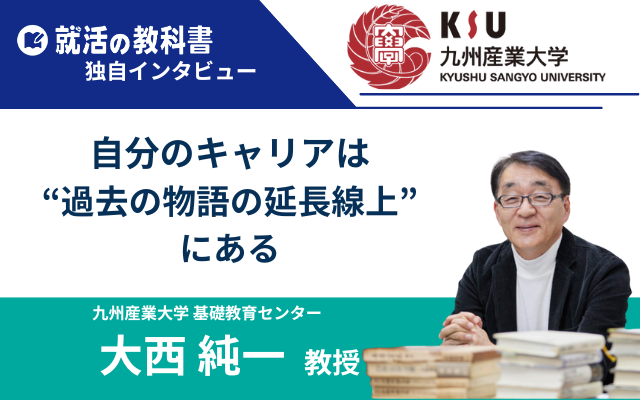「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの小林です。
本日は、九州産業大学基礎教育センター特任教授大西純一教授にお話を伺いました!
この記事を読めば、「日本の就職状況の変化」や「キャリアについての考え方」について知ることができます。
「キャリアってどう考えたらいいんだろう?」や「就職する際に大事なことってなんだろう?」などの悩みがある人は必見です!
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
大西教授、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
大西 純一 (おおにし・じゅんいち)
九州産業大学 基礎教育センター 特任教授
愛媛県西条市生まれ 1歳から横浜育ち
早稲田大学第一文学部入学後、同校を中退、学生向け情報サービス提供会社を設立。その後2社目となる日本初のPCオンラインによるアルバイト情報提供会社を設立(その後休眠)。
ニューメディア(当時)による情報提供会社に創立メンバーとして入社。
1995年頃から大学の要望に応じて、営業の傍ら全国52大学で講演・講義を行い、関西の主要大学のキャリア教育・就職指導に関わる。
2011年より九州産業大学基礎教育センター特任教授に就任。
上記の社会経験に基づいたキャリア教育を1年次、3年次に講義。就職率は過去最高を11回更新。九州トップの就職率を誇る。
目次
九州産業大学 大西純一教授にインタビュー①:20代で成功と失敗を経験 “私の授業は不安だった19歳の自分への手紙”
大学中退後、学生向け情報サービス提供会社を設立
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
大西教授は、20代で会社を設立されたとのことですが、当時のことについて教えてください!
私は大学を中退して、最初の会社を立ち上げました。ですので、他の教員とは異なる経歴かと思います。
世の中はすべて「情報」で成り立っていると考えていて、特に学生にとって大事なのは「お金を稼げる情報」です。
私は当時、早稲田の学生4万人を対象に、良質なアルバイト情報を無料で配る事業を始めました。今で言えばフリーペーパーの元祖のようなものです。
その延長で、たとえば「日曜にCM撮影があるから、学生を300人集めてください」なんて依頼も来るようになって。
当時は今のようにネットやアプリがない時代でしたから、自分たちで仕組みを工夫して何とか対応していました。(皆さんだったらどうやって集めますか?スマホ、PCなしで)
そうした活動のおかげで、最初の会社はまずまずうまくいったんです。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
ネットがない時代に、情報社会に対しての仕組みを作っていったんですね!
次に、それをパソコンで見られるようにしようと試みました。
都内に50台のPCを設置してアルバイト情報を検索できるようにしました。
日本初の試みです。が、当時はまだパソコンが一般的ではなく、多額の費用を必要とするため資金も足りずに会社を休眠しました。
その後、ちょうど困っていたところに学研から声がかかりまして、「うちでやらないか」と。それで初めてサラリーマンになったわけです。
私の場合は、サラリーマンから起業したのではなく、起業してからサラリーマンになったんですね。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
サラリーマンをしてから起業するのはよく聞いたことがありますが、その逆は珍しいですね!
10億かけたプロジェクトが失敗:「ポイントを見誤ると、どれだけお金を使っても失敗する」ことを20代で経験
ただ、そこでも10億円かけて事業を進めたんですが、結果的に失敗してしまった。
「ポイントがずれていれば、どんなにお金を使っても、情熱を注いでもうまくいかない」ということを、その時に痛感しました。
自分の貯金もゼロになりましたし、会社も解散寸前の状況にまでなりました。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
“10億かけた事業が失敗する”という経験を20代でされているんですね…
バブル前に「企業の採用ニーズを集めて、それを学生に提供する」新卒採用支援の仕事をスタート
そこからどうやって立て直すかを考えて、リクルートの事業モデルを参考にした新卒採用支援の仕事を始めました。
「企業の採用ニーズを広告として集めて、それを学生に提供する」という内容です。昔はそれを本にして配っていたんですね。
この事業がちょうどバブル前の時期でヒットしまして、最終的には億単位の利益が出るまでになりました。
私はその会社に企画として入社しましたが、現場のニーズを理解するために営業職に転身、法人営業として都内の1000社以上の会社を訪問しました。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
大きな失敗経験を乗り越えて、新しい事業で億単位の利益を出せるなんてすごいですね!
九州産業大学 大西純一教授にインタビュー②:日本の就職状況の変化・キャリア教育に携わるようになった経緯
バブル崩壊後、就職状況が悪化し「就職氷河期」に:昭和モデルの崩壊
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
日本の就職状況の変化をどのように見てこられましたか?
バブルが崩壊すると、当然ながら企業は採用を絞ります。そうなると実は困るのが大学なんです。
今では当たり前に思える就職支援ですが、昭和の時代までは大学が何もしなくても企業の方から学生を取りに来てくれていた。とくに有名大学なんて、学生が就活に苦労するなんてことはなかったんです。
でも、バブルが崩壊して、大学は「就職に強い」と打ち出して学生を集めていたのに、いざ卒業する頃には企業の採用枠が減ってきた。それが1992年ごろの話で、今で言う「就職氷河期世代」ですね。2004年ごろまでで約2,000万人いると言われています。
その後も就職状況は悪化し、就職先が見つからず、フリーターになる人が増えた。
そこでようやく国が「これはまずい」となって、キャリア教育が導入されるようになったんです。
つまり、90年代の劇的な転換によって、昭和的な「いい大学・いい会社・いい人生」のモデルがこの時点で崩壊に直面したということです。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
就職状況の悪化によってキャリア教育が導入されるようになったんですね!
1991年、世界と日本の転換点
不安定な時代であるからこそ、新卒で就職するチャンスは絶対に逃さない方がいいんです。
フリーターという選択肢もありますが、実はそれには長期的なリスクがある。
1995年に旧・日経連(今の経団連)が「雇用形態の3グループ化」という考えを提唱しています。
1つ目が「長期蓄積能力活用型」=正社員(無期雇用)
2つ目が「高度専門能力活用型」=年収1000万超クラスの専門職 これは新卒ではほぼ対象外
3つ目が「雇用柔軟型」=契約社員や派遣社員などの流動的人材
この構造が発表された背景を知らないと、「フリーターでも生きていけるから大丈夫」と思いがちなんですが、若いときは良くても、後で厳しくなるケースが多いんです。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
1995年には発表されたということは、背景としてバブル崩壊後の影響が大きいんでしょうか…?
1991年は大きな節目の年でした。日本ではバブルが崩壊し、同じ年にソ連も崩壊。
これにより冷戦構造が終わり、東西で分かれていた経済圏が融合していきました。
ドイツが東西に分断されていたように、冷戦時代は政治・経済体制の違いが国を分けていました。
そして自由と民主主義がある西側諸国のほうが、結果的に経済成長したんです。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
バブル崩壊だけでなく、ソ連とともに冷戦構造が崩壊した年だったんですね…!
時代の変化を正しく捉え、自分の立ち位置を見極めていくことが大切
冷たい水と熱いお湯が混ざるように、グローバルマーケットが広がった結果、先進国の成長は鈍り、発展途上国は賃金が上昇。
(賃金を水温ととらえると)もともとお湯側であった日本は放っておけば“ぬるま湯”になってしまう側です。
以前は日本とアジアの賃金格差が30倍〜40倍ありました。彼らは伸びしろがあるからモチベーションが高く、逆に我々は何もしなければ下がる立場。
アメリカでも中間層の没落が進み、「ラストベルト」のような現象が起きました。
この構造を理解すれば、たとえ会社を好きでも「全面的に頼る」のは危ないとわかります。
会社にぶら下がるのではなく、会社を“生かす”意識が必要なんです。
時代の変化を正しく捉え、自分の立ち位置を見極めていくことが大切だと思います。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
現代の日本:テクノロジーと働き方の過渡期
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
現代での働き方はどのようなものだと思いますか?
今やファミレスや回転寿司でも配膳ロボットが活躍していますよね。
人の手を介さない仕組みが急速に広がっていて、タブレット注文も当たり前になっています。
一度こうした流れが進むと、元には戻らない。
高級店ではまだ人が対応しますが、その分価格も高くなる。つまり、今の日本は「人が関わる仕事」と「機械・AIに置き換えられる仕事」が混在する過渡期=“汽水域”にあると感じています。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
今はまだ、完全にAI・機械化される前の段階ということを意識して考えていかなければいけませんね!
キャリア教育の始まりと大学での実践
学生によく伝えているのは「企業は本来、とてもありがたい場だ」ということです。
仕事を与えてくれて、先輩が教えてくれて、お金までもらえる。ところが「ブラック企業」という言葉が広まったことで、「企業=怖い」というイメージを持つ学生も増えてしまった。
実際には、バブル崩壊後に採用を絞った企業に対応できず、困ったのは大学側でした。
当時は就職支援のノウハウもなく、私たちは企業向けの事業から大学支援へと軸足を移していったんです。
ただ、キャリア教育はまだ手探りの段階で、法学部の教員が労働法から話したり、心理系の教員が自己分析に偏った授業をしたりと、学生の不安をあおるような内容も多かった。
「キャリア教育を自分でゼロから作り上げたい」と思っていたところ、九州産業大学から声がかかり、14年前に着任しました。
それからは就職支援を一から整備し、福岡では今、就職支援の実績としてもほぼトップクラスになっていて、ある程度その流れを作れたという自負はあります。(九州でのこの10年間の就職率伸び率はトップ)
これが、私が30年関わってきたキャリア支援の大きな流れですね。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
学生のためのキャリア教育というものを作り上げたいという思いから、大学で就職支援を始めたのですね!
九州産業大学 大西純一教授にインタビュー③:企業が学生に求めていること
「会社はいい場所だけれど、しがみつく場所ではない」
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
現代の日本で、企業は学生に対してどのようなことを求めていると考えられますか?
まず学生に伝えたいのは、「会社はいい場所だけれど、しがみつく場所ではない」ということです。
“この会社に入れば一生安心”という考え方は今の時代ではむしろ危険なんです。
会社の看板を借りながら、自分で商売をしているくらいの意識がちょうどいい。
そもそも「カンパニー」という言葉はラテン語が語源で、「パンを一緒に食べる仲間」という意味があるんです。
つまり、会社というのは本来ぶら下がるものではなく、一緒に働いて支え合う集団なんですよ。
ただ今は少子化もあって、企業の方から「ぜひうちに来てください」と声をかけてくれる時代です。
でも、ここで「自分が求められている」と勘違いしてしまうと危ない。
企業はあくまで「給料以上の働きをしてくれる人」を求めて採用するわけです。当たり前ですが、そこを履き違えてはいけません。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
よく「大企業に入れたら安泰だ」と思ってしまいますが、その考え方は現代では危険なんですね…
企業の基本原理を理解した上で社会に参加する
私は会社を作って一度は成功し、次は失敗し、さらにサラリーマンとしても働きました。
どの場面でも共通していたのは、「自分で考え、動いて、売上を立てないと会社は回らない」という現実でした。
私の考える企業の基本は、非常にシンプルです。
-
モノやサービスをつくり、売る(企画・開発・デザイン・営業・販売)
-
売った後のフォローを行い、信用を得る(生産管理・品質管理・アフターフォロー)
-
みんなが経費削減の意識を持つ(置き換え要素=契約派遣社員、AI、機械、外国人労働者など)
この3つを回すことで利益が出て、社員に給料を払ったり、新規投資もできる。これを目指していない企業は存在しません。
だからこそ、この仕組みを理解したうえで社会に参加することが大切なんです。
私たちの日常は他者のサポート(他者が会社の仕事に携わるという形で)で成り立っています。
すなわちその会社がまっとうな会社ならば、あなたの仕事は社会貢献につながっているはずです。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
ただ会社で働くだけでなく、一人ひとりが役割を持って行動することが求められるんですね!
面接とは「学生時代のキャリア」を問う場
企業の面接というのは、現実的には学生生活をどう過ごしてきたかを問う場です。
「どんな問題意識を持って何をしてきたか」という問いに対して、企業はそれをもとに、入社後に同じような姿勢で働いてくれるかを見ているんです。
それがいわゆるコア・コンピタンスであり、エントリーシートや面接、SPIなどでその再現性を確認しているというわけです。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「コア・コンピタンス」は、他社に真似できない核となる能力のことですね!
なんでガクチカとかを聞かれるんだろう?と思っていたんですが、企業は再現性を確認しているのですね!
九州産業大学 大西純一教授にインタビュー④:キャリア教育で学生気伝えていること
1年次から「就職就職」と追い立てない、キャリア形成は登山と同じ
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
キャリア教育で、授業や講演をされている中で学生に対してどのようなことを伝えていますか?
私は大学1年次のうちから「就職、就職」と追い立てるような指導はしません。
もちろんSPIのように将来必要になることは伝えますが、それ以上に学生時代にしかできない経験を重視すべきだと考えています。
中途半端にビジネスをまねても、プロの目から見ればそれは“おままごと”に過ぎません。本物の責任が伴っていないからです。
だからこそ、今しかできないことに本気で取り組んでほしいと伝えています。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
キャリア教育は「就活を意識しろ!」と言って急かすわけではないのですね!
授業の中では、キャリアをどのようなものとして伝えていますか?
私の授業では、キャリア形成を「登山」にたとえて説明しています。
登山する時、まず必要なのは地図ですよね。GPSがないとしたら、地図と天気予報とコンパスが頼りです。
でも地図を持っているだけでは意味がなく、最初に「自分が今どこにいるか」を知らなければならないんです。
この“現在地の確認”こそが、キャリアの第一歩。
だからこそ、学生にはまず自分をよく知ること、自分の価値観や行動の癖を知ることから始めてもらいたいと考えています
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
自分がどこにいるかわからないまま進んでしまっては、間違った方向ばかりに行ってしまいますもんね!
現代を理解するための「地図」としての学問
私の授業では、まず「日本がどういう時代を経てきたのか」を、4つのステージに分けて解説しています。
今の学生たちが生まれたのは第4ステージの時代。(高度消費社会)
その“当たり前”を相対化し、自分の立ち位置を理解することが重要なんです。
地図というのは一種のメタファーであり、自然科学・社会科学・人文科学のいずれも「世界を解き明かす地図」として成り立っています。
つまり、学問とは世界と自分を知るためのツールなんです。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
“学問”と聞くと「知識をひたすら入れる」というイメージでしたが、学ぶことで、自分を知ることにもつながるのですね!
議論より先に「知識」を身につける:大学での学びは企業でも活きる
1年次の授業では、議論は基本的にやらせていません。
なぜかというと、議論には“前提となる知識”が必要だからです。知識がないまま議論しても、内容のないやりとりになってしまう。
まずは物の見方、考え方の基本、社会や経済、政治などの最低限の知識を身につけた上で、はじめて立論や反論ができるようになります。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
知識をしっかりと身につけることで始めて、議論が有意義なものになるんですね!
企業においても、企画・開発から販売までの過程では、多角的な視点や論理的な議論力が必要になります。
だから大学での学び、とくに「テキスト」を通じて鍛える思考力は営業や企画でもしっかり役立つんです。それは文学部の学びでも同様です。企業現場における「役に立たせる方法」を伝えています。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
現代のAI時代において営業職は、人間ならではの生き残り戦略にもなる
1995年以降、日本の雇用は大きく変わりました。事務作業は機械化され、契約・派遣社員が増え、そして今はAI・ロボットの時代に入ってきています。
そのなかで、人間ならではの価値が発揮できるのが“営業”という仕事なんです。
営業の本質は「相手から情報を引き出し、問題を発見し、それをどう解決するか」を提案すること。
これはAIにも外国人労働者にもそう簡単に代替されません。
本学でも就職率が伸びた背景には、営業職への志望者が増えたことがあります。
成果が数字として評価される仕事だからこそ、人間ならではの生き残り戦略としても有効なんですね。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
機械化が進んでいるの中でも、「営業」という仕事は人間だからこその価値が発揮できるのですね!
九州産業大学 大西純一教授にインタビュー⑤:自分のキャリアのために行動できること
“自分の適性”は頭で考えてもわからない
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
自分のキャリアについて考える時に「自分の適性ってなんなんだろう?」と悩んでしまいがちなんですが、自分の適性ってどのように見つけたらいいんでしょうか?
人は誰しも「自分は何に向いているのか」と考えますが、実はそれでは間違えてしまうのです。
ジョハリの窓という理論をご存じですか? 自己理解には「開放領域」「盲点領域」「秘密領域」「未知領域」があります。
このうち、最も大事なのが「未知領域」。ここは自分でも他人でもわからない部分で、経験を通してでしか開いていきません。
だから、「頭でいくら考えても、本当の意味での適性には辿り着けない」のです。
つまり、いくら適性テストや自己分析をやっても、本当に自分に向いている仕事はやってみないとわからないんです。
自己分析や適性の見極めは大まかにやる必要はもちろんありますが、「適性を考えた結果やりたい仕事がないのでフリーターをしながら探す」なんて本末転倒に陥っては何にもなりません。自分の適応力を信じましょう。
社会に出てリアルな経験を積むことで、初めて「未知領域」が見えてきます。
「適性は考えるより動くことで見えてくる」ということですね。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
検索して出てくるような適性テストをしてみても、自分の本当の意味での適性はわからないんですね…
経験により「未知の領域」が開かれていく過程 :『千と千尋の神隠し』から読み解くキャリア
この点で『千と千尋の神隠し』はとても象徴的です。
千尋が少しずつ成長していくのは、まさにマズローの欲求5段階説でいうところのステップを一つひとつ登っているからです。
これは「所属の欲求」「承認」や「自己実現」の段階に近づいているということです。
千尋は最初、無力な子どもでしたが、仕事をし、誰かを助け、次第にまわりから認められるようになります。
だから顔つきも変わっていくんです。これは「承認」の結果です。
そして「ハク」の存在も象徴的です。彼は名前を忘れてしまった存在、つまり自分が何者かを見失っている。
でも千尋によって、彼は本当の自分を思い出し、美しい龍の姿に戻る。
これはまさに自己実現(アイデンティティの獲得)を意味しています。
このように、個人の「未知領域」が開いていくとき、それは他者との関わりの中で「承認される」「自分を見出す」というプロセスを通じて起きるんです。
千尋の変化は、経験によって「未知の領域」が開かれていく過程そのものです。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
『千と千尋の神隠し』をそのような視点で見たことがなかったです…!
千尋は自己成長する中で、他者にも影響を与えて自分の「未知の領域」が開かれていったんですね!
自分のキャリアは「過去の物語」の延長線上にある
もう一つ大事なのは、その変化は「実は個人だけでなく、集団や社会全体にも起こる」ものです。
たとえば、日本は戦後、焼け野原から23年で世界第2位の経済大国になりました。それは「未知の領域」を国全体で切り拓いた象徴的な出来事です。
これは皆さん自身の先祖の物語でもある。キャリアとは経歴であり、親や祖父母、さらにその上の世代にもそれぞれのキャリアがある。
私たちは、その時間の延長線上に生きているんです。
海外の大学では、自国の歴史や政治について語れないと大学生として認められません。ところが日本では、それを語れる学生が意外と少ない。
だからこそ、私はキャリアを「就職のテクニック」だけで終わらせず、「どういう時代を経て、今ここにいるのか」という文脈の中で考えてほしいと思っています。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
キャリアとは自分の将来を考えるだけではなく、過去に起こった出来事の延長上に自分がいるということを認識することが大切なのですね。
社会に出て、初めて「キャリア」が始まる
学生のうちに頭で適性を考えたって限界がある。
むしろ早く社会に出て「とりあえず働いてみる」ことで、初めて自分の「未知領域」が開いていくんです。
最初は失敗しても、「自分に合わないことがわかる」だけでも十分な収穫。
それが数年経って、自分の道を見つける土台になるんです。
キャリア形成というと、テクニックや自己分析ばかりが語られますが、“社会に参加すること”で企業の仕組みを理解し、「ぶら下がる」のではなく、自分の力で会社に貢献する。その過程で能力が磨かれていくのです。
水泳も、プールに入らなければ水の冷たさも抵抗も分からない。
キャリアも同じで、実際に社会に出てみないと分からないことが多いんです。
そして、その第一歩となる一番のチャンスが「新卒」のタイミングなのです。
私の授業は、あの千尋のような、漠然とした不安を抱えていた19歳の自分に対する未来からの激励です。「大丈夫!君にもできるよ」という。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
目先の情報や就活テクニックなどに踊らされないで、自分で行動して理解していくことが大事なんですね!
九州産業大学 大西純一教授にインタビューから学生へのメッセージ:歴史を受け継ぎ、誇りを持って歩んでほしい
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
素敵なお話をたくさんありがとうございました!
最後に、学生へのメッセージをお願いします!
今ある“当たり前”を次の世代に渡していく
どんな時代でも、真面目に生きようとすれば悩みはつきものです。
でも、今の日本は、過去に比べて多くのことが整っています。それは、私たちの先人が努力を重ねて築いてくれた成果です。
だからこそ、今ある環境を当たり前だと思わず、自分たちもその流れを受け継ぎ、より良い形で次の世代に渡していく責任があります。
歴史を忘れると、「今だけ、自分だけ、お金だけ」という価値観に陥りがちです。
けれど、本来の仕事とは、先人が築いたものをさらに良くして未来へ託す営みです。
その視点を大切に、社会に出てほしいと思います
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
日本に対して正当な誇りと自信を持ってほしい
日本は海外と比べて悲観されがちですが、実際には多くの外国人が日本人の柔軟さや粘り強さを高く評価しています。
私たちの強みは、何かを壊す力ではなく、より良く「作り変える力」。
それは長い歴史と文化の中で育まれてきた、日本人の大きな財産です。
だから皆さんには、日本に対して正当な誇りと自信を持ってほしい。私は大学で、その誇りを育む教育を行っています。
未来をつくるのは、皆さん自身です。自らの力を信じて、次の社会を築いていってください。
我々の先祖がそうしてきたように自立心と気概と矜持をもって。
 九州産業大学 大西純一教授
九州産業大学 大西純一教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
大西教授、本日は貴重なお話をありがとうございました!
私もしっかりと自分自身のキャリアに向き合っていこうと思います!