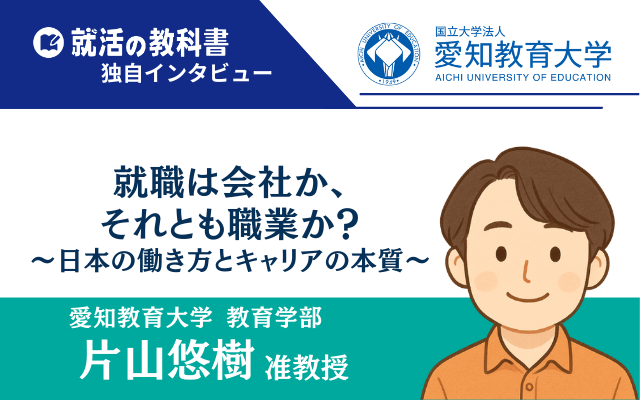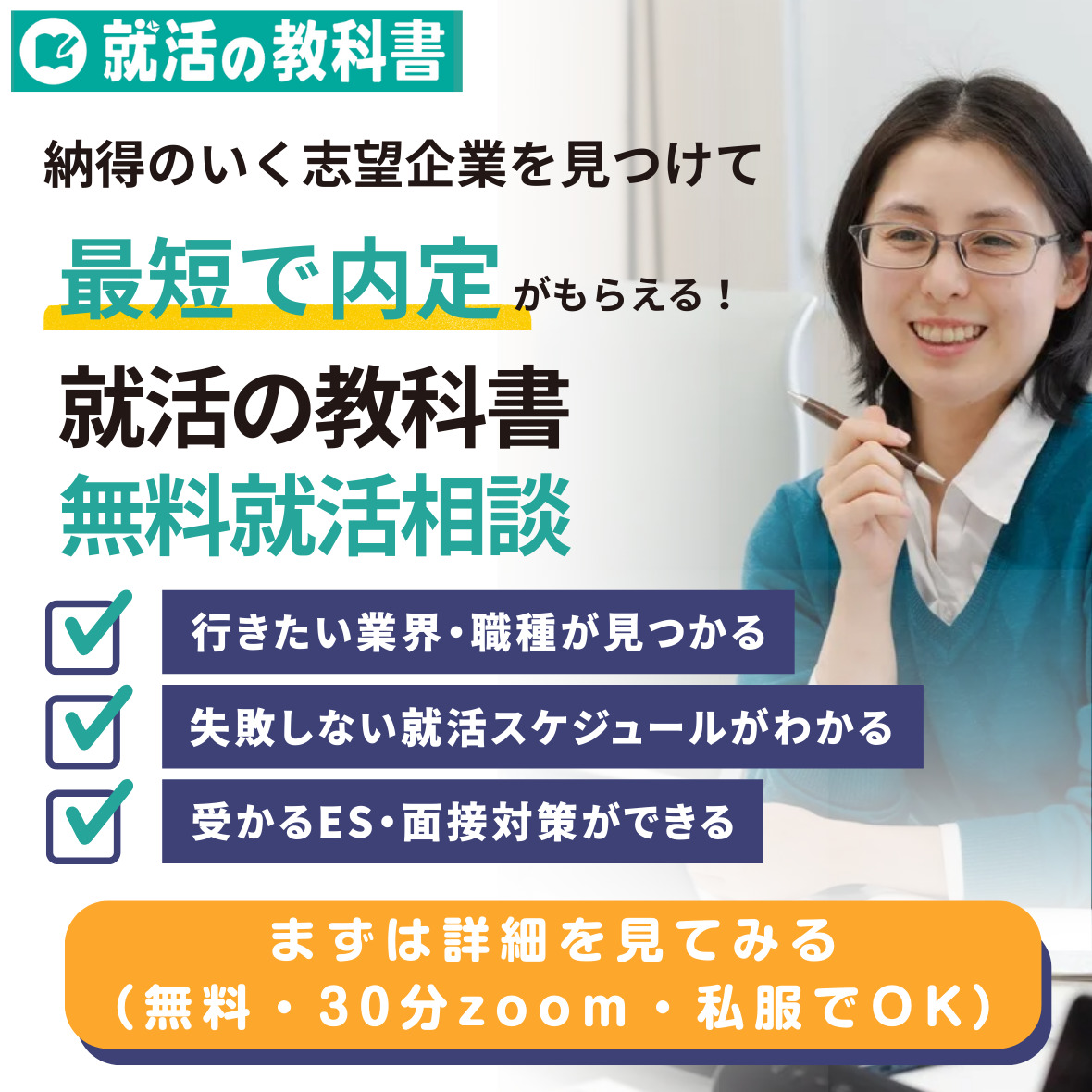「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの野口です。
本日は、愛知教育大学の片山悠樹准教授にインタビューしました。
片山先生、本日はよろしくお願いします!
よろしくお願いいたします。
 愛知教育大学 片山悠樹准教授
愛知教育大学 片山悠樹准教授

片山 悠樹(かたやま・ゆうき)
愛知教育大学 教育学部
教育社会学・職業教育論を専門とし、学校と職業をつなぐキャリア移行や教師の働き方を現場と制度の両面から検討する研究に従事。博士(人間科学)取得後、複数の科研プロジェクトを代表・分担し、政策・現場への示唆ある成果を発信。2025年には『就「社」社会で就「職」する若者たち』(編著)を刊行。
目次
愛知教育大学 片山悠樹准教授にインタビュー①:仕事とキャリアの考え方
「仕事」とは?
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
さっそくですが、片山先生がキャリア研究に携わるようになったきっかけを教えてください。
仕事って、人生の大半を占めるものですよね。でも「“仕事”って何なんだろう」と、つい考えてしまうんです。
「組織に属すること」が仕事なのか、あるいは「具体的な内容をこなすこと」が仕事なのかと、不思議と思ったのです。
大企業では営業、経理、製造と次々に異動するのが当たり前になっていますが、それって本当に自然なことなのかなと。
私自身は「仕事の内容を一貫してやりたい」という思いが強くて、それがキャリアや仕事を研究しようと思った最初の動機の一つでした。
 愛知教育大学 片山悠樹准教授
愛知教育大学 片山悠樹准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
確かに、いざ「仕事とは何か」と聞かれるとなかなか難しいですね。
就「社」社会で就「職」する
私の著書の一つに『就「社」社会で就「職」する若者たち』という少し変わったタイトルがあります。
ここでいう“就社社会”とは、“大多数が会社に就職する”という日本の慣行を指しています。
その一方で、会社ではなく“職業に就職する”人たちもいます。
典型的なのは美容師で、例えば、”お仕事は何ですか?”と尋ねると、勤め先ではなく“美容師です”と職業名で答えます。
私はそうした「職業」を中心とするキャリア形成を、専門学校の卒業生を中心に追跡してきました。
大きな企業に就職すれば、社内異動によって職務が変わるため、一貫した職業意識を持ち続けることは難しい。
日本において職業を一貫して続けられる人は、実はそれほど多くないのではないかと考えています。
 愛知教育大学 片山悠樹准教授
愛知教育大学 片山悠樹准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
企業に勤めると、部署異動などで自分の希望とは違う仕事をすることも少なくないですよね…
若者の中には「この職業をやりたい」と強い希望を持ち、そこにやりがいを感じる人も多くいます。
しかし企業に就職した場合、その希望が必ずしも実現できるわけではありません。
会社の都合によって職種が変わることもあるからです。
その点、美容師のように職業が一貫している人は、「美容師であり続ける中で、キャリアややりがいをどのように築いていくのか」が大きな関心となります。
一方で、給与や勤務実態といった課題も存在します。
美容師だけでなく、保育士なども同じ問題を抱えており、問題点を明らかにしつつ若者のキャリア形成を理解することが、私の研究テーマです。
大きく分けて、会社に就職する”就社型のキャリア”とひとつの職業を中心にキャリアを形成する”就職型のキャリア”という2つがあると言えますが、どちらが良い悪いという話ではありません。
重要なのは実態を正しく把握することだと考えています。
 愛知教育大学 片山悠樹准教授
愛知教育大学 片山悠樹准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
どちらが良い悪いではなく、それぞれの実態を理解することが重要なのですね。
私は現在、教員養成大学に所属しており、教師を目指す学生たちを教育しています。
その中でキャリア研究の延長として、近年大きな問題となっている“教師の働き方”にも関心を持ち、調査を進めています。
具体的には、長時間労働がなぜ発生してしまうのか、その原因や背景を学校現場で実態調査し、改善策を現場とともに検討することに取り組んでいます。
私にとっては教師の働き方も労働の問題であり、「働き方」「労働」というテーマで全てが繋がっていると感じています。
 愛知教育大学 片山悠樹准教授
愛知教育大学 片山悠樹准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
教師の働き方問題は度々ニュースになりますよね。教育も労働も働き方も繋がっているとお考えなのですね。
愛知教育大学 片山悠樹准教授にインタビュー②:キャリアをめぐる課題
コミュニケーション能力は個人の能力ではなく“関係性”の問題
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
研究の中で、課題に感じていることはありますか?
ここ十数年、「コミュニケーション能力を身につけましょう」と盛んに言われていますよね。
ただ、私はそれが一体何を指すのか、いつも疑問に思っています。果たして全員が身につけなければならないものなのか、あるいはそもそも“コミュニケーション能力”とは何なのか。
例えば、ビジネスの場では円滑にものごとを進める時、あるいは初めて会う人と仕事をする時に、一定のコミュニケーションのスタイルやパターンが必要になります。
一方で、気心の知れた友人と話す時、コミュニケーションのスタイルはビジネスの場よりもラフなスタイルになりますよね?
つまり、コミュニケーションは個人の能力ではなく“関係性”の問題です。
それを一律に“能力”と定義して教育や就職に組み込むことには、強い違和感を覚えています。
 愛知教育大学 片山悠樹准教授
愛知教育大学 片山悠樹准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
コミュニケーション能力というと、“誰とでも話せる能力”という印象が強かったのですが、1対1で考えると確かに関係性の問題なんですよね。
となると、コミュニケーション能力を身につけるというのは、どういうことなんでしょうか?
もし「コミュニケーション能力を身につけましょう」と言うのであれば、“どの場面で必要な能力なのか”を明確にして教育した方が良いと考えています。
以前、自動車整備士を調査したことがあるのですが、いま自動車整備士は、整備だけでなく顧客に作業内容を丁寧に説明する力が求められているそうです。
実際に整備を担当した本人が説明することで、ユーザーの安心感は増すというのが理由みたいですが、納得しますよね?
では、自動車整備士はただ話しているのかと言えば、違います。ユーザーとの関係性のなかで、整備の内容をわかりやすいかたちで話すことが求められています。つまり、コミュニケーションのスタイルは場面や文脈に埋め込まれたものなのです。
場面と文脈が具体的に示されていれば、コミュニケーション能力の重要性も理解できます。
しかし場面や文脈が曖昧なまま、「コミュ力が大事」と一括りにされると、若者は戸惑うでしょう。
実際に、必要以上に“コミュ力”を求められる圧力が強くなった結果、『自分はコミュ障だ』と自己評価する若者が増えてきたのではないかと感じています。
 愛知教育大学 片山悠樹准教授
愛知教育大学 片山悠樹准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「コミュ障」という言葉が今はもう定着してしまっていて、自信を無くしてしまう人も多いように感じますね。
性格診断・適職診断に頼りすぎない
最近でいえばMBTIなどの性格診断を、就職活動中の若者が頻繁に利用していますよね。
しかし、あのような診断で自身の能力が測れるのか、私は疑問に思います。
性格までも“能力”に変換してしまう社会の流れは、それ自体が問題ではないかと考えています。
 愛知教育大学 片山悠樹准教授
愛知教育大学 片山悠樹准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
情報やツールが多い分、自分で何が必要なのかを見極めていくことが重要ですね。
性格診断や適職診断は、あくまで一つの参考にする程度なら良いと思います。
ただ、それをもとに自分のキャリアを決めてしまうのは危ういと感じます。
 愛知教育大学 片山悠樹准教授
愛知教育大学 片山悠樹准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
最近は性格診断が流行っていますが、それに頼りきってしまうのは良くないですよね…
日本の企業では“仕事”と“能力”が結びつかない
日本では“仕事”と“能力”が結びつかない背景に、企業内での職務の扱い方があると感じています。
例えば営業で採用された人が、数年後には事務に異動することがあります。
しかし営業で必要とされる能力はプレゼン力で、一方、事務では正確な処理や書類作成の丁寧さといった異なる能力が求められます。
職務ごとに必要な能力は明確に定まっているはずです。
ところが日本の会社では、営業や事務を転々とさせられるため、“どんな能力を身につけるべきか”が曖昧になりがちです。
その結果、“コミュニケーション能力”といった抽象的な表現が氾濫したり、性格診断のようなツールに頼ってしまう。
私は、職種の範囲を明確にしない日本企業の仕組みに大きな問題があると考えています。
 愛知教育大学 片山悠樹准教授
愛知教育大学 片山悠樹准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
配属が変わることによって色々な経験を積めるといったメリットもあるのではないでしょうか?
かつての日本企業は、ジョブローテーションによって幅広い経験を積ませ、総合力を高めることで成長してきました。
しかし、それが今の若者や現代社会に合っているかといえば、必ずしもそうではないと思います。
むしろ、一つの職務を会社の中で一貫して続けられる仕組みがあっても良いのではないでしょうか。例えば営業で採用されたら、基本的には営業としてキャリアを積んでいくといった形です。
専門用語では“ジョブ型”と呼ばれますが、日本で最近使われている“ジョブ型”という言葉は、本来の意味とは異なる形で広まっていると感じています。
少なくとも従来のメンバーシップ型だけでなく、職務を軸にした働き方も考えられるべきだと思います。
 愛知教育大学 片山悠樹准教授
愛知教育大学 片山悠樹准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「一つの職務を一貫して続けられる」選択肢も選べるというのは重要なことですね!
愛知教育大学 片山悠樹准教授にインタビュー③:これからの企業の仕組みと学生への提言
就職前から「自分はどんな仕事をしたいのか」を考える意識を持つ
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「やりたい仕事がない」と職種を選ぶことができない学生は多いと思いますが、そのような学生はどうしたらいいのでしょうか?
通常の日本企業は“メンバーシップ型”なので、職務が明確に定まっていません。
しかし海外では“ジョブ型”が一般的で、採用時点で職務が決まっています。
そのため、若者は就職前から「自分はどんな仕事をしたいのか」を考えることになります。
ところが日本ではそれが曖昧なため、“就職したいランキング”には会社名ばかりが並ぶという奇妙な現象が起きています。
あれは“就職ランキング”ではなくむしろ“就社ランキング”と呼ぶべきでしょう。
若者が本当の意味で仕事を選べないのは、日本企業の仕組みに原因があるのではないかと思います。
 愛知教育大学 片山悠樹准教授
愛知教育大学 片山悠樹准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
今まで日本の就職活動にそこまで疑問を持ったことがなかったので、とても驚きました。そのような視点はなかったです…
若者がキャリアについて考えられる環境を整えるために、社会の仕組み自体を変えることが不可欠
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
学生に、キャリア教育を通してどんなことを伝えていますか?
私は若者に対して「しっかりキャリアを考えなさい」とはあまり言いません。
自分自身がそうしてこなかったこともあり、説得力がないからです。
ただし社会に対しては、若者がキャリアについて考えられるような環境を整える必要があると考えています。そのためには、会社の仕組み自体を変えることが欠かせません。
例えば、かつては転勤が当然のように行われていましたが、今の若者には“地元を離れたくない”“慣れ親しんだ地域に住み続けたい”という人が一定数います。
また、「残業をしたくない」「働く内容にこだわりたい」という声も多いです。
企業はこうした希望に柔軟に応じなければ、人材を集められなくなるでしょう。
日本の会社のあり方も少しずつ変化しており、その流れを後押しする形で、若者がキャリアについて考えやすい環境をつくることが大切だと思います。
 愛知教育大学 片山悠樹准教授
愛知教育大学 片山悠樹准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
社会が変化している中で、学生にあれこれ言うのではなく、“社会の仕組み自体”を変えることが求められるのですね…!
法律だけでなく、私たち一人ひとりの意識改革も必要
社会の仕組みそのものを変えなければ、若い世代はついてきません。
ですから私のような年長者が一方的に考えるのではなく、若者の意見をしっかり聞き、彼ら/彼女らが積極的に意見を発信できる環境をつくる必要があります。
ただ現実には、上司が残っていると帰りにくいなど、職場にはいまだに古い慣習が残っているといったことも聞くことはあります。
本来であれば、自分の仕事が終わったら帰ってよいはずです。こうした風習も見直していかなければなりません。
また、残業問題や教師の働き方なども、社会全体で議論し合意形成を進めるべきです。
例えば、私が取り組んでいる教師の働き方の改善もそうです。社会が教師に過剰な期待を寄せても、限界がありますし、保護者や地域も含め“働き方の線引き”を共有することが大切です。
さらに、子育てをしながら働ける環境づくりも、まだ十分とはいえません。
こうした課題は法律だけでなく、私たち一人ひとりの意識改革も必要だと思います。
 愛知教育大学 片山悠樹准教授
愛知教育大学 片山悠樹准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
キャリア教育というと個人のマインドセットに注目してしまうイメージでしたが、社会の流れを踏まえ、会社や個人の意識を変えていくことが大切なのですね!
愛知教育大学 片山悠樹准教授から学生へのメッセージ:「必要以上に自分を責めなくていい」
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
片山先生、ありがとうございました。
最後に就活生に向けてメッセージをお願いします!
就活生に伝えたいのは、「あまり自分を追い詰めないでほしい」ということです。
やりたいことや『こうしなければならない』という思い込みで自分の首を絞める必要はありません。
就職して合わないと感じたら、辞めて次を探せばよいのです。
“適職”という考え方に惑わされすぎるのも危険です。
私自身、就職氷河期を経験し、当時多くの同級生が就活で苦しむ姿を見ました。
うまくいかないと、人は「自分が悪いのでは」と考えがちですが、実際には環境の要因が大きいのです。
だからこそ、『必要以上に自分を責めなくていい』というメッセージを、常に若者へ伝え続けたいと思っています。
 愛知教育大学 片山悠樹准教授
愛知教育大学 片山悠樹准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
片山先生、本日は素敵なお話をありがとうございました!