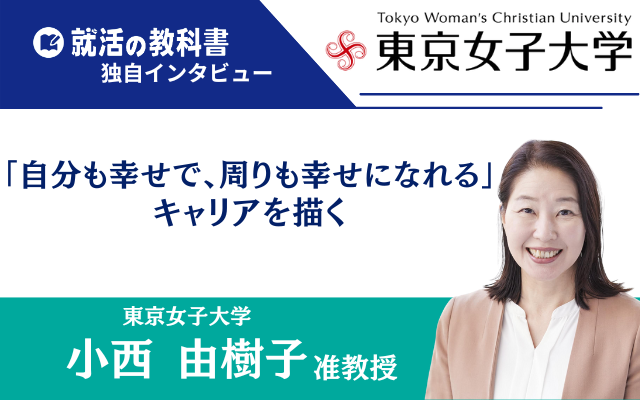「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの小林です。
本日は、東京女子大学の小西由樹子准教授にお話を伺いました!
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
小西先生、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
小西 由樹子 (こにし・ゆきこ)
東京女子大学 現代教養学部 経済経営学科
エンパワーメント・センター長 准教授
大阪大学経済学部卒業、早稲田大学大学院経営管理研究科(MBA)修了。
みずほ銀行勤務を経て、育児による一時離職後、子連れ留学や転職を経て大学教員に。
目次
東京女子大学 小西由樹子准教授にインタビュー①:挑戦と学びで広がったキャリア ― 銀行勤務から海外留学、そして教育者へ
サラリーマン生活の中で感じたもどかしさ
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
さっそくですが、小西先生がどのようにキャリアを歩まれてきたのかを知りたいです!
大学時代はどのようなことを学ばれていましたか?
大学では経済学を学んでいました。その中で「金融って面白い」と思ったんです。
お金の流れを追うことで企業の中身が見えてくるのがすごく面白くて、商業銀行に行きたいなと。それで、みずほ銀行に総合職で入社しました。
最初は京都支店で営業や窓口業務をして、そのあと東京本社の調査部に移りました。
GDPの予測や金利の動きを分析していましたね。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
お金の流れを追うお仕事というのはかっこいいですね!
その後、転職されているということですが、何かきっかけはありましたか?
子育てとの両立がだんだん難しくなり、一度退職しました。
サラリーマン生活って安定していていいなと思って入社したんですけど、やっぱり上司の承認なしに自分のアイデアを形にできないもどかしさもあって。じゃあ起業してみようかなと思ったんですね。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
40歳で留学を決意:留学による価値観の変化
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
起業は退職後すぐに始められたのですか?
いえ、まずは早稲田大学のビジネススクールに行って学びました。
でも実際にやってみると、「サラリーマン時代の安定がありがたかったな」と思うことも多かったです。
起業は24時間365日働く覚悟が必要で、ビジネスを実現するのは本当に難しいと感じました。
また、ビジネススクールで海外から来ている留学生と接する機会があって、その経歴に衝撃を受けました。
自国のインターナショナルスクールに行って、カナダやアメリカの大学に進み、大学院は日本…みたいな、本当にグローバルな教育環境で育っているんです。
私は大阪から東京に出ただけで大きな挑戦だと思っていたので、その経歴にすごく刺激を受けて、40歳で留学を決めました。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
そこで留学に行こう!という行動力が素晴らしいです!
留学での経験はどうでしたか?
やっぱり面白かったですね。今まで自分が正しいと思っていた価値観が、実は日本独自のものだったと気づきました。
日本にいても気づけることかもしれませんが、私の場合、まずビジネススクールに入ったときに、『大企業に勤めていれば世の中のことはだいたい分かっている』と思っていたんです。みずほ銀行に勤めていたので、なんとなくそういう自信もあって。
でも実際にビジネススクールで日本の社会人と話してみると、『あれ、自分は何も分かってなかったな』って思う場面がたくさんありました。そしてさらに海外に行くと、『本当に自分は何も分かってなかったな』という感覚になりました。
もともと好奇心旺盛でフットワークも軽い方なんですが、いろんな場所での体験は本当に面白い。
やっぱり自分で飛び込んで経験してみることの大切さを強く感じました。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
実際に飛び込んで経験されることで価値観が大きく変わったのですね!
価値観の変化の中で印象的だったものは何ですか?
やっぱり事業の進め方も違いますし、考え方そのものが変わる経験がありました。特に印象的だったのは二つですね。
一つ目は、『失敗が失敗じゃない』という感覚です。
例えば日本だと、生徒会に立候補して落ちると、『ああ、手を挙げなければよかったな』とか、『何回も落ちている人は格好悪い』という空気があったりしますよね。だから勝てそうな時だけ手を挙げるようになる。
でも、アメリカだと違っていて、落ちても『やる気がある』と評価されるんです。次に別のポジションが空いたとき、『前回立候補してくれたよね、やってみない?』と声をかけてもらえる。だから、声をあげないと損なんですよ。この考え方はすごく新鮮でした。
二つ目は、物事の教え方の違いです。
例えばスイミング。日本だとまずフォームを徹底的にきれいにしてから、タイムを競いますよね。
でもアメリカ(私がいたカリフォルニア)では、『とりあえず泳げ』なんです。めちゃくちゃなフォームでもいいから、泳ぎながら形を作っていく。これも衝撃でした。「やり方は一つじゃない」と。
こういう小さな気づきの積み重ねで、自分の価値観が大きく変わっていきましたね。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
日本だと、挑戦して失敗しまうことをマイナスに捉えてしまいがちですが、アメリカでは挑戦したこと自体が評価されるというのは大きな違いですね!
大学教員として学生に「自分とは違う世界があることを肌で感じてほしい」
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
帰国後は、どのようなキャリアを進みましたか?
カリフォルニアに約2年間滞在して、帰国子女と接しながら『グローバルリーダーってどうやって育つんだろう』という関心を持ち、それを研究テーマにしました。
早稲田大学大学院商学研究科博士課程に進み、博士論文を書きながら助手を務めました。
その後は名古屋大学で5年間、学生向けの起業家教育や大学発スタートアップ支援を担当しました。
2024年度からは東京女子大学の経済経営学科で、経営や人的資源管理、起業家教育を女子学生に教えています。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
留学での経験から、海外での教育スタイルなどを取り入れているのでしょうか?
私はアメリカの大学院しか経験していないですが、海外の教育スタイルや雰囲気はぜひ取り入れたいと思っています。
特に、上下関係が強くない“フラットな関係”ですね。そういう環境の中で学生と向き合いたいです。
それからキャリア教育の面でも、できるだけ学生が『自分の価値観は狭いかもしれない』と気づける場を作りたい。
スタディツアーやサマーキャンプに連れて行ったり、海外の現場を体験してもらったり――そういう機会を通して、自分とは違う世界があることを肌で感じてほしいと思っています。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
ご自身の経験から得たことを学生にも伝えたいという思いで教育に取り組んでいらっしゃるのですね!
東京女子大学 小西由樹子准教授にインタビュー②:キャリア教育が導く、個人の成長と社会の発展
時代の変化に応じた企業の視点を理解する
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
大学でのキャリア教育の授業では、どのようなことを行なっていますか?
今の時代に合った福利厚生や企業の戦略、人材育成の仕組みなど、企業の視点を理解することも大切だと考えています。
昔は社宅があれば喜んでたんですけど、今は「みんなで社宅に入るのはちょっと嫌だ」という人が多くて、リモート勤務や借り上げ住宅の方が好まれるなど、どんどん変化しています。
だから学生には、企業のこうした視点を学ぶことが大事だと思って教えています。
就職活動に一番関心があると思いますが、会社の経営や人事の戦略を理解して、適応できる力をつけることには大きな価値があります。
また、広告やウェブサイトだけではわからないことも多いので、有価証券報告書などを見て『この会社は本当に何をしたいのか』と考える力、企業を見る目も養うように指導しています。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
自分に合うところを探すのではなく、まず与えられた仕事で実績を上げる
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
キャリア教育というとマインドセットがメインのイメージだったんですが、実践的なことに取り組まれているのですね…!
正直、マインドセット系の話ってあんまり好きじゃないんです。
もちろん大事ではあるんですけど、経験や実績を積むとマインドセットも自然と変わるものだと思っていて、最初から『気持ちを変えましょう』っていうのは違うかなと。
特にキャリアの話になると、最近は『自分の適性を知って、自分に合う企業を探そう』みたいなアプローチが多いんですけど、まだ20歳ぐらいですよね。
小学校卒業して10年くらいしか経っていない段階で、自分に合うものを見つけようっていうのは少し無理があると思うんです。
それよりも、まずは『やりたいこと』を見つけることの方が大事だと思います。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
就職活動で「適性診断から始めよう!」という流れが一般的になってきていますが、確かにそれをしてみても自分に合うものは実際にはわからないですよね…
経験を積むことでだんだん分かってくると思いますけど、知識や能力がついて初めて、自分が何に向いているか分かるわけです。
小さい頃から『これに向いてるかな』なんて考えても、正直あまり意味はないと思います。
だから私が学生たちに伝えているのは、『自分に合うところを探すんじゃなくて、まずは自分のできること、与えられた仕事で実績を上げなさい』ということです。
能力がついてくると、裁量も増えて、やりたい仕事もできる仕事も広がっていきます。その後で自分の適性は考えればいい。
マインドセットももちろん大事ですが、まずは能力をつけることが先だと思っています。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
実際にやってみないとわからないことばかりの中で自分の適性を頭で考えるよりも、まずやってみて能力をつけて初めて自分の適性がわかるんですね!
自分の市場価値を高めることで、初めてやりたいことを選べる
起業家教育でもよく言うのですが、ビジネスチャンスを見つけるには「やりたいこと」「できること」「社会が求めていること」、この三つが揃わないと難しいんですよ。
やりたくないことをやってもつらいし、できないことはできない。逆にやりたいことだけやっても、それを求める人や会社がいなければ成立しないんです。
だからまずは、自分の能力を高めて、市場価値をつけることが大事です。
それができて初めて、やりたいことを選ぶ立場になれる。つまり「自分をマーケタブル(Marketable)にしてから選択しなさい」ということですね。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
能力や経験がないままでは、やりたいことを選ぶことすらできないんですね…!
リーダーシップの基礎:自分の価値を信じて実績とともに示す
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
起業・リーダーシップ育成の授業では学生にどんなことを伝えていますか?
起業家教育は、単にビジネスを立ち上げる訓練ではなく、リーダーシップを実践的に学ぶ場だと思います。
例えば私も全天候型自転車を作ろうとしましたが、市場がないと気づいたり、人を巻き込む力が必要だと実感しました。
結局、起業でもビジネスコンテストでも、一人では進められず、周りの人を動かすリーダーシップが不可欠なんです。
リーダーシップやスキルは座学だけではなく、実践で身についていくものだと思います。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
リーダーシップも実践していく中で、身についていくものなのですね。
周りを巻き込んでいくためにはどのようなことが大切なのでしょうか?
結局、自分が動かないことには誰も応援してくれません。
リーダーシップを身につけるには、まずは動くこと。あるいはロールモデルを真似ることが大切です。
アイドルやスポーツ選手でもいいので、発言や立ち振る舞いを観察し、自分ならどうするかを想像してみる。そうして行動や発言を積み重ねていくうちに、自信も育っていきます。
就活中は不安で自信を失いがちですが、企業は自信のない人を採用しません。
だからこそ、自分の価値を実績とともに具体的に示すこと。それが就活の成功につながり、リーダーシップの基礎にもなると思います。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
ロールモデルを真似て動いてみると、いつの間にかそれが自分の実績となって自信も育つのですね!
“自己実現をしながら世の中を良くする”というキャリアを築いてほしい
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
大学でのキャリア教育を通して、学生には卒業時にはどのような姿になっていて欲しいですか?
これまで“実績を”という話をしてきましたけれども、結局のところ、卒業後は“自己実現をしながら世の中を良くする”というキャリアを築いてほしいと思います。
自分も幸せで、社会も幸せになる。そんなキャリアを焦らずに、一歩一歩積み上げていってほしいですね。
それから、夢は大きく持っていただきたいと思います。
最近は学生の中に自信をなくしている方が多いように感じるのですが、まずは自分が幸せになること、そして周囲の人も幸せにすること。
会社だけではなく、社外、日本だけでなく世界へと、少しずつスコープを広げてほしいです。
若い世代の皆さんには、ぜひ世の中を良くしていく存在になっていただきたいと願っています。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
自分がやりたいことを突き詰めて行った結果、周りの人も幸せになっていたらとても素敵なことですね!
東京女子大学 小西由樹子准教授にインタビュー③:エンパワーメント・センター設立の背景
「職業としてのキャリア形成」の取り組み
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
小西先生は東京女子大学のエンパワーメント・センターのセンター長を務められてるそうですが、設立の背景や目的について教えてください!
東京女子大学エンパワーメントセンターは、在学中はキャリアセンター、卒業後はセンターがサポートするという形で「ライフキャリア支援」を行ってきました。
2024年度からは卒業生に加え、一般の社会人にも対象を広げ、特に「職業としてのキャリア形成」を重視して取り組んでいます。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
在学生だけでなく、卒業生のサポートもされているんですね!
働くことは、経済的自立を通じて人生の選択肢を広げる重要な要素です。
病気や家庭の事情で一時的にキャリアを中断することがあっても、自らの意思で働き続ける力を持つことが大切です。
キャリア教育の観点からも、学生の段階で「働き続ける意義」を理解し、将来のライフキャリアを主体的にデザインできる力を育んでほしいと考えています。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
ジェンダー教育とキャリアの壁
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「働き続ける意義」というのは、女性は特に結婚・出産などのライフイベントに左右されやすいという点からも重要なのでしょうか?
学生時代は「女性だから」という扱いにピンとこない人も多く、「女性リーダー育成」といった枠組みに抵抗を感じる場合もあります。
しかし、社会に出ると“善意のバイアス”が現れます。
例えば、出張や海外赴任で危険地域を避けさせられたり、厳しい交渉業務から外されたりと、女性が守られる形で経験を積む機会が制限されることが少なくありません。
こうした配慮は悪意ではなくても、結果的に男性との間で経験値の差が広がり、それが賃金格差にもつながります。すべての女性が困難な仕事を避けたいわけではなく、挑戦を望む人も多いはずです。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
女性だからと善意で配慮しているつもりが、挑戦の機会を制限されることになってしまっているのですね…
多くの女性は20代~30代の間、結婚や出産の可能性を意識しながらキャリアを考えています。
そのため、家庭と仕事の両立を意識した働き方を選ぶ傾向があり、男性とはキャリア観が異なる場合があります。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
昇進や役職なしのキャリアを続けることは、やりがいや達成感の面で影響
一方で、昇進や役職がないキャリアを続けることは、やりがいや達成感の面で影響があります。
周囲がどんどん前進していく中で、自分だけ同じ仕事と責任にとどまっていると、達成感やモチベーションを失いやすくなるという現象もあると指摘しています。
学校に例えると分かりやすいかもしれません。
周りがどんどん進級していく中で、自分だけずっと1年生を繰り返しているような状態になるわけです。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
最近は「責任が増えるだけだから昇進したくない」と思う人が増えていると聞きますが、昇進しないとモチベーションが低下してしますのですね。
自分の能力が発揮できない状態で働くことになり、モチベーションが下がり「必要以上の仕事はしない」といった態度につながることがあります(いわゆる「静かな退職」)。
こうした状況は個人としては問題ないかもしれませんが、チーム全体の士気や会社の競争力に影響します。
だからこそ、キャリアを描くなら「自分も幸せで、周りも幸せにする」ような仕事を選んでほしいと思うんです。
せっかく働くなら、誰かを幸せにできる仕事をしてもらいたいなと。
学生に一番伝えたいのはやっぱり、「自分の可能性を自分で狭めないでほしい」ということですね。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
私も正直、「昇進しなくてもいいかな」と思っていたんですが、「“自分だけそのまま”の状態でいたくはない」と思いました!
そう思ったら、どんどん昇進してやりがいや達成感を感じていきたいです!
自分の市場価値を高め、次のステップに進める力をつける
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
男女平等なキャリアが求められているような時代の中で、大切な視点はありますか?
今は男女問わず、1〜2年で仕事を辞める人も増えていますけれども、大事なのは「市場価値を高めておくこと」だと思うんです。
転職市場も発達していますし、人手不足もあるので、力をつけておけば次のステップに進めるんですよね。
育児や健康などの事情で仕事を休む時期があってもいいんです。
ただ、その後また戻れる力を持っておくことが本当に大切だと思います。
私の世代では専業主婦も多かったですが、経済的に自立していないことで、自分の望む人生を選べないケースも見てきました。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
もし、今までやっていたことが途切れることになってしまっても、また別の生き方を選べるような道を作っておくことも重要なのでしょうか?
自分の人生だけでなく、パートナーの人生のためにも、男女にかかわらず稼ぐ力を持っておくことが必要だと思います。
例えば、夫が36歳で大企業を辞めて独立したいと言ったとき、私は「いいんじゃない、一度きりの人生だから」と背中を押しました。自分も働いていたので、最低限の生活は守れると考えられたからです。
経済的に支え合える基盤があったからこそ選択できた。
結果として夫は独立して成功し、感謝もしてくれました。今は転職や独立が当たり前の時代ですから、互いに『やってみたらいい』と言える関係を築くことが、お互いの人生において大きな支えになると思います。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
お互いにしっかりとした基盤があるからこそ、支え合える素敵な関係ですね!
東京女子大学 小西由樹子准教授から就活生へのメッセージ:「就活は“自分を試す場”として楽しんで欲しい」
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
素敵なお話をたくさんありがとうございました!
最後に、就活生へのメッセージをお願いします!
やっぱり自分の可能性を自分で狭めないでほしいと思います。
「大学がここだから」とか「ガクチカが足りないから」とかで、自信をなくしてしまう人も多いですけど、自信のない人は選ばれにくいんですよ。
だから、自分なりに頑張ってきたことを誇りに思って、堂々と就活に臨んでほしいんです。
就活って短期間で一気に決めないといけないから希望企業が決められない人もいると思います。そんな時も内定をもらってから考えればいいんです。
それに、就活はテストの点数で決まる大学受験とは違って、正解のない戦いなんですよね。
会社との相性や採用枠などの事情で選ばれないこともある。でもそれは“自分がダメだから”じゃなくて、条件が合わなかっただけなんです。
だからこそ、自信を持って、自分を試す場だと思って楽しんでやってほしいと思います。
 小西由樹子 准教授
小西由樹子 准教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
先生のお話を聞いて、私も前向きに就活に取り組んでいこうと思えました!
小西先生、本日は貴重なお話をありがとうございました!