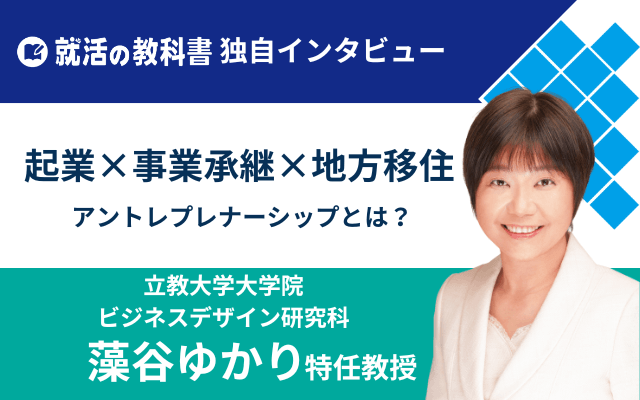「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの野口です。
今回は、立教ビジネススクール(立教大学大学院ビジネスデザイン研究科)の特任教授である藻谷ゆかり先生にインタビューしました。
藻谷先生、本日はよろしくお願いします!
よろしくお願いいたします。
 藻谷ゆかり先生
藻谷ゆかり先生

藻谷 ゆかり(もたに・ゆかり)
立教ビジネススクール 特任教授
1986年3月に東京大学経済学部を卒業し、日興證券(現SMBC日興証券)に総合職として入社。MBA取得を志し、ハーバード・ビジネス・スクールに留学。帰国後は複数の外資系企業の経理職を経て、1997年にインド紅茶の輸入・ネット通販会社を起業。2002年に長野県に移住。起業家として地域に根ざしたビジネスを継続する一方、2016年からは昭和女子大学で客員教授。2024年4月からは立教ビジネススクールの特任教授に就任。実務家教員として「アントレプレナーシップ」「地域イノベーションデザイン」など起業や地域活性化に関する授業を担当している。
目次
立教ビジネススクール藻谷ゆかり特任教授にインタビュー①アントレプレナーシップとは
起業=スタートアップだけではない
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
さっそくですが、藻谷先生はアントレプレナーシップの授業を担当されていますよね。起業の定義について、受講者にどのように伝えていらっしゃいますか。
起業と聞くと、世界を変えるようなスタートアップを思い浮かべがちですが、実はもっと多様な形があります。
たとえば私自身が行ったような、小さな会社をつくって地道に継続する「スモールビジネス」も起業の一形態です。また雇われるのではなく、独立して自分のペースで働くというフリーランスも起業の一形態だと思います。
 藻谷ゆかり先生
藻谷ゆかり先生
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「新規のプラットフォームを構築しました」や、「〇〇億円の資金調達を得ました」などの話をよく聞きますが、それだけが起業やアントレプレナーシップではないのですね。
人口が減少している今の日本において特に大切なのが「事業承継」です。実家が豆腐屋さんであれば、それを継ぐこともイノベーションの一歩になります。また、第三者として事業承継を行う例もあります。地方の旅館や食品会社など、後継者不足で廃業寸前の企業を引き継ぐのも起業のひとつです。
農業であろうと、豆腐屋さんであろうと、日本酒の酒造であろうと、すべての事業において若い世代が次の世代として、今の時代に合ったイノベーションを起こしていくことが起業であり、アントレプレナーシップだと思います。
 藻谷ゆかり先生
藻谷ゆかり先生
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
後継者不足が日本の課題だと思いますが、そういった方から事業を譲り受けることも起業になるのですね。
「イントレプレナー」──会社の中でも起業はできる
会社に勤めながら新規事業を立ち上げる「イントレプレナー」も注目すべきスタイルです。社内でビジネスプランを提案したり、新規事業部に関わったりすることも、起業と同様の意義があります。こうした取り組みも、社内でアントレプレナーシップを発揮することになりますので、広い意味でのアントレプレナーシップと言えると思います。
このように起業という言葉の意味を広く捉えると、必ずしも自分で独立して会社を持ち、何億円も資金を調達して事業を拡大するという典型的なスタートアップだけが起業ではないということを、理解していただけたらと思います。
 藻谷ゆかり先生
藻谷ゆかり先生
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
社内で新規事業に関わることもアントレプレナーシップの一部なのですね。
1から1000に。映画『ファウンダー』から学ぶ
私は「1を100、1000に育てる」ことも大切だと伝えています。
授業でも紹介している映画『ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ』は、まさにその象徴です。世界的なハンバーガーチェーンのマクドナルドがどのように大きくなっていったかを、実話に基づいて描いた映画です。
マクドナルドは、カリフォルニアの田舎町でマクドナルド兄弟が営んでいた人気のあるハンバーガーショップでした。そこにシカゴ出身のレイ・クロックという人物がやって来て、フランチャイズ権を取得し全米に展開していきました。そして最終的には、マクドナルド兄弟に200万ドルを支払い、すべての権利を買い取りました。
マクドナルドというファーストフードのシステムを作ったのはマクドナルド兄弟であり、世界中にマクドナルドを広めていったのはレイ・クロックです。このどちらもアントレプレナーシップだと私は考えています。
そう考えると、会社を買収して大きくしていくことも、アントレプレナーシップの一つです。実際に0から1を生み出すのは非常に難しいため、変化を加えてイノベーションを起こしていくことも、アントレプレナーシップの実践になります。
 藻谷ゆかり先生
藻谷ゆかり先生
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
マクドナルドはレイ・クロックさんがフランチャイズにしたことで広まったのですね。そういった取り組みもアントレプレナーシップなのですね。
事業承継=GDPを維持する
私自身、起業して地方移住し、そしてその事業を譲渡したのですが、地方には、本当に良いビジネスが存在しています。旅館や食品会社だけでなく、メーカーなどでも、そこにしかない技術を持っているにもかかわらず、後継者がいないという問題があります。
一般的にアントレプレナーシップというと、スタートアップ型の起業、つまり「世界を大きく変える」といった志向が重視されがちです。そうしたスタートアップ型は、GDPを増やす方向に貢献します。
私がもう一つ強く主張しているのは、事業承継型のアントレプレナーシップです。これは、GDPを維持する点に価値があります。すでにあるビジネスが続いていたにもかかわらず、後継者がいないという理由だけでやめることになってしまうのは、非常にもったいない。そうなると、GDP自体も下がってしまいます。
たとえば旅館の場合だと評判も良く、お客さんも来ているのに、後継者がいないという理由で廃業してしまうケースがあります。若い世代が第三者事業承継をして、予約システムを変更したり、運営のやり方を少し変えるだけで、利用者が増えたり、収益性が上がったりすることもあります。こうした取り組みも、アントレプレナーシップの一つとして捉えています。
 藻谷ゆかり先生
藻谷ゆかり先生
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
継ぐ人がおらず廃業してしまうことは、本当にもったいないですね。事業承継型のアントレプレナーシップはGDPを維持できるのですね。
立教ビジネススクール藻谷ゆかり特任教授にインタビュー②越境学習
“欠点を長所に変える”発想
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
先生の著書『山奥ビジネス』は、どんなコンセプトなのでしょうか?
「条件不利」と思われがちな山奥でも、欠点を長所に変えるという発想と工夫次第で人を惹きつけるビジネスが可能です。
そこで地方で素晴らしいビジネスを展開している事例を取材しました。たとえば、北海道の山奥で開業したパン屋さんは「ここではクマしか買いに来ない」と地元の人に言われながらも、新聞社やテレビ局などに取り上げられ繁盛しました。
大切なのは、“欠点を長所に転換する”という視点。これは、多くのビジネスにも通じる考え方です。
 藻谷ゆかり先生
藻谷ゆかり先生
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
欠点を長所に変換する考え方は就活でも、ビジネスにも役立ちますね。
例えば旅館であれば、「うちはテレビも時計も置いていません」といった、一見すると欠点のような点であっても、それによって静かな滞在ができるという価値につながることもあります。
伝え方次第で、あらゆるプロダクトやサービスにも通じることだと思います。お客様にご納得いただけるような十分な説明や背景となる物語があれば、それは魅力として受け取ってもらえるのではないかと思います。
私自身の経験からも言えますが、インターネットさえあれば、どこにいてもビジネスは可能です。そういった意味では、本来は東京に集中しなくても成り立つはずなのですが、現実には東京への一極集中がむしろ進んでいる状況です。
 藻谷ゆかり先生
藻谷ゆかり先生
越境学習と地方移住──地方こそがフロンティア
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
東京で就職したいという学生も多いですが、IターンやUターンについてはどうお考えですか?
私が著書『六方よし経営』の中で主張したのが「越境学習」という考え方です。地方に住んでいると、東京の大学に進学したい、東京で働いてみたいという気持ちは、誰にでもあると思います。
自分の今いる居心地の良い場所、いわゆるコンフォートゾーンから一歩出て、チャレンジするという気持ちはとても大切です。進学や就職で都市部に出てみるというのも、非常に意味のある挑戦だと思います。
実際、20代でしばらく都市で働いてみると、自分の育った場所の良さに気づくことがあります。家業を持つ家庭で育った人の中には、子どもの頃から親の苦労する姿を見て、「家業だけは継ぎたくない」と感じていた人も少なくありません。しかし、進学や就職で一度家業から離れてみると、「家業にも良さがある」「自分の故郷にも魅力がある」と気づくことがあります。
そうしたとき、戻ってくるという選択肢もあってよいと思います。地方は暮らしやすく、不動産も安く、さまざまな面で環境が整っています。
さらにビジネスの観点から見ても、地方には伸びしろが大きく残されています。地方こそが成長のフロンティアであるというのが、私が『山奥ビジネス』や『六方よし経営』の中で主張してきたことです。
 藻谷ゆかり先生
藻谷ゆかり先生
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
なかなか一歩を踏み出す勇気がない学生や社会人はどうしたら良いのでしょうか。
現在は、都市部と地方の「関係人口」を増やそうという取り組みも活発に行われています。たとえば、能登半島地震が起きた能登半島などに観光で訪れてみて、現地の様子を自分の目で見てみる。あるいは、その周辺の自治体に足を運んで、「自分はこんな場所に住めるだろうか」と考えてみる。そういった形で、可能性を探っていくこともできると思います。
また、就職してからでも「地域おこし協力隊」のような制度を活用すれば、一定の給与を得ながら3年間ほど地方でチャレンジすることも可能です。そういった制度に挑戦してみるというのも、自分の可能性を広げる手段のひとつになります。
 藻谷ゆかり先生
藻谷ゆかり先生
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
地域おこし協力隊という制度もあるのですね。自分の可能性が広がりそうです。
“Expand your horizons”
私が授業でよく伝えているのは、“Expand your horizons”――「あなたの地平線を広げましょう」ということです。
留学していた時、同級生から「あなたは車を持ってる?」と聞かれて、「持っていない」と答えたら、“If you have a car, you can expand your horizons” と言われました。「車を持ったら、あなたの地平線を広げられる」ということです。
“Expand your horizons”は、「視野を広げよう」という意味の慣用句だったようですが、当時の私はそのまま文字通りに受け取って、「車を持ったら本当に地平線が広がるんだ」と思い、その言葉が強く印象に残りました。
自分が今やっていることが一種のルーティンになっていると感じたら、少し旅行に出てみたり、転勤のチャンスがあれば思い切って挑戦してみることがおすすめです。少しだけ冒険してみることが、次のチャンスをもたらすかもしれません。
 藻谷ゆかり先生
藻谷ゆかり先生
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
視野を広げてみることが良いのですね。少し冒険してみようと思いました。
立教ビジネススクール藻谷ゆかり特任教授にインタビュー③就活生へのメッセージ「自分探しより居場所探しを」
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
藻谷先生は、どのようなキャリアを歩まれてきたのでしょうか。
私は東大を卒業した後、国家公務員になりたいと考えていましたが、試験に落ちてしまいました。その後、民間の企業に勤めることができましたが、証券会社に勤めるとは思っていませんでした。
結果としてその会社に入り、さまざまな経験をさせていただきました。社費留学の機会もありました。今、就職活動をしている学生の皆さんも、自分がやってみたいことや希望する業種があると思います。たとえそれが叶わなくても、自分を雇用してくれる会社があるということは、受け入れてくれる体制があるということです。
呼ばれたところに行くような就職の形でも、幸せになれる可能性は十分にあるということを、私の経験から伝えたいと思います。
私は還暦を過ぎましたが、「自分とは何か」と自分探しをするよりも、自分が居心地よく過ごせる「居場所探し」をする方が良いと感じています。
「この会社ならうまくやっていけそうだ」という予感があるところに進むことが、就職活動では大切だと思います。
 藻谷ゆかり先生
藻谷ゆかり先生
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
予想外の出来事もあったのですね。
最後に就活生にメッセージをお願いします。
就職先を検討するにあたり、客観的な情報も大事ですが、ご自身の主観や直観も大事にして下さい。今の時代は情報が溢れていて、自分が何に向いているか迷うことも多いと思います。実は私自身も、自分のことが完全にわかっているわけではありません。
「自分探し」をしてもうまくいかないことが多いのです。それよりも、「ここなら楽しんでやっていけそうだな」と感じるような、ちょっとした勘や直感のようなものを大切にするほうが良いと思います。そうしたご縁に耳を傾けることも大切です。
そして、必ずしも最初から希望の会社に入れなくても、仕事をしているうちに次のチャンスが必ずやってきます。ですから、自分の理想を「これが正解だ」と決めつけすぎず、まずは就職してみて、その中で起こることを少し客観的に見てみるという姿勢も大事だと思います。
 藻谷ゆかり先生
藻谷ゆかり先生
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
アントレプレナーシップの幅広さについてお話いただきました。
藻谷先生、本日はありがとうございました!