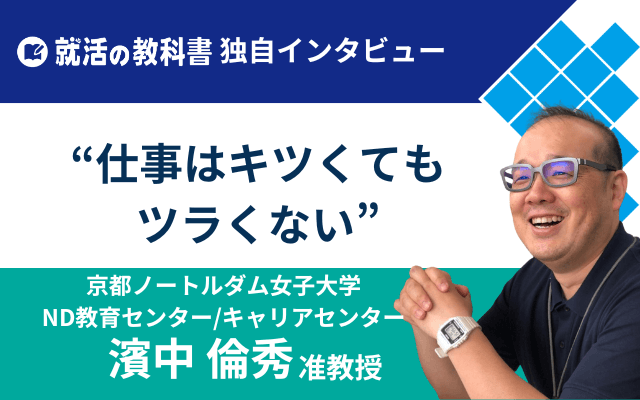「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの野口です。
今回は、20年以上キャリア教育に関わっている京都ノートルダム女子大学の濱中倫秀准教授にインタビューしました。
濱中准教授、本日はよろしくお願いします!
よろしくお願いいたします。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授

濱中 倫秀(はまなか・りんしゅう)
京都ノートルダム女子大学 社会情報学環
ND教育センター/キャリアセンター
キャリア教育歴20年以上。教育系企業での人事経験を経て独立し、大学生向け就職支援を展開。京都を拠点に多くの大学でキャリア講座や授業を担当。約10年前に大学教員となり、現在はノートルダム女子大学にてキャリア教育を担う。
目次
京都ノートルダム女子大学の濱中倫秀准教授にインタビュー①「キャリア形成ゼミ」とは
PBL型授業:ブライダルや環境問題など
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
さっそくですが、京都ノートルダム女子大学のキャリアセンターではどのような取り組みをされているのか教えてください。
京都ノートルダム女子大学では、一般的な進路支援はもちろんのこと、企業との連携授業を盛んに行っております。いわゆるPBL(プロジェクトベースドラーニング)と呼ばれるもので、企業や団体から課題をいただき、1年間にわたり取り組む授業です。この授業については、私が全体の責任者を務めております。多様な種類の授業を展開しており、「キャリア形成ゼミ」という名称で実施しています。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
PBLを実施されているのですね。どのようなプロジェクトがあるのでしょうか。
学外の企業や団体(京都府などの自治体・NPO法人)と連携した授業を展開しております。毎年多いときで7つ、少ない時でも5つ程度開講されています。毎年社会のトレンドや学生のニーズに合わせてゼミのラインナップは検討し、適宜変更しています。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
- しがに広める十三参りゼミ
京都では比較的知られている「十三参り」というイベントを、ブライダル系企業と連携して隣県である滋賀県に広めていく活動を実施 - 食を通して人が幸せになることを探求するゼミ
学生食堂を運営する企業と連携し、顧客満足度向上を目指した企画やイベントに取り組みます。 - 気候コミュニケーションゼミ
NPO法人気候ネットワークと連携し、気候変動への理解を深め、脱炭素社会に向けた行動を促すFM番組を企画・放送しました。 - メディアデザイン・企画・編集ゼミ
滋賀の情報誌「チェキポン」と連携し、読者がアクションを起こしたくなる特集を企画し、実際に取材から編集までを実践的に学びます。 - 京都大学硬式野球部応援ゼミ
関西で低調な大学野球人気を高めるため、同年代の学生目線で課題を探し、企画提案・実装・効果検証に取り組みます。
※上記内容は令和7年度のものです。
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
どのゼミも面白そうで、どこに参加しようか悩みますね。
キャリア形成ゼミに参加された学生さんからはどのような声が寄せられますか?
「キャリア形成ゼミ」は学科・学環や学年混合のグループで取り組むため、順調にいかないことも多いです。各ゼミは、最少で2〜3名、多いところでは10名以上の学生が参加しており、どうしても参加動機や価値観、熱量に個人差が出てきます。
その結果として、「自分ばかりが頑張っているように感じる」「他のメンバーが十分に取り組んでくれていない」といった不満や衝突が生まれることがあります。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
チーム活動の難しいところですね。
企業の採用部長にプレゼンして「順位付け」
また、キャリア形成ゼミの最終回では取り組みの成果についてプレゼンテーションが実施され、上位表彰も実施されます。
そうした場面では、「勝ちたい」と思う学生もいれば、「まあ、それほど気にしなくてもよいのでは」という温度感の学生もおり、熱量の差が明確になります。こうしたバラつきのあるチームの中で、いかに協働して成果を出すかという経験は、学生にとって大きな学びの機会になっていると感じております。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
上位表彰ですか?どのように評価されるのでしょうか。
企業の採用担当を経験された方々など、実務経験を持つ外部の方々にご協力をお願いしています。毎年、十数名の審査員をお招きしています。
来場される審査員には、他大学の就職支援部長や企業の採用部門で部長クラスの方など、学生にとってはなかなか緊張が高まるような方々も含まれています。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
そんなお偉い方々に対してプレゼンするのですか。緊張しそうです。
学生たちは大変緊張しながらも、真剣に発表に臨んでいます。学内でありながら普段とは空気の異なる、ピリッとした雰囲気の中での実施となることが恒例です。学生にとっては、将来の就職活動や進路選択を見据え、「初対面の社会人に自分の取り組みや成果、そして成長をどう伝えるか」という実践の場となることを重視しています。
もともと学生と一緒にビジネスプランコンテストにチャレンジすることが好きであったこともあり、「キャリア形成ゼミ」においても、競争的要素を含んだテイストにしています。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
⇒京都ノートルダム大学【産学連携】キャリア形成ゼミ 2024年度成果発表会を開催
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
HPのお写真から雰囲気が伝わってきます。
非常に良い経験になりそうですね。
ただし、「学びに順位をつける」のではなく、あくまでプレゼンテーションとしてのスキルを競う、という点は丁寧に学生に伝えるようにしています。
上位に入った喜びもある一方で、選ばれなかったゼミの学生には悔しさや上位表彰をすることへの不満や疑問の声が出ることもありました。
しかし、社会に出れば評価や順位は明確に下されることになります。だからこそ、この授業においてはあえてそのような要素を取り入れております。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学の濱中倫秀准教授にインタビュー②「キャリアポートフォリオ」とは
学生の軌跡を「見える化」
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
キャリア形成ゼミは社会勉強になりそうですね。
他にも京都ノートルダム女子大学のキャリア教育で取り組んでいることを教えてください。
キャリア形成の授業で「キャリアポートフォリオ」の作成を課しています。
キャリアポートフォリオは、自分のルーツやこれまでの取り組み、実績などを数枚の用紙に視覚的にまとめる形式を採用しています。例えば、学生団体やクラブ活動、アルバイトやサークルの新規設立といった具体的なエピソードを写真画像とともにわかりやすく整理することで、自分の軌跡を「見える化」しています。
この取り組みは、特にオンライン面接時に有効活用するように勧めており、口頭や文字だけでは伝わりにくい内容を、視覚的に伝える手段として活用しています。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
サークルやアルバイトの経験を記入しても良いのですね。
自分の頑張りが見えると就活のモチベーションにもつながりそうです。
美大の体験と採用現場での課題感から生まれた
「キャリアポートフォリオ」を導入した背景は2つあります。
1つ目は、美術大学でのキャリア支援経験です。前職では美術大学にてキャリア支援を担当しておりました。その際に初めて「ポートフォリオ」というものに出会いました。
美術大学の学生は、人見知りの学生も多く、また学んでいる領域が一般の人にはイメージしにくい場合があります。そのため口頭の対話だけでは人間性やスキルをPRすることが困難でした。しかし、ポートフォリオを通じて、学生のスキルや製作への姿勢・人となりを効果的に伝える現場を何度も見てきました。加えて、一人ひとりがまったく異なるものを作成するため、その人の個性や価値観が可視化されるという特長も実感しました。
この経験から、一般大学においても「ポートフォリオを作成すれば効果的なのでは」と考えるようになりました。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
ポートフォリオはデザイナーの就職・転職などで使われますよね。キャリアポートフォリオは個性をアピールできるので、就活のスタンダードになると面白いですね。
2つ目は、私自身が企業で採用担当をしていた経験です。現在では、履歴書やエントリーシートといった文字情報だけでは学生の人物像が十分に伝わらないケースが多くなってきていると感じています。
その点で、ポートフォリオのようなビジュアル資料があると、写真や図表を通じて普段の様子や取り組みの雰囲気を効果的に伝えることができ、採用側にとっても受験者への理解が深まりやすいと考えています。これは、採用におけるミスマッチを防ぐための一助にもなり得ますし、話すことに苦手意識がある学生にとっても新たな自己表現の手段となります。
目に見えて選考のためにひと手間をかけたことがわかりますので、採用側の印象もよくなると個人的には考えています。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
ミスマッチの防止にもつながるのですね。
ただ一方で、ポートフォリオになじみのない学生からは「何を書いたらいいですか?」「何を載せた方がいいですか?」と、正解を求める質問が多いです。
学生たちに伝えているのは、「何をしたか」よりも、「なぜやろうと思ったのか」(動機)や、「その経験を通じて何を得たのか」(学び)という点のほうが、はるかに重要だということです。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「なぜそれをやったのか」「そこから何を得たのか」を丁寧に振り返ることが、キャリアの本質につながるのですね。
京都ノートルダム女子大学の濱中倫秀准教授にインタビュー③就活生へのメッセージ
不採用=会社と相性が合わなかっただけ
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
キャリアポートフォリオを私も作成してみたいと感じました。
就活に悩む学生さんにどのようにアドバイスされているか教えてください。
多くの学生が自己PRやガクチカの言語化において手を焼いています。
本学の学生においても自分の経験に自信が持てず、自ら価値を下げてしまう傾向が見られます。「自分は大したことをやっていない」と、自身の経験に蓋をしてしまうのです。
しかし、その経験が価値あるものかどうかを判断するのは他者であり、自分で先に評価してしまう必要はありません。アウトプットはアウトプットへの反応・内省で磨かれます。そうした意識の転換を促しながら、まずは徹底的に書いてみて、自分の行動と言葉を言語化するトレーニングを積ませています。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
自分の経験に対して「こんなの大したことない」と思ってしまいがちですよね。
確かに判断するのは自分ではないですものね。
また、経験を言語化できても相手に伝える段階でつまずく学生も多いです。特に面接については、「オーディションのように評価される場」と感じ、過度に緊張して本来の力を出せないことがあります。
そのため、「落ちた=能力がない」ではなく、「その会社との相性が合わなかっただけ」という視点を持たせるように指導しています。採用とは“能力評価”ではなく、“相互選択の場”であるという考え方を、学生に伝えています。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
面接に落ちてしまうと、自信がなくなってしまいますが「相性が合わなかっただけ」なのですね。
「自分軸」と「まずやってみる力」が必要
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
濱中先生、本日はありがとうございました。
最後に就活生にメッセージをお願いします。
私は約20年間キャリア教育に携わってきましたが、それ以前から実際の採用現場で仕事をしており、25歳でその職を任されて以来、採用と就職支援の現場に約25年関わってきました。
この間、就職活動の在り方は大きく変わりました。最大の変化は、情報の量とアクセス手段が大幅に広がったことです。SNSの発展により、簡単に就職に関するヒントや答え(らしきもの)に出会える時代になっています。これは学生にとって大きなメリットだと感じています。
しかしその一方で、情報過多になってしまい「何を信じればいいのか」「どれが正解かわからない」と迷いや不安が増す場面もあるでしょう。ブラック企業や早期退職、パワハラといったネガティブな情報も簡単に目に入り、不安が強まってしまうことも少なくありません。
だからこそ、情報を自分なりに取捨選択し、納得できる道を見つける力がこれまで以上に大切です。焦らず、自分のペースで、自分らしいキャリアを築いていってください。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
選択肢が広がることは一見いいことのように思えますが、それが「決められない」「間違えたくない」という不安につながってしまうのですね。
「自分の中に軸を持つこと」は昔から大切だと言われていますが、自然と持てるものではないと思います。先に述べたキャリア科目のように、集団の中の自分を知り、経験の中で自信を積み上げていってこそ「軸」が形成されると考えています。
自分の意思があって他人に無理に合わせない、情報に流されない学生は低学年のうちから学内外を問わず良い経験(成功も失敗も)を積んでいる学生が多いですね。今のように選択肢が溢れる時代において、就職活動だけではなく社会における仕事を進めていくうえでも不可欠な力です。
実際、採用担当者の目にも、自分の意思をしっかり持っている学生の方が魅力的に映るように思います。ですから、キャリア教育においても、単なる知識の習得ではなく、経験も交えた学びの環境づくりがこれまで以上に求められていると感じています。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
情報が多い今だからこそ、自分の軸を持つことが大切になのですね。
やりたいことが見つからない。自分の意思がない学生さんも多いのではないでしょうか。
学生にぜひ伝えたいのは、社会人との接点を持ち、まずはやってみてほしいと思います。それがどれほど大きな経験になるかということを、どこかのタイミングで実感できるはずです。
成功するかどうかにこだわる必要はありません。学生時代の失敗はほとんどの場合、取り返しがつきます。
むしろ、学生時代から失敗を恐れて挑戦を避けていては、社会に出てからも同様にリスクを避け、「何もしない人」になってしまいます。だからこそ、失敗してもいい場面で飛び込んでみるべきだと、私は考えています。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
失敗を恐れずに飛び込んでみることが大切なのですね。
「仕事はきつい。でもつらいわけではない。むしろ楽しい。」
私たち大人には、若い世代に「働く姿」をどう見せていくかという、大きな責任があると感じています。
社会人にはストレスも多く、学生時代よりもプレッシャーが増す場面も少なくありません。その一方で、仕事にはダイナミックな仕事に取り組めるチャンスも、経済的な余裕から生まれる多様な選択肢など、ポジティブな側面もたくさんあります。
だからこそ、社会人が「仕事の楽しさ」や「やりがい」を積極的に発信していくことが必要だと考えています。
今の学生たちの中には、「仕事=つらいもの」という先入観が強く根づいてしまっているケースが少なくありません。特にBtoB企業のように、学生の目に触れにくい分野で活躍する社会人と出会う機会が乏しいため、仕事の多様な面が伝わりづらい現状があります。
大学のキャリアセンターに携わる立場としても、学生と社会をつなぐ接点をどう設けていくかは、常に意識すべき課題です。そして私自身も一人の大人として、「仕事は大変だけれども、面白い」と伝えていきたいと思っています。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
濱中先生のように「楽しんで働く大人の背中」を見せてくださる存在がいることは、学生にとって貴重ですね。
少し脱線しますが、NHKの番組『筋肉体操』の中で、指導されている先生がトレーニング中に発した「キツくてもツラくない」という言葉が、非常に印象的でした。
この言葉は、私の仕事観にも通じるものがあります。「仕事はきつい。でも、つらいわけではない。むしろ楽しい。」
その感覚を、どうすれば学生たちに伝えられるか。それを考え続けることが、私たち大人の役割なのだと思っています。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
私も学生時代は働くことに対してネガティブでしたが、社会に出てみると「仕事って大変だけど楽しい」と思うことが多いです。学生たちに伝われば良いですね。
京都ノートルダム女子大学は、2026年度以降の学生募集を停止すると決定いたしました。
私にとっては本学の学生・OGたちが京都ノートルダム女子大学の一番の財産です。
「大学がなくなる」ことを悲しむのではなく、「大学が存在していたこと」に誇りを持ってほしい。そして本学での学びや経験を、胸を張り、社会で頑張ってほしいと思っています。
 京都ノートルダム女子大学濱中准教授
京都ノートルダム女子大学濱中准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
キャリア教育に対する深い愛情と責任感、そして“学生の未来に本気で向き合う姿勢”を強く感じました。
濱中先生 、本日はありがとうございました!