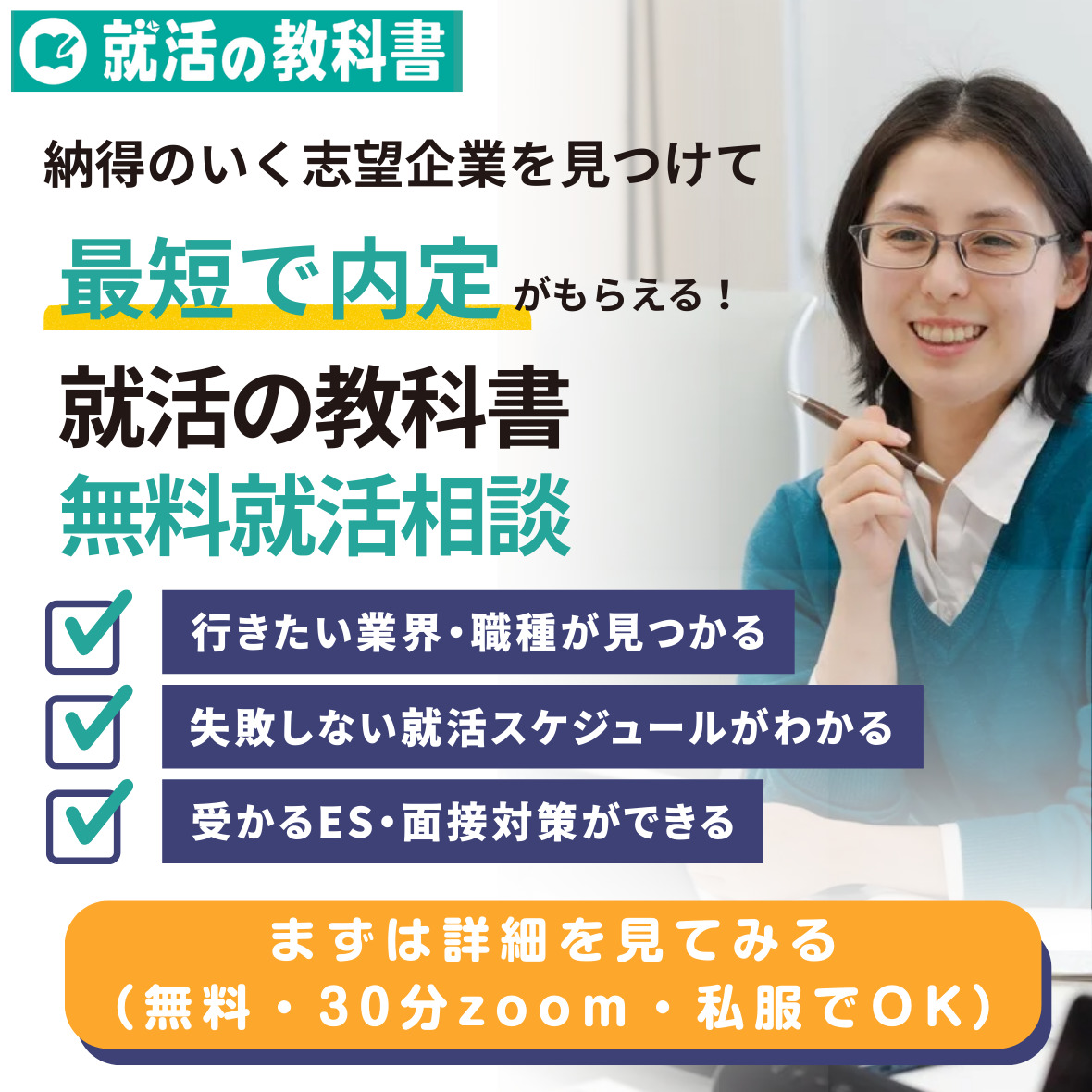「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの小林です。
本日は、北九州市立大学地域戦略研究所・地域創生学群所属で、北九州市立大学のキャリア教育を担当する見舘好隆教授にお話を伺いました!
この記事を読めば、「キャリア教育の重要性」や「企業を選ぶ上で重要なこと」について知ることができます。
「自分のやりたいことが見つからない…」や「企業ってどう選ぶんだろう?」などの悩みがある人は必見です!
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
見舘先生、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
見舘 好隆(みたて・よしたか)
北九州市立大学 地域戦略研究所 教授(地域創生学群専任)
1967年京都府生まれ。関西大学文学部卒業、立教大学大学院ビジネスデザイン研究科修了。大学卒業後、民間企業に15年間勤務したのち、首都大学東京(現、東京都立大学)、一橋大学大学院を経て現職。その他、リクルートワークス研究所客員研究員や福岡県立高校「新しい学び」プロジェクトアドバイザーなどを経験。
目次
北九州市立大学 見舘好隆教授にインタビュー①:学生のうちからキャリアに向き合う重要性
以前は“キャリア”を考える機会が少ない時代だった
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
先生ご自身が学生だった頃や社会人経験を経て、キャリア教育の必要性を感じた場面はありましたか?
私が大学生の頃、就職支援はあっても、キャリア教育はありませんでした。
日本のキャリア教育は、バブル崩壊以降の大学生の就職難および、フリーター、ニート問題などを背景に、2011年4月よりスタートしています。しかし、最新の社会情勢に対応できていないと感じていました。
だからこそ、社会人として15年の経験を積んでから教員になり、その実務経験をキャリア教育に活かしたいという思いがありました。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
民間企業で15年間勤められてから、大学でキャリア教育に関わるようになったきっかけを教えてください!
旅行会社で働いていた頃からのつながりで、大学で毎年、3年生向けの就職講座を行う機会がありました。
3年生向けだと過去の学生生活の振り返りが主になり、大学生活でどう過ごすべきかといった未来のアドバイスがほとんどできません。
当時はインターネットビジネスに携わっていたものの、自分にとってやりがいがあることは、「大学1年生から、将来の働き方に連なるキャリア教育をすることだ」と感じるようになりました。
その思いから大学教員を目指し、働きながらMBAや国家資格キャリアコンサルタントを取得しつつ、研究歴(論文執筆や学会発表)と教歴(短大の非常勤講師)を積み上げて、大学教員への転職を実現しました。転職準備に5年かかりました。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
大学生は社会人に比べて、年間でおよそ100日も多く休日がある
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
キャリアを考える上で、学生にとって重要なことはありますか?
大学生は社会人に比べて、年間でおよそ100日も多く休日があります。
社会に出ると、どれだけ長くても一週間程度の休みが限界で、留学はもちろん、本業以外のビジネスや趣味活動に1ヶ月以上の単位で取り組む機会はほぼなくなります。
だからこそ、大学1年生のうちから、人生を敷衍して、その“貴重な時間をどう活かすか”を真剣に考えてほしいと思います。
言い換えれば「今しかできないこと以外はしない」ぐらいの心構えが必要です。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
大学生が持つ“貴重な時間”をどのように活かすべきだと思われますか?
大学生は自由に使える時間が4年間あるわけです。
これは社会人になってからは、お金を積んでも得られない貴重な資産です。
この時間を、何に投資するかで、人生の可能性は大きく広がります。
たとえば、留学や語学研修、長期間のインターンやアルバイト、その他社会人と協働するプロジェクトなどに挑戦すれば、視野が広がり、就職・進学・起業など将来のキャリアの選択肢が増えます。
逆に、何となく過ごしてしまうと、視野が狭く実践経験のないまま限られた選択肢の中で判断することになりかねません。
それほど、大学時代の時間の使い方には価値があるのです.
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
たくさんある時間をただ浪費してしまうのか、投資して自分の人生の可能性を広げていくかで大きく差が出ますね!
北九州市立大学 見舘好隆教授にインタビュー②:キャリア教育で行っていること
「時間の投資先を考える」「企業の方に来てもらい、社会に触れる」
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
先生が実際に行っているキャリアの授業ではどのようなことを行っているのでしょうか?
まず、本学の学生の1年生のほとんどが前期に履修する授業「キャリアデザイン」で、この時間の使い方について徹底的にアクティブ・ラーニングを通して体得してもらっています。
同時に、授業で質の高い「時間の投資先」を伝えています。
キャリアセンターが主催する低年次向けインターンシップや学内合同説明会運営プロジェクト、大学広報の部署が主催するオープンキャンパス運営プロジェクト、図書館が主催するビブリオバトル、北九州市役所が主催する無料のプログラミング講座、その他、他大生と協働するプロジェクトなど。どの大学でもある活動ですが、これらで成長した学生=ロールモデルが授業で登壇して宣伝することで、参加する1年生はどっと増えます。
実際、ETIC.が主催する「地域ベンチャー留学」に参加する大学生の数は、本学が全国トップクラスと聞いています。
授業で時間の使い方を教えても、実際にその投資先を伝えなければ、学生はなかなか動いてくれませんから。
次に、低年次向けのインターンシップなど、仕事を体験する機会を全員に提供するのは難しいので、企業の方に大学へ来て話してもらう取り組みを行っています。
特に2年生のうちに社会の現実に触れることが重要。3年生になると就職活動が本格化してしまうからです。
企業の方には三部構成で話してもらっています。
第1部は「VUCA時代に対応した事業内容」。
その団体を取り巻く環境と、その環境における貴団体の独自性、および今後の方向性について。主にDXや海外展開、SDGs、生成系AIの活用、新規事業など。
第2部は「仕事とやりがい」。登壇者の現在の仕事のやりがいと、仕事のやりがいを支える仕組みについて。仕事上の失敗談や成長物語や、それを支えた制度(リモートワークやフレックスタイム、副業、ワーケーション、社内公募、育児や介護両立支援、長期休暇など)です。
そして、第3部が「学生時代の何が今に繋がるのか」。登壇者が学生時代に力を入れたことや、今の所属団体を選んだ理由、そして学生時代を振り返って、何が今に繋がっているかについて語って頂いています。
同時に、履修者は事前に登壇企業団体のwebサイトを読み込み、質問を提出してから参加しています。
そして、教員がファシリテーターとして、事前に回収した学生たちの質問を投げかけた深掘りも行うため、表面的な会社説明会にはなりません。
これを授業として14団体も行えば、インターンシップでの実践体験には及びませんが、働くことに対する学生たちの視野は、大きく広がるはずです。
特にBtoB企業の事業や仕事内容は、学生はほとんど知らないですから。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
自分で会社説明会に行かなくても、企業の方が大学に話をしに来てくれるというのはとても嬉しいですね!
越境学習:ホームからアウェイに飛び込む
特に授業でやるべきだと伝えているのが、「越境学習」です。
越境学習とは、自分が慣れ親しんだ環境=ホーム(例えばゼミやサークルや趣味などのコミュニティ)から飛び出し、全く異なるコミュニティ=アウェイに飛び込む経験を指します。
そこで、自分が今まで培ってきた仕事の進め方や考え方が、アウェイでも通用するのかを試すことで、大きな学びが得られます。
大学時代に没頭したことや力を入れた活動を軸に、そうした“越境”の経験を持つことが、その学生のアイデンティティやキャリア展望の形成につながっていきます。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
越境学習と聞くと海外へ行ったりすることだと思っていたんですが、自分のコミュニティから飛び出すということなんですね!
越境学習の代表的な実例として、JAL(日本航空)の客室乗務員による出向の取り組みがあります。
新型コロナウイルスの影響でフライトが大幅に減少した中、JALの客室乗務員は延べ1,500名規模で官公庁や民間企業へ出向し、新たな業務に取り組みました。
慣れ親しんだ航空業界を離れた彼女たちは、「機内や空港で培ったホスピタリティが他の職場でも通用するのか」といった葛藤を抱えながらも、新しい環境で成果を上げることで、自身の能力に対する自信を深め、さらなるスキル向上を実現しました。
その結果、元の職場に戻ってからの成長はもちろん、新たなキャリアへの挑戦やビジネスの立ち上げにつながる事例も生まれています。
こうした経験は、まさに異なる環境を往還することで学びを得る「越境学習」の好例といえるでしょう。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
異なる環境に飛び込むと自然と頑張らざるを得ない状況になる
サークルやアルバイトで「自分はできている」と思っていても、それはあくまで“井の中の蛙”のようなもので、本当に通用するかは外に出てみないとわかりません。
異なる環境=アウェイに飛び込むと、自然と頑張らざるを得ない状況になります。
例えば留学では、英語が通じないからといって逃げられません。生活や授業の中で必死に対応するしかありません。長期インターンシップも同じ。職場に相性が合わない人がいるから嫌だなんて言ってられません。
また、欠点を指摘された時、ホームでは素直になれなくても、アウェイだと受け入れやすくなり、自分を客観視して、改善して、成長できます。
そうした経験こそが越境学習であり、それを授業として取り入れています。
具体的には、2年生向けに、市内の企業に課題を出してもらって挑戦するプロジェクト型の授業や、カンボジアやラオスなどのNPOで活動するスタディツアーを設計しています。
もちろん、全ての学生には提供できないので、留学や長期間のインターンシップ、アルバイト、プロジェクトで越境学習をするように指導しています。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
いつも同じところにいては分からないことが、違う環境に行くことで自分を客観視して気づき成長できるのですね!
就職活動が始まる前に実践的なキャリア形成に取り組んでほしい
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
3年生になって就職活動が本格化してしまう前にキャリア教育は一通り受けておくのが理想なのでしょうか?
3年生になると就職活動が始まってしまい、キャリア教育としてできることは限られてきます。
これまで学んだキャリアに関する学びをもとに、自分の経験を振り返り、就職活動に活かしてもらうことくらいしかできません。
理想としては早い段階で、越境学習など実践的なキャリア形成に取り組んでほしいのですが、越境しなくても、全力で「今しかできないこと」を深掘りした経験(没入経験)があれば、何とか「後付け」してその経験を面接官に語ることができます。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
3年生になってからでも、自分を成長させるためにできることはありますか?
3年生でも、まだ自分の中に没入経験や越境的な学びが少ないと感じているなら、夏休みのインターンシップをできるだけ積極的に活用するべきです。
具体的には、社名や業界にこだわらず、「困難な課題に取り組む」「他大生と協働する」「社員との対話の時間がある」インターンシップを選ぶのが良いでしょう。
インターンシップは、3年生からでも挑戦できる、自分の視野を広げつつ成長できる数少ない手段ですから。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
自分の視野を広げつつ、成長しようとする姿勢が大切ですね!
北九州市立大学 見舘好隆教授にインタビュー③:やりたいことを仕事にする
キャリアを考える上で大切なのは「没入経験」と、その先にある「感動」
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
自分がやりたい仕事を見つけるために、重要なことはなんでしょうか?
小中高、そして大学時代を含めて、寝食を忘れて没頭する経験、いわゆる没入経験を持っている人はキャリア形成において非常に強いです。
そうした経験がないまま就職活動を始めると、自分が何をやりたいのか分からずに迷ってしまうことが多い。
だからこそ、キャリアを考える上で大切なのは「没入経験」と、その先にある「感動」です。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「やりたいことが見つからない」というのは、没入経験がないからなんですね!
キャリア形成では、“感動経験”に出会うことが重要
キャリア形成の土台にあるのは、「やりたいこと」です。
だからこそ、大学に入ったら、学業以外の全ての時間をすべて「やりたいこと探し」に使ってもいいくらいです。無料で使える図書館があり、知識や経験を惜しみなく教えてくれる教員もたくさんいます。大学は、まさに自分を見つけるための最高の場所なのです。
そして、最も大事なのは、好きなことを深掘りすることで出会う、“感動経験”です。
高校では、好きなことを調べて深掘りする“探求学習”という学びがありましたよね。でも大学ではそのような自己探求を促す授業が少ないのが現状です。大学のキャリア教育は、学業以外の分野での深掘りをあまり奨励しておらず、そこに弱点があると感じています。
大学時代に幅広くさまざまなことを経験して視野を広げることは大切です。しかし、一方で「一つのことに集中して深掘りすること」も同じくらい重要です。困難を乗り越えながら努力を積み重ねる過程で、初めて大きな「感動」に出会えることが多いからです。表面的に触れるだけではわからない世界の奥深さや、自分自身の成長を実感できる瞬間は、やはり深掘りの中で訪れることが多いのです。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
だから、自分から、自分の好きなことを深掘りして、“感動経験に出会う”ことが重要ですね!
仕事と私生活が調和する「ワークライフハーモニー」という考え方
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
先生が考える“理想的な働き方”とは、どのようなものですか?
自分の「やりたいこと」がそのまま仕事になれば、人生はとても楽しくなります。
近年では「ワークライフバランス」という言葉は古くなりつつあり、今は仕事と私生活が調和する「ワークライフハーモニー」という考え方が重要になっています。
仕事と趣味の境界が曖昧で、オフの時間にも自然と仕事に関わる活動をしている――まさに私自身もそんな働き方をしています。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
趣味が仕事であれば、全く苦になりませんね!
私は授業づくりや授業そのものが本当に楽しくて、土日を丸ごと使っても苦になりません。
もともとそれがやりたくて大学教員になりましたし、キャリア教育に資する本を自腹で買ったり、そのネタ探しに自費で海外に行ったりすることも全く厭わない。
そう思えるのは、自分の「やりたいことの本質」がはっきりしているからです。そしてそれを仕事にするのが、最も自然で正しいキャリアの形だと考えています。
その原点は、学生の頃の「自分の心が動いた瞬間」にあるのだと思います。私の場合は、大学を卒業してから感じた、大学生が成長する姿を見た時の感動なのですが。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
自分がやりたいことの原点は、学生時代の感動にあるのですね!
本当に頑張れる人というのは、“心から好きなことに出会えた人”
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「好きなことは仕事にしないほうがいい」という考え方があると思うんですが、これに対してどのように見ていますか?
漫画『ブルーピリオド』の主人公のように、好きなことに感動し、それを本気で追いかけることはごく自然でまっとうな生き方です。
彼が東京芸大を受験するか悩んだ末に美術部の先生に相談したとき、「好きなことは趣味でいい。これは大人の発想だと思いますよ」という言葉が印象的でした。
本当に頑張れる人というのは、“心から好きなことに出会えた人”。
だからこそ、オンとオフを完全に分けるのではなく、仕事自体が楽しく、日常とつながった働き方が理想です。
休日も単なる休養だけに使うのではなく、美術館に行ったり、旅をしたり、友達と語り合ったり、新しい自分を発見するための時間にしてほしい。
でも、平日に嫌な仕事を続けていると、その気力すら失われてしまいます。
だから、仕事とオフを切り分けず、シナジーを持たせることで、人生100年時代を本当に楽しく生きられるのだと思います。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
「好きなことは仕事にしないほうがいい」は時代遅れの発想
「好きなことを仕事にできたらいいな」という思いに対して、「それは甘い」「仕事は我慢するもの」というのは、もはや昭和的な、時代遅れの発想です。
もしそういうことを言う大人がいたら、「そうですね」って流しながら、心の中で「この人の考え方、古いな」と思っておけばいいんです。
本当に頑張れるのは、好きなことに出会った人です。
だから、仕事も余暇もシナジーのある人生を自分の軸で創っていくことが、これからの時代には何より大事なんだと思います。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
周りの声ばかりに左右されないでまっすぐ自分の好きなことを貫いていきたいです…!
北九州市立大学 見舘好隆教授にインタビュー④:企業を選ぶ上で大切なこと
自分の好きなことを社会課題と結びつける
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
就職活動において、企業を選ぶ上で大切なことはありますか?
これからの時代は、趣味や没入経験が社会課題と結びついていることが、より重要になってくると感じています。
キャリア選択において、何かの社会課題をビジネスの形で解決しようとしている企業を選ぶのも一つの道です。
自分の発信や行動によって誰かの課題が解決され、その結果として誰かが幸せになる――そんな仕事ができたら、本当に楽しいし、最高の働き方だと思います。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
自分が好きなことをすることで、それが他の人の幸せに繋がるなんて素敵ですね!
「自分が学んだことを誰かに還元したい」という思いはどんな企業でも活かせる
自分が学んだことを、まだ享受できていない人たちに還元したい――もしそんな思いを言語化できていれば、その志はどんな企業でも活かせます。
たとえば伊藤園は、単にお茶を販売するだけでなく、耕作放棄地をお茶畑として再生する取り組みを行っています。
また、明治は、カカオ農家支援活動に取り組み、すべての調達先において児童労働ゼロを目指すなどの活動をしています。
このようなSDGs(持続可能な開発目標)に基づいた企業の社会的取り組みは、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の観点からも注目を集めており、持続可能性と社会的価値を兼ね備えた事業が企業に強く求められています。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
ただお茶やチョコレートを売るだけではなくて、社会課題にもアプローチしているのですね!
自分の「やりたいこと」の原点にある“感動”、小学校から大学までのどこかで感じた強い気持ちを思い出してみてください。
そして、その感動を社会に還元する形で事業を展開している会社を探してみるのも一つの方法です。
たとえば、高齢の事業主が後継者不在で廃業を考えている現場に対して、若い後継者とマッチングする支援を行う企業もあります。それも、その事業を引き継ぐ後継者側から手数料を取ることで、事業主には負担がかからない仕組みも生まれています。
また、空き家を借り上げてリフォームし、賃貸物件やシェアハウス、店舗、コワーキングスペースなどに活用している不動産会社もあります。
こうした社会的な課題に向き合いながら、自分の関心や感動とつながるビジネスをしている会社は、実は探せばたくさんあるのです。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
見つけられていないだけで、自分の関心に繋がる会社はいっぱいあるんですね!
企業の“IR資料”を通して、自分のやりたいことができるか見極める
企業選びにおいて絶対にやってほしいのが、IR資料の読み込みです。
ほとんどの学生は採用サイトしか見ていませんが、それだけでは企業の本質はわかりません。
IR資料(投資家向け情報)は、上場企業であれば必ず公開されており、「社名+IR」で検索すれば簡単に見つかります。
IR資料には、「会社がどこで儲かり、どこで失敗したか」、「どこに課題を感じ、今後どんな方針で投資をしていくか」、「ダイバーシティやサステナビリティへの取り組み」などが具体的に書かれており、企業のリアルな姿勢や価値観が見える最も信頼できる情報源です。
その企業が「自分のやりたいことと重なるかどうか」を、IR資料を通して見極めてください。特に、決算説明会のパワーポイントをPDF化した資料が読みやすくて良いと思います。
自分の感動の本質と、企業が目指していることの接点を見つけることができれば、志望動機が明確になり、同時にどんな面接でも説得力のある自己PRを伝えることができるようになります。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
いつも企業の採用情報の募集要項しか見ていませんでした…!
さっそく、自分の気になる企業のIR資料を見てみます!
北九州市立大学 見舘好隆教授から学生へのメッセージ
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
素敵なお話をたくさんありがとうございました!
最後に、学生へのメッセージをお願いします!
大学1,2年生へのメッセージ:「没入経験」と「越境学習」で自分の成長の幅を広げる
大学生は社会人よりも年間約100日、行動の自由度があります。
この貴重な時間をどう使うかが、その後のキャリアに大きな影響を与えます。
とくに大学1・2年生には、「没入経験」と「越境学習」の2つを意識して過ごしてほしいです。
没入経験では自分の「好き」を深掘りすること。スポーツでも映画鑑賞でも何でもいい。
「オタク」と呼ばれるくらいまで没頭することで、自分だけの知識の塊やスキルが形成されます。
越境学習ではその没入経験で培った知識の塊やスキルが、まったく別の場所でも通用するのかを試すこと。
自分の「ホーム」から一歩外に出て、「アウェイ」に身を置くことで、自分の成長の幅が一気に広がります。
こういった経験があるからこそ、3年生になったときに、就職活動で「何がやりたいのか」が見えてくる。
逆にそれがないと、有名企業や知っている業界の中からしか選べなくなってしまいます。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
就活生へのメッセージ:「自分の心が動いた瞬間」こそが、キャリア選択の出発点
就活に向けた自己分析は、単に自分の強みや適性を洗い出すだけではありません。
最初にやるべきことは、自分の「感動経験」を思い出すことです。
「自分の心が動いた瞬間」こそが、キャリア選択の出発点になります。
業界名や職種、企業名といった“ラベル”ではなく、「自分が本当にやりたいこと」に向き合うべきです。
たとえば、「人前で話すことで感動し、それが誰かの役に立った」という経験があるのなら、それは立派なキャリアの原点です。
その原点を手掛かりに、「話すことで社会に還元できるような仕事」ができる会社を探すべきです。
そんな軸が見えてきたら、その企業で「それが本当にできるのか」を徹底的に調べる。できればインターンシップで、難しければIR資料を読み込んで。
そうすることで、納得感のある企業選びができるようになります。
 北九州市立大学 見舘好隆教授
北九州市立大学 見舘好隆教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
先生のお話を通して、私自身もキャリアについて改めて考えようと思います!
本日は、本当にありがとうございました!