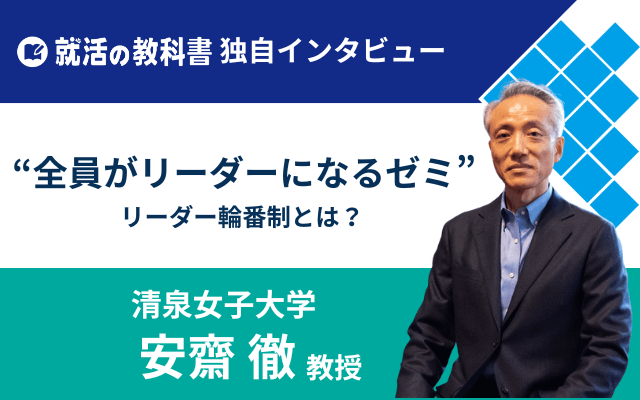「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの野口です。
今回は、清泉女子大学の安齋徹教授に「リーダーシップ」について伺いました。
安齋教授、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授

安齋 徹(あんざい・とおる)
清泉女子大学 地球市民学部 教授
1960年東京都生まれ。一橋大学法学部卒業、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科修士課程修了、修士(社会デザイン学)、早稲田大学大学院社会科学研究科博士課程修了、博士(学術)。28年にわたる企業勤務を経て、大学教員に転身。群馬県立女子大学、目白大学を経て2020年より現職。元社会デザイン学会副会長、元日本ビジネス実務学会監事。著書『女性のためのキャリアデザイン』(共著、樹村房)『アニメ映画から学ぶ生き方のヒント』(共著、樹村房)『ソーシャル就活ガイドブック』(共著、三恵社)『ソーシャルZ~社会のため女子大学で、できること~』(三恵社)など。
目次
清泉女子大学安齋徹教授へのインタビュー①リーダーシップは「引っ張る」だけではない?
多様化する21世紀型リーダーシップの在り方
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
さっそくですが、安齋教授はリーダーシップについての授業を担当されていますよね。授業内容を詳しく伺ってよろしいでしょうか?
地球市民学部の専門科目の授業の中でリーダーシップ論を教えています。
ほとんどの学生や社会人は、リーダーをカリスマ型で「先頭に立つ人」と捉えています。そのため「自分はリーダータイプではない」と決めつけてしまうケースが多いと感じています。ただ、そうした先頭に立って引っ張るようなリーダー像は、どちらかというと20世紀型のリーダーシップのスタイルです。
21世紀では、多様な文化や価値観を抱えた人たちが混在する組織をマネージしていく必要があり、そういう中では協調型のリーダーが求められています。そこで、「リーダー」のイメージを多くの人が誤って捉えている可能性があるということを、大学で伝えています。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
リーダーシップと聞くと、どうしてもメンバーを引っ張っていくイメージが強いです。
「羊飼い型」「フェミニン型」…学生に響くリーダー像とは
リーダーシップには様々なスタイルがあります。たとえば下から支える「サーバントリーダーシップ」、声高に指示するのではなく、沈着冷静に対応していく「静かなリーダーシップ」。あるいは「羊飼い型リーダーシップ」というものもあります。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「羊飼い型リーダーシップ」ですか。初めて聞きました。
「羊飼い型リーダー」は後ろからメンバーを見守りながら導いていくタイプのリーダーで、ハーバード・ビジネス・スクールのリンダ・ヒル教授が提唱しています。
女子大学における授業で「羊飼い型リーダー」は学生たちから人気があり「自分は羊飼い型リーダーになりたい」と言う学生がたくさんいます。
さらに、「フェミニンリーダーシップ」という見方もあります。もちろん個人差はありますが、フェミニンリーダーシップとは女性の特性を活かしたリーダー像を表すもので、男性が競争を重視するのに対して、女性は協力を重んじる。また、男性が結果や勝利を求める一方で、女性はプロセスや品質を重視するといった傾向があると言われています。
このような特徴を持つ女性の特性を活かしたリーダーシップスタイルは、現在求められている「協調型リーダーシップ」と相通じるものがあると考えています。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「フェミニンリーダーシップ」も初めて耳にしました。様々なリーダーシップの形があるのですね。
女子大学でこそ育むべき“広義のリーダーシップ”
女性の活躍推進は、ジェンダー平等を目指す人々にとって長年にわたる課題であり、その中でも指導的地位にある女性を増やすことは近年特に大きな政策課題となっています。しかしながら、2020年までに指導的地位に就く女性比率30%を目指すとしていた政府の目標も遠く未達成であり、国際的にも低水準です。2014年の「ウィメン・イン・ビジネス・サミット」で当時の首相が唱えた「女性の活躍は経済成長の1丁目1番地」という掛け声もむなしく、いまだ「女性活躍後進国」であるというのが現状です。
女子大学の学生すべてが必ずしも管理職を目指す必要はないのですが、広い意味でのリーダーシップを蓄えて社会に送り出したいと願っています。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
学生時代に正しいリーダーシップの意味を理解できると、キャリアにも良い影響がありそうです。
清泉女子大学安齋徹教授へのインタビュー②「ワクワクするゼミ」から生まれる挑戦
社会課題に取り組むプロジェクトで学ぶリアルな責任感
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
安齋ゼミではどのような活動をされているのでしょうか。
安齋ゼミでは,「日本一ワクワクドキドキするゼミ」を目標に「企画力」「行動力」「協働力」を身につけながら,これからの社会やビジネスをいかにデザインするかを探究しています。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
日本一ワクワクドキドキするゼミですか!楽しそうですね。
教室の中で「少子高齢化の対策を考えましょう」と言って議論はできますが、学生が真剣になりづらいです。
一方で企業や地域の課題を解決するというプロジェクトだと、目に見えるリアルな相手がいて、期限があり、責任感も生まれます。最近はハンドクリームやアロマスプレーなどの商品開発にも取り組んでおり、実際に「形になる」プロジェクトは学生に取って非常にやりがいがあります。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
教室の中だけでは得られない“責任感”や“やりがい”を学生時代に経験できることは、貴重だと思います。
「リーダー輪番制」と「フォロワーとの同時体験」が成長を促す
また、安齋ゼミでは「リーダー輪番制」を採っています。これは輪番でリーダーを経験するという方式で、「自分はリーダータイプではない」と感じている学生も含めて、順番にリーダーを経験します。その中で、自分らしいリーダーシップスタイルを見つけて欲しいと思っています。
安齋ゼミでは同時並行で複数の案件を進めていますので、ある案件ではリーダー、別の案件ではフォロワーというように、リーダーとフォロワーを同時に体験することになります。
この「リーダーとフォロワーの同時体験」が成長を促すと考えています。リーダーとして孤独を感じたときに、周囲に対して「もっとこうしてほしい」と思うことがありますが、フォロワーとして自分がどう行動できているかを問い直すきっかけになります。そういった様々な立場での経験の積み重ねを通じて確実に成長することができます。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
リーダーとフォロワー、どちらも経験できることは勉強になりそうです。
安齋ゼミの卒業生からは「複数の案件を同時にこなせるようになる」「思い通りにいかないことも含めて色々な経験を積んで成長できる」「頑張り癖がついた」などの声が寄せられています。
ゼミ生には社会に出て10年後に「あのときの経験があって良かった」と思えるような経験を学生時代にしておいて欲しいなと考えています。卒業生が社会の荒波の中で頑張って活躍している姿を見ると嬉しいです。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
「未来人材育成モデル」とは?──社会で活きる3つの柱
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
私も大学生だったら安齋教授のゼミに参加してみたいと感じました。
安齋教授がおっしゃっている「未来人材育成モデル」とはどのようなモデルなのでしょうか。
「未来人材育成モデル」とは、自分が行っている教育の中で、「ポイントになるのは何か?」ということを、考えてみた私見です。経済産業省が提唱している「社会人基礎力」とも重なる部分もあると思います。大きく3つの柱があります。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
(1)ベーシックな能力・スキル→協調力・創造力
・コミュニケーション
・リーダーシップ
・クリエイティビティ
(2)未来に向けた視野・ビジョン→思考力・構想力
・自分:自己理解→自己鍛錬(自己肯定感の向上)
・ビジネス:ビジネス理解→ビジネス創造(ビジネスマインドの習得)
・社会:課題認識→社会貢献(社会変革意欲の醸成)
(3)実際に現場で行動・挑戦する経験・タスク→行動力・実行力
・協働経験:チームワーク・コラボレーション
・企画経験:プランニング・イノベーション
・失敗経験:ストレッチ・タフネス
まず1つ目は、「大学で身につけて欲しい」スキルです。
- コミュニケーション
- リーダーシップ
- クリエイティビティ(創造性)
これらを大学時代にしっかり身につけて欲しいと考えていて、授業やゼミでも重点を置いています。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
どれも社会で求められる基本スキルなので、学生のうちに身につけられると良いですね。
2つ目は、「視野をどう広げていくか」という点です。未来や社会を見据える力を育てたいと思っています。
- 自分を理解する
- ビジネスを理解する
- 社会を理解する
これは単に知識を覚えるだけではなく、多面的な視点を持って、自分の立ち位置や役割を捉え直し、それらを社会や未来でどのように発揮していきたいかを考えることです。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
知識を「覚える」だけでなく、自分の視点で「捉え直す」ことが大切なんですね。
3つ目は、「経験値」をどう積むかという点です。
- 誰かと協力しながら遂行する経験(協働)
- 新しい価値を創り出す経験(企画)
- あえて失敗するぐらいの経験(ストレッチ)
特に、失敗するぐらいの挑戦をすることが重要です。学生が「Comfort Zone(居心地の良い空間)」の中にとどまっている姿が気になっており、そこを超えていく必要があると考えています。
簡単ではないですが「背伸びすれば届くかも」というような課題に次々と挑戦し、成功することもあればうまくいかないこともあることを理解して欲しいです。むしろ、良質な失敗経験こそが学生の成長につながると思っています。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「失敗してもいい」「むしろ失敗こそが学びになる」というメッセージは、多くの学生にとって救いになると思います。挑戦すること自体に価値があるんですね。
実際に学生の中には、「失敗から学ぶことの方が多かった」という声もあり、そこまで深く学べたことは教員としてもとても嬉しいです。
加えて、頑張るってこと自体がいいことなのだ、という実感を持って欲しいです。うまくいっても、いかなくても、その経験を前向きに活かしていく姿勢――それこそが大事だと伝えています。人生はそうしたこと(成功や失敗)の繰り返しだからです。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授へのインタビュー③就活生へのメッセージ
「社会に出ること」を前向きに
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「失敗したくない」と考える学生さんも多いと思いますが、失敗を経験することも大事なのですね。
就活生へメッセージをいただけますか?
私は企画や営業、事務、海外勤務、秘書、人事、研修などいろいろな経験をしてきましたが、学生の頃に想像していたよりも「仕事や社会での活動は楽しかった」と感じています。
もちろん失敗や挫折もたくさんありましたが、自分ひとりの力より、取引先の方や上司・同僚などの力も借りながら、国内や海外で想像以上に多種多様で様々なことを達成できたという実感があります。突き詰めれば、仕事とは、誰かの悩みや課題を解決する営みであり、広い意味で世のため人のために汗を流すことです。
昔に比べて働き方改革も進んでいて、今はだいぶ働きやすくなってきたと思います。もちろん仕事だけが人生ではないですが、仕事を充実させることが、人生全体の充実にもつながります。
働くことに対してぜひポジティブな期待を持って、社会に羽ばたいていって欲しいと思っています。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「社会人になりたくないな」などネガティブな感情を持つ学生さんが多いかなと思いますが、安齋教授は「仕事が楽しい」と感じられたのですね。
私はワーク・ライフ・バランスは、次の5つの軸で構成されていると考えています。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
- 仕事
- 家庭
- 学習
- 社会
- 自分
この5つすべてをバランスよく充実させていくことが、人生の目標になると思っています。その中の一つが「仕事」です。仕事は給料を得たり、お客様や社会の役に立ち、何よりも人生の多くの時間を費やす場であるという点でもとても重要です。だからこそ、自分に合った「良い職場・仕事」を見つけて、充実したキャリアを歩んで欲しいというのが、私の願いです。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
大学生活の充実=最高の就職対策
今は全体として少子化による人手不足の影響もあり、就職市場としては若干の追い風があるとは思います。
しかし「何をしたらいいかわからない」「全部がうまくいく訳ではない」「面接で落ちてしまう」などの不安や悔しさがあると思います。だからこそ、就活で一喜一憂しないで欲しいなと思っています。
それよりも大事なのは、大学生活そのものをしっかり充実させることです。
小手先の就職対策ばかりをするのではなくて、大学でどんな経験をして、どう成長するか――それがそのまま就職活動でも活きてくると思いますし、企業が求めているのもそういう地に足をつけてしっかりと汗を流してきた人材だと思っています。
究極の就職対策は、大学生活を充実させることだというふうに考えています。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
大学生活の充実と就職活動はつながらないと思っていました。大学での経験は大事なのですね。
清泉女子大学安齋徹教授へのインタビュー④書籍『ソーシャルZ』に込めた思い
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
著書『ソーシャルZ~社会のために女子大学で、できること~』をどのような思いで作られたのか教えてください。
2025年6月に『ソーシャルZ~社会のために女子大学で、できること~』(三恵社)を上梓しました。閉塞感漂う社会や企業に少しでも風穴を開けられるような元気と勇気のある人材を育成することを使命と自覚し,教育現場で創意工夫を凝らしながら日々試行錯誤を繰り返しており、群馬県立女子大学や清泉女子大学における教育実践を通して、Z世代の女子大生の奮闘ぶりを伝えたいと思い立ち本書を執筆しました。
教室を飛び出す学びは学生の成長を促します。教室の中でありきたりのテーマに取り組むよりも、現場のリアルな課題に取り組み、誰かのために真剣に考え、責任感をもって真摯に行動することで学生は成長します。企業や地域と連携しながら、社会課題の解決に取り組むプロジェクトを幾度となく繰り返し、挑戦する学生たちが着実に成長していく様を目の当たりにしてきました。そこで、社会のために行動するZ世代の学生たちの奮闘ぶりを「ソーシャルZ」と命名し、書名にしました。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
Z世代のリアルな奮闘を描いた本なのですね。
教室を飛び出し社会と連携し、同時並行で複数の案件を輪番でリーダーを務めながらチームで取り組むことが成長を促し、ストレッチ(負荷)をかけた学生時代の「良質な企画経験や挑戦経験」(成功・失敗)が卒業後の飛躍に向けた源泉(基礎や原動力)になるという教育観を体現したのが本書になります。
教員になってからの日々はまだまだ浅いですが、群馬県立女子大学や清泉女子大学の教え子の中には、管理職として活躍する人、市議会議員として地域のために奮闘する人、海外で子育てしながら働く人、創意工夫を凝らして着実に成果を収めている人が出てきています。ゼミから巣立った「未来の担い手」の今後の活躍に期待しています。
 清泉女子大学安齋徹教授
清泉女子大学安齋徹教授

 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
安齋教授のお話を通して、「リーダーシップ」のイメージが大きく変わりました。
また「失敗こそが学び」という言葉もとても印象的でした。
本日は貴重なお話を本当にありがとうございました。