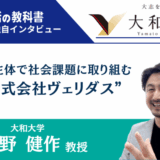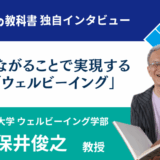「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの野口です。
本日は、四日市大学総合政策学部の小西琴絵准教授にインタビューしました。
この記事を読めば、「時間的展望とは?」「就職活動で企業が見ていること」などが分かります。
小西先生、本日はよろしくお願いします!
よろしくお願いいたします。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
小西 琴絵(こにし・ことえ)
四日市大学 総合政策学部 特任准教授
愛知県出身。神戸大学大学院で修士課程を修了後、博士課程に進学するも出産を機に一度中断。現在は立命館大学大学院・人間科学研究科で博士後期課程に在籍し、研究を続けながら大学でキャリア教育の講義を担当している。
目次
四日市大学 小西琴絵特任准教授にインタビュー①:「時間的展望」とは?
人の“時間軸をどう捉えるか”が意思決定や行動に影響する
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
さっそくですが、先生の研究テーマである「時間的展望」について教えていただけますか?
時間的展望とは心理学の概念で、人が過去・現在・未来をどう認識しているかによって、意思決定や行動が変わってくることを指します。
たとえば過去を否定的に捉えている人や、自暴自棄になっている人は、アルコール依存や危険運転に陥りやすいといった研究があります。
逆に未来志向の強い人は計画的に物事を進め、学業やキャリアにおいて成果を上げやすいことが分かっています。
研究では、特に大学生から40代を対象に、「時間軸の捉え方が、就職活動やキャリア選択の場面に影響しているのか」を調べています。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
過去・現在・未来の認識で、キャリアや行動が変わるのですね。
時間的展望は大きく5つの志向に分けられます。
過去・現在・未来の三つに分かれ、過去と現在にはそれぞれ“ポジティブ”と“ネガティブ”の二軸で、未来が一軸です。
この5つは世界中の研究で広く使われていて、私の研究もこの考え方をベースにしています。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
- 過去ポジティブ
「昔は良かった」「懐かしい思い出が多い」といった、過去を前向きに捉える傾向。
例:家族旅行の思い出を大切にしている。
- 過去ネガティブ
「嫌なことばかりあった」「辛い経験が多い」といった、過去を否定的に捉える傾向。
例:失敗やトラウマを繰り返し思い出す。
- 現在快楽志向(Present Hedonistic)
「今が楽しければいい」という考え。衝動的・冒険的で、未来のリスクよりも現在の快楽を重視する。
例:やりたいことをすぐ行動に移す。
- 現在運命志向(Present Fatalistic)
「すべては運命で決まっている」「自分ではどうにもならない」と考えがち。受け身的・諦めの姿勢につながる。
例:「頑張っても結局は運命だから」と努力を避ける。
- 未来志向
「目標を立てて努力する」「将来のために今を我慢する」という考え。計画性・忍耐力がある。
例:試験勉強のために遊びを我慢する。
過去については、出来事をポジティブに受け止めるか、ネガティブに捉えるか、その人が今どう感じているかで判断しています。
現在については“快楽”と“運命”という軸があり、快楽は『今が楽しければいい』という志向、運命は『すべては神が決めるものだから自分ではどうにもならない』という志向になります。
未来については基本的にポジティブに捉えられることが多く、未来をしっかり見据えられる人は前向きで計画性があり、予期せぬことが起きても柔軟に対応できる、という研究結果が出ています。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
“自分がどの立ち位置で過去や未来をどう認識しているのか”が重要
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
キャリアにおいては、未来志向が強いことが重要なのでしょうか。
時間的展望は、キャリアの分野では“これが一番いい”という軸はないんです。
精神疾患の治療では、現在運命や過去否定の思考をポジティブに変換することに焦点を当てることがあります。ただ、キャリア選択のように病的でない場面では“どの軸が強いのが良い”ということはなく、むしろバランスが大事なんです。特に未来志向と過去肯定志向が高く、全体的にバランスの取れた時間認識を持っている人は、精神的にも安定していて、納得感のある意思決定ができるという研究が進んでいます。
キャリアの研究では「未来志向の強さや過去を肯定的に捉えることが、挑戦や成長につながる」という結果も出ています。
実際、就職活動では『将来どうしたいか』と同時に『これまで何をしてきたか』も聞かれます。
その時、過去の経験をどう受け止めているかで自己表現は大きく変わります。
大事なのは、どの軸が良い悪いではなく、“自分がどの立ち位置で過去や未来をどう認識しているのか”をきちんと理解すること。
その確認を通じてサポートしていくことが重要だと考えています。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
就職活動では「過去に何を頑張ったのか」「将来何をしたいのか」を聞かれることが多いので、時間的展望の考え方はとても重要ですね。
未来志向の学生が必ずしも就活で成功するわけではない
研究で2023年3月に全国の大学3年生、約400人にアンケートを取りました。
従来の研究では未来志向が強い学生ほど積極的に就職活動に取り組むと考えられていたんですが、実際には計画的すぎるのか、むやみにエントリーや説明会に参加せず、狙った企業にだけ絞る傾向が見られました。
逆に、過去にネガティブな体験を持つ学生ほど『今度は頑張ろう』という形で積極的にエントリーや説明会に参加する動きが見られたんです。
この結果は、単純に「未来志向の学生が就活で成功する」という従来の見方だけでは説明できない新しい視点を示しているのかなと思っています。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
ただ未来志向であるというのが、就職活動の成功に直結するわけではないというのは面白い結果ですね。
しっかりとした目標があるからこそ、特定の業界や企業に絞りすぎてしまうという面があるのですね。
これまでの定説では、過去をネガティブに捉える人は前に進めず立ち止まってしまうと考えられていたんです。
でも実際に調査してみると、逆に『何とかしよう』と積極的にもがいて動いているような印象を受けました。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
企業が見ているのは、未来志向だけでなく「過去をどう受け止めて乗り越えてきたか」
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
今までの調査の中で、印象的だったことはありますか?
以前、人事の方とお話ししたときに、『未来志向の強い学生は話も上手で自信もあって頼もしいけれど、いざ就職活動が始まると意外と脆さが出ることもある』と聞いたんです。
逆に、過去に痛みや挫折を経験し、乗り越えた学生の方が、社会人になった時に強く、面接でも軸がぶれずに話せる。
実際に『この子と一緒に働きたい』と思わせるのはそういう学生だとおっしゃっていました。
その話を聞いて、やはり未来志向だけでなく、過去をどう受け止めて乗り越えてきたかを企業は重視しているんだなと感じました。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
ガクチカは『何人のマネジメントをした』とキラキラした実績を書く学生が多かったりしますよね。実際に人事の方が見ているのは、“過去にどんな困難があって、それをどう乗り越え、そこから何を学んだか”という部分なんですね。
四日市大学 小西琴絵特任准教授にインタビュー②:大学でのキャリア教育・学生に伝えたいこと
自己分析では、“過去の経験がどう自分を形づくってきたか”を考える
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
大学でのキャリア教育では、「時間的展望」の観点から行っているのでしょうか?
今、四日市大学では経営学の入門や経営管理、マーケティング論を担当しているので、時間的展望についてじっくり話す機会はあまりありません。
ただ、キャリアに関する授業では『将来どうしたいかを考えるのも大事だけど、これまでの経験をどう捉えるかも大切』という話はよくしています。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
見落としてしまいがちですが、とても大切な視点ですね!
就職活動では業界研究や企業分析をして、その上でガクチカを考えようと学生に伝えるんですが、どうしても『将来どんな仕事をしたいか』『どんな業界に行きたいか』という未来の話ばかりに偏りがちなんです。
だからこそ私は『ちょっと待って、そのためにまず過去を振り返ろう』と伝えています。
自己分析のタイミングでは、“過去の経験がどう自分を形づくってきたか”を考えることが大事なんです。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
まずは自己分析をして、過去を振り返ることが重要ですよね。
学生の中には『自分には特別な経験がない』と言う子もいます。
でも、実際は部活での浮き沈みや、アルバイトでのしんどい経験、友達との人間関係など、日常の中に必ず振り返る材料があります。
私はそうした「身近な出来事からでも十分に自己理解につながるんだよ」と伝えるようにしています。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
学生に寄り添ってアドバイスをしていらっしゃるのですね。
「今」が優先で就職活動を進められない学生が多い
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
キャリア教育の授業について、学生からはどのような声がありますか?
今年度は3年生向けに必修科目を担当しているんですが、正直、前期の段階で『なんでこんな授業を受けなきゃいけないの?』と思っている学生も多いと思います。
夏休みにはインターンシップが始まって、そのまま選考に進んでいくので『早く動こう、早く考えよう』と伝えていますが、学生にとっては部活や留学、旅行など、今やりたいことが優先で、就職活動どころではないという声もあります。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
就職活動は早く始めた方がいいと思いますが、学生さんは忙しいですよね。
でも実際には、そうした経験のすべてが就職活動につながるんですよね。
社会人の方からは『学生時代にこんな先生がいたらよかった』と言っていただけるんですが、学生は『いやいや、今が楽しければいい』という思いがまだ強いように感じます。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
社会人になると、就職活動に関してアドバイスしてくれる先生がいるのはありがたいことに気づくんですけどね…
キャリアにおいて一番重要なのは『ここで働いていていい』と思える納得感
授業ではよく、自分の就職活動や仕事の経験も話すんです。
私は証券会社の営業として働き始めたんですが、約1年で辞めました。
学生からは『そんなに早く辞めてもいいんですか?』と聞かれることもあります。
でも私は、若いうちにやりたいことを探す時間を持てるのは大事だと思っていて、合わないと思ったら次を見つけに動いてもいいと伝えています。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
就職活動が重要ということを伝えるのと同時に、「辞めてもいい」とも伝えているのですね… !
もちろん新卒で入った会社に価値はありますが、それだけが全てではありません。
短期間で辞めても『そこでこう学んだから今の自分がある』と説明できれば問題ないし、最近は第二新卒や転職の道も広がっています。
耐えることが必要な場面もありますが、将来に希望が持てない環境で無理に耐える必要はありません。時には辞めることも前向きな選択肢なんです。
家庭を持ったり背負うものが増えてからゼロからやり直すのは大変ですが、若いうちは身軽だからこそ『これもやってみたい』『あれも挑戦したい』と動いてみる時間を大切にしていいと思います。
合わないと感じたら早めに次に進むのも一つの方法ですね。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
人生100年時代、転職が当たり前になってきた時代で、選択肢が一つでないというのは大切な考え方ですね。
今は勤続20年・30年と続けること自体が評価される時代ではありません。
それよりも大事なのは、自分がその仕事に納得しているかどうか。
給料や休み、働き方も含めて『ここで働いていていい』と思える納得感こそが、キャリアにおいて一番大切だと考えています。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
自分が“納得できる”のは人生においても、とても大切なことですね。
就活生へのメッセージ:「今できる限りのことをやった自分は偉い」と認めながら進んでほしい
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
小西先生、ありがとうございました。
最後に就活生に向けてメッセージをお願いします!
学生にとって就職活動は人生を決めるくらい大きなものに感じられると思います。
もちろん希望の職種を目指して一生懸命取り組むのは大事ですが、実際に就活で失敗して別の道に進んだ身からすると、少し肩の力を抜いて取り組んでほしいと思うんです。
人生は長いですし、40年後まで見通すことなんてできません。
だからこそ『今できる限りのことをやった自分は偉い』と認めながら進んでほしいですね。
学生を見ていると、授業を休んでインターンや説明会に行くなど、本当に全力で頑張っています。
その熱意は素晴らしいですが、その分失敗したり,上手くいかなかったときにポキッと折れてしまうことも心配になります。
だから私は『失敗しても大丈夫だよ』と常に伝えたいと思っています。
頑張る一方で、力を抜ける場所や息抜きも大切にしてほしいと学生に話しています。
 小西琴絵 准教授
小西琴絵 准教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
小西先生、本日はありがとうございました!