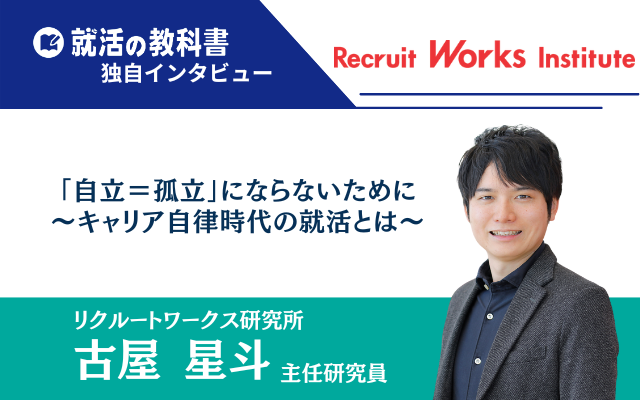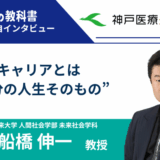「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの小林です。
本日は、リクルートワークス研究所主任研究員の古屋星斗さんにお話を伺いました!
この記事を読めば、「キャリア自律とは?」や「企業選びのポイント」について知ることができます。
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
古屋さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
古屋 星斗(ふるや・しょうと)
リクルートワークス研究所 主任研究員
2011年一橋大学大学院社会学研究科 総合社会科学専攻修了。
同年、経済産業省に入省。産業人材政策、法案作成、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。
2017年より現職。労働市場分析、未来予測、若手育成、キャリア形成研究を専門とする。著書に「ゆるい職場-若者の不安の知られざる理由」(中央公論新社2022)、「なぜ『若手を育てる』のは今、こんなに難しいのか」(日本経済新聞出版2023)、「『働き手不足1100万人』の衝撃」(プレジデント社2024)、「会社はあなたを育ててくれない」(大和書房2024)。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。
目次
リクルートワークス研究所 古屋 星斗さんにインタビュー①:キャリア自律の時代に起きている問題とは?
自分のキャリアは自分で選ぶ時代
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
古屋さんが「労働」や「キャリア」について研究されるなかで、現代の労働環境に対してどのようなことを感じていますか?
私は、よく「自立が孤立になってはいけない」と言っています。
現代社会は、AIをはじめとして技術の進化がものすごく早い。
ほんの1〜2ヶ月で使えるソフトやプラットフォームが変わることもあるでしょう?
それに、企業の状況も主力商品が変わったり、部署の仕事内容が大きく変わったりしていて、とにかく変化が激しいのです。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
AIの登場をはじめとして、環境がすごく変化しているのを感じますね。
そういった社会では、一人ひとりが“自分のことを自分で考える”ことを求められるようになってきてます。
これまでみたいに会社任せでは、もう安心できない。転職や投資など、自分で決めなくてはいけないことが増えています。
キャリアの自由度が増えた一方で、判断力も必要になってきているのです。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
選択肢が増えたからこそ、しっかりと自分で選択する必要が出てくるのですね。
“自立”を“孤立”にしないために
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「自立が孤立になってはいけない」というのは、どういうことでしょうか?
今の時代、“キャリア自律”という言葉が注目されてますけど、これは裏を返せば“孤立しやすくなる”ということです。
自分のことで頭がいっぱいになって、誰にも相談できなくなる。
頑張れば頑張るほど、SNSの“いいね”が減っていく感覚に近い。
そういう孤独が広がりやすい社会になってきているなと感じています。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「一人でなんとかしよう」と思って一人で抱え込んでしまいますよね…
だから僕は、“自立を孤立にしない”ことが今とても重要だと思っています。
キャリアの選択肢が広がるのはいいことですが、それに伴って人とつながる機会や支え合う仕組みを考えていかないと、苦しくなってしまいますよね。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
“実際に行動を起こす人ほど、相談できる相手が減っていく”
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
孤立しやすい人というのは、どのような人が多いのでしょうか?
“実際に行動を起こす人ほど、相談できる相手が減っていく”という現実があります。
組織の中でも、立場が上になればなるほど相談相手がいなくなるものです。
総理大臣や大企業の社長など、社会的に高い地位にいる人こそ、実は孤独な立場にあるわけです。
逆に、一社員である間は相談相手は多く存在します。
しかし、組織の上に行けば行くほど、また、自分の意思で行動を起こそうとすればするほど、同じような立場の人が減っていく。
そのような中で重要になるのが、“共に挑戦できる仲間”の存在です。一人で頑張るのではなく、誰かと協働することが求められます。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
「頼れる人がいること」が本当の自立
また、日本社会においては“自立”という言葉が誤解されていると私は感じています。
アメリカではキャリア自律とは、具体的な行動を伴うものです。
たとえば、社会人が大学院に進学したり、自主的に勉強会に参加したりといった“行動量”がキャリア構築に直結しています。
一方、日本では“自立”が単なるマインドセットや精神論に留まりがちです。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
私も“自立”というとマインドセットのようなものだと思っていました…
また、アメリカでは“相談できる人がいるか”という点でも日本と大きな差があります。
日本では“自立=一人で頑張ること”という誤解が根強いですが、これは大きな間違いです。
真にキャリア自律している人とは、まず“頼れる人を見つけている人”です。そしてその上で、自らの体験や経験を積み重ねていく。
これが、本来あるべき“キャリアの自立”だと思います。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
一人で抱え込むのではなく、周りに頼って行動できる人が真に“自立”している人なのですね!
リクルートワークス研究所 古屋 星斗さんにインタビュー②:情報過多の時代が生んだ新たな課題
職場環境改善と若手育成のジレンマ
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
今は「昔に比べて働きやすくなった」と思いますが、実際にはどうなのでしょうか?
現在、日本の企業では労働時間の短縮が進んでいます。
これは法改正などによって、“早く帰る”ことが徹底されるようになった結果です。
また、ハラスメント対策も非常に強化され、職場環境は改善されています。
これ自体は非常に重要な進展であり、社会にとっては歓迎すべき変化です。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
法改正によって制度として働きやすくなっていますよね!
しかしその一方で、従来のように現場で“ビシビシ鍛える”ようなOJT(On-the-Job Training)が実施しづらくなってきているのも事実です。
例えば以前であれば、多少厳しい指導も含めて若手を成長させる文化がありましたが、今はそれが難しい。
結果として、若手に十分な成長の機会を提供できない“ゆるい職場”が生まれてきているのです。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
離職率上昇の背景にある“見えない不安”
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
労働環境が整備されている中にも関わらず、自分のキャリアについて悩んでいる人は多いように感じます…
結局のところ、多くの人が不安を感じるようになってきています。
現代社会は非常に変化が激しく、個人にとっても転職などのキャリアイベントが起こりやすい環境になっています。
SNSでは、自分のキャリアや活動を発信する人が増えています。
副業で成功した話やメディア掲載の報告など、見栄えの良い情報ばかりが流通していますよね。
そのため、たとえ自分が何も変化していなくても、周囲の“変化”や“成果”を見て焦りを感じてしまう。
これは現代的なキャリア不安の大きな要因です。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
自分が転職したいから転職するのではなく、「みんなが転職しているから転職しなきゃ」と焦ってしまうのですね…
興味深いのは、労働環境そのものは改善されているにもかかわらず、大手企業を中心に離職率が上昇しているという事実です。
これは、外的な条件に加えて、内面的な“不安”や“焦り”が引き起こしていると考えられます。
いわば、情報過多の時代が生んだ新たな課題と言えるでしょう。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
“不安”は行動の源となる
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
周りの変化に対して不安や焦りに対して、どのように対処したらいいのでしょうか…?
焦りや不安を感じること自体は、決して悪いことではありません。むしろ、それは非常に人間らしい自然な感情です。
実際、「将来の仕事や生活を明確にイメージできていない」と答える社会人、特に39歳以下の層では、7割近くにのぼるというデータもあります。
つまり、多くの人が漠然とした不安を抱えているというのが現実です。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
不安を感じているのは自分だけじゃないんですね!
面白いことに、仕事に対して不安を抱く人の方が、まったく不安を感じない人よりも行動量が多いことが分かっています。
さらに、その後のキャリアや年収にも良い影響を与えているという研究結果もあるのです。
つまり、“もやもやした気持ち”や“不安”は、よりよい人生を目指すためのエネルギーになり得るのです。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
大切なのは“共有できる相手”の存在
ただし、不安や焦りそのものよりも重要なのは、それを“誰かと共有できるかどうか”です。
共感してくれる仲間や、安心して話せる相手がいるかどうかが、個人の心理的な安定や成長に大きく関わってきます。
不安を持つことは自然なことです。
しかし、それを抱え込まず、話し合える環境や関係性を持てているか。そこにこそ、本質的な問いがあると思います。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「キャリア自律は一人じゃできない」というのはここにも繋がっているのですね!
リクルートワークス研究所 古屋 星斗さんにインタビュー③:行動と体験がキャリアを作る
情報は無料、差がつくのは“自ら行動し得た実体験”
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
“キャリア自律”が求められる中で、どのような姿勢が大切になってきますか?
私はずっと「情報よりも行動が大事だ」と伝えています。
現代は情報化社会であり、AIやSNSを通じて、あらゆる情報が無料で簡単に手に入る時代です。
しかしその反面、誰でも同じ情報にアクセスできるため、その情報自体の価値は相対的に下がっているとも言えます。
私自身の研究でも、情報が多いことによるアドバンテージは、わずかな行動によって簡単に覆されることが明らかになってきています。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
情報が簡単に手に入るからこそ、その価値が下がっているのですね…
ですから、いま重要なのは“n=1”の自分自身の体験や経験を重視する姿勢です。
無限の情報が容易に手に入る時代だからこそ、他者と差がつくのは、自ら行動し得た実体験です。
そこにこそ、大きな価値があると考えています。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
“n=1”の体験が持つ意味
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
情報が溢れる中で、その情報を活かすということは難しいのでしょうか?
無限に情報が手に入る現代において、その環境をうまく活かせる人というのは、結局のところ“n=1”の体験や経験をしっかり積んでいる人なんです。
AIの*ハルシネーションのように、どの情報が正確で、どれが信頼できないのか。正しさが見えづらくなってきているのが現実です。
言い換えれば、“何が正しいか”が分かりにくくなっている時代とも言えるでしょう。
(*ハルシネーション…AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘や幻覚のような情報を生成する現象)
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
AIに聞けばすぐ情報が得られるのは便利ですが、それが正しいかどうかはなかなかわかりませんよね…
そうした情報の洪水の中で、地に足のついた判断ができる人というのは、自らの体験や経験に裏打ちされた“実感のある軸”を持っている人です。
その軸があるからこそ、自分にとって意味のある情報を選び取り、活かすことができるのだと思います。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
経験による“実感のある軸”こそが、自分にとっての力になるのですね!
“小さな行動”がキャリアを切り拓く鍵になる
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
“行動して経験を積む”には、どのようなことをしたらいいのでしょうか?
社会人になった後、自分のキャリアに納得し、満足して働けるかどうかには、“学生時代にどのような経験をしてきたか”が大きく関係してきます。
現代社会は情報過多の時代です。だからこそ、“小さな行動(スモールステップ)”を実践する価値がますます高まっているのです。
何かを始めようとするときに意味があるか不安に思うこともあると思います。
しかし、 そこから得られる実感や知見が、キャリア形成における貴重な材料になっています。
何かに悩んだ時は、「自分は〇〇に向いているのではないか」という仮説を立て、インターンに参加する、人に会って話を聞くといった小さな行動で、その仮説を検証していくことが大切です。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
大学生活では、授業だけでなく課外活動も重視されていますよね!
大学生は、ある意味で“ノーリスク”で多様な経験を積むことができる立場にありますよね。
ですから、規模の大小を問わず、さまざまなことに挑戦し、体験を通じて行動し、情報をコストパフォーマンスよく得ていくことが非常に重要です。
私は、学生にはそのような“動きながら学ぶ姿勢”を強く勧めたいと思います。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
“向いていないこと”の発見が未来を導く
キャリア選びにおいて“やりたいこと”を探すのはもちろん大切ですが、同じくらい“やりたくないこと”や“苦手なこと”を見つけることも重要です。
むしろ、自分が“これは違う”と感じたことの方が、自分の軸を見つけるきっかけになります。
私自身、大学時代にスタートアップで働いた経験を通じて、『自分はこの世界は向いていない』と痛感しました。
ビジネスの現場で感じた違和感が、今の研究者としてのキャリアにつながっています。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
古屋さん自身も、挑戦を通して今のキャリアに繋がっているのですね!
リクルートワークス研究所 古屋 星斗さんにインタビュー④:就活における企業選びの3つの視点
就活のポイント①:寄り道と偶然を許容する
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
選択肢が多い中で、就活生はどのように企業を選んだら良いのでしょうか?
今の就職活動は、非常に多くの選択肢があります。それは素晴らしいことではありますが、同時に悩みや迷いも生じやすい状況です。
企業側も採用意欲が高く、複数社から内定を得る学生もいれば、1社からの内定に不安を感じる学生もいます。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
就活が早期化したり、内定を複数社からもらうのが当たり前にもなってきていますね。
内定を複数貰うことがキャリアの成功に繋がるわけではないのですけどね。
現代は“近道”を選びやすい時代です。
自分の希望に合った会社・職種、自分で選べる制度。
しかし、キャリア理論で知られる“プランド・ハップンスタンス・セオリー(計画的偶発性理論)”が示すように、偶然の出会いや予期せぬ出来事が将来に大きな影響を与えることも少なくありません。
希望と異なる配属や予想外の業務から成長や成功が生まれることも多く、むしろ自分で選べることが増えたからこそ、そうした偶然を与えてくれるような環境を選ぶことが重要だと言えます。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
近道だけが正しいのではなく、偶然の寄り道に成功があったりするのですね!
就活のポイント②:ライバルの存在
次に重視すべきは、“ライバルがいるかどうか”です。
同じ職場で互いに切磋琢磨できる存在は、仕事への満足度や将来的な幸福度に大きく影響することが、金沢工業大学・金間先生の研究でも明らかになっています。
現代の若者には“仲間”はいても“ライバル”が少ない傾向があります。
だからこそ、面接や説明会で“ライバルになり得る人材がいそうか”という視点で企業を見ることも、キャリア選びにおいて有効です。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
尊敬できる人がいるかどうかは聞いたことがありましたが、“ライバルがいるかどうか”という視点はなかったです!
ライバルとは、決して“敵”ではありません。
自分にとって“近い存在”だからこそ、悔しさやモヤモヤといった感情が湧くのです。
私は若手と話す時によく伝えるのですが、「誰かに対して悔しいと感じる」というのは、実は自分が成長している証でもあります。自分でも「あれくらいできるのではないか」と思えるからこそ、その感情が生まれるのです。
つまり、悔しさやもやもやを抱けるということは、今の自分と相手の距離が近づいているということ。
その感情をポジティブなエネルギーに変えられるなら、ライバルの存在は人生において非常に貴重な要素になるのです。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
悔しさは自分の成長につながるのですね!
就活のポイント③:共感と“違和感”のバランス
最後は、“共感と違和感”です。
多くの人が感じるその企業の魅力(例:待遇・福利厚生、風通しの良さ、新規事業の豊富さなど)に共感することも大切ですが、それだけで終わらず、自分だけが感じる“推しポイント”=独自の魅力を感じているかどうかが、入社後の満足度を左右します。
企業口コミサイトなどで情報を得ることも大切ですが、ほかの就活生からは違和感を持たれるかもしれないような、“自分だけが感じているかもしれないその会社の魅力”を持てた企業こそが、自分にとって本当に合った職場である可能性が高いことが調査からわかっています。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
“違和感”も自分の中での大切な要素なのですね!
リクルートワークス研究所 古屋 星斗から就活生へのメッセージ:「就職活動は“最後”ではなく“最初”の選択」
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
古屋さん、ありがとうございました。
最後に、就活生へのメッセージをお願いします!
現代は“選択の時代”、就活はもはや“人生最後の選択”ではありません。むしろ、“最初の選択”になってきています。
したがって、就活の目的は単に「内定を得ること」ではないのです。
むしろ、相談できる人と出会う、良いライバルを見つける、自分のエネルギー源となるものを発見する、さまざまな体験を重ねる。
こうした“キャリア資本”を小さく積み重ねていくことが、将来の幸せなキャリアにつながります。
 古屋 星斗さん
古屋 星斗さん
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
素敵なお話をたくさんありがとうございます!
古屋さん、本日は本当にありがとうございました。