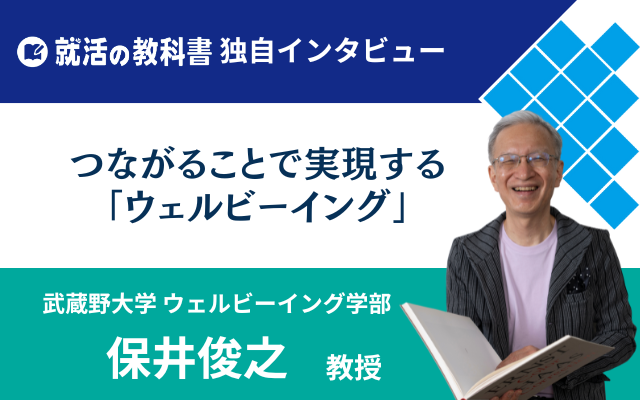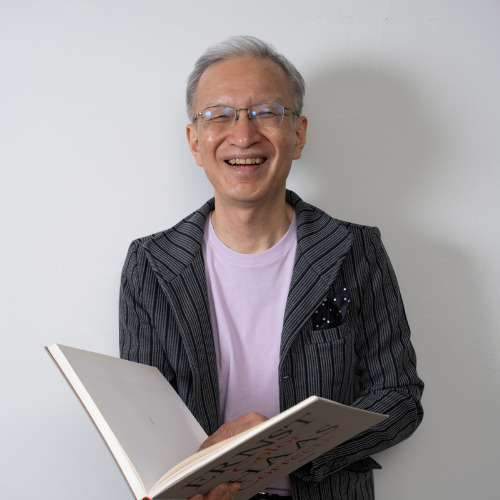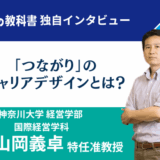「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの野口です。
本日は、武蔵野大学 ウェルビーイング学部 保井俊之教授にインタビューしました。
保井先生、本日はよろしくお願いします!
よろしくお願いいたします。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
保井 俊之(やすい・としゆき)
武蔵野大学 ウェルビーイング学部 教授
1985年東京大学卒、財務省および金融庁等の主要ポストやパリ、インド並びにワシントンDCの国際機関や在外公館等に勤務したのち、地域経済活性化支援機構常務取締役、国際開発金融機関IDBの日本ほか5か国代表理事等を歴任。慶應義塾大学大学院SDM特別招聘教授等を2008年から兼務。2021年~24年に広島県立の叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部の初代学部長。米国PMI認定PMP、地域活性学会副会長、ウェルビーイング学会監事兼学会誌編集委員会委員長。日本ポジティブサイコロジー医学会評議員。
目次
武蔵野大学 保井俊之教授にインタビュー①:自身の経験から見えた課題
財務省での経験を経て
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
保井先生は、財務省を経て現在の研究に至っているということですが、その当時のことについて教えてください。
本当は大学卒業後すぐに大学院に進学して将来は研究者になりたかったのですが、家計の都合もあり、財務省(旧大蔵省)に就職しました。
面接で印象的だったのは、「財務省には日本中の課題という課題が集まる」という言葉です。
予算、税や財政投融資などお金が関わるところには、複雑で絡み合った人々の利害や感情が絡まり、解決が容易ではない複雑な課題になって持ち込まれて来る。それらを一つひとつ解決していくのが財務省の仕事だと聞いて、興味を持ちました。
最初は10年ほどで研究者を目指す世界に戻ろうと考えていましたが、「問題を解く」という仕事があまりにも面白く、やりがいがあり、そのまま35年勤め上げました。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
財務省には日本中の課題が集まっているのですね。
お仕事をする中で、どのようなことを感じましたか?
ワークライフバランスという言葉もない時代でしたから、ほぼ毎日昼夜を徹して働き続けました。仕事をチームで進めることにやりがいを感じていました。しかしあるとき、気づいたのです。東京の霞が関や丸の内などにいて官庁や大企業で働く、とても優秀で人柄もとてもよく、優しく頼もしくて誠実な同僚や友人たちの働きぶりが、ストレスが多く、どうも幸せそうに見えないことに。
その理由は「仕事を自分で決められない働き方」にあると感じました。役所や大企業の仕事の多くは、「天から」ある日降ってきて、黙々とこなすものという感覚がわたくしにはあります。自己決定と自己実現は実は、幸せつまりウェルビーイングの源泉なのですが、そこには自己決定も自己実現も少なく、自分で選んでいる感覚がありません。
「人は自分で決め、自分で成長できるときにこそ、幸せに働けるのではないか」。
そう思ったことが、現在の「ソーシャルシステムデザイン(社会の仕組みづくり)」と「ウェルビーイング(心身社会の幸せ/良い状態)」の研究につながっています。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
国家公務員時代に“自己決定と自己実現ができる仕事”を模索する中で「ウェルビーイング」に興味を持たれたのですね。
日本の多くの組織では、働く人々がどこか閉塞感を抱えており、あまり幸せそうに見えない——それが私の強い問題意識の出発点です。
この閉塞感を打ち破るには、どのような仕組みを作り、提案するスキルがあるといいのか。
それを探る研究ができないかと考えるようになりました。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
9.11テロを「生き残ってしまった」経験が、自分を変えた
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
確かに、しんどそうな会社員はドラマなどでもよく描かれたりしますよね。
研究に携わるようになった経緯について教えてください。
2001年9月11日、私は出張中にアメリカ・ニューヨークのワールドトレードセンターの中にいました。
あの同時多発テロの瞬間を現地で経験し、多くの人の命が失われる中、私はたまたま生き残ってしまいました。
その出来事は私に深い衝撃とその後PTSDをもたらしましたが、テロの犯人を憎む気持ちはまったくなく、やがて「なぜこんなことが起きたのか」「何が原因だったのか」を知りたいという思いに変わっていきました。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
9.11の現地にいらっしゃったのですか?言葉が出ないです…
9.11の背景には、貧困、憎悪、暴力といった複雑な因果関係のループがありました。 それを“逆回し”にして「平和や希望を生み出す良い循環に変える方法はないのか?」と考え始めました。
その探究の中で出会ったのが「システム思考」と「デザイン思考」でした。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
同時多発テロを経験した上で、悪循環を良循環に“どう変えていくのか”と探究されていたのですね。
ウェルビーイング実現に向けて、仕組みから変えていく
私は財務省で働きながら、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)で、夜間と週末に無給の教員として研究・教育の活動を始めました。
「ものごとをつながり、すなわちシステムとして捉え、全体のつながりを俯瞰することで問題解決を行う」システム思考や「ありたい未来を自ら協創する」デザイン思考を学び、教え、教科書を出し、社会課題の構造的な解決に挑む教育・研究を行っていきました。
しかしある時、ふと考えました。 「私は何のためにシステム思考やデザイン思考を使って問題解決をしているのか?」
その答えは、「人と地域と地球が良い状態であるため」でした。
つまり、人と地域と地球が良い (well) 状態 (being) でいれる——ウェルビーイングの実現こそが、すべての社会問題の解決の本質ではないかと気づいたのです。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
そこで、「ウェルビーイング」に着目されたのですね。
2016年頃からは、人間、地域、地球が良好な状態であること、つまり「ウェルビーイングな状態」をデザインすることを目指し、
- 貧困
- 環境問題
- 暴力
- 偏見
といった社会課題をシステム的に解決する新しい仕組みづくりの教育と研究に取り組むようになりました。
それが、現在の研究・教育テーマです。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授にインタビュー②:「ウェルビーイング」とは?
身体と心と社会での状態が心地よく、幸せだと感じられる状態
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
保井先生にとって、「ウェルビーイング」とはどのようなものでしょうか?
私が研究で用いているウェルビーイングは、“主観的ウェルビーイング”と呼ばれるもので、「自分の心で感じる幸せ」を指します。
学問的には、「身体的・精神的・社会的に良好な状態」あるいは「人生の心理的・認知的な評価」とも定義されます。
わかりやすく言えば、「ハツラツ、ウキウキ、イキイキ」、ハツラツ=身体的ウェルビーイング、ウキウキ=精神的ウェルビーイング、イキイキ=社会的ウェルビーイングが三位一体であること、「身体と心と社会での状態が、心地よく、幸せだと感じられる状態」と捉えてもらえればよいでしょう。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「身体と心と社会での状態が、心地よく、幸せだと感じられる状態」がウェルビーイングなのですね。
私の「幸せの原点」、いわばウェルビーイングの出発点は、瀬戸内海の町で過ごした子ども時代の夏でした。
祖父母の家にひと夏預けられ、青い海や緑の山、さんさんと輝く太陽の下で、海水浴をしたり、貝を採ったり、みかん畑で遊んだりした体験が、私にとって「心から幸せだ」と感じる感覚の土台になっています。
その「原体験」こそが、今の研究テーマである「ウェルビーイングな社会をどう実現できるか」を考える原動力になっています。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
とても素敵な原動力ですね!
“精神的健康”という観点では、心理学と近しいものがあるのでしょうか?
ウェルビーイングの研究は、もともと「ポジティブ心理学」という学問から始まりました。
これは、2000年ごろから広がった比較的新しい心理学で「普通の人が、より幸せに生きるにはどうしたらいいか?」という視点から、心身社会の健康や幸福感を研究する分野です。
私の思い込みかもしれませんが、それ以前の心理学が「心の不調にどう対応するか」に主に焦点を当てていたのに対し、ポジティブ心理学は「普通の生活をしているひとが、よりよく幸せに生きるにはどうしたらよいか」を追求しています。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
ポジティブ心理学は人生をよりプラスにしていくイメージなのですね。
ポジティブ心理学の広がりとともに、ウェルビーイング研究も進化していきました。
最初は「個人の心の状態」が中心でした。次に「学校や職場などの組織全体のウェルビーイング」へと拡大していき、現在(2020年代)は「社会全体の幸せ=ウェルビーイング3.0」をどう実現するかが研究の主流になっています。
地球環境(エコロジー)や、地域社会の持続可能性といったグローバルな課題とも連動する、大きな視野を持つ学問領域になってきているのです。
私自身は「主観的ウェルビーイング(人が「幸せだ」と感じる心の状態)を高めるには、どういった社会の仕組みすなわちシステムが必要で、それをテクノロジーがどう加速できるのか?」をテーマに研究しています。
つまり、「人と人」「人と地域」「人と社会」「人と自然」が、より良い関係を築くためには、どんなシステムのデザインが必要か。そうした視点から、社会全体のウェルビーイングを高める方法を探っているのです。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「社会全体の幸せを追求する」とは、とても素敵な研究ですね!
ウェルビーイング実現のカギは「全体を俯瞰すること」と「つながりをつくること」
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「社会全体のウェルビーイング」を実現するためには、どのようなことが必要なのでしょか?
まず一つは、「全体が見えること」です。
世の中は、人と人、人と自然、組織や社会など、さまざまな要素がつながり合ってできている「システム」です。 この「つながりの構造を理解すること=システム全体を俯瞰する力」がとても重要です。
なぜなら、社会を構成する要素のつながり、すなわち社会システムの全体が見えないままでは、自分が何に影響され、どこに向かっているのかがわからず、無力感や閉塞感につながってしまうからです。
逆に、自分がどこにいて、どうつながっているかが見えると、「主体的に生きている実感」が生まれ、よりよく動くことができるようになります。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
世の中を“つながり”で捉えることが重要なのですね。
もう一つの鍵は、「ポジティブなつながりをつくること」です。
有名なハーバード大学の「成人発達研究」では、長く幸せかつ健康に生きる人の特徴は、「お金」でも「地位」でもなく、“良好な人間関係=ポジティブなつながりを持っていること”だったと報告されています。
これは人と人とのつながりに限らず、人と自然との関係にも当てはまります。 自然とのふれあい、つながりもまた、心身社会の健康=ウェルビーイングの源泉です。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
人と社会だけでなく、自然とのつながりも重要なのですね。
ウェルビーイング実現の「第3のカギ」は、“成長”と“自己実現”
これまで「全体を俯瞰すること」「つながりをつくること」がウェルビーイングを実現する鍵だと話してきましたが、実はもう一つ、大切な要素があります。
それが、「人として成長し何かを成し遂げること」=成長と自己実現です。
では、どうすれば人は成長できるのか?
大切なのは、次の3つです。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
-
自己決定:自分で「こうしよう」と決めること
-
学びと成長:決めたことに向かって学び続け、何かを成し遂げること
-
やり抜く力 (グリット):最後まで粘り強くやり抜くこと
この3つが組み合わさると、人は内側から変わっていき、より高い次元でのウェルビーイングを実現できるのです。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
自己成長することで、さらにウェルビーイングを実現できるのですね。
私の研究では、こうした「人の成長を支える仕組み=学び・つながり・自己実現のデザイン」をどう社会や組織の中で実現するか?ということもテーマとしています。
それは単に会社や社会の制度やルールを変えることではなく、「一人ひとりが自分で決めて、他者とつながり、自分の未来をつくっていく」デザインのスキル、つまりソーシャルシステムデザインのスキルを会得していくことです。
そんなウェルビーイングの循環が起きるデザインのスキルを広めていくことを目指しているのです。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
自分のウェルビーイングが他者にも広がり循環していくのはとても素敵ですね。
武蔵野大学 保井俊之教授にインタビュー③:「ウェルビーイング」を高めるために
自然とつながることで心が満たされる
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
自身の「ウェルビーイング」を高めるために、どのようなことが大切なのでしょうか?
ウェルビーイングを高めるために大切なのは、学び・成長・自己決定だけではありません。
自然とのつながりもまた、心の状態を大きく改善する要素です。
例えば、週末に山や森へ行くことはもちろん、2週間に1度、公園に行くだけでも主観的ウェルビーイング(幸福感)が向上するという研究があります。
また、自然とのつながりを意味する「ネイチャー・コネクティッドネス」という概念では、
-
自然との一体感が感じられる
-
自然に触れることで注意力が回復する
-
大きな自然だけでなく、小さな自然(盆栽や観葉植物)でも効果がある
という結果が示されています。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
山や川に行って自然に触れるだけでなく、街の中の公園のような身近な自然でも効果が感じられるのですね。
人の幸せには、大きく分けて2つの形があります。
-
人と人とのつながりによる楽しさ(例:お祭りや仲間との時間)
-
自然や自分自身との対話による静かな満足感
後者は一人で森を歩いたり、公園で過ごしたりして、内省的に自分と向き合う時間です。
都会の中でも週末だけ自然に触れるだけで、この静かな幸せを感じることができます。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
私自身も社会人になってから自然と触れ合う時間が減ってしまったので、意識的に触れ合っていきたいですね。
自然との関係を「人間対自然」と捉えると、自然は利用する対象になってしまいます。
そうではなく、「人間は自然の一部」だと感じることが大切です。
この感覚があることで、自然と一体になり、より深い幸福感が得られます。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
お金とウェルビーイングの関係:ファイナンシャル・ウェルビーイング
アインシュタインも「人類最大の発明は金利」と評したほど、お金は人類が発明した大きなテクノロジーです。
しかし、おカネは人を幸せにしない、おカネがないと幸せになれれない、と二つの声が聞かれ、意見は分かれます。
実際には、お金自体は中立的なテクノロジーであり、「どう稼ぎ、どう使うか」によっても幸福度は変わります。
最近注目されているのが「ファイナンシャル・ウェルビーイング」という考え方です。
これは、「お金を上手に使うことで幸福を実現しよう」というもので、ポイントは、お金の“種類”と流れ方にあります。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
お金は幸福度に大きく関わるものですね!詳しく教えていただきたいです。
作家ミヒャエル・エンデは、お金を2つに分けています。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
-
資本のお金
株式市場などで高速に回転し、利益を生むためのもの。 -
ありがとうのお金
パン屋でパンを買って「ありがとう」と手渡すような、人と人を温かくつなぐお金。
現代では円やドルやユーロなどの法定通貨、つまり資本のお金が注目されがちですが、地域に住むひとたちの気持ちを温め、恩送りや恩返しに使われる「ありがとうを伝えるためのおカネ」も昔から存在しており、地域通貨や「雪下ろしを手伝ったら、翌朝玄関先に誰からのとも知れず置いてくださっていた野菜いっぱいの段ボール箱」のような感謝のトークンの形で受け継がれています。
法定通貨の資本のおカネとは別に、「ありがとうのお金」を循環させて人と人をつなぎ、地域全体のウェルビーイングを高める仕組みをどう作るか。
私はこのテーマを10年以上研究しており、経済活動と人間の幸福をテクノロジーがつなぐ新しいモデルを模索しています。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「地域通貨」というのは、その国で使用されている通貨ということでしょうか?
おカネと呼ばれるものは、日本円やドルなどの法定通貨だけではありません。
地域限定で使える「地域通貨」という仕組みがあります。これは普段、日本円として使っているお金ではなく、「ありがとう」や「おすそ分け」などの共感や感謝の気持ちを循環させるための社会的な道具です。
例えば、われわれの研究結果によると、神奈川県鎌倉市や広島県三原市などの地域では、地域通貨や分散自立型組織 (DAO) と呼ばれるWeb3.0という新たな電子プラットフォームを通じて人々がつながり、地域により愛着を持ち、熱心に地域活動を行うようになっています。
買い物だけでなく、地域の文化や歴史を体験し、人と交流するきっかけにもなります。
われわれの研究からわかっているのは、地域通貨がウェルビーイングを高めるには次の3つの要件が大切だということです。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
-
体験 — 物を買うより、ヨガ教室やワークショップなどの「体験」に使う
-
利他 — 自分だけでなく、家族や友人など大切な人のために使う
-
つながり — 地域通貨を通じて地域の人と交流し、つながりを拡大・深化させる
このように、地域通貨やDAO等のWeb3.0は単なる経済活動を超え、人と人とのつながりを育みながら幸せを広げる仕組みとして注目されています。
就活生にとっても「人をつなぎ、幸せを増やす仕組みづくり」は、これからの社会で重要なテーマのひとつになるでしょう。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
その地域に馴染みがない人でも、「地域通貨」や「Web3.0」によって交流ができたら幸せが広がりそうですね。
幸せな人は創造的で成果も出す
これまでの研究によると、ウェルビーイングが高い社員はそうでない社員に比べて、
-
創造性(クリエイティビティ)は約3倍
-
生産性(エフェクティビティ)は約30%アップ
という結果が出ているそうです。
つまり、幸せであることが仕事をやる上での「能力」や「成果」にも直結するということ。
まず自分が「ウェルビーイングである」ことは、遠回りなようでいて、実はとても合理的でクリエイティブなキャリア戦略でもあるのです。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
ウェルビーイングが高い人は創造性も生産性も高いのですね!
武蔵野大学 保井俊之教授から就活生へのメッセージ
就活は「つながり」と「成長」のチャンス
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「ウェルビーイング」についての素敵なお話をありがとうございました!
最後に、就活生へのメッセージをお願いします。
人とつながることは、幸せの源泉です。
就活もまた、今まで出会ったことのない人や世界とつながる機会です。そのつながりを通じて、自分の成長のきっかけを得られると考えてみてください。
就活を「ただ何社も回ってエントリーシートを書く作業」としてではなく、「新しい人や世界と出会い、自分の視野を広げ、ひとつ上のステージに進むためのプロセス」と高い視野の意義として捉えることが大切です。
就活は人生で一度きりの出来事ではありません。
今後も形を変えて、何度も「成長」と「自己決定」の機会は訪れます。就活はその最初のステップです。そして次のステージへ自分が成長するために、次の就職の機会を探す、というように自らを高めていく就活の機会はこのあとの人生で何回も訪れるかもしれせん。
だからこそ、自分なりの目的や意味を見つけながら、この経験を「ウェルビーイング」につなげていきましょう。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
成人発達理論から見る「就活」という成長のステージ
人は子どものときだけでなく、大人になってからも成長できます。
成人発達理論(ロバート・キーガン氏の研究をはじめ多くの研究があります)によると、大人の成長には大きく3つの段階があります。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
-
指示されたことを正確にこなせる段階
「社会的な自己」と呼ばれ、他者や組織、社会の価値観や期待を自分の内面に取り込み、それに従って行動する段階です。まずは上司や先輩に言われたことをできるようになること。しかし意外と難しく、ここでつまずく人も多いです。 -
自分で考え、リーダーシップを取れる段階
「自己主導的な自己」と呼ばれ、自分自身の価値観や信念を形成し、それに基づいて意思決定を行う段階です。指示を待たずに、自分から課題を見つけ、リーダーシップを以て動けるようになります。このレベルに到達できる人は限られています。 -
全体を俯瞰し、最適な行動を選べる段階
「自己変容的な自己」と呼ばれ、自分の信念や枠組みすら相対化し、柔軟に再構築できる段階です。異なる価値観やシステムを俯瞰的に捉え、複数の枠組みを統合しながら思考・行動します。組織や社会全体の動きを理解し、自分の行動が全体にどう影響するかまで見える状態です。ここに到達できる人はごくわずかです。
そして大人になってから成長のきっかけは、多くの場合「逆境」や「チャレンジ」、時にはショックからトラウマになる出来事です。
就活も、時に厳しい現実や挫折に直面する場面があります。しかし、その経験こそが次の成長ステージに進むための土台になります。
「就活での出会いや経験は、自分の成長曲線を一気に引き上げるチャンス」と捉えてみてください。
 武蔵野大学 保井俊之教授
武蔵野大学 保井俊之教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
苦戦していることも、自分が成長する機会と捉えたら前向きに進んでいけそうです!
保井先生、本日はありがとうございました!