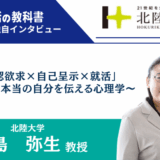「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの小林です。
本日は、拓殖大学の佐藤一磨教授にお話を伺いました!
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
佐藤先生、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
佐藤 一磨 (さとう・かずま)
拓殖大学 政経学部 教授
1982年生まれ。慶應義塾大学商学部を卒業後、同大学院商学研究科後期博士課程単位取得退学(博士〈商学〉)。
外資系経営コンサルティング会社や明海大学での勤務を経て、2016年より拓殖大学政経学部准教授、2023年から教授を務める。
キャリアデザイン教育にも携わり、キャリアデザイン学会所属。近年は「幸福の経済学」をテーマに研究を行っている。
目次
拓殖大学 佐藤一磨教授にインタビュー①:「幸福度」とは?
幸福度はどのように測る?
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
さっそくですが、佐藤先生の専門である「幸福度」の研究についてお伺いしたいです!
幸福度とは、どのように測るのでしょうか?
幸福度の測り方は、とてもシンプルなんです。
「あなたはいま、どのくらい幸せですか?」という質問に、0から10の段階で答えてもらうだけです。
一見すると簡単すぎるように思われますが、この方法は2000年代から世界中で使われており、多くの研究によって信頼性が確認されています。
たとえば、同じ人に数週間後に再び質問しても大きく結果が変わらないことや、「幸せ」と答えた人が実際に笑顔が多い、友人関係が良好など、他の幸福に関わる指標とも関係していることが分かっています。
こうした検証を経て、現在ではこのシンプルな質問が「主観的な幸福度」を測る国際的な基準として広く使われています。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
シンプルな方法で、幸福度を測ることができるのですね!
人の幸福は一生を通じて一定ではなく、年代や人生の状況によって変化していく
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
幸福度に関する研究の中で、興味深い結果はありますか?
幸福度に関する研究の中で興味深いものはいくつかあります。
たとえば、日本を含む多くの国で「女性が子どもを持つと幸福度が一時的に下がる」という結果が出ているんです。
これは日本だけでなく、世界的にも共通して見られる傾向で、データとして示されたときには多くの反響がありました。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
子供ができると、幸福度が上がりそうなイメージがありましたが、一時的に下がるという結果には驚きです…!
また、年齢と幸福度の関係を調べた研究もあります。
アメリカの経済学者デビッド・ブランチフラワー氏の分析によると、世界145か国のデータを集めて調べた結果、人の幸福度はおおよそ48歳前後で最も低くなることがわかっています。
日本でもほぼ同じで、48〜49歳あたりがいわゆる“幸福の谷”にあたります。その後は再び幸福度が上がっていく、いわばU字型のカーブを描くような変化が見られます。
こうした研究から、人の幸福は一生を通じて一定ではなく、年代や人生の状況によって変化していくことがわかります。
データを分析していくと、人間の心の動きや人生の面白さを改めて感じることが多いですね。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
年齢に応じて環境も変わってくるので、幸福度にも影響が大きいのですね。
学生の幸福度はどう変わる?:恋愛と就職活動
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
学生の間に、幸福度の大きな変化は少ないのでしょうか?
学生の場合、人生の中で大きな変化の少ない時期ではありますが、やはり幸福度に影響する出来事はいくつかあります。
たとえば「恋人ができる」といった出来事は、幸福度に大きく関係しています。
統計的なデータは多くありませんが、アンケート調査などを見ると、恋人ができた学生は日常生活がより楽しく感じられる傾向があるようです。
また、大学生活の中で大きな節目といえば、やはり就職活動の時期でしょう。
将来に向けた不安や期待が入り混じる時期であり、幸福感が変動しやすいタイミングでもあります。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
学生に大きなライフイベントは少ないですが、将来への選択を迫られたりと不安と期待でメンタルに大きく影響がありますね…
拓殖大学 佐藤一磨教授にインタビュー②:幸せに生きるために大切な要素とは?
心の通ったパートナーは、幸福度の低下を緩やかにする
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
幸福度が下がりすぎてしまうことを防ぐことはできるのでしょうか?
幸福度が年齢によって下がり、再び上がるという「U字型のカーブ」を描くことは先ほどお話ししましたが、その“落ち込み”を和らげる要因がいくつかあります。
一つは「人とのつながり」です。
特に心の通ったパートナーがいる人は、幸福度の低下が緩やかになる傾向があると分かっています。
落ち込むような出来事があっても、精神的な支えがあることで影響が小さくなるのです。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「パートナー」というと恋人や結婚相手を考えてしまいますが、仲の良い友達でもいいのでしょうか?
結婚やパートナーの存在についての研究では、「何でも話せる関係」であることが特に幸福度を高めると分かっています。
たとえば、楽しいことやつらいことを気軽に話し合えるような関係性があると、精神的な支えが強まり、幸福感がより大きくなる傾向があります。
これは必ずしも恋愛関係に限らず、信頼できる友人との関係でも同じような効果が見られます。
誰かと心を通わせ、安心して話せる人がいること――それが人生の幸福を支える大切な要素の一つだといえるでしょう。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「何でも話せる関係」というのが大切な要素なのですね!
この“支え”は、必ずしも人間だけに限りません。
最近の研究では、ペットを飼うことがパートナーと同じようなプラス効果をもたらすという結果も出ています。
イギリスの研究では、ペットの存在が幸福度を高めることが明らかになっており、「ペットも人生のパートナーになり得る」といえるでしょう。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
言葉を直接交わすことができなくても、パートナーになり得るのですね…!
経済的な余裕があると、幸福度の低下を防ぐことにつながる
もう一つの要因は「お金」です。
もちろん、極端に裕福である必要はありませんが、ある程度の経済的な余裕があると、日常の不安や問題を軽減でき、幸福度の低下を防ぐことにつながります。
経済的な安定や心の支えがあることが、人生の中で訪れる幸福の“谷”を緩やかにする大きな鍵になるのです。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「幸せはお金では買えない」とも言いますが、やっぱりお金も大事ですよね。
体を動かすことで、心の健康と幸福感がつながっていく
また健康面では、定期的な運動習慣が重要です。
運動には身体の健康だけでなく、メンタル面を整える効果もあることが多くの研究で示されています。
最近よく「筋トレがメンタルに良い」と言われますが、それはあながち間違いではないんです。
体を動かすことで、心の健康と幸福感がつながっていくということですね。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
運動すると、体だけでなく心もスッキリするので、やっぱり大切なのですね!
こうした「人間関係」「お金」「健康」という三つの要素を意識的に整えていくことが、長い人生の中で幸福を持続させる鍵になると考えられます。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
拓殖大学 佐藤一磨教授にインタビュー③:キャリアと幸せのバランスとは?
キャリアに必要な視点:「自分の人生の中で家庭をどのように築いていきたいのか」
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
佐藤先生は、外資系の企業で働いていた経験もある中で、学生に「キャリア」についてどのようなことを伝えていますか?
キャリアについて考えるときには、「どんな仕事をしたいか」だけでなく、「どんな家庭生活を送りたいか」も含めて考えることが大切です。
仕事で成果を上げたい、やりがいを感じたいという目標はもちろん重要ですが、それと同じように「自分の人生の中で家庭をどのように築いていきたいのか」という視点も欠かせません。
この二つの目標をバランスよく考え、計画していくことが、結果的に「幸せな人生」につながると私は学生によく伝えています。
キャリアの授業でも、こうした考え方を基本として教科書をもとに話をしています。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
キャリアというと、仕事のことばかり考えてしまって「どんな家庭を築きたいか」はつい忘れてしまいますね…!
妄想でもいいから“自分にとってのベスト”を具体的に描いてみる
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
人生の目標というのは、どのように設定すれば良いのでしょうか?
授業の中では、学生に「10年後、20年後の自分が思い描く“最高の人生”を考えてみてください」と伝えています。
それは仕事の場面だけでなく、私生活も含めて構いません。
たとえば結婚、家庭、住まい、仕事での立場など、人生のさまざまな要素を想像しながら「自分にとって理想的な状態」を思い描いてもらいます。
妄想のようなもので構わないから、とにかく“自分にとってのベスト”を具体的に描いてみることが大切なんです。
そうすると、学生たちは「自分にとって何が幸せなのか」「そのために今、何をすべきか」を自然と考えるようになります。
そうした過程の中で、初めて自分の人生における“最高のかたち”が見えてくるのだと思います。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「何が自分にとって最高なのかな?」と考えることから、どう行動すべきかも見えてくるようになるのですね!
拓殖大学 佐藤一磨教授にインタビュー③:大学でのキャリアデザイン授業
実際に社会で活躍している人を招いて「生の声」を聞く
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
大学でのキャリアデザインの授業では、どのようなことを行なっていますか?
キャリアの授業では、キャリアの考え方を学ぶだけでなく、実際に社会で活躍している方々を招いてお話を伺う機会も設けています。
たとえば、東京消防庁や警視庁で重要な役職を務めた方など、豊富な経験を持つ方々に来ていただき、ご自身のキャリア形成について語ってもらいます。
学生たちはその話を聞くだけでなく、質疑応答や交流を通して、社会人としての考え方や仕事への向き合い方を学んでいきます。
こうした実践的な学びの場を通じて、キャリアというものをより身近に感じ、自分の将来を考えるきっかけにしてもらうことを大切にしています。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
すごい経歴を持った方が来るんですね…!羨ましいです。
毎回の授業が席替え形式:多くの学生と関わりが生まれ、友人関係が広がっていく
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
キャリアデザインの授業を通して、学生からはどのような声がありますか?
キャリアの授業を受けた学生の中には、「友達が増えた」と言ってくれる人が多いんです。
その理由のひとつが、授業の進め方にあります。
毎回50〜60人ほどの学生が参加しますが、席をランダムに入れ替え、初めて会う人同士でチームを組み、ディスカッションを行うようにしているんです。
この形式にすることで、自然と多くの学生と関わりが生まれ、友人関係が広がっていきます。
また、キャリアを築いていく上では、知らない人と積極的にコミュニケーションを取り、考えを伝える力がとても重要です。
そうした能力を育てることも、この授業の大きな目的のひとつになっています。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
大学の講義は、いつも決まった席で決まった友達の近くに座ってることばかりなので、毎回授業で席替えがあるのはすごく面白そうですね!
話をしていく中で、大切なことが少しずつ明確になっていく時間を大切に
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
変化が激しいと言われる時代の中で、キャリアに対してどのような姿勢を持つべきでしょうか?
キャリアを考えるうえでは、「なりたい姿を持ち続けること」と同時に、「状況に合わせて柔軟に見直すこと」が大切です。
学生時代に描いた理想と、実際に働いてから感じる現実は違うこともあります。
そのときに無理に理想にこだわらず、自分に合う方向へ軌道修正できる人ほど、結果的にうまくいくことが多いです。
就職活動でも、柔軟に判断できる人のほうが内定につながりやすいというデータがあります。
理想を持ちながらも、環境の変化に合わせて前向きにキャリアを見直す姿勢が大切だと思います。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
理想はしっかり持ちつつも、変化にも柔軟に対応できるような姿勢が求められるのですね!
拓殖大学 佐藤一磨教授から就活生へのメッセージ:「自分の可能性を信じて、一歩踏み出してみて欲しい」
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
佐藤先生、ありがとうございます!
最後に、就活生へのメッセージをお願いします!
就職活動をしている皆さんに伝えたいのは、「焦らず、広く考えてほしい」ということです。
今の就職活動は、かつてに比べるとスムーズに進むようになり、早めに内定を得られる学生も増えています。
ただ、最初に選ぶ仕事はその後の人生に大きな影響を与えるものです。
だからこそ、限られた期間の中でも、できるだけ幅広い業界や職種に目を向け、自分に合う仕事をじっくり探してみてほしいと思います。
日本では今も「新卒採用」が他の国に比べて有利な仕組みになっています。
その意味でも、少し背伸びをしてでも興味のある企業に挑戦してみる価値はあります。
思い切ってチャレンジすることで、自分の人生が思いもよらない方向に良い変化を遂げることもあるでしょう。
ぜひ、自分の可能性を信じて、一歩踏み出してみてください。
 佐藤一磨 教授
佐藤一磨 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
素敵なメッセージをありがとうございます!
佐藤先生、本日は本当にありがとうございました!