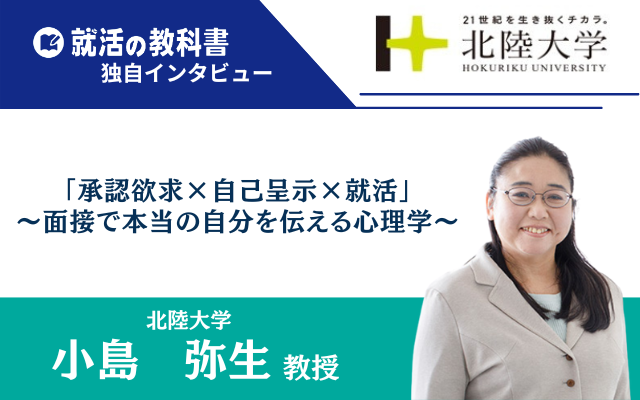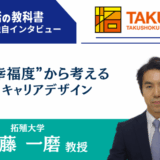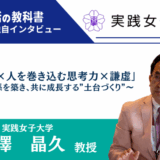「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
こんにちは!「就活の教科書」取材チームのチェです。
本日は、北陸大学の小島弥生教授にお話を伺いました!
小島弥生教授、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
 小島弥生教授
小島弥生教授

小島 弥生(こじま・やよい)
北陸大学 国際コミュニケーション学部・心理社会学科 教授
立正大学心理学部助手、埼玉学園大学専任講師・准教授を経て、2021年より現職。
北陸大学 国際コミュニケーション学部・心理社会学科教授。専門は社会心理学、パーソナリティ心理学、産業・組織心理学。
人の承認欲求(賞賛獲得欲求・拒否回避欲求)が行動や対人関係に及ぼす影響を中心に研究し、「社会・集団・家族心理学」「キャリアの心理学」などを担当。
目次
北陸大学 小島弥生教授にインタビュー①:”承認欲求との向き合い方”「心理学が教える“認められたい”と“知られたくない”心のバランス」
そもそも、承認欲求とは?「”認められたい”、”知られたくない”2つの心の働き」
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
さっそくですが、「承認欲求」とはどんなものですか?
一般的に知られている「認めてもらいたい」「すごいと思われたい」といった気持ちも、承認欲求のひとつです。
一方で、「良いところを認めてほしい」というよりも、「悪いところを知られたくない」「嫌われたくない」という気持ちもありますよね?
例えば、「今、あなたが知っている私でいい。そのままのイメージで見てほしい」と思う感覚。
これも立派な承認欲求です。
 小島弥生教授
小島弥生教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
承認欲求は「認めてもらいたい」という気持ちだけだと思っていました。
そう感じている人は多いと思います。
しかし、世間的に言われる承認欲求と、心理学の研究で扱う承認欲求は少し違います。
「今の自分をそのまま受け入れてほしい」「これ以上は見せたくない」という感覚も、心理学的には承認欲求に含まれます。
私は「このような自分の弱さを知られたくない」という側面の承認欲求に注目して研究しています。
本日は、主に「見せたくない自分を守ろうとする承認欲求」の側面についてお話ししたいと思います。
 小島弥生教授
小島弥生教授
承認欲求自体は悪くない?「就活における承認欲求との上手な付き合い方」
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
「自分は承認欲求が強いのではないか」と感じている学生も多いですが、ポジティブに捉えてもいいのでしょうか?
そういった学生に、私は著名な心理学者である「聖心女子大学の菅原健介先生」のアイデアを引用して説明しています。
承認欲求には大きく2種類あります。
一つ目は「自分の良いところを認めてもらいたい」という賞賛獲得欲求。
もう一つは「自分の悪いところを知られたくない」「嫌われたくない」という拒否回避欲求。
菅原先生は、承認欲求を車に例えると、「賞賛獲得欲求は車の“アクセル”、拒否回避欲求は“ブレーキ”」として表現しています。
どちらも行動をコントロールするために必要ですが、バランスが大事ですよね?
賞賛獲得欲求が強すぎると、アクセルを踏みすぎて暴走してしまう。
逆に拒否回避欲求が強すぎると、ブレーキを踏みっぱなしで動けなくなってしまいます。
 小島弥生教授
小島弥生教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
バランスを取ることが要点ですね。
就活でも同じです。
「自分の弱みを知られたくない」と思いすぎると、何もアピールできず、企業に自分の魅力が伝わりません。
一方、「自分はこんなにすごい」とアピールばかりしてしまうと、企業との“コミュニケーションのキャッチボール”ができなくなってしまいます。
就活は自分をアピールする場でありながらも、一方的ではなく双方向のコミュニケーションであることを忘れないでください。
承認欲求は「自分をよく見せたい」という想いが形になったもので、決して悪いものではありません。
うまく使えば、就活における大きな原動力(アクセル)になります。
ただし、加減がとても大事です。
思い込みが強すぎると空回りしてしまう。
自分の中の“アクセルとブレーキ”を上手に使い分けることが、成長につながると思います。
 小島弥生教授
小島弥生教授
”承認欲求=自己中心的”は誤解?「本来の承認欲求”の意味」
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
承認欲求が強いと「自己中心的」と言われるなど、面接でネガティブに見られるという話をよく耳にします、、、
まず、「採用の場で言われる承認欲求」と「心理学でいう承認欲求」は、少し意味が違うということを知ってほしいです。
そのため、「承認欲求=わがまま」「自己中心的」といった誤解が生まれやすいと思います。
 小島弥生教授
小島弥生教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
本来の承認欲求は、ネガティブなものではないですか?
私の専門であるパーソナリティ心理学では、承認欲求を「自分という軸を持ちながら、状況に応じて他者との関係を調整する力」として捉えています。
例えば、自分が今どんな場にいて、「どんなことが求められているのか」を考えたうえで、「この場では自分の性格のどんな側面を強調したら受け入れられるだろうか」「嫌われないだろうか」を考える。
この”調整しようとする意識”こそが承認欲求の働きなのです。
確かに、「自分の良いところを認めてほしい」という思いだけを強調すると、自己中心的に見られがちです。
しかし、本来の承認欲求は他者の視点を意識し、場に適応するための原動力です。
決してネガティブなものではありません。
 小島弥生教授
小島弥生教授
北陸大学 小島弥生教授にインタビュー②:就活で嘘をついている気がする?「自己呈示と就活のリアル」
“自己呈示=嘘をつくこと”ではない?「本当の自己呈示とは?」
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
就活で「偽りの自分を演じているようで虚しい」と感じる就活生もいる中で、こうした行動は「心理学でいう“自己呈示」で説明できるとお聞きしました!
自己呈示の中に、「偽りの自分を見せる」という側面がまったくないわけではありません。
ただし、一般的に言われる“自己呈示”と、心理学の研究で扱う“自己呈示”には少し乖離があると感じています。
本来の自己呈示とは、「一人の人間の中にある複数の側面のうち、場面に応じてどの側面を見せるか」という行為です。
例えば、私がインタビューを受けているときの「話し方」「しぐさ」は“私の一側面”です。
家庭にいるときはまた違う話し方をしています。
それでは、インタビュー中の私は“作られた自分”でしょうか?
そうではありません。
この場にふさわしい一面を、少し強調して出しているだけなのです。
 小島弥生教授
小島弥生教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
嘘をついているように見えても、実際はそうではないということですね。
心理学での自己呈示とは、「相手にこう思ってほしい」という印象を意図して作る行為です。
就活生は面接で「有能そう」「誠実そう」という印象を持たれるように行動します。
一方で、日常生活では「守ってあげたい」「助けてあげたい」と思わせたいときもありますよね。
例えば、そこまで落ち込んでいなくても少し弱音を吐いてしまう。
それも自己呈示に含まれています。
人間という生き物は、状況に応じて“相手の中にどんな印象を持たせたいか”を考え、自然に振る舞いを変えます。
 小島弥生教授
小島弥生教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
それでは、「自己呈示は演技をすること」と考えてもいいでしょうか?
「完全な作り話」「一から人格を作り上げるようなこと」は自己呈示ではないです。
当然ながら、俳優が脚本のない舞台に立つように、ゼロから自分を創り出すことも含まれていません。
自己呈示とは、「自分の中にすでにある側面の一部を、その場に合わせて強調する行為」なのです。
一方、自己呈示は常に失敗する可能性をはらんでいます。
例えば、「有能な人だ」と思ってもらいたくて振る舞っても、相手が「本当なのかな?」と疑えば、自己呈示は失敗します。
リスクはありますが、うまく印象を伝えられれば、選考やコミュニケーションで得られる成果も大きい。
逆に「口先だけ」と思われてしまうと残念な結果になります。
自己呈示は“嘘”ではなく、“伝える力”の一部。
それをどう活かすかが、就活でも重要なポイントです。
 小島弥生教授
小島弥生教授
“話を盛る”ことは自己呈示?「就活と自己アピールの境界線」
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
商品の宣伝で「吸引力がいい掃除機」を「世界一の吸引力」など、大げさに言うことも見かけますが、「話を盛る」行為は、自己呈示に含まれるのでしょうか?
まず、「吸引力がいい」という事実を伝えるだけなら問題ありません。
しかし、「他社製品より優れている」「世界一の吸引力」といった表現を加えた時点で、それは誇張や虚偽広告になります。
自己呈示も同じです。
“自分の良さ”を伝えることは大切ですが、事実を超えて盛ってしまうと“嘘”になってしまいます。
特に中途採用のようにスキルが重視される場面では、「これもできます」「あれも得意です」と言って採用されたのに、実際にはできなかったというケースがあります。
これはもう自己呈示ではなく虚偽です。
 小島弥生教授
小島弥生教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
例えば、実際は3か月しか働いていないのに「2年やっていました」と答えた場合、これは自己呈示とは言えないですよね。
事実と異なることを言うのは虚偽であって、自己呈示とは言えません。
自己呈示とは、「事実の中で自分をどう見せるかを工夫する行為」です。
「3か月という短い期間ですが、そこでこれだけの経験を積みました」「自分にとって大きな学びがありました」と伝えることは、立派な自己呈示になります。
自己呈示の本質は、「事実をどのように見せるか」にあります。
逆に、事実と自分が話そうとしている内容が一致しないと、それは虚偽の演出です。
就活生は、「この話は本当のことか?」「伝えたい印象と事実が異なっていないか」を一度確認してみるのが大切ですね。
 小島弥生教授
小島弥生教授
”なりたい自分を信じる行為”は嘘じゃない?「自己呈示と成長の関係」
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
もともと明るい性格ではないが、営業職に憧れて「そういう人になろう」と信じて行動することは、自己呈示に含まれますか?
それも自己呈示に当てはまります。
ここで大切なのは「信じ込むこと」です。
話すのが得意でない人でも、誰の中にも必ず“明るい一面”はあります。
その側面を少し強調して引き出し、「自分にはこういう一面もある」と信じて行動する。
それが自己呈示の第一歩なのです。
 小島弥生教授
小島弥生教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
今はそうではなくても、信じ込むことで自己呈示になりうることですね。
「役割取得」という心理学の概念に近い考え方です。
人はある役割を演じていくうちに、「最初は違和感があっても、徐々にその役割にふさわしい自分」になっていきます。
例えば、中学から高校に進学したとき。
以前はおっとりしていた学生が「高校では積極的に友達を作ろう」と決意して行動すると、最初はうまくいかなくても、次第に「自分は人と話せるタイプだ」と思えるようになる。
行動を通じて“自分像”が変わっていくわけです。
信じるだけでは妄想で終わってしまいますが、行動を伴えばそれは現実になります。
ただし、周りからの反応も大切です。
自分では明るく振る舞っているつもりでも、他人がそう受け取らない場合もありますよね。
そうしたとき、「自分は明るくない」と落ち込むのではなく、「私は落ち着いている」「安心感を与えられるタイプかもしれない」といった別の自分の良さを発見してほしいです。
こうして、人は他者との関わりを通して少しずつ“自分”を定義し、変えていく。
それが、自己呈示と成長の関係なのです。
 小島弥生教授
小島弥生教授
自己呈示が得意な人と苦手な人の違いとは?「セルフモニタリング能力」
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
やはり、自己呈示をうまく使える能力は生まれつきの性格による部分が大きいのでしょうか?
心理学ではこの能力に関して「セルフモニタリング(自己監視)」という概念がよく使われます。
セルフモニタリングとは、「自分の言動や表情、発言のタイミングを客観的に観察し、この状況ではどう振る舞えばいいかを判断する力」のことです。
例えば、「こういう場面でこの発言をすれば相手にどう受け取られるか」「今の自分の態度は適切か」といったことを意識的にモニタリングできる人は、自己呈示が得意な傾向が見られます。
これは、どちらが先か(自己呈示が上手いからセルフモニタリングが高いのか、逆なのか)は明確ではありませんが、「自分を客観的に見られる人ほど、状況に合わせた表現が上手い」という相関があります。
就活でも、こうした「場の空気を読んで行動できる人」は、「自然と自分を上手に表現できるタイプ」だと言えますね。
 小島弥生教授
小島弥生教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
どうやって自分のことを客観的に見るかが気になります、、、
生まれ持った特性として「セルフモニタリングが高い人」もいますが、後から育てることも十分可能です。
例えば、心理学を学ぶことで「自分を俯瞰して見る力」を養うことができます。
就活でも、自分の言動や感情を整理し、「なぜそう考えたのか」「相手にはどう映るのか」を意識的に振り返ることができるようになります。
「自分を客観的に見つめ直すことが苦手」だと感じる学生こそ、心理学的な視点を取り入れてみることを推奨します。
きっと新しい“自分理解”のヒントが見つかるはずです。
 小島弥生教授
小島弥生教授
北陸大学 小島弥生教授にインタビュー③:就活生へのメッセージ
就活にも役立つ?「心理学を学ぶことで得られる力」
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
就活生にとって「心理学はどのように役立つのか」について教えてください!
心理学というのは、「日常で何気なく行う行動の裏側にある仕組みを明らかにする学問」です。
心理学を学ぶことで「自分が気づかないうちに、実はこういう心理的メカニズムで動いている」ということを理解できるようになります。
さらに、日常生活で起こる出来事を「なぜ自分がこう感じるのか」「なぜこういう行動を取るのか」など、客観的に見つめ直す力がつきます。
つまり、自分の「振る舞い」や「感情」を一歩引いて考えられるようになるのです。
また、心理学を勉強している学生の特徴として、「自分の主観だけでなく、他の人が同じ出来事をどう見ているのか」を意識できるところがあります。
他人が自分と同じように感じているとは限らない。
この“当たり前のようで難しい視点”に気づけるのが、心理学の大きな魅力です。
 小島弥生教授
小島弥生教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
自分のことを客観視できることは、就活においても強みになりますね。
例えば、「今、自分はストレスを感じているな」と気づいたとき、「どうすればそのストレスを減らせるのか」「どんな考え方に切り替えるとよいのか」といった発想法を身につけるのです。
また、これまで受験などの大きな壁を経験してこなかった学生もいますよね?
自己推薦や特技だけで進学してきた人にとって、就職活動は人生で初めての“挫折や評価”の場になることもあります。
そのとき、面接で批判的なことを言われると、「自分のすべてが否定された」と感じてしまいがちです。
心理学を学んでいると、そうした場面でも「これは自分の価値全体を否定されたわけではない」と整理できるようになります。
就活という“初めての試練”に直面する学生にとって、心理学的な視点は確実に役立ちます。
 小島弥生教授
小島弥生教授
”お祈りメール”はあなたの否定じゃない? 「心理学から見る就活の心の整理法」
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
お祈りメールで悩んでいる就活生は多いと思いますが、どのようなマインドを持つべきでしょうか?
それを受け取ると、自分自身がすべて否定されたように感じてしまい、就活への意欲を失ってしまう人もいると耳にします。
私は学生にそのように考えないでほしいと伝えています。
お祈りメールというのは、採用する側の事情によるもので、たまたまその時の採用方針や条件に合わなかっただけです。
採用する側も、応募してくる学生一人ひとりをじっくり見る余裕があるとは限りません。
極端の話、選考の初期段階では、応募者は「多数の中の一人」にすぎないかもしれません。
最終面接のような段階になってから、ようやくじっくり見てもらえるのです。
 小島弥生教授
小島弥生教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
つまり、就活生は自分のことを否定しなくていいことですね。
心理学には「認知の二重過程モデル」という考え方があります。
私たちは、「無意識的に自動で情報を処理する場合」「意識的にじっくり情報を分析する場合」
この2つのシステムを使っています。
採用面接などでは、面接官が「この学生は合わないかもしれない」と直感的に感じることがありますよね?
しかし、その時に「応募者のどこが合わないのか」を言語化できる面接官はほとんどいないと思います。
つまり、無意識のうちに印象で判断しているのです。
そうなると、応募者がどんなに一生懸命アピールしても、その情報を受け取る側が意識的に処理しない限り、伝わりにくくなってしまいます。
人間は「ちゃんと聞こう」と意識しないと、相手の話を深く理解できないものです。
 小島弥生教授
小島弥生教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
「学生がコントロールできるもの」ではないということですか?
学生は「仕方がない」といった考えを持つことが大事だと思います。
あなたが悪いわけではなく、採用側に余裕がなかっただけなのです。
もし第一印象が良くなかったとしても、「ではどうすれば印象を変えられるか」を考えることに意味があります。
人間の情報処理能力には限界があります。
それを理解したうえで就活に取り組むと、納得感のある結果が得られる場面が増えると思います。
また、採用する側の「思考」や「事情」は、就活生からは見えません。
採用には計画があり、あらかじめ決められた枠に「ピース」として合うかどうかで決まる側面もあります。
どんなに頑張ってアピールしても、「タイミング」や「条件」が合わなければ難しい部分もあります。
だからこそ、「自分ではコントロールできない部分もある」と理解し、覚悟を持つことが大切です。
 小島弥生教授
小島弥生教授
就活が順調に進んでいることは喜ぶべき?「内定=ゴール」ではない
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
逆に就活が順調に「進んでいるな」と思うときに気を付けた方が良いことはありますか?
採用が順調に進んで内定をもらえることは、言うまでもなく喜んでいいことです。
それを「ラッキーだった」と思うのもいいですし、「自分の努力が実った」と自信を持つこともいいと思います。
ただし、採用はゴールではなくスタートということを忘れないでほしいです。
内定をもらった段階は、まだ“スタートラインに立っただけ”です。
そこから実際に社会人として走り出すフェーズに移るとき、そのまま鼻高々な状態だと、周囲からの「協力」や「信頼」を得ることが難しくなってしまいます。
就活で企業にエントリーする時は、その会社に対して理想や期待などを持っていたはずです。
そして、「入社したらこんなことをしたい」「こんなふうに成長したい」と思う気持ちは大切です。
しかし、実際に働いてみると「思っていたのと違う」と感じる場面も出てきます。
そのとき、就活が順調すぎて苦労を経験していない人ほど、落差を強く感じてしまいがちです。
つまり、成功体験が大きかった分、反動も大きくなるということです。
 小島弥生教授
小島弥生教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
就活で経験してなかったからこそ、挫折から立ち直ることが難しくなりますよね。
それを防ぐためにも、まずは迎えてくれる先輩社員の「行動」や「考え方」を謙虚に受け入れる姿勢が大切です。
「自分は優れているから採用された」と思い込むのではなく、「自分の何かがたまたま会社にフィットしただけで、採用された理由はまだ明確ではない」と考えた方がうまくいくはずです。
入社してから会社の「ルール」「文化」「規範」を理解し、その中で自分がどう貢献できるかを探る。
そうして働くうちに、「自分のこういう部分が評価されたんだ」と真の意味での評価が見えてくるはずです。
その段階でこそ、自分の真価を発揮できると思います。
 小島弥生教授
小島弥生教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
小島弥生教授、本日は貴重なお話をありがとうございました!