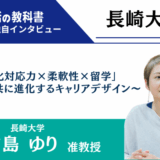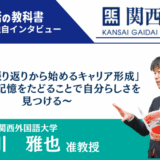「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの野口です。
本日は、日本経済大学の荒木貴之教授にインタビューしました。
荒木先生、本日はよろしくお願いします!
よろしくお願いします。
 荒木貴之 教授
荒木貴之 教授
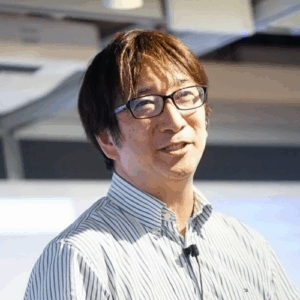
荒木 貴之(あらき・たかゆき)
日本経済大学 経営学部 教授
東京都内公立中学校で理科教員、東京都北区教育委員会・東京都教育庁で指導主事を歴任後、立命館小学校設立に参画。追手門学院でこども園設立や中高の教頭を務め、「グローバル人材育成塾」を主宰。河合塾では新設校(ドルトン東京学園)の設置準備を行い、2015年に武蔵野大学へ着任。翌年、千代田女学園中高校長として共学化と国際化を推進。IT企業NetLearning執行役員としてオープンバッジの普及啓発・人的資本経営支援に従事。現在は日本経済大学経営学部教授。文部科学省DXアドバイザー等、公的委員も歴任。
目次
日本経済大学 荒木貴之教授にインタビュー①:オープンバッジとは?努力を見える化する時代へ
“学び続ける力”がキャリアを左右する時代に
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
さっそくですが、リスキリングや学ぶことに対してどうお考えですか?
みなさんには小学校の頃、「できなかったことができてうれしい」「わかってうれしい」などの感覚があったと思います。
逆に他人から「こういうことが大事だから学んだ方がいい」と言われて勉強しても楽しくないですよね?
つまり、私は学びにおいて「楽しさ」や「喜び」がないと、長続きしない可能性が高いと思います。
また、頑張ったことが正当に評価される仕組みがあれば、人は自発的に学びつづけられると考えています。
 荒木貴之 教授
荒木貴之 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
これまでいくつかの学校で校長を務めてきましたが、ペーパーテストで力を正確に測定できるのかについては疑問を感じています。
受験の点数ではなく、「3ヶ月間継続して学習できた」という結果があれば、「この人は粘り強く努力できる」と明確に分かります。これは社会に出てからの評価にもつながる要素だと思います。
さらに、「この資格を取得したい」「スコアを上げたい」という目的意識を持って行動し、そのことを自分から面接担当者にアピールできれば、採用のミスマッチも減るはずです。
つまり、粘り強さや努力の継続、レバレッジの効かせ方といった非認知能力をデジタルで可視化できれば、「働きたい人」と「人を採りたい人」の間で、より的確なマッチングが可能になると考えています。
だからこそ私は、「努力を正当に評価できる仕組み」を構築するために、日頃からオープンバッジの普及活動に取り組んでいます。
 荒木貴之 教授
荒木貴之 教授
オープンバッジ=人間性や活動を証明するバッチ
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
オープンバッジとはどのようなものでしょうか。
オープンバッジとは、画像とメタデータからなる「スキル」・「知識」・「コンピテンシー」などのデジタル証明です。
さらに、第三者の裏付けである「エンドースメント(endorsement)」機能を使えば、信頼できる人から活動の信憑性を保証してもらうこともできます。
たとえば、部活動での実績を顧問の先生や先輩が「○○さんはこういう活動をしていました」と証明するような形です。
 荒木貴之 教授
荒木貴之 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
活動の信憑性を保証ですか…?
たとえば、大学のゼミの先生が「この学生はこんな研究をしていました」と記載することもできます。
研究内容がバッジで可視化されていれば、どんな人物かがより明確に伝わります。
この仕組みによって、採用のミスマッチを防ぎ、労働市場の流動性を高められると考えています。
 荒木貴之 教授
荒木貴之 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
ゼミの教授などが、学生の研究を証明することができるのですね!
努力のデジタル化はミスマッチ防止につながる
現在の日本では、人口および労働力が年々減少しています。
一方で、当然ながら人口が増加している国も存在します。中でもインドは、人口が14億人を超えて世界一となり、今後は17億人に近づくとも言われています。
インドでは若年層の人口が増加している一方で、彼らの仕事は必ずしも国内に十分存在しているわけではありません。そのため、多くの若者が起業をしたり、海外での就労を希望しています。
こうした背景の中で、「この人はこういう努力をしてきた」「これだけの日本語能力がある」といった情報が、事前に日本の採用担当者に共有されていれば、ミスマッチを防ぎながら、国際的な労働の流動性を高めることが可能になると考えています。
 荒木貴之 教授
荒木貴之 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
外国人人材の採用にも役立ちそうですね。
オープンバッジはアメリカの標準団体が定めた世界標準規格で、すでに世界で1億個以上発行されています。
アメリカ、ヨーロッパ、そして日本でも活用が広がっていて、日本国内でもすでに100万個を超えていると予想されています。
 荒木貴之 教授
荒木貴之 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
大学生や就活生でも、オープンバッジを作ることはできますか?
オープンバッジは、大学生や就活生も発行・活用することが可能です。
しかし、日本におけるデジタル化の進行は、依然として遅れをとっています。
たとえば、大学を卒業すると「学士(経済学士/教育学士など)」といった学位が授与されますが、それをデジタル証明書として発行している国内の大学は、現時点で全体のわずか0.3%程度にとどまっています。
日本は「資格」や「努力の成果」といった個人の実績を、デジタルのかたちで証明・共有する分野において、世界と比べて大きく後れを取っているのが現状です。
 荒木貴之 教授
荒木貴之 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
まだまだ日本では普及していないのですね。
仮に、これから海外の教育大学院に留学する人がいるとします。
そのとき、「学校でこれくらいインターンをしました」「日本でこういう活動をしました」という実績をデジタル証明できるようになると、それがアドミッション(入学審査)の材料にできます。
まだ事例は多くありませんが、少しずつそうした動きも出てきています。
さらに、国内でも「数学検定」をはじめ、「漢字検定」「英語検定」などの各種検定協会がオープンバッジ発行の準備を進めています。
 荒木貴之 教授
荒木貴之 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
入学審査の材料や、資格もオープンバッチで管理できると便利ですね。
現在、アナログで保有している資格や実績を、デジタルで発信できるようにする取り組みを進めています。
オープンバッジは、「LinkedIn」「Facebook」「X(旧Twitter)」「Pinterest」などのSNSにシェアすることが可能です。
これにより、自分のスキルや強みをデジタルのかたちで可視化し、表現できるようになります。
オープンバッジを活用することで、「自分がどんな努力をしてきたか」「どのような価値を持っているか」といった情報を、自信と誇りをもって発信することができると考えています。
 荒木貴之 教授
荒木貴之 教授
日本経済大学 荒木貴之教授にインタビュー②:社会教育士とは?課題の解決に向けて、地域に暮らす人々を支える
地域の“学び”を支える新しい称号の役割
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「社会教育士」についても教えていただけますか?
学校の先生には「教員免許」があります。教員免許を取得したうえで、学校で授業を行うのが一般的です。
一方で、学校教育以外の学び、たとえば地域での学習活動や社会における教育的取り組みは「社会教育」と呼ばれます。しかし、以前はこの社会教育の分野には、明確な資格制度が存在していませんでした。
 荒木貴之 教授
荒木貴之 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
社会教育の資格ですか。あまりイメージが湧きません。
しかし近年では、「人口減少」や「市区町村の合併」などの影響により、社会教育主事として配置される人員は年々減少しています。
一方で、社会全体を見渡すと、学びの対象となる人はむしろ増加しています。人生100年時代を迎える中で、生涯にわたって学び続けることの重要性が高まっているのです。
 荒木貴之 教授
荒木貴之 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
社会全体を見ると学びの対象者は増えているんですね。
また、在留外国人の数も増加しており、当然ながら彼らも高齢者と同様に、社会教育や生涯学習の重要な対象となります。
このように、「教育委員会」や「首長部局」に所属する”社会教育に関わる職員数”が減少する一方で、「地域で社会教育や生涯学習を推進する人」や「地域コミュニティを支える人」の存在が、ますます求められています。
そうした背景のもとで令和2年に誕生したのが、「社会教育士」という称号です。
 荒木貴之 教授
荒木貴之 教授
社会教育士の活動内容とは?「専門性を“地域の学び”に生かす人たち」
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
どのような方が社会教育士になっているのでしょうか。
社会教育士を取得しているのは、「図書館司書」「学校の先生」「企業で研修を担当している方」「大学教職員」など、社会教育や生涯学習に関わる幅広い人たちです。
NPO法人で社会教育の活動に取り組んでいる方々も多く見られます。
それぞれの専門分野で活動していて、社会教育士を取得する方が多く、専門性に教育的視点を加えることで、活動の幅を広げています。
私の講座を受講した中に、気象庁に勤務している方がいました。その方は、防災に関する知識は非常に豊富でしたが、「地域住民と一緒に防災ワークショップを実施したい」という想いを抱いていました。
その方は、赴任先で防災ワークショップを開催されてきていましたが、「社会教育」や「生涯学習に関する知識」や、「ワークショップの運営方法」や「ファシリテーションのスキル」を身につけたいと思っていたそうです。
そこで、社会教育士の学びを通して「防災 × 教育」の実践力を身につけたいと考え、社会教育士の称号を取得されました。
 荒木貴之 教授
荒木貴之 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
専門知識と社会教育の知識を掛け合わせて活動を広げているのですね。
博物館の学芸員の方も社会教育士として活躍されています。
その方は“万博”の専門家で、今回の関西万博でも各国の展示物にアドバイスを送るなど活躍されました。
昨年、社会教育士の称号を取得された後、同期の仲間と「大人の遠足」と題して、かつての万博で象徴的であった「太陽の塔」の見学をしたり、関西万博をどのように社会教育や生涯学習に活かしていくか、という観点で、全国の社会教育士の仲間とともに、パビリオンの見学などを行いました。
専門性のある人が社会教育士の称号を得ることによって活動の幅を広げ、地域やコミュニティに貢献する形を作れるのです。
 荒木貴之 教授
荒木貴之 教授
日本経済大学 荒木貴之教授から就活生へのメッセージ:「自分をブランディングすることが大事」
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
荒木先生、ありがとうございました。
最後に、就活生へのメッセージをお願いします!
学生には少し抵抗があることなのかもしれませんが、私は自分のことをブランディングすることが大事だと思います。
ここで「ブランディング」とは、”オープンバッジ”や”sns”などを使って、「私はこういうスキルがあります」「こういう資格持ってます」と発信することが当てはまります。
LinkedInの場合、スキルや資格が一覧で表示される仕組みになっています。
私も、自分が持っている「資格」や「スキル」を、LinkeInで表示したところ、世界中のさまざまな方からオファーを受けることもあります。
だからこそ、自分を売り込むために、そういったデジタルのツールもぜひ使ってほしいです。
 荒木貴之 教授
荒木貴之 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
荒木先生、本日は本当にありがとうございました!