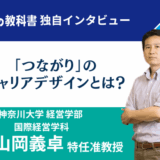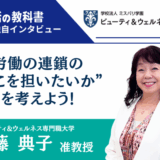「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの野口です。
今回は、京都橘大学でキャリア教育を担当されている乾明紀教授にインタビューしました。
乾教授、本日はよろしくお願いします!
よろしくお願いいたします。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授

乾 明紀(いぬい・あきのり)
京都橘大学 経済学部 経済学科 教授
15年間の大学職員のキャリアを経て、大学教員となる。研究・教育の領域は、心理学を応用したキャリアデザイン教育、シティズンシップ教育、探究学習、PBL(プロジェクト型学習)。2011年 立命館大学 大学院応用人間科学研究科修了、2015年 同大学院 政策科学研究科 博士後期課程退学。
京都橘大学乾明紀教授にインタビュー①京都橘大学のキャリア教育とは
人生100年時代を見据えたキャリアデザイン
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
さっそくですが、京都橘大学ではどのようなキャリア教育をされているのでしょうか。
私は京都橘大学でキャリア教育全体の設計を担当しています。その根幹には「人生100年時代」を見据えた視点があり、加えて低回生の場合は、就職活動までの2年間をいかに充実させるかを軸に授業を構成しています。
キャリア教育が重要なのは、かつてのように変化しない社会を前提としたキャリア設計が通用しなくなったからです。多様化・個性化が進む現代においては、「自分はどんな経験を積み、どこへ向かうのか」というキャリアを主体的にデザインする力が求められています。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
- キャリアデザイン科目
- 産学公連携科目
- 資格取得支援科目
「キャリアデザイン科目」では、主に学生が自分自身の未来を構想するための考え方や方法などを学びます。
「産学公連携科目」では、インターンシップやクロスオーバー型課題解決プロジェクトなど、実践的な活動を通じて越境する力を育みます。
キャリアデザイン科目の授業、たとえば、「キャリア開発演習Ⅰ」では講義を聞くだけでなく、ワークを通じて「これまでの経験」や「これから挑戦したいこと」を振り返る時間を設けています。さらに、卒業までに履修する124単位がどのようにキャリア形成につながるのか、その意味づけも行い、学部・学科での学びと卒後キャリアが分断されないよう意識づけをしています。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
キャリア教育の土台にある3つの理論
授業では「キャリア」という概念について、その語源にも触れながら解説しています。たとえば、「キャリア」を単に「働くこと」と狭く捉えるのではなく、荷車にたとえて説明します。学生には、経験を通じてスキルや能力、役割、知識といった要素を荷車に積み込み、他者とかかわり(ときに他者の支援も受け)ながら、それを引いて未来へ進んでいく──そして、その歩みの結果として経歴や人生が形づくられていく──というイメージをもってもらいます。こうした比喩を用いることで、「キャリア」という言葉の本質、すなわち人生を通じた継続的な成長や歩みのプロセスとしてのキャリア理解を促しています。
また、授業では、主要なキャリア理論を3つに整理して教えています。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
- 偶然活用型キャリアデザイン
偶然訪れたきっかけや予期しない出来事を前向きに受け止め、それらを活かしながらキャリアを開発していくアプローチ。
- 目標設定・逆算型キャリアデザイン
明確な目標を定め、その達成に向けた計画を立て、マネジメントしながらキャリアを開発していくアプローチ。
- 目的創造・物語構築型キャリアデザイン
これまでの経験や出来事を振り返り、自らのキャリア・ストーリー(物語)を築き、そこから価値を含んだ目的を創り出し、その目的に向かってキャリアを開発していくアプローチ。
「偶然を活かして、自分の道を見つける」
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「偶然活用型のキャリアデザイン」とは初めて耳にしました。
目標を設定し、目標に向かって進むことだけに重きを置いたキャリア指導は、かえって問題を生じさせることがあります。「目的や目標がなければならない」という価値観に縛られすぎてしまい、「やりたいことがない」と自信を失っている学生に出会うことがあります。
そのため、この授業ではあえて最初に「偶然活用型キャリアデザイン」を取り上げています。学生に「自分には可能性がある」という感覚を持たせることが重要だと考えているからです。
たとえば、不本意入学というケースもあります。京セラを創業した稲盛和夫氏も大学は不本入学だと聞いたことがあります。つまり、キャリアの形成は環境との相互作用の中で化学反応のように起きるものであり、目的や目標だけで決まるものではありません。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
まさに私も「目標がなければいけない」と縛りを感じていました。
キャリアは化学反応のように形成されるのですね。
私たちがこの場で出会ったのも偶然ですが、その偶然が今後どこかで何かを生み出すかもしれない。このような「偶然性の価値」を学生にも理解してほしいと思っています。
たまたま友人に勧められて音楽を聴き、そのアーティストを好きになる。そうした偶然の積み重ねが、自分の価値観や信念、さらには「やりたいこと」の芽生えにつながっていくのです。私は心理学を学んできたので、こうした行動から価値が生まれるという考え方を、心理学に基づいて伝えています。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
「やりたいことがない」学生への処方箋
「やりたいことがない」という状態は、一概に悪いとは言えません。経験が足りていないか、まだ適切に振り返っていないだけです。そこで「行動しなければやりたいことは見つからない」と伝え、学生が前向きにキャリアを考えられるよう意識づけています。
また、「偶然がキャリアを作る」というクランボルツの理論も紹介しています。特に、楽観性・柔軟性・持続性・好奇心・リスクテイクといったスキルを持つ人は、偶然を活かしやすいとも言われています。何もしないことが一番のリスクであり、「まずはやってみよう」という姿勢を持って行動することが大切です。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
就活生時代「やりたいことがない」ということに対し、引け目を感じていました。行動しなければやりたいことは見つからないのですね。
付箋の「ポスト・イット」は強力に接着するボンドを開発しようとしていたにもかかわらず、結果的にほとんど接着力のないものができてしまったという失敗が誕生のきっかけでした。失敗で済まさず「何かに使えないか」と考えた結果、現在のポストイットが生まれました。
他にもペニシリンやX線など、画期的な発明や発見の多くは、偶然から生まれたものです。このように、セレンディピティ(偶然の幸運な発見)が重要な役割を果たすことは、科学や技術の分野でもよく知られています。
偶然というのは、物事を前に進める非常に大きなチャンスでもあると考えています。「ご縁に感謝」や「怪我の功名」といった言葉があるように、思わぬ出来事が良い結果につながることもあるのです。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
偶然から生まれたものも世の中にはたくさんあるのですね。
しかし、こうした偶然をどう受け取るかは人それぞれです。そのため、授業では「ライフラインチャート」を用いて、自分にとってどのような偶然が人生に影響を与えてきたのかを可視化しながら考えてもらうようにしています。
大切なのは、偶然を「起こす主体性」と、「活かす主体性」の両方を持つことです。偶然は待っているだけでは起きません。自ら動き、行動することで偶然を呼び込むことができます。そしてそれをどう受け止め、どう活かすかは自分自身にかかっています。
その際、楽観的な姿勢や前向きな気持ちも重要です。ポジティブな視点を持つことで、偶然をチャンスとして受け止めやすくなるからです。思いがけない出来事や受動的な行動(やらされている活動)の中にも、大きな可能性が眠っている。そういったメッセージを学生たちにも伝えるようにしています。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
偶然を起こすことと活かすことが必要なのですね!
私の今までのキャリアも、偶然だったことが多々ありました。
ワークライフインテグレーション=仕事と私生活の充実
また、「ワークライフインテグレーション」つまり、仕事と私生活を切り離さずに両方を充実させるという視点からキャリアを考えるよう伝えています。
こうした考えは、ドナルド・E・スーパーが提唱している「キャリア・レインボー」に近いものであり、「キャリア=就職」と捉えるのではなく、人生全体を通じた活動として捉えることが、本質的な理解につながると伝えています。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
キャリア=仕事と捉えがちですが、充実した人生を生きるためにはプライベートも重要ですね。
京都橘大学乾明紀教授にインタビュー②シティズンシップ教育とは
シティズンシップ=社会や人はどうあるかを考え続ける
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
シティズンシップとは、市民としての権利と義務、そして社会への積極的な参加という意味を持ちますよね。キャリア教育とつながるところがあるのでしょうか?
シティズンシップ教育というと「選挙に行く」など政治的参加をイメージされがちですが、それだけではありません。
大人の都合のよい社会を支えるためではなく、「社会や人はどうあるべきか」を考え続ける姿勢にこそシティズンシップの本質があると考えています。
「自分が暮らす場所」とは、単なる住所ではなく「地域社会」を意味します。たとえば、夜道を安心して歩ける街や、ゴミのない環境は、そこに住む人々がより良い社会をつくろうと関わっているからこそ成り立っているのです。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
地域の安心や快適さは、そこに暮らす人々の意識や行動に支えられているんですね。
もちろん、行政が担う部分もありますが、それだけで地域社会は保てません。市民ができる範囲で関与しつつ、必要な部分は行政や政治に託す──そうしたバランスが、地域社会を成り立たせています。
選挙による社会参加も重要ですが、何より大切なのは、自分が社会の「当事者」として関わっている、あるいは関わっていこうとする意識を持つことです。「どうしてこの状態が当たり前になっているのだろう?」や「こういう社会にしていきたい」という思いが芽生えれば、自然と社会に関心を持ち、行動へとつながっていくはずです。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「当事者として関わる」という意識が、シティズンシップの根本なのかもしれませんね。
「社会的自立」もキャリア教育の目的
キャリア教育の目的は、「職業的自立」だけではありません。
社会の一員として暮らす「社会的自立」も含まれています。
そのためには、シティズンシップ=市民性を育むことが欠かせません。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
キャリアは「自分個人のこと」だと思いがちですが、実は社会とのつながりの中にあるんですね。
まさにその通りです。キャリアは「自分ごと」であり、同時に「社会ごと」。
この2つを切り離さずに、重ね合わせて捉えることが、キャリア教育のあり方だと考えています。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
「得か損か」ではなく、共通善を目指すシティズンシップ
そのために必要なのが、「自分・他者・社会」の三者関係で考える視点です。
自分だけを考える一者関係でもなく、「得か損か」「敵か味方」などの二者関係にとどまらず、「自分にも他者にも社会にも良いことは何か?」と三者関係でとらえ、共通善を目指すことが、シティズンシップの姿勢だと考えています。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
社会にも良いことを目指す必要があるのですね。
「シティズンシップ(citizenship)」という言葉の語尾にある「-ship」には、「形づくる(shape)」という意味が込められています。たとえば、スポーツの大会で選手が「スポーツマンシップに則り…」と宣誓するのは、競技に臨むにあたり、スポーツマンとしてふさわしい姿勢や態度を自らに形づくることを誓っているからです。
同様に、シティズンシップとは、市民としてふさわしいあり方で社会に関わろうとする姿勢を意味します。その本質は、「自分にとって良いこと」だけでなく、「他者や社会全体にとって望ましい状態」を目指すという共通善(common good)の実現にあります。そして、そのような社会を築く主体として、自らも積極的に関わろうとする意識が求められるのです。
このような視点を持たず、「自分さえよければよい」「就職できればそれでよい」といった考え方で将来を捉えることは、キャリアの本質を見失うことにもつながりかねません。私は学生たちに、キャリアとは単なる職業選択にとどまらず、社会との関わりの中で自分をどう位置づけ、どのように生きていくかという広い視点から考えることの大切さに気づいてもらえるよう働きかけています。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「内定がゴール」と捉えがちですが、社会との関わり方も同時に考える必要があるのですね。
そもそも大学において「教養教育」が設けられているのはなぜかというと、それは専門学校とは異なり、さまざまな分野の学問に触れる機会を提供するためです。
単なる知識やスキルの獲得を目指すのではなく、図書館などの学びの場を活用しながら、「自分はどう生きるべきか」「社会はどうあるべきか」といった問いに向き合ってほしい。そのように思索する時間を大学4年間の中でしっかりと持ってほしいと考えています。それこそが、大学に通う意義なのではないかと、私は思っています。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授にインタビュー③アンパンマンのマーチの問い
「何のために生まれて、何をして生きるのか」
「目的創造・物語構築型キャリアデザイン」を紹介する際、私は学生に「アンパンマンのマーチ」を取り上げています。
「何のために生まれて、何をして生きるのか?」という歌詞は、多くの学生が子どもの頃に何度も耳にしているはずです。しかし、この問いに真正面から向き合い、自分なりの答えを出したという人は、意外と少ないのではないでしょうか。私は、この問いには、キャリア教育の本質を突くものがあるように感じています。せっかく大学に進学したからには、「自分は何のために生きるのか」という問いに、自分なりの答えを見つけて卒業してほしい、そう願っています。
社会の複雑化にともない、「教育は中学校や高校で終わるものではない」という認識が広がり、大学へ進学する人が増えました。つまり、大学とは単に労働の準備をする場所ではなく、社会に出たときに「どのように生きるか」をじっくりと考えるための時間でもあるのです。仕事を免除されているこの期間だからこそ、自分自身の生き方に向き合うことができる。そうした意味で、大学生活をキャリア形成の核となる時間にしてほしいと考えています。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
アンパンマンのマーチには深い意味があったのですね。「自分はどう生きるのか」をしっかりと考えることが大切なのですね。
ゴールは就職ではなく、自分の答えを持つこと
私のキャリア教育は、就職をゴールとするものではありません。「どのような自分でありたいか」を問い直すことを重視しています。
加えて、キャリア教育の本丸は、学部・学科で展開される教育にあります。各学科が掲げる「ディプロマ・ポリシー」は、学生がどのように成長し、どのような姿で卒業していくかを示すビジョンであり、その実現過程がまさにキャリア開発です。
一方で、大学にはキャリアセンターがあり、職業キャリアの形成のための就職支援をしています。私が担当しているキャリア教育は、この「学部・学科としてのキャリア教育」と「職業キャリア支援(就職支援)」の間を橋渡しをする役割を担っています。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
学部・学科教育とキャリア教育はつながっていないと思っていました。
専門教育の重要性を伝えつつ、社会に出る前に「自分はどうあるべきか」「どんな未来を望むか」といった問いに向き合う場をつくり、その思考を通じて、学生が自らの学びへのモチベーションを高めることを狙いとしています。私は、学部・学科の勉強の応援隊でもあると自負しています。
また、4年後には卒業し就職する必要もあるため、学生にはキャリアセンターの活用もすすめています。学問と就職活動を上手に両立させながら、社会的・職業的自立に向けた準備を進めてほしいというのが、私のキャリア教育のスタンスです。
「キャリア教育=就職支援」だと誤解されがちですが、そうではありません。「どう生きたいか」「どんな社会であってほしいか」といった問いに向き合うキャリア教育は、単なる進路選択のための準備ではなく、自分と社会との関係を見つめ直し、自らの生き方を主体的に構想していく営みだといえるでしょう。
 京都橘大学乾明紀教授
京都橘大学乾明紀教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
就職活動で自己分析をして「何があっているのか」考える学生が多いと思いますが、常に「どう生きたいか」考え続けることが大切なのですね。
乾先生 、本日はありがとうございました!