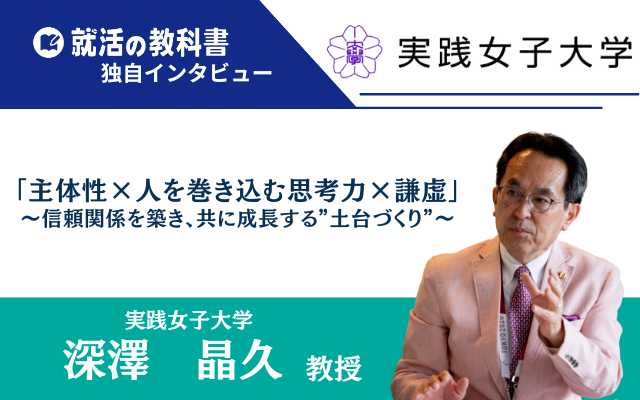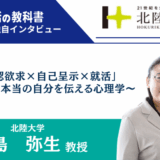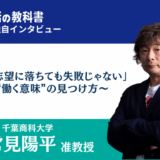「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
こんにちは!「就活の教科書」取材チームのチェです。
本日は、実践女子大学の深澤晶久教授にお話を伺いました!
深澤晶久教授、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授

深澤 晶久 (ふかざわ・あきひさ)
実践女子大学 文学部国文学科 教授・学長補佐・社会連携推進室長
1957年東京生まれ。慶應義塾大学法学部卒。
株式会社資生堂で営業・マーケティング・商品開発・新規事業・労働組合中央執行委員長などを経て、2004年から人材開発室長。2007~2014年新卒採用約1,000名、研修対象約16,000名を統括。
2009年に「キャリアデザインセンター」を設立。
2014年より実践女子大学特任教授としてキャリア教育を担当。
文科省・東京商工会議所・東京五輪組織委員会文化教育委員会等の委員を歴任。
目次
実践女子大学 深澤晶久教授にインタビュー①:テクノロジーでは測れない“人間らしさ”――AI時代でも大切な“人とのつながり”
AI面接が面接官ガチャに終止符?「激変の時代でも大切なのは“人と人の相性」
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
さっそくですが、AI面接が増える中で、就活生と面接官の相性が「合う・合わない」問題はなくなると思いますか?
面接官との相性の問題は本当に難しいテーマだと思います。
ここ数年、就職活動の中でAI面接という言葉が増えてきました。
私はAI面接を否定するつもりではありませんが、面接の基本は“人対人”だと考えています。
当然ながら、人間同士で面接をしているので、相性の問題が出てくるのも事実ではあります。
しかし、そういう“ご縁”のようなものがあるからこそ、成り立っていると考えています。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
確かに、AI面接が増えているとはいえ、根本的な部分は人と人の面接ですよね。
企業で面接を担当してきた中で私が感じたのは、学生と一対一で話すことで、「人柄」「何を大切にしているのか」「将来どんなことをやりたいのか」が次第に見えてくることでした。
でも、それを”ほんの短い時間で”、しかも”数回しかない選考の中”で完全に理解することは難しいと思います。
そして、今は人手不足で企業も人材確保が大変だということは理解しています。
それでも、やはり時間をかけて、もう少し丁寧に“本当の意味でのマッチング”をはかる必要があると思います。
入社してから様々な経験を重ね、企業に貢献できる人材になるまでには時間がかかるため、なおさら慎重に採用活動を行う必要があります。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
「人間らしさ」は残るのか?「AI面接の時代でも、人の温度は消せない」
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
AI面接については就活生の中でも賛否両論が分かれていますが、先生はどのようなスタンスをとっているのでしょうか?
私は“両面ある”と思っています。
だから、決して全面的に否定しているわけではありません。
ただ、やはりAIの使い方についてはもっと慎重に考えていく必要があると感じています。
また、「学生の人となりをAIが本当に分かるのか?」ついては、もう少し議論する必要があります。
というのも、勤務形態として「リモートワーク」「在宅勤務」など、様々なスタイルがありますが、やはり企業というのは“人”で成り立っているからです。
会社は単なる建物ではなく、社員同士が集まり、議論をしながら「良い仕事をして社会に貢献しよう」「良い商品を作ってお客様に喜んでもらおう」と努力する場所です。
その過程こそが企業の本質です。
技術の発展により、VR(仮想現実)を通じてオフィスを完全に再現できたとしても、実際の場所で感じる「温度感」「空気」「出会いの偶然性」までは再現できないと考えています。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
AIが進化しているものの、その“リアルな人との関わり”は代えがたいですよね。
当然ながら、AIの良い面があります。
例えば、「調べ物をするとき」「自分が書いた文章を整理したいとき」に使うと非常に便利です。
ただ、今は企業のエントリーシートにも生成AIが使われていますよね?
それを受け取る企業側が、「AIで作られた文章」をどう見極めているのかについて考える必要があります。
そこはまだはっきりしない部分も多いと思います。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
企業としてはせっかく「その学生本人の素の姿を見たい」と思っていたのに、「この学生の本当の良さが伝わってこないな」と感じてしまいますよね。
今はまさに“過渡期”だと思います。
学生も企業も、AIとの付き合い方を考えながら「お互いに後悔のない」「お互いにとって有意義な関係」を築いていく必要があります。
結局、AIというのは人間が作ったものです。
確かに便利なツールではあるが、使い方を間違えるとAIに依存してしまい、人間としての根本的な力を失ってしまう可能性があります。
ある課題に対してAIがヒントを与え、それをもとに自分で考える。
この繰り返しを通して初めて、人間の思考力が育つのではないかと思います。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
面接での無意識なバイアスとは?「採用の現場で起きている変化」
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
面接や採用の段階で働くバイアスについてお聞きしたいです。
例えば、「外国人は協調性が足りない」「女性はすぐやめてしまう」など、そういった偏見で判断されるケースはありますか?
私が製造業の採用を担当していた頃は、留学生も積極的に採用しましたが、そこにバイアスは全くなかったです。
「協調性が~~」「外国人は~~」など、そういう疑問を持ったことは一度もありません。
私が採用面接で重視していたのは「働き方」と「環境への適応」でした。
実際、採用した方々は入社後に活躍してくれました。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
海外で就職したい日本人学生にも参考になりますね。
私が面接でよく聞いていたのは、「家族は今、母国にいるのか?」「一人で留学しているのか?」というような、生活面や環境面のことでした。
私が勤めていた会社がグローバル企業を目指していたこともあり、総合職の採用条件として「国内外どこでも勤務できること」という要件がありました。
そのため、海外の事業所に配属される可能性があることを前提で確認していました。
「ずっと日本で働いても大丈夫なのか?」「将来的に母国などへ戻る予定はあるのか」など、日本人には馴染みのないことも確認していましたが、「協調性」「文化的な違い」を理由に判断を変えるようなことは一切ありませんでした。
つまり、採用の場では「外国人だから」という偏見ではなく、一人ひとりの能力・意欲・適応力を正しく評価することが求められています。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
そういったバイアスは、女性にもあったとお聞きしました。
例えば、「女性は出産や結婚ですぐ辞めてしまうのではないか?」のような理由で採用を控える企業もあったと思いますが、今はどうですか?
昔は「男女雇用機会均等」の整備もまだ十分じゃなく、休業制度だって今のようには整っていなかった時代がありました。
その時代では、女性に対する偏見やバイアスがあったと思います。
しかし、今は時代が変わりました。
そもそも、法律で決まっているし、企業によっては法定以上の育児休業を取れる時代になっています。
そのため、「女性を採用してもすぐやめてしまうから採らない」ということは、今ほとんどないと思います。
もし、企業がそれを理由に採用を控えると、逆に人が来なくなる時代です。
それ以前に、若い人たちがもっと社会で活躍できるようにしないと、「少子高齢化」の日本の国力がますます下がっていくと思います。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
差別や偏見がなくなっていく中で、若者にとってはチャンスが訪れたかもしれないですよね。
実践女子大学 深澤晶久教授にインタビュー②:「主体性×協働×挑戦」――“動ける人”が社会を変える時代へ
社会で活躍する人の共通点は?「主体性」と「人を巻き込む思考力」
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
仕事で大事なことについてお聞きしたいのですが、深澤先生の「仕事に大切な七つの基礎力」という本でその答えを得られますか?
本の中には、全部で43の項目があり、それぞれ大事だと思います。
それ以前に、私は何事にも「謙虚で誠実なこと」がその力の土台になると考えています。
人間として「周囲から信頼を得て、成長していくために」必要なマインドだと思います。
一方、社会人として必要な能力はたくさんありますが、特に「主体性」と「人を巻き込む思考力」を私は大事にしています。
まずは、人としては「謙虚・誠実」であること。
そのうえで、主体性を持って行動する。
学生のみなさんは一人で完結する仕事はまずないことを忘れないでほしいです。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
人を巻き込む思考力について詳しく教えてください!
私は「人を巻き込む思考力」とは相手の話をしっかり聴く力が土台になると考えます。
つまり、傾聴力だと思います。
実は、「話すこと」より「聴くこと」の方が何倍も難しいことです。
話していて安心する相手は、言葉を遮ってすぐ自分の話に切り替えない人。
しっかり受け止めてくれるからこそ、「安心感」や「信頼」につながるのです。
そうすると、「一緒にやろうよ」「これ考えてくれない?」と持ちかけた時に、自然に“巻き込まれて”くれるのです。
その時に、「絶対巻き込んでやる」と強引にいくのはNGです。
相手の話を聴いて理解しようとすると、自然に“力を貸したくなる”関係が生まれる。
これが基本だと思っています。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
確かに、傾聴が大事だと分かっていても、それを意識する学生は少ない気がします、、、
ただ、「受け身になれ」という意味ではないです。
主体性を持って常に動くことで出会いが増えていくのです。
そこで挑戦のきっかけが生まれる。
「幸福の女神は前髪しかない」という格言があります。
要するに、あなたにとってのチャンスが毎日目の前に現れているが、その時に「できないかな」「面倒くさいかな」と言っていると、女神は通り過ぎてしまう。
後から「あれ、やりたかったな~」と思っても、もう後ろ髪はないから掴めないのです。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
コロナ禍で失われたものは?「“対話と挑戦”」
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
コロナ禍で学生生活を送った世代は、やはり「人との関わり方」や「行動の面」で影響を受けているように見えます、、、
今の大学1~2年生は「中学校・高校」時代にちょうどコロナ禍の真っ只中だったはずです。
当時は、非常事態宣言が出て、ほとんどロックダウンに近い状態でしたよね?
言うまでもなく、学校も休校になり、授業もオンライン化されました。
Zoomなどのオンラインツールが広まったのは良い面ですが、とても大事な時期に「直接会って話す」機会を失ってしまったことは学生に大きな影響を与えたと思います。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
その失われた時間を取り戻すためにどうしたらいいですか?
だからこそ、私は学生に「とにかく行動しなさい」と伝えています。
その時にできなかった経験を取り戻すくらいの気持ちで、大学時代にたくさん挑戦してほしいです。
いろんな人に会って、いろんなことにぶつかってみる。そして失敗も経験する。
それを経験できるのが、大学時代という最高のチャンスなのです。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
世界経済にも大きな影響を与えましたが、それ以上に「人々の思考」や「行動」にブレーキをかけたという側面も大きいですよね。
そうした影響は長期的に見ても大きいと思います。
だからこそ、大学としては、学生に「その時間を取り戻してほしい」と思っています。
その頃にできなかった経験を大学で数倍にして取り戻す。
そのために、私はできるだけ「多くの出会い」や「経験の機会」を提供したいのです。
「自分は何もできなかった」と悲観する学生もいると思いますが、「今動くことが何より大切である」ことを伝えたいです。
その一歩を踏み出せるかどうかが、社会人になった時の大きな差につながると思います。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
何から動けばいい?「行動の第一歩”とウェルビーイングの学び」
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
行動することの大切さは理解している学生は多いと思いますが、「どこから行動したらいいのか?」「何を始めたらいいのか?」など、具体的にどうしたらいいのかを悩む人も多いと思います、、、
これは多くの学生が抱える悩みですが、当然ながら「自ら動いて外の世界に飛び出す学生」もいます。
例えば、長期インターンシップに参加して社会と関わって活動している学生もいますし、NPOに参加して被災地支援を行っている学生もいます。
そういう行動自体は素晴らしいことですし、より一層やってほしいと思っています。
一方、「何をしたらいいかわからない」「最初の一歩が怖い」という学生も少なくありません。
そういう学生のために、大学では学内でできるチャレンジや外部プログラムの紹介を常に発信しているのです。
私自身は、「ウェルビーイング・プロジェクト(JWP)」を通じて学生がその糸口を見つけるように指導しています。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
ウェルビーイング・プロジェクト(JWP)について詳しく教えていただけますか?
ウェルビーイングという言葉は、長らく注目されてなかったのですが、2015年に国連のSDGsが採択されたとき、「すべての人に健康と福祉を」の中でウェルビーイングが明確に位置づけられました。
その後、日本企業の間でも「ウェルビーイング経営」といった言葉が広まり、「社員の幸福」や「健康」を重視する取り組みが本格化しました。
業種によって捉え方は異なりますが、基本は「社員を大切にし、その力を最大限発揮してもらい企業を発展させる」という考え方です。
ウェルビーイング・プロジェクト(JWP)では、学生たちが企業のウェルビーイング経営などを研究しています。
「ウェルビーイングとは何か」「どうすれば社会や企業で実現できるのか」といったテーマを調べ、学生同士で議論します。
こうした取り組みを通して、社会との接点を持つ最初の一歩を踏み出せるのです。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
大学で学生のためにチャレンジする機会を作ることは素敵ですね。
似たようなプログラムは各大学にもあるはずです。
その前に、行動のきっかけは「小さな興味」からでいいという意識を持ってほしいです。
「ちょっと面白そうだな」「やってみようかな」など、こういった小さな興味が行動の原点です。
どんな経験も無駄にはなりません。
主体性を育てるには、まず一歩踏み出すこと。
その一歩が、自分の可能性を大きく広げるのです。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
実践女子大学 深澤晶久教授から就活生へのメッセージ:「使命感と挑戦心を持って、行動してほしい」
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
最後に、就活生へのメッセージをお願いします!
今の若い人たちにはこれからの社会を思い切って変えてほしいと思っています。
私はよく「2050年責任世代」という言葉を使うんです。
これからの50年をつくっていくのは、まさに今の若者たち。
だからこそ、使命感やチャレンジ精神を持って行動してほしいです。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
若者がもっと挑戦する環境を作っていきたいですね。
そして、私がとても好きな言葉を学生に伝えたいです。
「アンパンマン」の原作者として知られている「やなせたかしさん」の言葉ですが、「人生は喜ばせごっこ」という言葉を残されています。
つまり、お互いに相手を喜ばせる。
自分が誰かを喜ばせれば、その相手もまた自分を喜ばせてくれるのです。
そうして幸せが循環していく。
ぜひ、学生のみなさんも「誰かを喜ばせる人生」を目指してほしいです。
 深澤晶久教授
深澤晶久教授
 「就活の教科書」編集部チェスンウ
「就活の教科書」編集部チェスンウ
深澤晶久教授、本日は貴重なお話をありがとうございました!