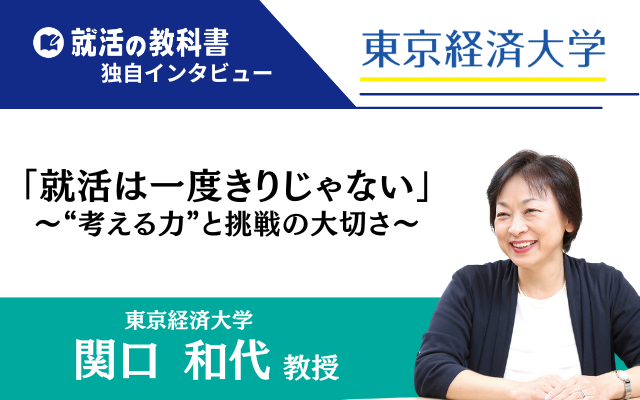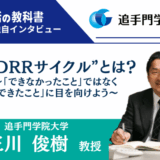「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの野口です。
本日は、東京経済大学経営学部学部長の関口和代教授にインタビューしました。
関口先生、本日はよろしくお願いします!
よろしくお願いいたします。
 関口和代 教授
関口和代 教授
関口和代(せきぐち・かずよ)
東京経済大学 経営学部学部長・教授
金融機関の研修部門が分離独立した会社にて、主に管理職研修の企画・運営を担当。そこで、人事院出身の上司2名の薫陶を受ける。
社内勉強会や上司が主宰・参画する研究会等に同行したこと等から、人事、教育、キャリアについて研究したいと考え、上司達のサポートもありキャリア・チェンジ。
研究テーマは人材育成、キャリア形成、メンタリング、BPO(アウトソーシング)、過重労働等。主な担当科目は「人的資源管理論」「産業心理学」。ゼミは2〜4年生の合同運営で、2・3年生が「人材」を主題にグループ研究に取り組む。毎年、海外研修を実施し、現地の実践事例に触れることで学生の視野拡張とネットワーク形成を促している。
目次
東京経済大学 関口和代教授にインタビュー①:産業心理学から考える“就活力”
“やりたいこと”と“向いていること”は必ずしも一致しない:自己理解の必要性
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
さっそくですが、「産業心理学」について教えてください。
産業心理学は、もともとジョブマッチングをテーマに始まりました。
新天地を求めてアメリカに移民として来た人びとが、専門とは異なる仕事に就かざるを得なかったこと、たとえば医師であった人がアメリカでは工場労働者として働かざるを得ないといったことが背景にありました。
現在も、ジョブマッチングは課題となっています。そこで、学生には事例を交えながら、“やりたいこと”と“向いていること”は必ずしも一致しないし、状況によって変わるということを伝えています。また、過度な自己分析は勧めませんし、客観的な判断が必要です。
 関口和代 教授
関口和代 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
就活生にとって「何がやりたいか」は一番悩むテーマでもありますね。
さらに、産業心理学では、コミュニケーションやリーダーシップ、モチベーションといったテーマを扱います。
従業員や後輩を導くうえで、こうした知見はマネージャーや先輩にとって不可欠です。
企業・組織だけでなく、さまざまな分野で必要な事柄でもありますので、幅広い学部の学生にとって重要な学問だと考えています。
 関口和代 教授
関口和代 教授
リーダーとフォロワー:双方の視点で捉えるリーダーシップ
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「リーダーシップ」は社会人として必要なスキルですよね。
リーダーシップといっても、リーダーが頑張るだけでは成り立ちません。
ついてきてくれるフォロワーがいてこそです。
したがって、リーダーとフォロワー双方の視点で考えることが重要だと思います。
 関口和代 教授
関口和代 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
「リーダーシップ」というと、リーダー個人に注目してしまいがちですが、リーダーとフォロワーの双方を考える必要があるのですね。
モチベーションの多様性:個人に合わせて活かすことが重要
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
産業心理学でいう「モチベーション」とはどのようなものでしょうか?
産業心理学でのモチベーションは、主に仕事に対する意欲を指しますが、その源泉は人によって異なりますし、同じ人でも時と場合によって変わります。
ですから、上司は一人ひとりを丁寧に見て、その人に合った形でモチベーションを喚起するべくサポートしていくことが大切だと思います。
 関口和代 教授
関口和代 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
モチベーションには、上司の行動も大きく影響されるのですね。
モチベーションの源泉には、給料、人からの賞賛、社会貢献など、多様な要素があります。
だからこそ上司は一律に対応するのではなく、一人ひとりをよく見て適切にサポートする必要があります。
 関口和代 教授
関口和代 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
より人材育成の重要性が感じられますね。
東京経済大学 関口和代教授にインタビュー②:合同ゼミの工夫––“先輩が後輩を導く”学びの場
学年混成グループで研究:テーマは人材を軸に幅広く
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
東京経済大学のゼミ活動で、特色的なことはありますか?
東京経済大学の経営学部のゼミは2年生から参加でき、同じ時間帯で一緒に活動します。
そのため“3年で基礎、4年で卒論”というような指導が難しく、レベル合わせには悩む部分もあります。
そのため、2・3年生で混成グループを作り、先輩が後輩をリードし研究をする仕組みにしています。
4年生は就活で忙しい時期もありますが、可能な範囲でグループ研究をサポートしてもらうようにしています。
 関口和代 教授
関口和代 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
テーマとしては学生はどのようなことに取り組んでいますか?
ゼミのテーマは基本的には“人材”を扱っていますが、テーマ設定は自由です。漁業や自動運転といったテーマで研究したグループもありました。
学生達のグループ研究を全力でサポートするようにしています。
 関口和代 教授
関口和代 教授
海外研修:日系企業訪問と現地学生交流で視野を広げる
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
ゼミで海外研修を行っていることについて具体的に教えてください。
私のゼミの海外研修では、主に現地の日系企業を訪問し、ローカルスタッフのマネジメントや駐在員の状況等について学びます。
また、現地大学生や同世代の日本語学習者と交流する機会を必ず設けています。
同世代のキャリア観・労働観、異文化に触れることで、学生が新たな気づきを得ることを期待しています。
海外研修の期間はおおよそ8泊10日ほどです。直近の3年間は、カンボジア、モンゴル、マレーシアを訪問し、それぞれ現地の企業や大学等を訪問しました。
 関口和代 教授
関口和代 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
海外に赴き、実際の労働環境に触れているのですね…!
海外研修では学生が大きく成長します。
「海外は嫌だ」と言っていた学生が海外でのキャリアを視野に入れた一歩を踏み出すこともあれば、現地企業のトップと交流して人脈を築き、第一志望の会社に就職したケースもあります。
逆に、受け身のままで機会を逃す例もあります。20〜30万円かかる研修費用に見合うよう、研修先でさまざまなことに貪欲に積極的に挑戦してほしいと思っています。
 関口和代 教授
関口和代 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
一歩踏み出せるかどうかで、成長に大きな差が出るのですね。
東京経済大学 関口和代教授にインタビュー③:就活生へのアドバイス
判例で学ぶ就活の契約問題:「ゆっくり考える」視点を持つ
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
就活の場で、学生はどのようなことを理解しておくべきでしょうか?
まずは、内定者の囲い込みや承諾書の問題など、“就活の契約関係は法的にどこまで認められるか”を理解しておく必要があります。
人的資源管理論の授業では判例も紹介しながら、学生に“ゆっくり考える”視点を持ってもらうようにしています。
 関口和代 教授
関口和代 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
内定承諾についてのトラブルに巻き込まれるという話はよく聞きますね。
“ゆっくり”考えることが就活の場では、学生にとってはなかなか難しいですよね…
日本の就活は非常に画一的で、波に乗らないといけないという雰囲気が学生を焦らせています。
内々定が早く出る傾向がありますので、周囲の状況に流されて、あまり考えずに決めてしま
いがちですが、立ち止まって冷静に考える時間が必要だと思います。
 関口和代 教授
関口和代 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
就活がどんどん早期化し、焦らされるような雰囲気の中で、学生はしっかりと立ち止まって考えることが重要なのですね。
「自分の身は自分で守る」ことが大切です。
過重労働で健康を損ねたり、メンタル面で不調をきたす例もあります。
若い人たちが法的知識を持たずに働く危険を避けるため、人的資源管理論の授業ではゲスト講師も招き、具体的に伝えるようにしています。
 関口和代 教授
関口和代 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
ワーク・ライフ・バランスが整ってきたといわれる中でも、労働による負担には慎重にならなければなりませんね。
大手の手厚さとスタートアップのダイナミズム:第三者の意見も参考に
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
就活生はどうしても大企業にばかり目がいってしまいがちですが、それに対してはどのようにお考えですか?
大手企業は新入社員研修が非常に手厚く、丁寧に学べる点、中長期的にキャリアを検討できる点等で魅力があると思います。
一方で、スタートアップには、挑戦できる環境や成長スピードの速さといった点で魅力があります。
どちらが良い悪いではありません。自分自身の志向にあわせて検討してほしいと思います。
キャリア志向や向き不向きを見極めるためには、自己分析だけでなく家族や周りの方等の第三者の意見も取り入れてほしいと思います。
 関口和代 教授
関口和代 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
中小企業にも、大企業にはない魅力がありますよね。
「将来の変化に備えて視野を広げ、いつでもチャンスを掴める自分でいてほしい」
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
関口先生、ありがとうございました。
最後に就活生に向けてメッセージをお願いします!
私自身も転職を二度経験し、三度目のキャリア・チェンジで大学教員となりました。
キャリア決定は一度きりではなく、チャンスはたくさんあります。
就活で追い詰められて涙ぐむ学生もいますが、本来はもっと気軽に取り組んでいいはずです。
画一的な採用活動を含め、閉塞的な雇用システムであることは懸念されますが、変化の兆しがありますので、それに備えて視野を広げ、いつでもチャンスを掴める「自分」でいてほしいと考えています。
もっとチャレンジしてほしいと切に思います。小さくまとまりすぎず、国内だけでなく海外も含めて、若いうちにしかできないこともありますので挑戦してほしいですね。
 関口和代 教授
関口和代 教授
 「就活の教科書」編集部野口
「就活の教科書」編集部野口
関口先生、本日はありがとうございました!