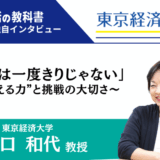「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの小林です。
本日は、大妻女子大学キャリア教育センターの井上俊也教授にお話を伺いました!
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
井上先生、本日はよろしくお願いします!
よろしくお願いします。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
井上 俊也(いのうえ・としや)
大妻女子大学キャリア教育センター 教授
愛媛県出身。慶應義塾大学経済学部卒業後、日本電信電話公社(現・NTT株式会社)に入社。
フランスのグランゼコールのHEC(アッシュ・ウ・セ経営大学院)でも学び、営業・企画・国際業務などを中心にNTTグループで26年間勤務。2010年に大妻女子大学へ。
教授としてキャリア教育センターで正課外のキャリア教育講座の大妻マネジメントアカデミー(OMA)の企画・運営に携わる。
専門はスポーツビジネス、マーケティング、情報通信産業論。スポーツ産業やICT人材育成に関する学会・団体で活動し、著書・研究実績も多数。
目次
大妻女子大学 井上俊也教授にインタビュー①:海外で気づいた「合格歴社会」——大学教育への思い
フランスで実感した日本との違い“学んだことが評価される社会”
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
さっそくですが、井上先生が大学教育に携わるようになったきっかけはありますか?
フランスのグランゼコールに行ったとき、日本の大学との大きな差を実感しました。
最大の違いは“学んだことが社会で評価される”という点です。
したがって、大学院や大学という高等教育機関のサービスとしての教育が優れていたのです。
これが高学歴社会というものだと感じました。
日本では、“どこの大学に合格したか”が重視されます。
つまり、学んだ内容ではなく、入学試験に合格した実績が評価されます。
これを評して『日本は高学歴社会ではなく、合格歴社会だ』という人もいます。
カタカナにすると濁点の位置が移動しただけですが、大きな違いです。
海外で厳しい学生生活を経験した私はそれを痛感しました。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
日本は「高学歴社会」だと思っていましたが、実際には「合格歴社会」なのですね…!
実績や能力によってスタート地点の処遇の差がつく
日本では新卒の初任給は大学に関係なくほぼ横並びです。
でもフランスでは違っていて、新卒であっても人によって給与が変わります。
どこの大学を卒業したか、大学時代のパフォーマンスはどうであったかが問われます。
日本の大学の評価の1つが入学時の偏差値ですが、フランスでは卒業生の平均初任給は注目の集まる評価指標です。
プロ野球のドラフトと同じで、実績や能力によってスタート地点の処遇に差がつく。
だからこそ、みんな“学ぶこと”に真剣になりますし、教える方も真剣です。
強豪の大学野球部を連想してくれればわかります。
そういう経験を経て、私自身も「大学の教育に関わりたい」と思うようになったのです。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
日本とフランスでは、そんな大きな差があったのですね。
企業在籍中に研究・教育歴を得られた背景
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
企業で働く中で、大学教員を目指すというのは難しくありませんでしたか?
私が勤めていたNTTは1985年に民営化しましたが、それまでは電電公社という公共企業体でした。
その電電公社時代から兼業が認められる制度がありました。
さらに1週間連続して夏休みをまとめて取るルールもありました。
それを利用し非常勤講師や海外学会にも参加できました。
そのおかげで教育歴と研究歴を積むことができ、大学教授になる道が開けました。他社では無理だったと思います。
NTTを退職して大学へ移ったのは48歳で、自分でも少し早いと感じましたが、NTTにはとても感謝しています。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
会社にいながらも、働きながら教員への道がひらけたのですね!
大妻女子大学 井上俊也教授にインタビュー②:OMA(大妻マネジメントアカデミー)とは?——正課外で実践力を鍛える
3つの柱:営業楽部/資格取得・スキル育成コース/キャリアエンパワーメントコース
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
井上先生が現在、大学で取り組まれていることについて教えてください!
私のミッションは“大妻マネジメントアカデミー(OMA)”という正課外講座の企画・運営です。
私が大学に移った時は国際的にはリーマンショックの直後で大学生が就職に苦労している時期であるとともに、国内的にはキャリア教育を大学だけではなく高校以下の学校でも取り組むようになった時期でした。
そのためにキャリア教育センターという組織を立ち上げて専任教員を配置しました。
その中の1人が私で、プログラムの企画構想の段階から始めました。
それまでの本学では、大企業で補助的な一般職に就き、結婚後は専業主婦という昭和的な願望を持った学生が多くいましたが、時代の流れとしては絶滅危惧種です。
本学の創始者の大妻コタカは85歳で生涯を閉じるまで働き続けました。
「人生100年時代と言われる中で女性が働き続けるためにはマネジメントの知識が必要である」と考え、「大妻マネジメントアカデミー」という正課外のプログラムをスタートさせました。
その名の通り、ビジネスやマネジメントに役立つ知識やスキルを学ぶためのプログラムです。
学生は所属している学部・学科での学びに加えて、マネジメントの知識を習得することができます。
これは正課外のプログラムですから卒業単位にはなりません。
学生は所属している学部・学科の正課の授業がありますから、開講する時間帯は土日中心で平日だと夜間になります。
正課の授業とバッティングすることもあるので、コロナ禍の前からオンライン授業を行い、現在もオンデマンドやオンラインの授業もあります。
本学の学生は履修登録なしに誰でも受講でき、受講科目も自由に選択できます。
受講料は無料です。ただし、テキスト代や検定料は学生自身に負担してもらっています。
このOMAは三つの柱から成り立っています。
一つ目は“営業楽部”です。
これは単なる営業職養成ではなく、どんな世界でも通用する人材を育てるという広い意味での営業を学ぶ場です。
なお「楽部」としたのは、正式な学部ではないことがまずありますが、世の中からは苦しいと思われている営業を「楽しく学ぶ」という思い、そして本学の創始者の大妻コタカが残した「楽学自尊」という言葉に由来しています。
二つ目は“資格取得・スキル育成コース” です。スキルを可視化する資格取得を支援します。
三つ目は“キャリアエンパワーメントコース” です。
得たスキルや知識を実際に社会で活かすためのプロジェクトやコンテストへの参加を促しています。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
大学の授業とは別で学ぶことができるのですね!無料なんて羨ましいです…
営業楽部で学ぶ“広い意味での営業”とはどのようなものでしょうか?
営業を単にモノやサービスを売ることだけではなく、 “相手に自分を理解してもらうこと” “相手の心のハードルを低くすること”そして“自分自身を営業すること”と捉えており、そこには論理的思考力や表現力、相手を説得する力が必要です。
ビジネスでは謝罪やプレゼンテーションのスキルも重要になります。
つまり社会人に求められる基本的な力を幅広く学べるのが、この営業楽部の狙いです。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
“自分を営業する力”を学ぶことができるのですね!
ビジネスの世界で活躍している外部講師から学べる
大妻マネジメントアカデミーでは年間600コマ近く講座を開いていて、学内の専任教員も私のようにビジネス経験がありますが、ビジネスの世界で活躍している外部講師の方が、全体の3分の1くらいの授業を担当しています。
今年は53人の外部講師が指導していただいています。
大学は実務家教員のウエイトを大きくしようとしていますが、正課の非常勤講師は基本的には15コマを同一曜日の同一時限に担当しなくてはならず、ビジネスの最前線で活躍されている方には負担が大きいです。
ところが正課外のOMAの場合、授業時間の設定も自由度があり、多くの企業人や専門家に外部講師としてご協力いただいています。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
実際に企業で働いている人から学べるのはとてもいいですね!
女子大ならではのホスピタリティ領域
また、女子大ならではの取り組みとして、特に力を入れているのはホスピタリティ系です。
客室乗務員や観光、ホテル業界などで活躍する女性を育成するための講座が多く設けられています。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
女子大ならではの、女性のキャリアを意識した講座を展開されているのですね。
成年女性であれば、聴講生という形で受講することができます。
聴講生は随時出願可能ですので関心のある方はお待ちしています。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
大妻女子大学 井上俊也教授にインタビュー③:キャリア教育の本質とは?——“学び直し”の重要性
キャリアの語源は“轍”:自分がどんな人生を歩んできたかを振り返り、それをもとに将来どう進むか
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
キャリア教育において、大切にされていることは何ですか?
私たちが担っているのは“就職支援”ではなく“キャリア教育”です。
エントリーシート添削や面接練習は就職支援センターが担当しますが、私たちはキャリアそのものを考え、キャリア開発のベースとなる知識、スキルを学ぶ場を提供しています。
キャリアの語源はラテン語で“轍”です。
つまり、自分がどんな人生を歩んできたかを振り返り、それをもとに将来どう進むかということです。
日本の場合、これまでは企業が各社員のキャリアをデザインし、各社員の能力を開発し、発揮させるためのキャリアパスを準備していました。
それが、社員個人にとっても組織である会社にとっても最適解となっていました。
ところが、近年はキャリアは社員自身がデザインするものになってきました。
そこで大学以下で必要となってきたのがキャリア教育です。
したがって、就活はキャリア教育のほんの一部でしかありません。
自分の希望するキャリアを描いたうえで、その道に進むための力が足りない部分を、教育を通じて補っていく。それがキャリア教育です。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
キャリア教育は就職支援とは違い、自分の人生、キャリアをどう生きるかを教えてくれるものなのですね!
キャンパスでの勉強とキャンパス外での実践、その繰り返しが大切
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
日本のキャリア教育における課題は何でしょうか?
インターンシップとギャップイヤーでしょう。
日本のインターンシップはまだ多くが会社説明会の延長に過ぎず、学生のキャリア形成にはつながっていません。
インターンシップは本来は学びの一環であるべきで、EUではインターンシップは大学の授業でなくてはなりません。
すなわち、大学のキャンパスで勉強したものが、キャンパスの外、すなわち社会に出てどれだけ通用するかを確認する機会です。
当然、経験の少ないインターン生は社会に出て自らの学びが足りない部分を痛感します。そして足りない部分をキャンパスに戻って学び直すわけです。
キャンパスでの勉強とキャンパス外での実践、その繰り返しが大切なんです。
キャンパスの延長に社会があるからキャンパスでの学びが評価される仕組みになっています。
体験型授業は学生に人気がありますが、学内での学びと学外での体験を結びつけることのできる学生はどれだけいるでしょうか。
同じことがギャップイヤーにも言えます。
欧米ではギャップイヤーを取るのが当然になり、米国では5年、欧州では4年かけて卒業するのが標準的な姿になっています。
ギャップイヤーというと日本では1年間ある夏休みくらいにしか考えられていません。
しかし、社会での経験を通じて“自分は何を学ぶべきか”を明確にして大学に戻ってくる欧米の学生とリフレッシュするだけの日本の学生には大きな差がついてしまいます。
インターンシップやギャップイヤーでは、職場や社会で得た経験をきっかけにキャンパスに戻って知識を補い、同時に自分の強みも見つけてほしいです。
このプロセスの繰り返しを経たうえで自分自身を活かせる企業を選んでほしいと思います。
そういう点で言うと②でお話ししたOMAの場合は、営業楽部や資格取得・スキル育成コースで学んだものをキャリアエンパワーメントコースで社会で発揮し、そこでの経験をもとに再び営業楽部や資格取得・スキル育成コースで学ぶという学生もいます。
少しは自分の思いが実現したのかな、と思っています。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
日本で、大学に入る時に“何を学ぶべきか”が明確になっている学生はほとんどいませんね…
いや、欧米でも18歳で大学入学した場合は似たようなものでしょう。
ただし、欧米の学生はインターンシップやギャップイヤーで、大学に入ってから大きく変わります。
上級生になるほど“何を学ぶべきか”が明確になる仕組みになっています。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
欧米ではインターンシップやギャップイヤーのある欧米と日本では違いがあるのですね。
インターンシップやギャップイヤーも欧米で昔から存在していたわけではありません。
私が留学していた30年前に私の周りではギャップイヤーを取得する学生はいませんでした。
それが、この30年間で大きく進化しました。
日本ではインターンシップやギャップイヤーに対する認識が十分ではなく、この意識の差が国全体の停滞の一因になっています。
取り組んでこなかった日本は、結果的に“失われた30年”を経験することになりました。
制度が違うのではなく、制度の変化に追いつけなかったことが問題でしょう。
これはインターンシップやギャップイヤーに限らず、様々なところで見られる現象です。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
元々の制度が違っていると思っていましたが、日本が変化に追いつけていない、ということだったのですね…!
大妻女子大学 井上俊也教授にインタビュー④:会社選びの視点——“年功序列”の本質とは?
年功序列は“年齢に応じてスキルを高めなければならない”という仕組み
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
昔に比べると比較的“就職がしやすい”中で、会社はどのように選んだら良いのでしょうか?
「年功序列の会社はダメ」という意見も聞いたことがあります…
若い世代の方は「年功序列は古いダメな制度」と感じられることが多いかと思いますが、年功序列の時代から生きてきた私から言うと、年功序列は一見不公平にも見えますが、かなりうまくできていて、さらには残酷な制度です。
年功序列は“年齢に応じてスキルを高めなければならない”という仕組みです。
さきほどドラフト指名される大学の野球選手の例を出しましたが、大学の野球部を企業に見立ててみましょう。
この野球部が年功序列で選手を決めているのであれば、レギュラーは必ず4年生です。
もちろん勝利を目的とするスポーツですからレギュラーには技量が要求されます。
下級生が優秀でも、上級生は下級生よりも高い技量を持って試合に出場しなくてはならないのです。
当然、下級生には甲子園で活躍したスーパー1年生がいるかもしれません。
そういうスーパー1年生にレギュラーの座を奪われないように4年生は努力する、これを全部員が続けることにより、全部員が成長を意識し、組織全体が強くなるのです。
大学の野球部は4年間ですが、企業は30年以上勤続するケースも多いでしょう。
会社に入って30年間、社員が成長し続け、その結果としてスキルアップし、昇格し、昇給していくというサイクルを実現する手法が年功序列なのです。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
年功序列は、単にいればいるほど給料が上がっていく仕組みだと思っていましたが、「常に後輩よりも優秀でなければならない」という仕組みだったのですね…!
ところが、いいことだけではありません。
まず、上級生が下級生より技量が上回るためには努力、野球で言えば練習になります。
大谷翔平選手のような1年生が入学してきて、ポジションを取られないために練習する、大谷翔平選手を上回るためにはいくら練習しても無理です。
そういう「無理ゲー」を強いられるのが年功序列です。
職場の場合はこれが過重労働につながります。高度経済成長期の日本人の長時間労働の一因は年功序列という制度にありました。
ここが「残酷な制度」と言った理由です。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
一見楽に見える会社は将来の成長や存続には不安が残る
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
それは本当に「無理ゲー」ですね。
私は年功序列というと「働かない50代」というイメージでした。
「働かない50代」、いい指摘です。次にお話ししましょう。
そして、その「無理ゲー」から「一抜けた(いちぬけた)」と言って試合には出なくていいから、大谷翔平選手がホームランを打った時だけベンチで出迎える、ということだけで満足してしまっているのが「働かない50代」なのです。
「年功序列」ですから試合に出なくてもベンチには入る、それが現実です。
そこで、ホームランを打った選手を出迎えるのだけが仕事という選手しかベンチにいないチームがどうなるかわかりますよね。
おそらくそういう組織が小林さんの想像する「働かない50代のいる年功序列の会社」です。
年功序列かどうかは別として、「働かない50代がいるかどうか」を見極めることは会社選び、就活の一環です。
そういう人が多い会社は一見楽に見えますが、将来の成長や存続には不安が残ります。
だから学生には必ずリサーチするよう伝えています。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
インターンシップは“入社するため”ではなく、“成長する機会”であり、“学びのモチベーション”
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
会社選びのためのリサーチとしても、インターンシップは重要になってきますか?
そうですね。そのためにはインターンシップ自身が現在とは姿を変える必要がありますね。
私は留学時代2年間のうち、6か月はインターンシップをしていました。
学生の楽しみである2回の夏休みはまるまるインターンシップの期間でした。
インターンシップを半年も経験すれば、その会社が自分に合うかは分かります。
言ってみれば“同棲”のようなものです。
ところが日本では、多くの業界でインターンシップが単なる会社説明会や体験会にとどまっていて、学生のキャリア形成にはつながっていません。
本来は企業と学生がお互いを知り、学生が成長する機会であり、学びのモチベーションとなるべきなのに、今の日本では“入社するためのインターンシップ”、まさに合格歴社会の延長になってしまっているのです。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
会社説明を聞いても、実際の会社の本質はなかなか見えてきませんよね…
大妻女子大学 井上俊也教授から学生へのメッセージ
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
最後に学生へのメッセージをお願いします!
学生生活の本分は立場上、勉強と言わなくてはならないのですが、私は部活やサークル、アルバイト、恋愛など、授業以外にも大切な経験がたくさんあると思っています。
ただし“就活”だけは学生生活の本分ではありません。
「学生時代に何をしましたか?」と聞かれて「就活です」と答えられるのは一番残念です。
私もビジネスの世界で「人生のピークが就職活動の最終面接だった」という人をたくさん見てきました。
学生には、最終面接を人生のピークにするのではなく、その先に続く長いキャリアのスタートとして位置づけてほしいです。
ビジネス社会で活躍する大人は皆そう思っていますが、ビジネス界の人は学生に直接教えることはできません。
社会の現実の声を大学に伝えるのは、社会で働いた経験のある自分の使命だと思っています。
 井上 俊也教授
井上 俊也教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
井上先生、本日は素敵なお話をたくさんありがとうございました!