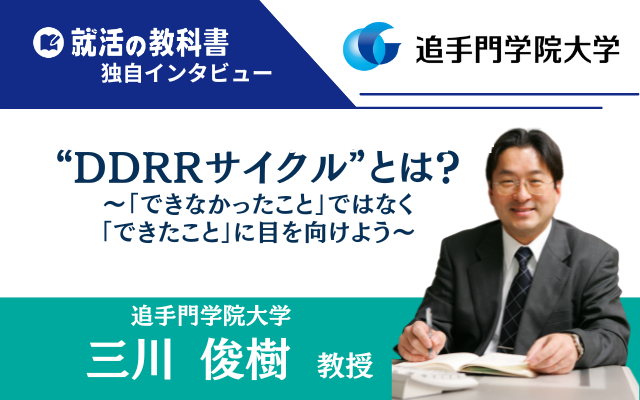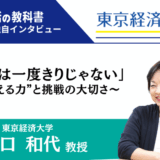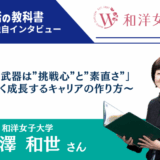「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
こんにちは!「就活の教科書」取材チームの小林です。
本日は、追手門学院大学心理学部の三川俊樹教授にお話を伺いました!
この記事を読めば、「キャリアカウンセリング」や「DDRRサイクルとは?」について知ることができます。
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
三川先生、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
三川 俊樹(みかわ・としき)
追手門学院大学 心理学部 心理学科 教授
大阪大学人間科学部を卒業後、同大学大学院で学び、追手門学院大学にて助手・講師・助教授を経て、2004年より教授に就任。
研究テーマは、「生涯にわたるキャリア発達をどう支援するか」「そのための教育方法や専門家の養成・訓練」など。
特にキャリアカウンセリングやスーパービジョンに関する研究と実践を重ね、学生や社会人のキャリア形成を支援。
目次
追手門学院大学 三川俊樹教授にインタビュー①:やりたくなかったことが“キャリア”になった
学部時代:想像と違った心理学、臨床心理学・カウンセリングとの出会い
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
三川先生は、どうしてキャリアカウンセリングに興味を持ったきっかけについて教えてください!
心理学に興味があり、大学で人間科学部へ入学したのですが、最初に学んだ心理学は正直あまり面白くなくて、「なんでこんなものを学ぶために大学に来たんだろう」と思ったくらいです。
ただ、2年生の頃に他学部向けの心理学の授業に“潜り込んで”みたら、それが臨床心理学の授業で、すごく衝撃的で。
心理療法やカウンセリングについて学ぶ中で、「これを専門にしよう」と思うようになりました。
それで3・4年生はカウンセリングを学び、卒業時には「もっと勉強したい」と考えて大学院に進みました。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
潜り込んだ他学部向けの授業で、臨床心理学に出会い、カウンセリングに興味を持たれたのですね!
カウンセリングからキャリア指導へ
ところが大学院では、恩師から「進路指導(キャリアガイダンス)を学べ」と言われて大反発しました。
「私はカウンセリングをやりたいのに!」と抵抗しました。
でも恩師は「不適応の根っこには進路の問題がある。進路指導はキャリアカウンセリングそのものだ」と強く説得してくださった。
半ば“騙された”ような気持ちで学び始めたのが、私のキャリアの大きな転機でした。
私は最初「キャリア? 就職? そんなの心理学じゃない」と思っていました。
でも叱られて初めて気づきました。進路や仕事は人の人生に直結する。そこに心理支援の重要な場があるんだと。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
今振り返ると、その“やりたくなかったこと”が先生自身のキャリアになったわけですね。
キャリアとは“人生そのもの”
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
三川先生にとって、“キャリア”とはどのようなものですか?
私は「キャリアというのは人生そのものである」と伝えるようにしています。
進路とか経歴と説明されることもありますが、私にとっては「生き方」よりも「人生」という言葉が一番しっくりくるんです。
ただ、「キャリア教育」を「人生教育」、「キャリアカウンセリング」を「人生相談」と言うと、なんだか怪しく聞こえてしまいますよね。
だからあえてキャリア教育、キャリアカウンセリングという言葉を使っています。
でも根っこにあるのは、「私たちがどう生きるか」そのものがキャリアなんです
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
“キャリア”と聞くと、就職だけにフォーカスしてしまいがちですが、本来キャリアとは人生そのものなのですね。
就職や進学は「人生の一コマ」
進学や就職はもちろん大事ですが、それだけが人生のすべてではありません。
就職して終わり、進学して終わりではなく、その後どう生きていくか、どう展開していくかが大切です。
また、夢や希望を実現するにはその瞬間の選択だけでなく、そこに至るまでの準備も必要になります。
そう考えると、就職や進学といった節目も含め、私たちが生きていく営みそのものがキャリアだと言えるのです。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
進学先や就職先はゴールだと思ってしまい、就活を重く捉えすぎている人が多いので、「就職は人生の一コマである」という考え方はとても大切ですね!
追手門学院大学 三川俊樹教授にインタビュー②:キャリアカウンセリングと自己理解
人は語ることによって気づく
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「キャリアカウンセリング」について教えてください!
キャリアカウンセリングで一番大事なのは、一人ひとりとしっかりと向き合い、対話をすることです。
私は「人は語ることによって気づく」という言葉が大好きです。
話すことで、自分が何を感じ、何を考えていたのかがはっきり意識できる。これが自己理解や洞察につながります。
だからカウンセラーがすることは、「あなたはどう考えていますか?」と問いかけ、その人自身に語ってもらうこと。
アドバイスを押しつけるのではなく、語りながら自分で自分の生き方に気づけるように促すのが大切なんです。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
“カウンセリング”というと、ただ話を聞いてあげることだと思っていましたが、「語ってもらって気づいてもらう」ことが大切なのですね!
自分のことを語れるのは、相手がきちんと話を聞いてくれるからです。
聞いてもらえることで、その人の内面に大切な気づきが生まれます。
ところが実際には、相手の話を最後まで聞かずに自分の経験を語ったり、頼まれてもいないのに余計なアドバイスや情報を押しつけてしまう人が多いんです。そうすると、かえって相談者を混乱させてしまいます。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
聞き上手な人と話しているとついつい喋りすぎてしまうのに近いですね!
逆に、自分の話を全然聞いてくれない人に語ろうとは思いませんね…
自己理解が不足している学生が多い
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
これまでカウンセリングをしてきた中で、どのような悩みが一番多いと感じますか?
これまでカウンセリングをしてきて感じるのは、「自分で自分のことがよく分からない」という悩みが非常に多いということです。
自分の能力や適性、やりたいこと、生き方が見えない――自己理解が不足している学生が多いのではないかと思います。
本来、自分の強みや関心が分かれば、将来の進路選択も少しずつ見えてくるはずです。
でも、その自己理解が難しいからこそ、悩みが深くなります。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
性格診断や自己分析ツールなどが流行っていますが、「結局のところ、自分がよくわからない」と悩んでいる人は多いですね…
もう一つ多いのは、「人とうまく関われない」という悩みです。
- コミュニケーションが苦手
- 集団の中でどう振る舞えばいいか分からない
- 周囲と協力して何かをするのが難しい
といった人間関係の難しさです。
「空気が読めない」こと自体は大した問題ではありません。
でも、実際に場面ごとにどう対応するか、どう話しかけるかが分からず苦しむ学生は多いのです。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
社会で生きる中で、人間関係の悩みは尽きませんよね…
就活直前ではなく、早い段階から少しずつ自己理解を積み重ねていくことが必要
学生相談を担当していたときに、「先生、僕って一体何なんでしょうか?」と突然聞かれたことがありました。
話を聞くと、その学生は就活準備の自己分析セミナーに参加し、友達やお母さんに自分の長所を聞いてみたら、それぞれが違うことを言ってくれて、かえって分からなくなってしまったというのです。
このエピソードから感じたのは、大学生になってから急に自己理解を深めようとしても難しいということです。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
就活で自己分析は一番最初にぶつかる壁ですね…
今まで何も考えていなかったのに、就活で急に「自分は何か」と考えるのは難しいです…
本当に必要なのは、就活直前ではなく、もっと前から少しずつ自己理解を積み重ねていくことです。
高校や中学、さらには小学校の段階から「自分を理解する」準備ができていると、大学生になってから迷わずに済むのではないかと思います。
だから私はキャリア教育の場でも、「自己理解は大学生からでは遅い。もっと早い時期から始めよう」と伝えてきました。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
急に自己理解しよう!として難しいのは当然であるので、早いうちから少しずつ自己理解を進めることが重要なのですね!
追手門学院大学 三川俊樹教授にインタビュー③:スーパービジョンでのカウンセラー育成
カウンセラーが自分の課題に気づき、乗り越えるための“指導”の場
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
キャリアカウンセリングにおける「スーパービジョン」とはなんでしょうか?
スーパービジョンとは、カウンセラーが自分の課題に気づき、乗り越えるための“指導”の場です。
- カウンセリング:相談者(クライアント)が対話を通じて「自分に気づき」、迷い・悩みを自分で解いていくプロセス。
- スーパービジョン:そのカウンセリングを行うカウンセラー側の理解不足や聞けていない点に気づかせ、よりよく支援できるよう指導するプロセス。
さらに上位にはスーパービジョン・メンタリングがあり、スーパーバイザー自身の課題を支援する“指導者のための指導”まで階層的に続いています。
例えばですが、「会社を辞めたい」と言われたときに「どう辞めるか」「転職の手順」は世間話でやる話です。
カウンセリングの視点はそこではありません。
本当に大事なのは、なぜ辞めたいのかを丁寧に聴き、背景(人間関係のストレス等)を理解することです。
もし本音が「合わない人とうまくやっていきたい」なら、その関わり方を一緒に考える方が効果的なのです。
カウンセラーが「相手が嫌がるかも」と遠慮して本質の質問を避けると、誤った支援につながってしまう。
スーパービジョンでは、こうした“聞けていない自分”に気づき、どう聞けばいいかを反復練習します。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
「スーパービジョン」はカウンセラーを育成するためのものなのですね!
カウンセラーの役割はアドバイスではなく“聴く”こと
私はカウンセラーを指導する際に「人の話をちゃんと聞いてあげて」とよく伝えています。
カウンセラーの役割はアドバイスではなく“聴く”こと。でも、勝手に解釈したり急いで助言したりしがちなんです。
アドバイスよりもまず、相手の話を誠実に受け止めることがカウンセリングの基本であり、キャリア支援でもっとも大事な姿勢だと思っています
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
カウンセラーは、みんな話を聞くのが上手いものだと思っていましたが、それぞれに課題があり、その指導が重要なのですね!
追手門学院大学 三川俊樹教授にインタビュー④:自分のキャリアを生きていくために
解決だけがすべてじゃない:“しのぐ・かわす・つなぐ”姿勢が大切
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
就活で悩みすぎてしまう学生はどうしたらいいんでしょうか?
キャリアというのは、期待通りに進むことの方がむしろ少ないものです。失敗や挫折、不本意な出来事は誰にでも起こります。
その時に大切なのは、それをどう受け止め、次につなげていくかです。
心理学では、それを「キャリア・レジリエンス」と呼んでいます。
- つらいことや苦しいことがあっても、しのぐ
- うまくストレスをかわす
- そして次へつなぐ
この「しのぐ・かわす・つなぐ」という姿勢が大切です。
必ずしも完璧に問題解決できるわけではありませんし、堂々と対処できることばかりでもありません。
でも、逆境を受け流しながら前へ進む力こそ、キャリアを歩む上で欠かせないものだと思います。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
問題に対して“解決する”だけが全てではなく、うまく流すというのも一つのスキルなのですね。
すべての課題に正面から挑んで努力すれば解決できる、というわけではありません。
むしろ、解決しないことを抱えながら生きていく知恵が大切なのだと思います。
若いうちは「今すぐ解決しなきゃ」と思いがちですが、長く生きていると「すぐには解決できないこともある」ということが自然に理解できるようになります。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
見えない未来を追いかけるより、これまでの自分の歩みを振り返る
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
変化する時代の中で、未来の自分をどう考えたらいいのでしょうか?
現代はVUCA(不安定・不確実・複雑・曖昧)の時代。10年後の未来を正確に描くことは難しくなっています。
そこで大事なのは、見えない未来を追いかけるより、これまでの自分の歩みを振り返ることです。
- 苦しかった経験も、振り返れば自分を成長させた大切な糧になっている
- 「偶然に思えた出来事」も、振り返ってみると計画されていたかのような意味を持つ
これはスタンフォード大学のクランボルツ教授が提唱したプランド・ハプンスタンス理論とも通じます。
「幸運は偶然ではなく、後から振り返って意味を持つもの」という考え方です。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
自分の人生を考えようと、先ばかり見てしまい、落ち込んだりわからなくなってしまって、しっかりと今までの自分を振り返ることをしていませんでした…!
PDCAではなく「DDRRサイクル」
従来のPDCA(Plan-Do-Check-Action)は、明確な目標を決めて改善を重ねるサイクルです。
ですが、キャリアや人生における体験学習は必ずしも「目標を定めて達成する」ものではありません。
そこで私が提案するのが DDRRサイクルです。
Desire(願望・望み) ― 明確な目標でなくてもよい。小さな願いや望みから始める。
Do(実行) ― 肩肘張らず、とりあえずやってみる。
Reflect(振り返り) ― 結果よりもプロセスをじっくり思い返す。
Realize(実感) ― 少しでも願いが形になったことを実感し、自信につなげる。
これにより、「できなかったこと」ではなく「できたこと」「積み重なったこと」に目を向けられるようになります。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
PDCAと違って「Desire(願い)」が最初に来るのが特徴的ですね。
結果も大事ですが、行動した中で「自分が何をしたのか」に注目することも大切ですね!
「前向きに生きる」とは何か
私は大きな病気で1年近くも入院と自宅療養を経験しました。「生かされている」と実感する出来事でした。だからこそ「できたこと」に光を当てることの大切さを強く感じています。
復帰後、ある講演会で「前向きに生きる!」というテーマを与えられました。
でも正直、どうすれば前向きになれるのか分からなかったんです。
そんな時、電車の中である出来事に出会いました。
5歳くらいの男の子が「ママ、この電車バックしてる!」と叫んだんです。
するとお母さんが「アホか、お前が後ろ向いてるからや!」と答えた。その言葉が、まるで私に向けられたように胸に刺さりました。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
何気ない親子の会話が、三川先生の胸に刺さったのですね。
病気で苦しかった頃、私は「なぜこんなことになったんだろう」「もう自分の人生は終わりかもしれない」などと後ろ向きに考えていました。
でもあの母子のやりとりで、自分の捉え方が後ろ向きだから苦しさが増していたんだと気づけたんです。
もちろんすぐに前向きになれたわけではありません。
でも少しずつ「できないこと」ではなく「できたこと」「進歩していること」に目を向けるようになり、立ち直ることができました。
この経験が、先ほどお話しした DDRRサイクル(Desire→Do→Reflect→Realize) を考えるきっかけにもなりました。
- 願いや望みを持つ
- とりあえずやってみる
- 振り返る
- できたことを実感する
この流れの中で「できたこと」に目を向けることができれば、人生の見え方は大きく変わります。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
自分が「できたこと」に目を向けることが、前を見ることにつながっているのですね!
追手門学院大学 三川俊樹教授から就活生へのメッセージ:「過去を振り返ることが前向きにつながる」
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
素敵なお話をたくさんありがとうございます。
最後に、就活生へのメッセージをお願いします!
「前向きに生きる」というと未来ばかりを見がちですが、むしろ過去を振り返ることが前向きにつながるのです。
思いがけない出来事や挫折に直面しても、過去を振り返れば必ず「自分はここまでやってこれた」という証拠が見つかります。
その事実が「これからもきっとやっていける」という自信につながります。
その積み重ねを力にして、また一歩前に進んでみてください。
 三川俊樹 教授
三川俊樹 教授
 「就活の教科書」編集部小林
「就活の教科書」編集部小林
三川先生、本日は本当にありがとうございました!